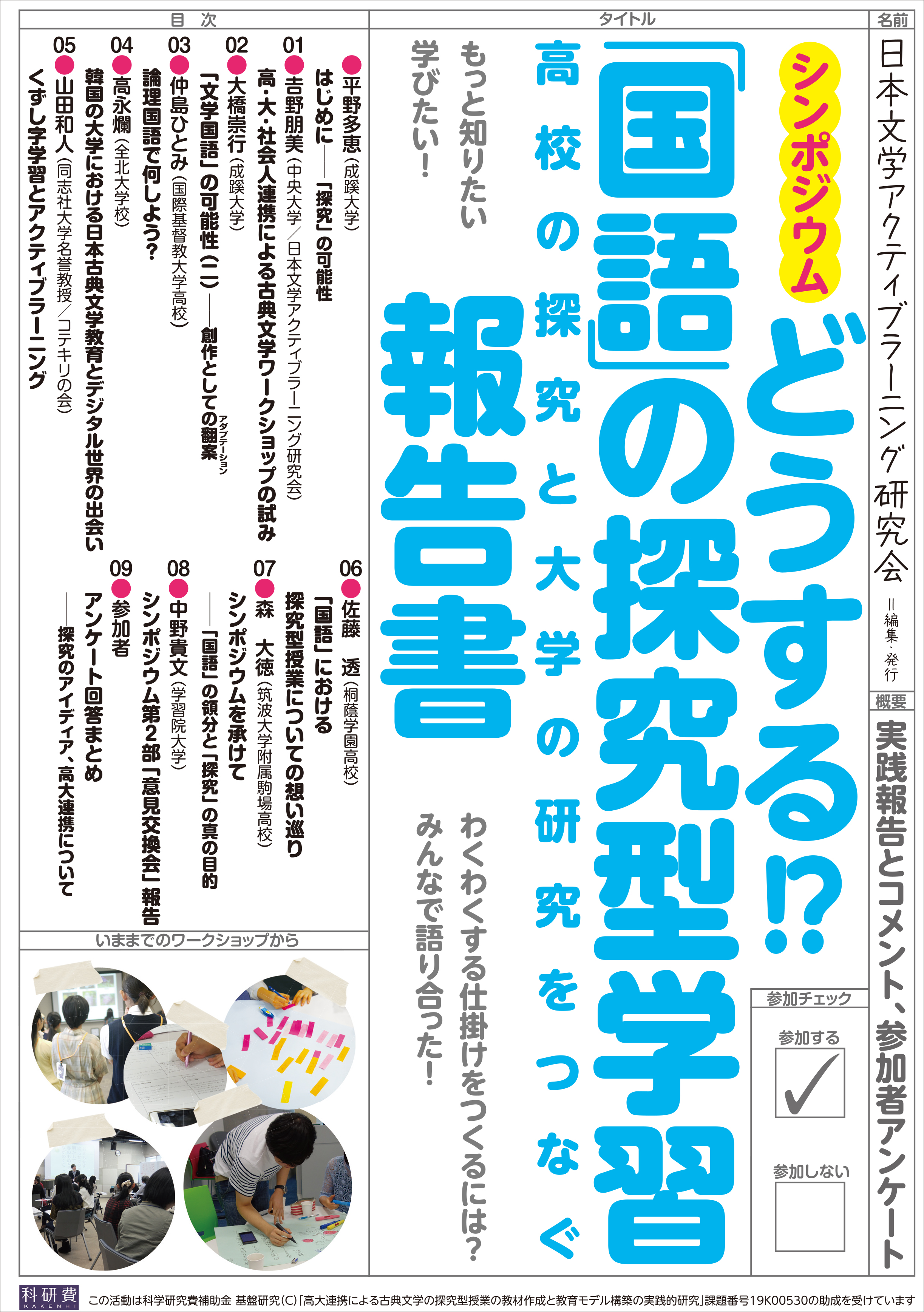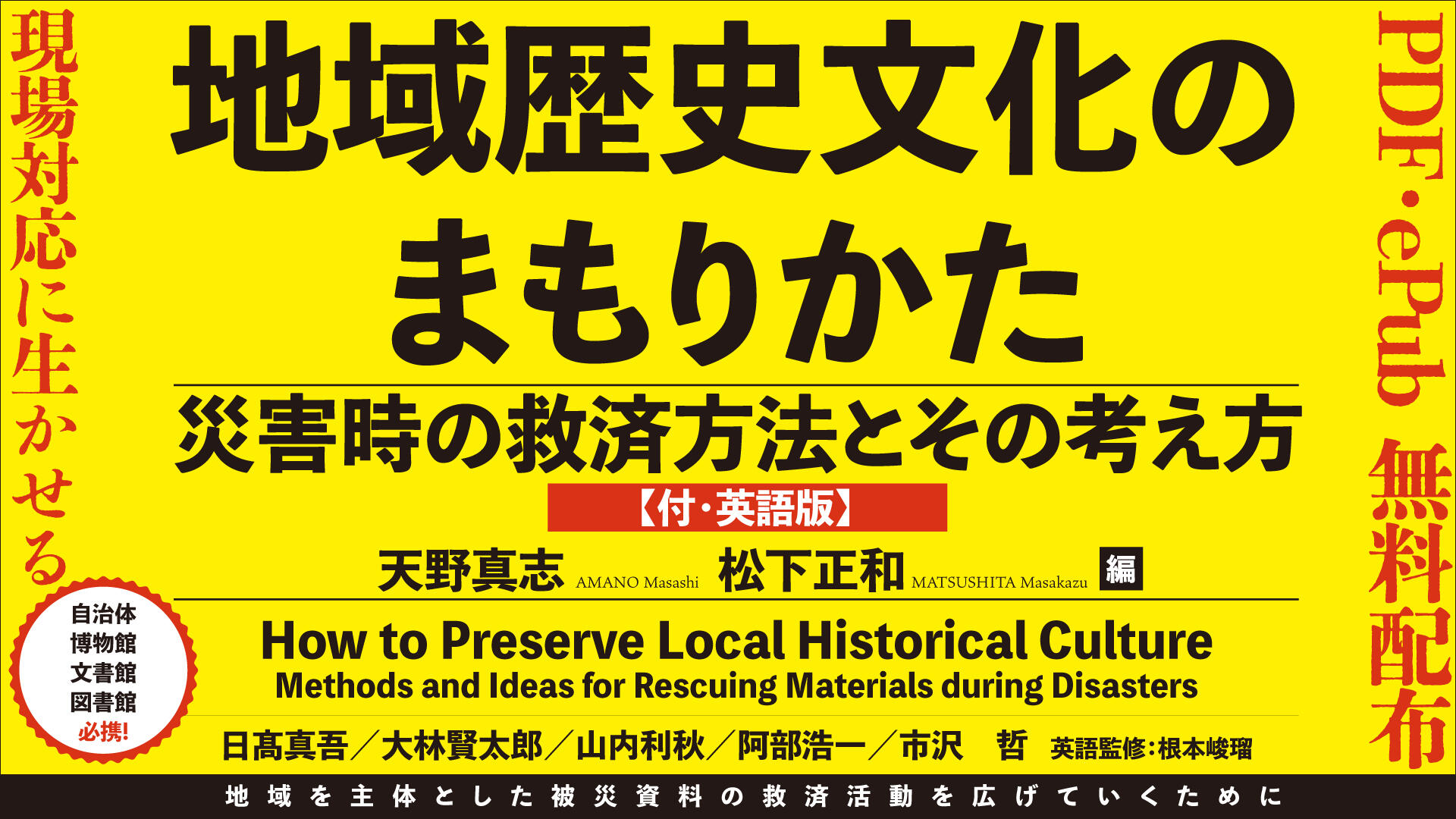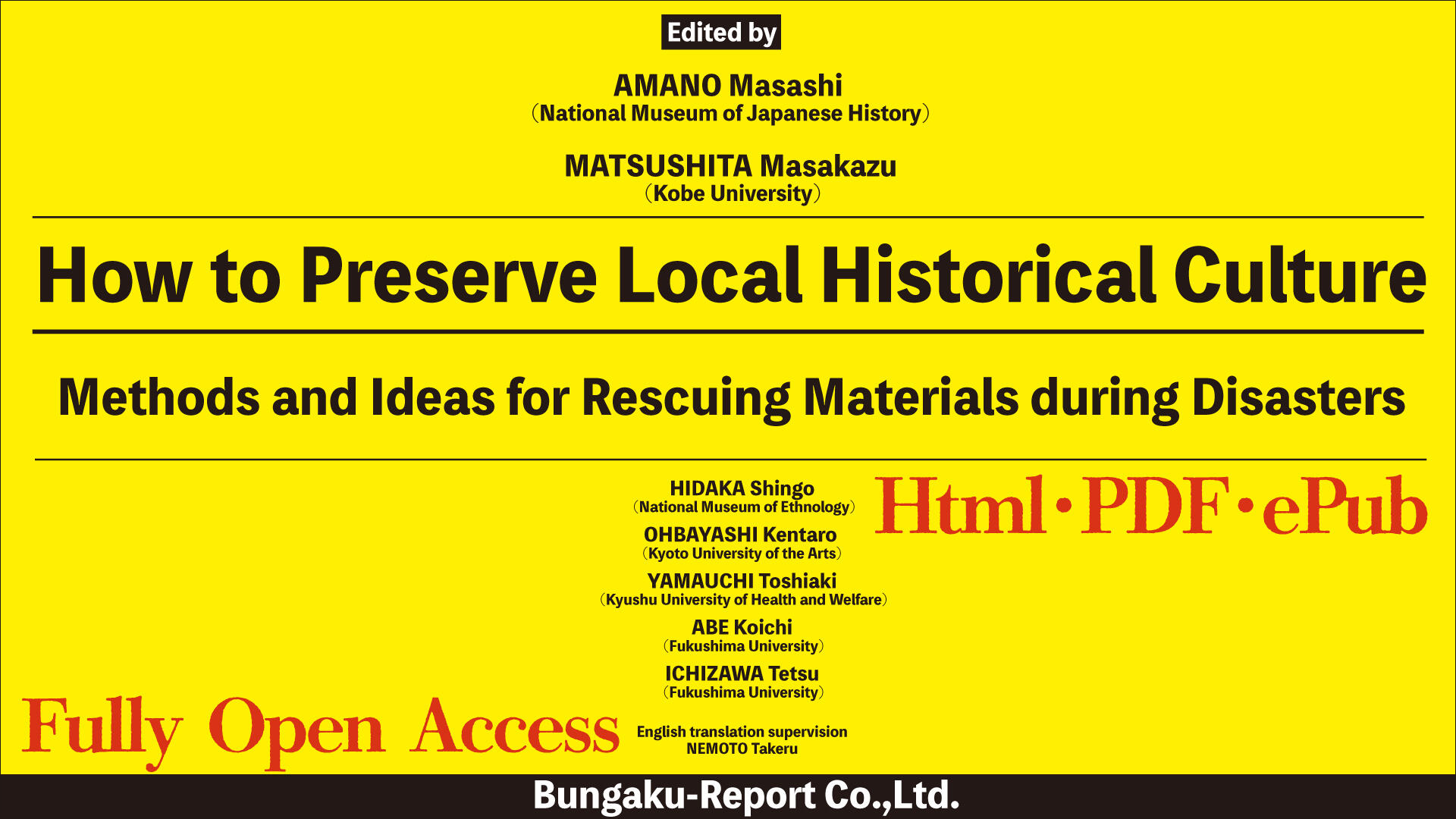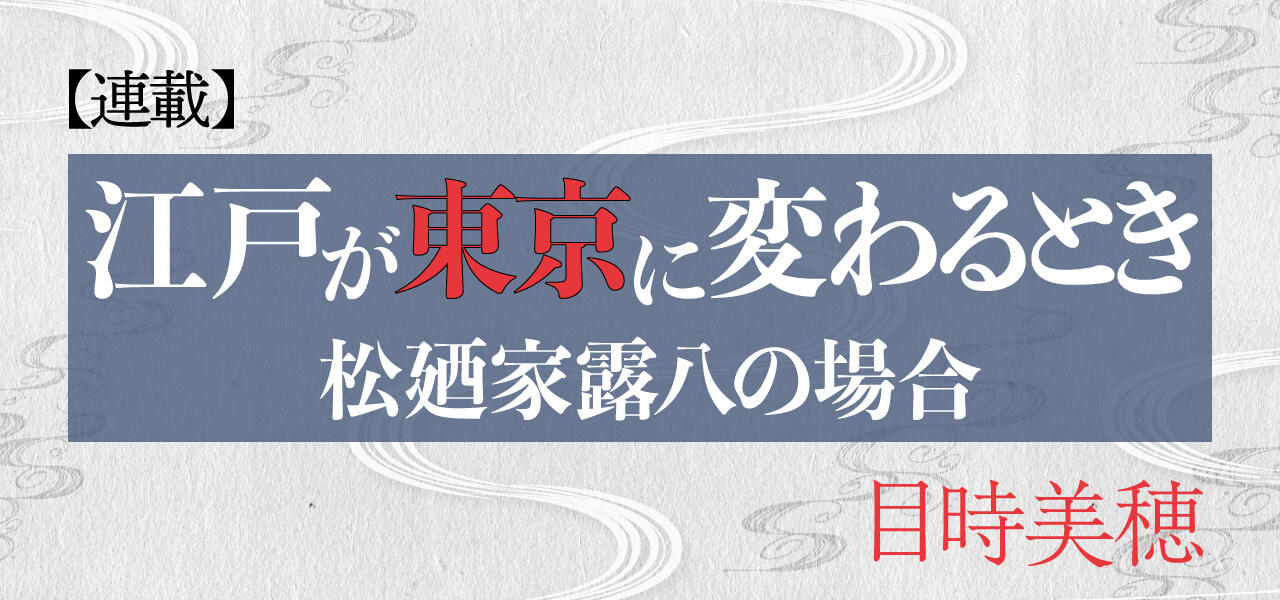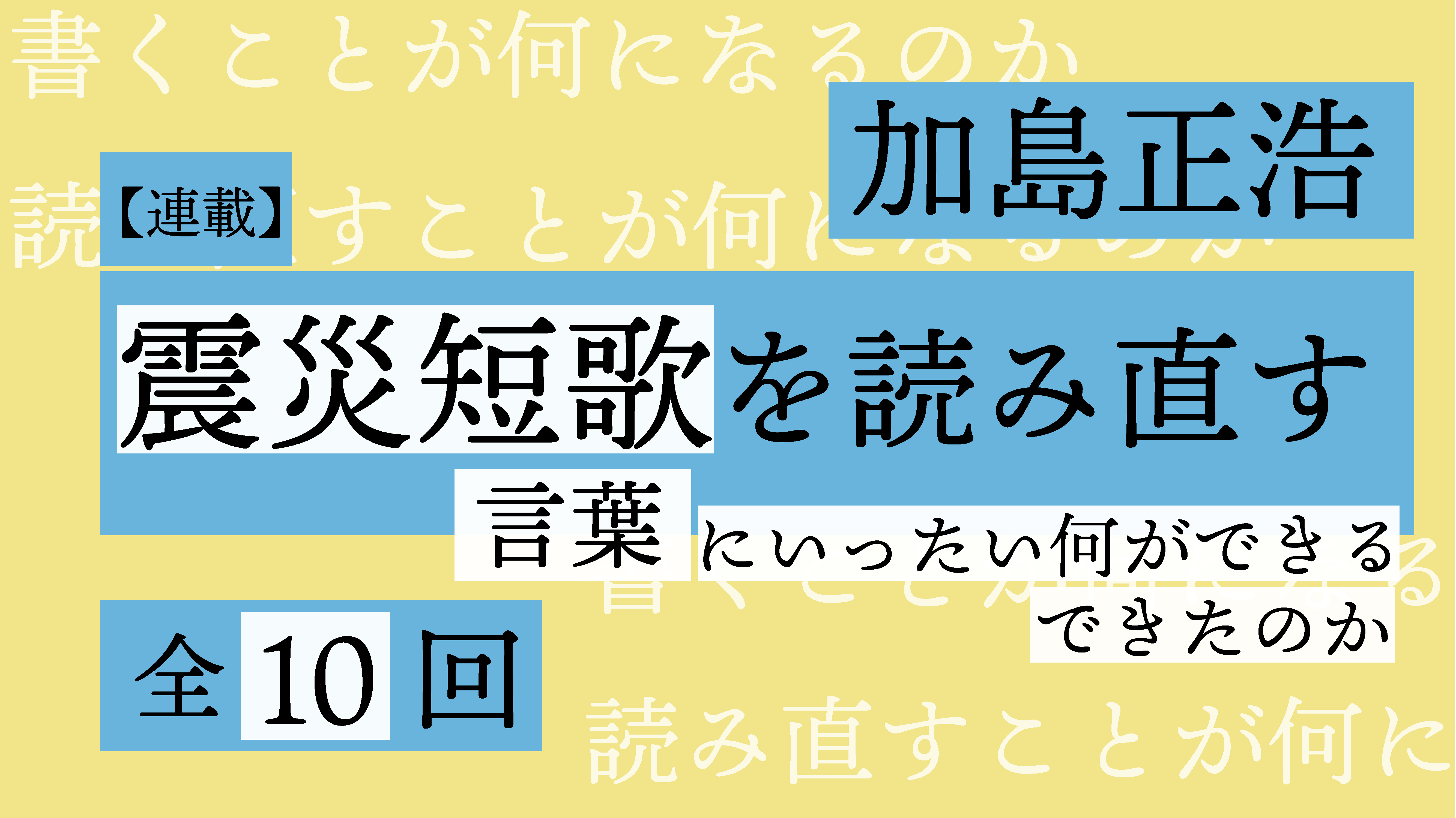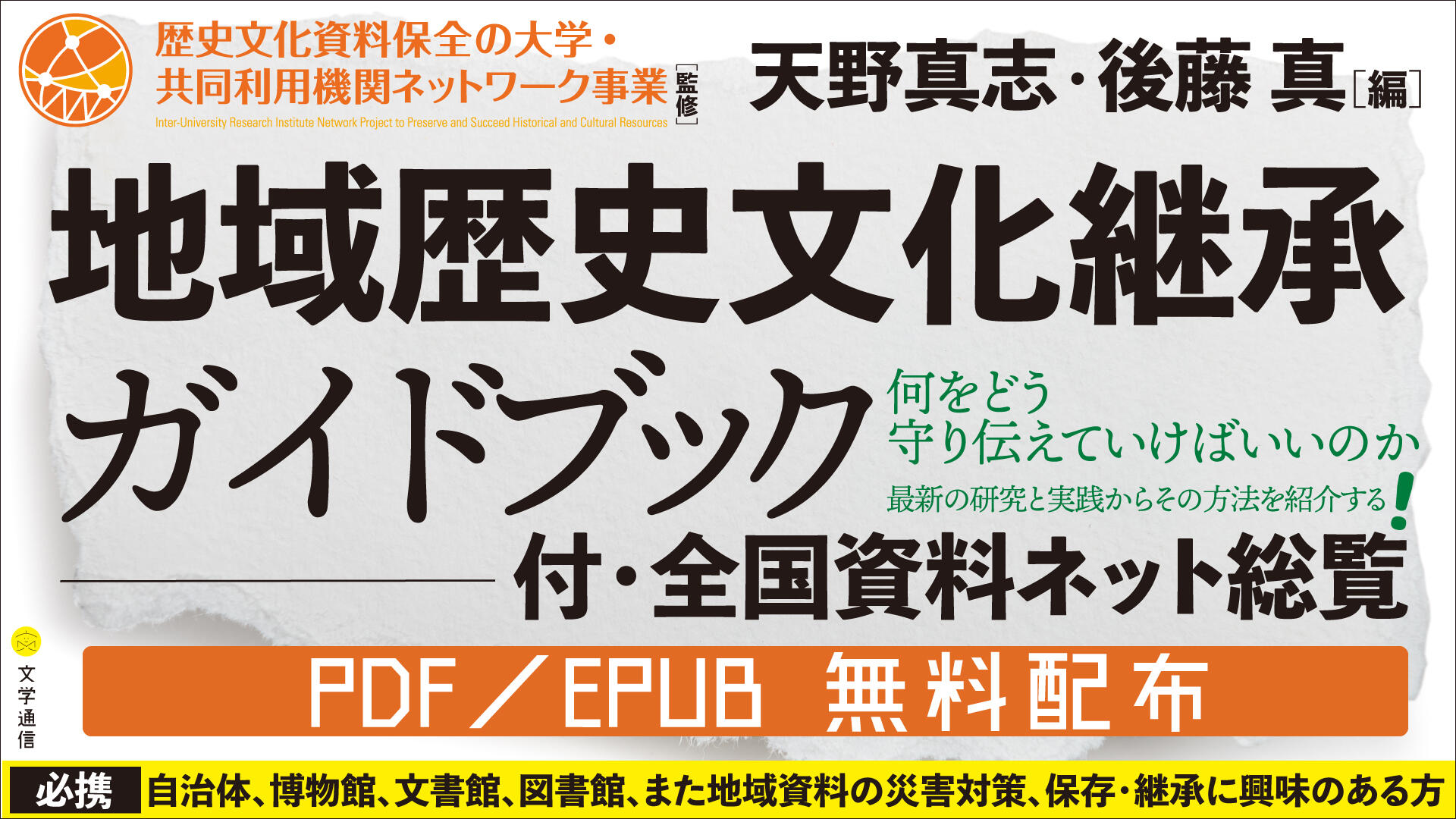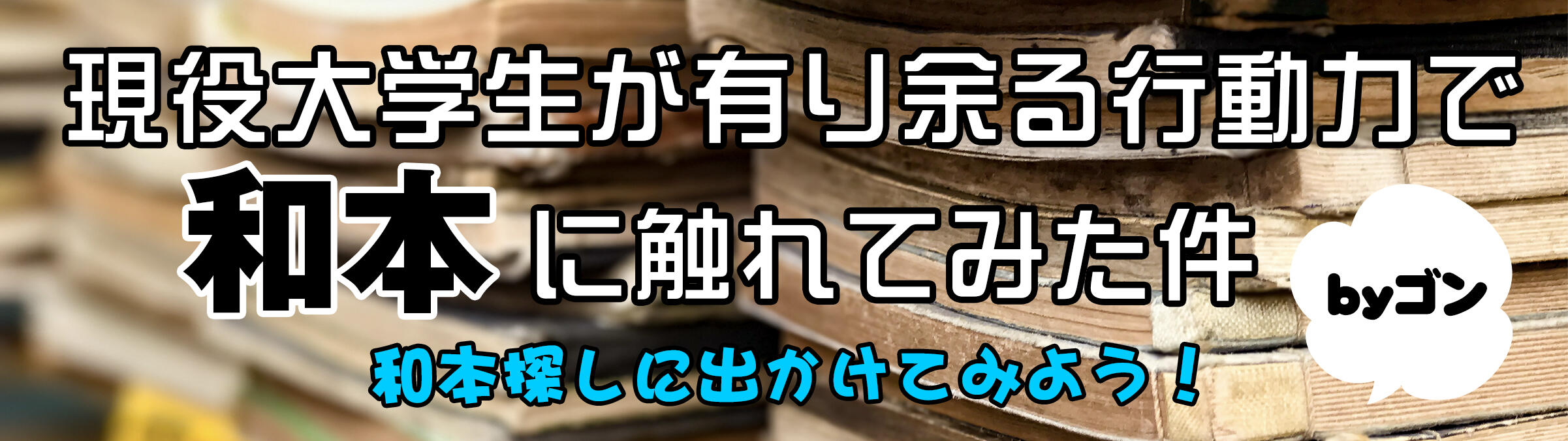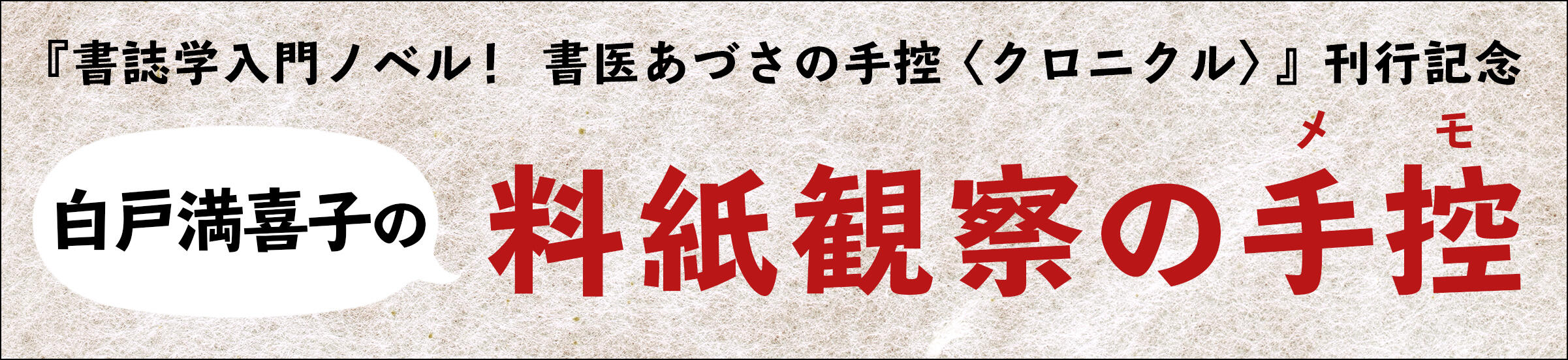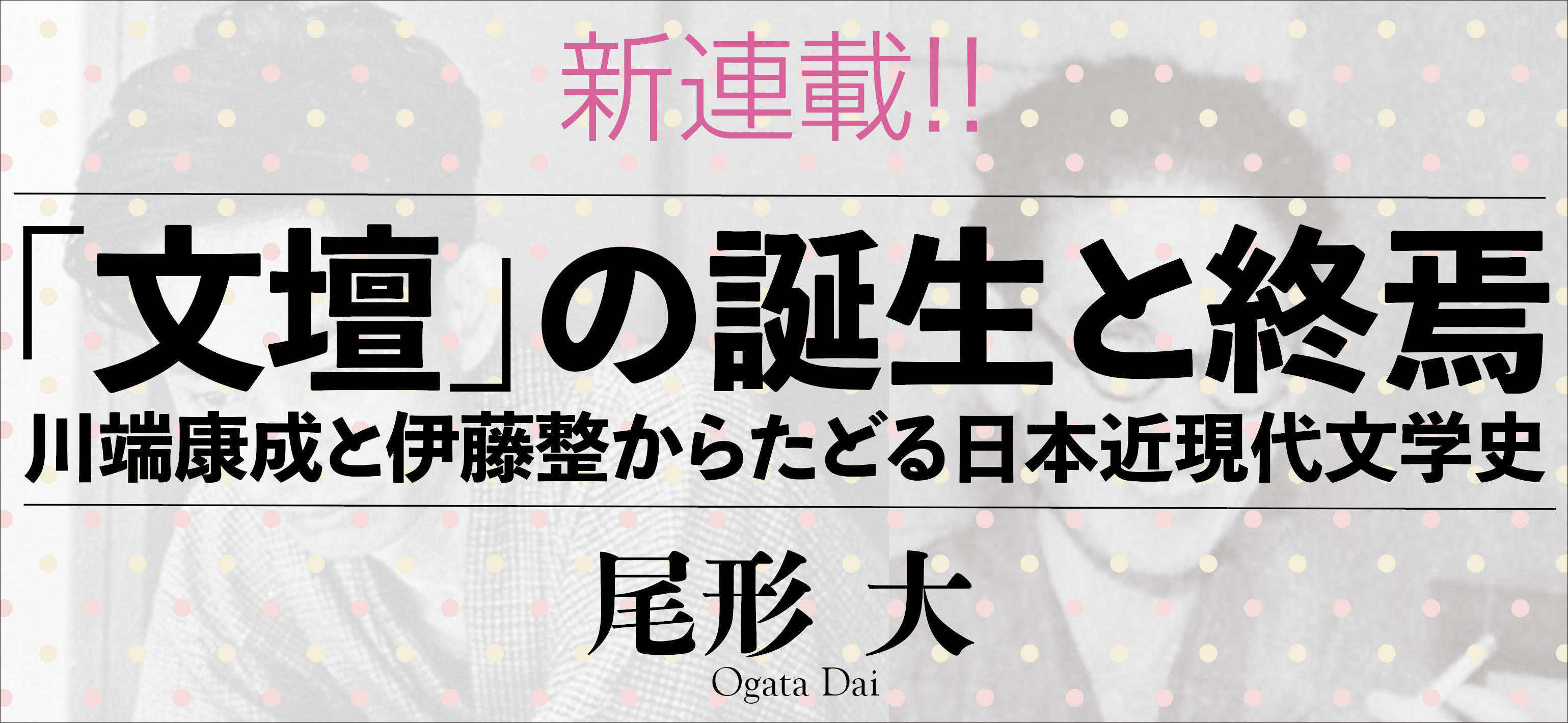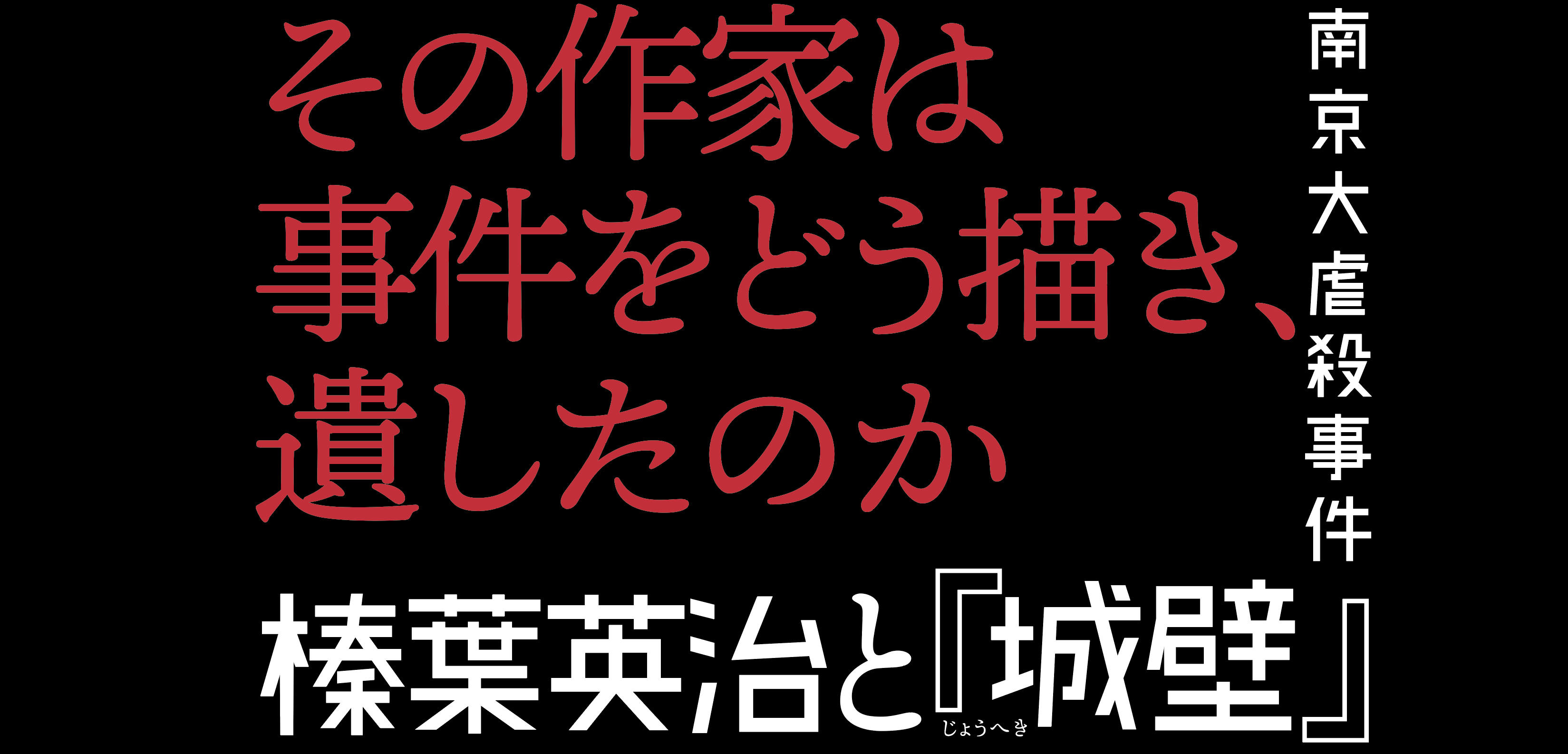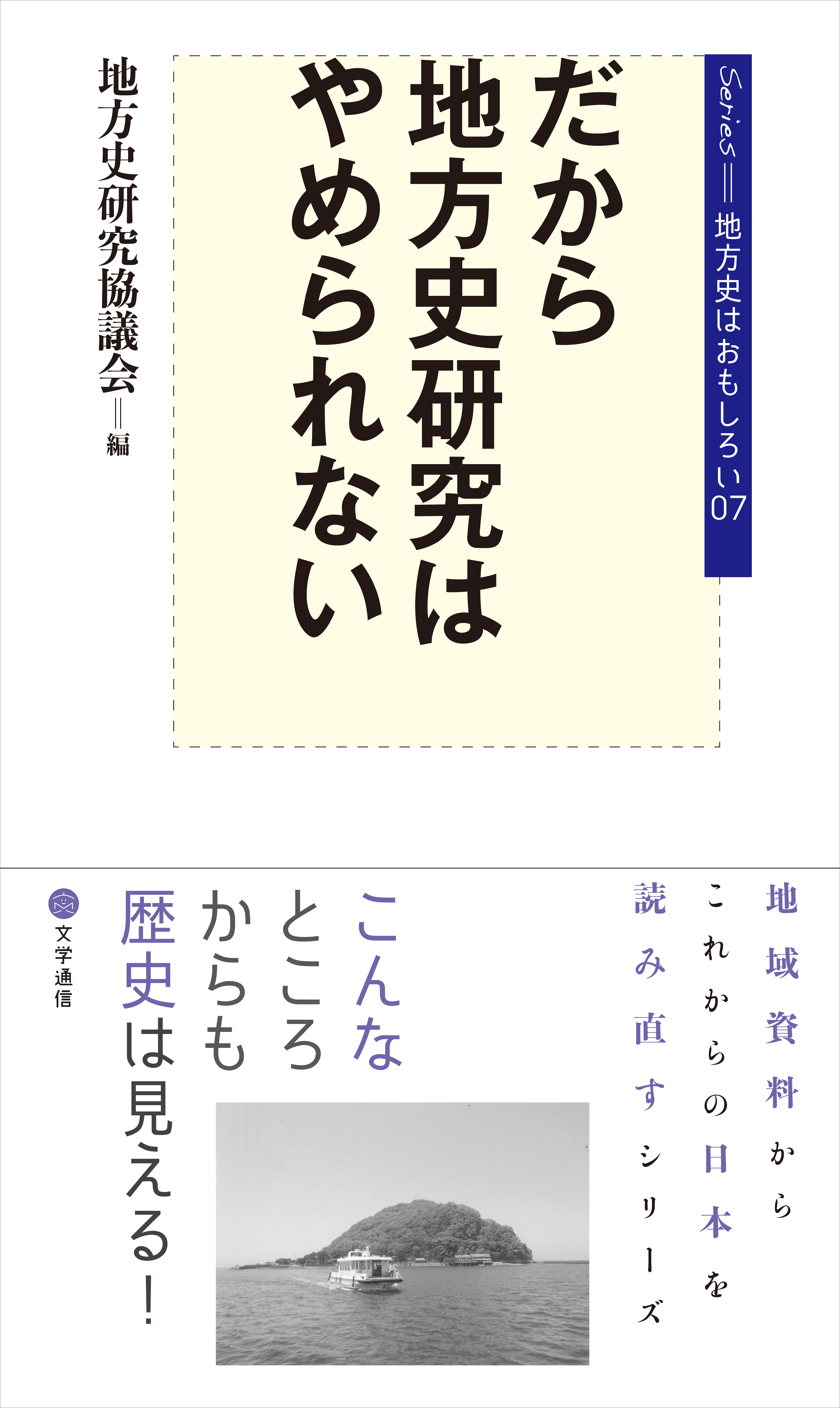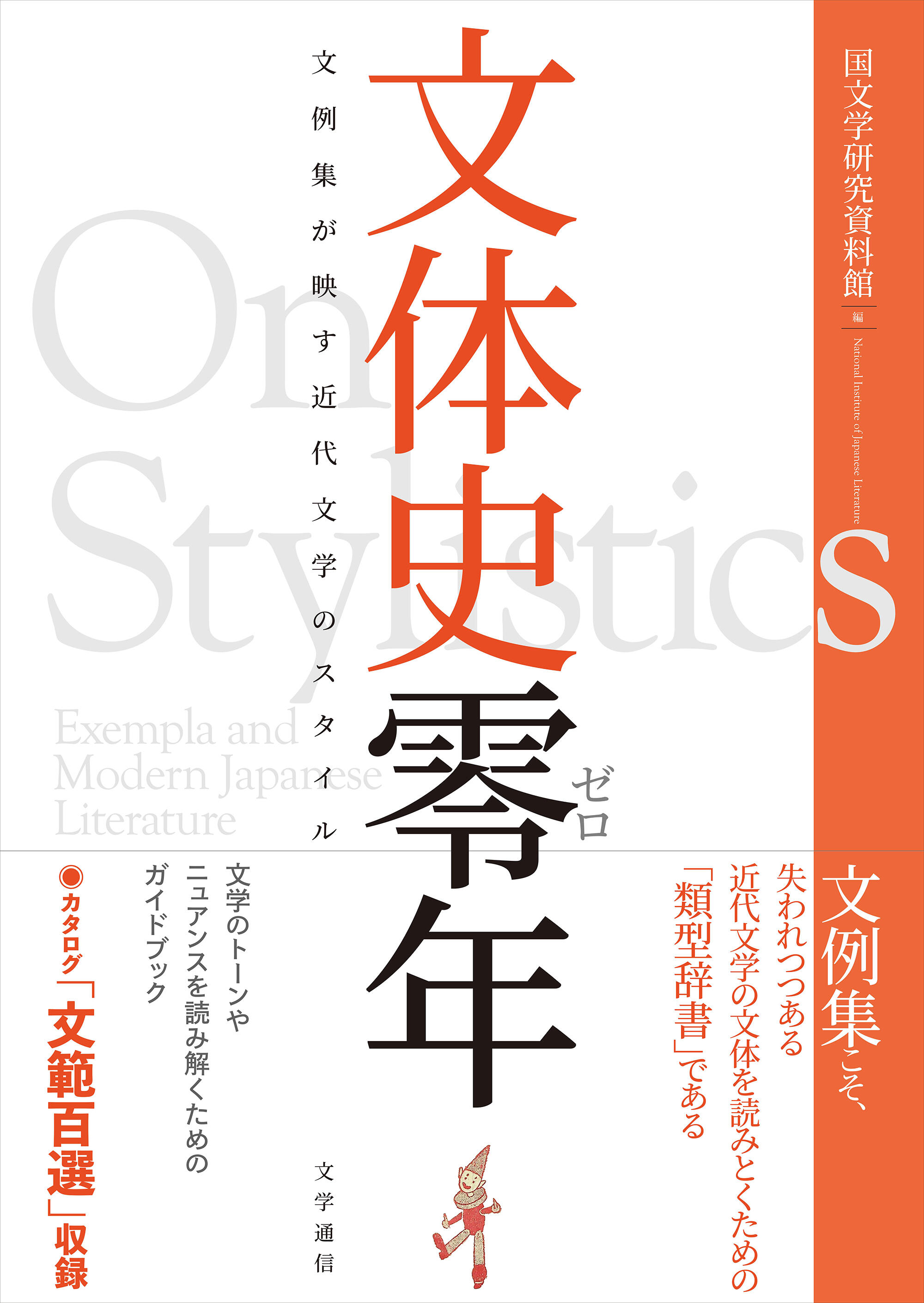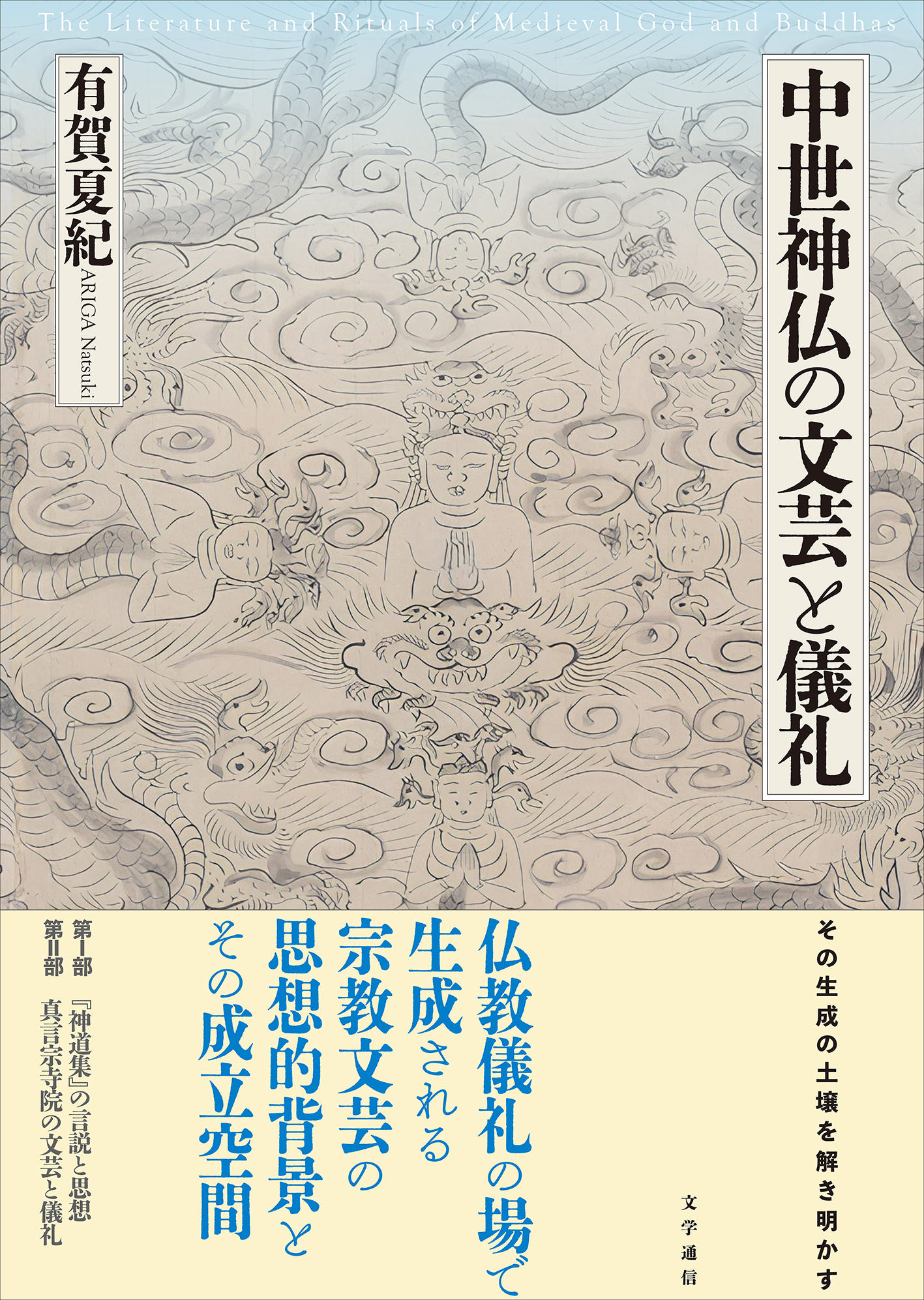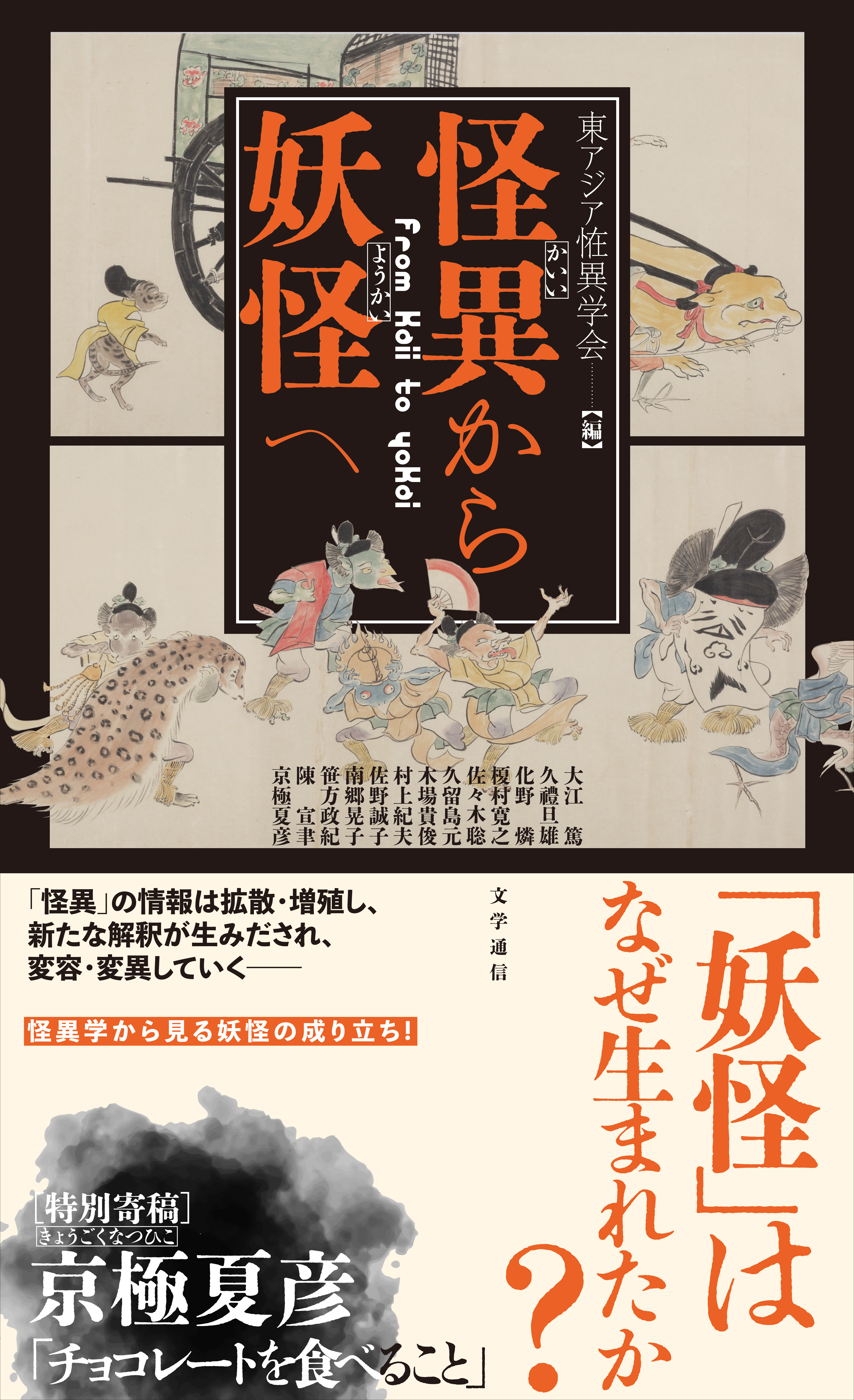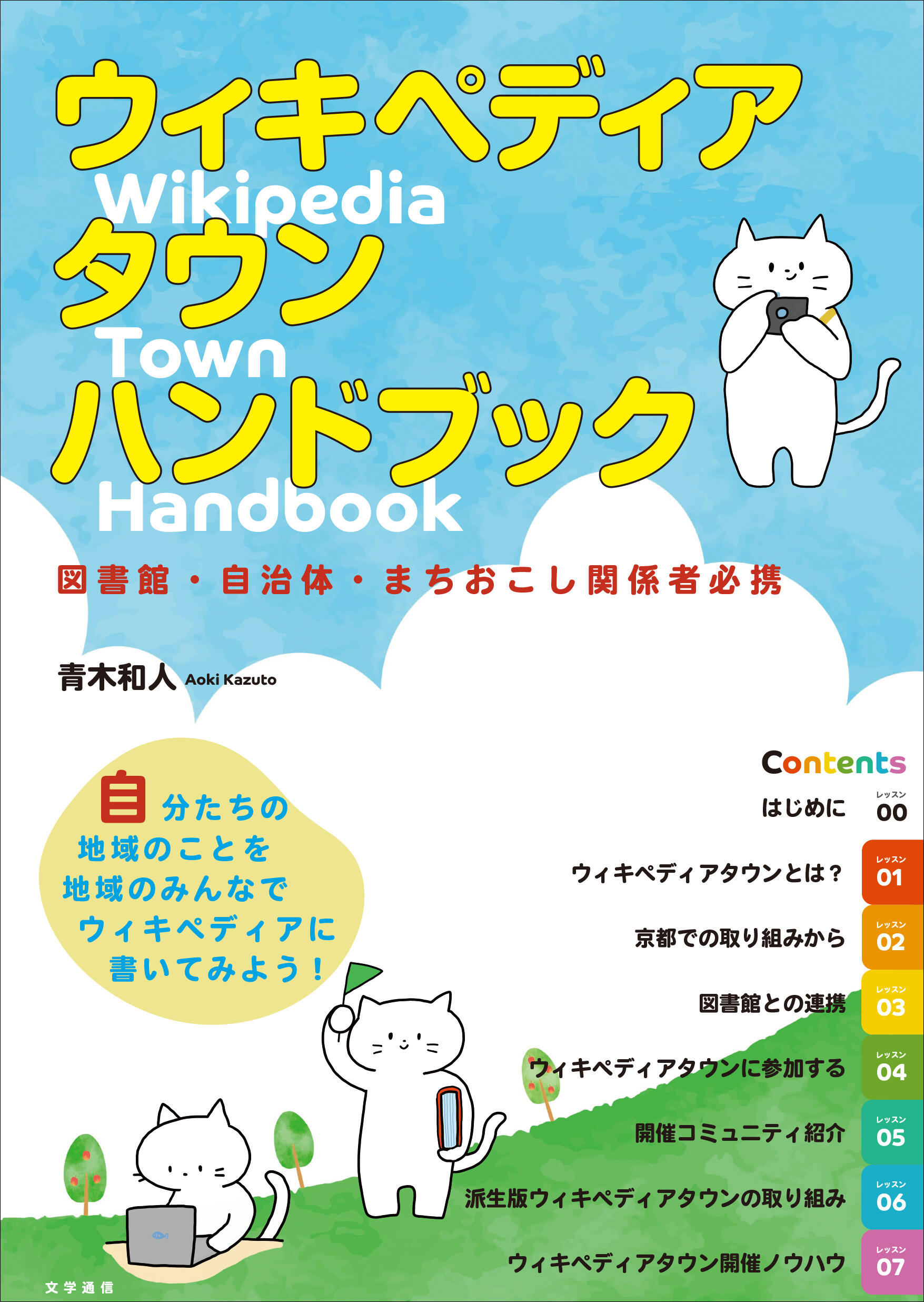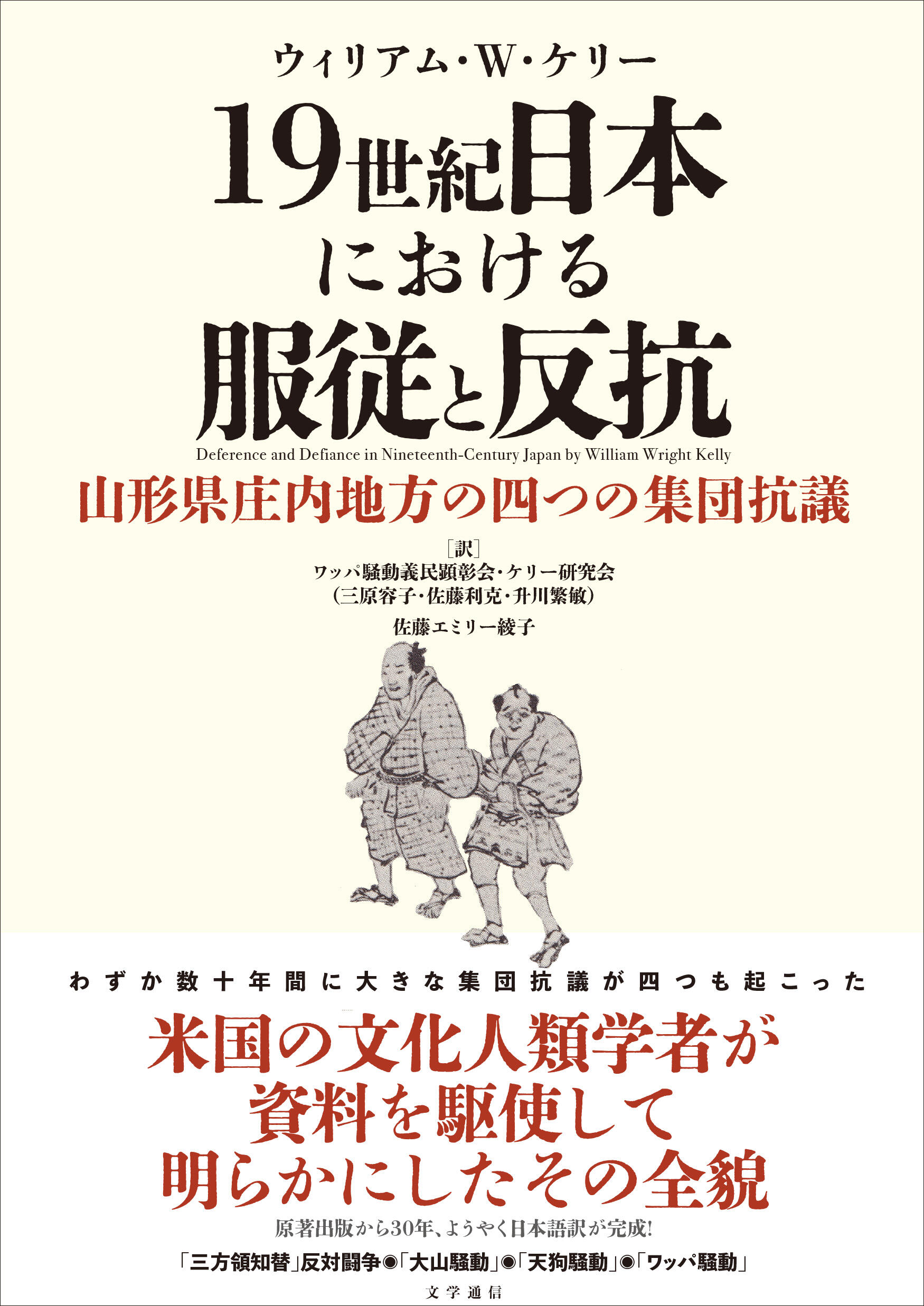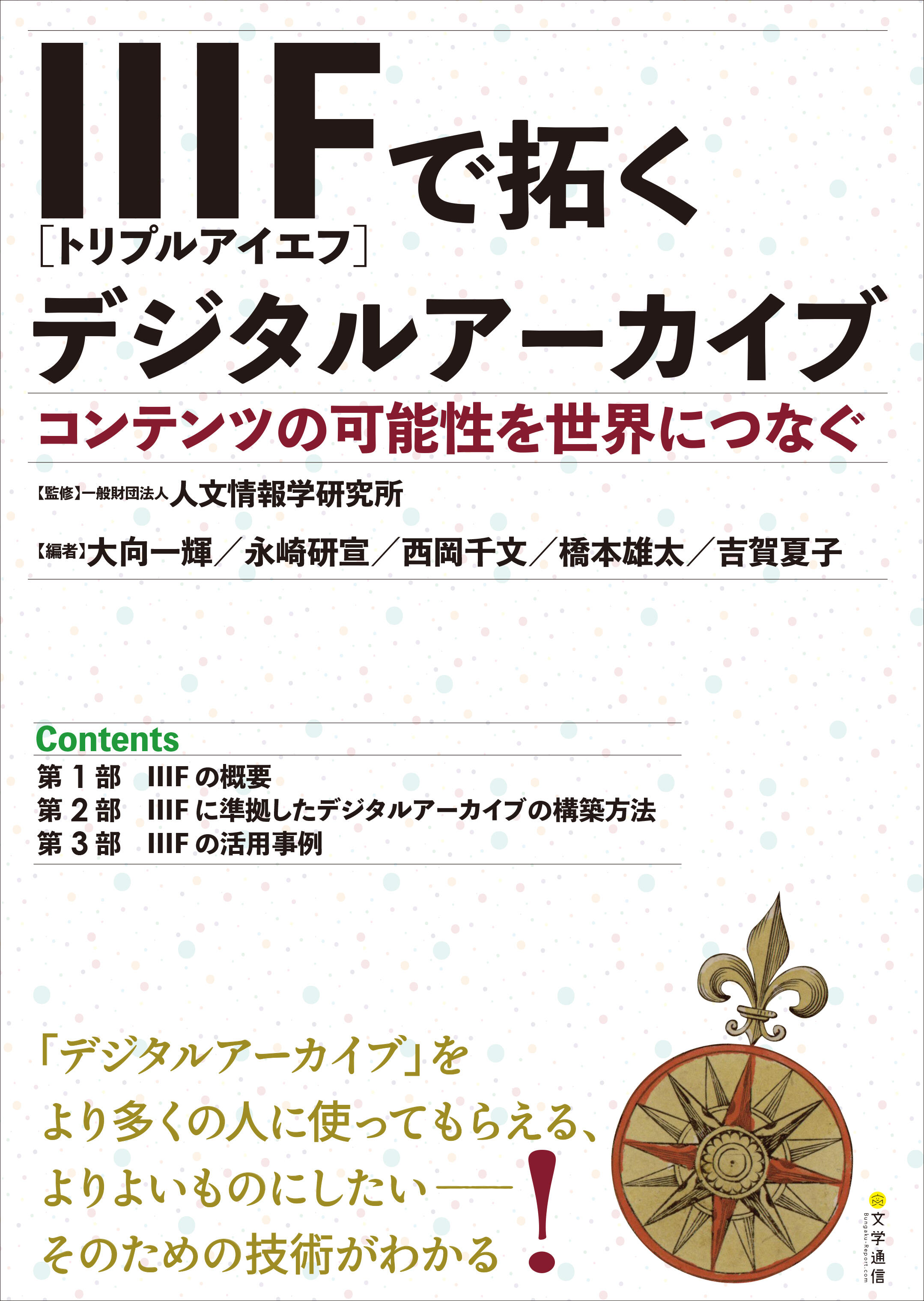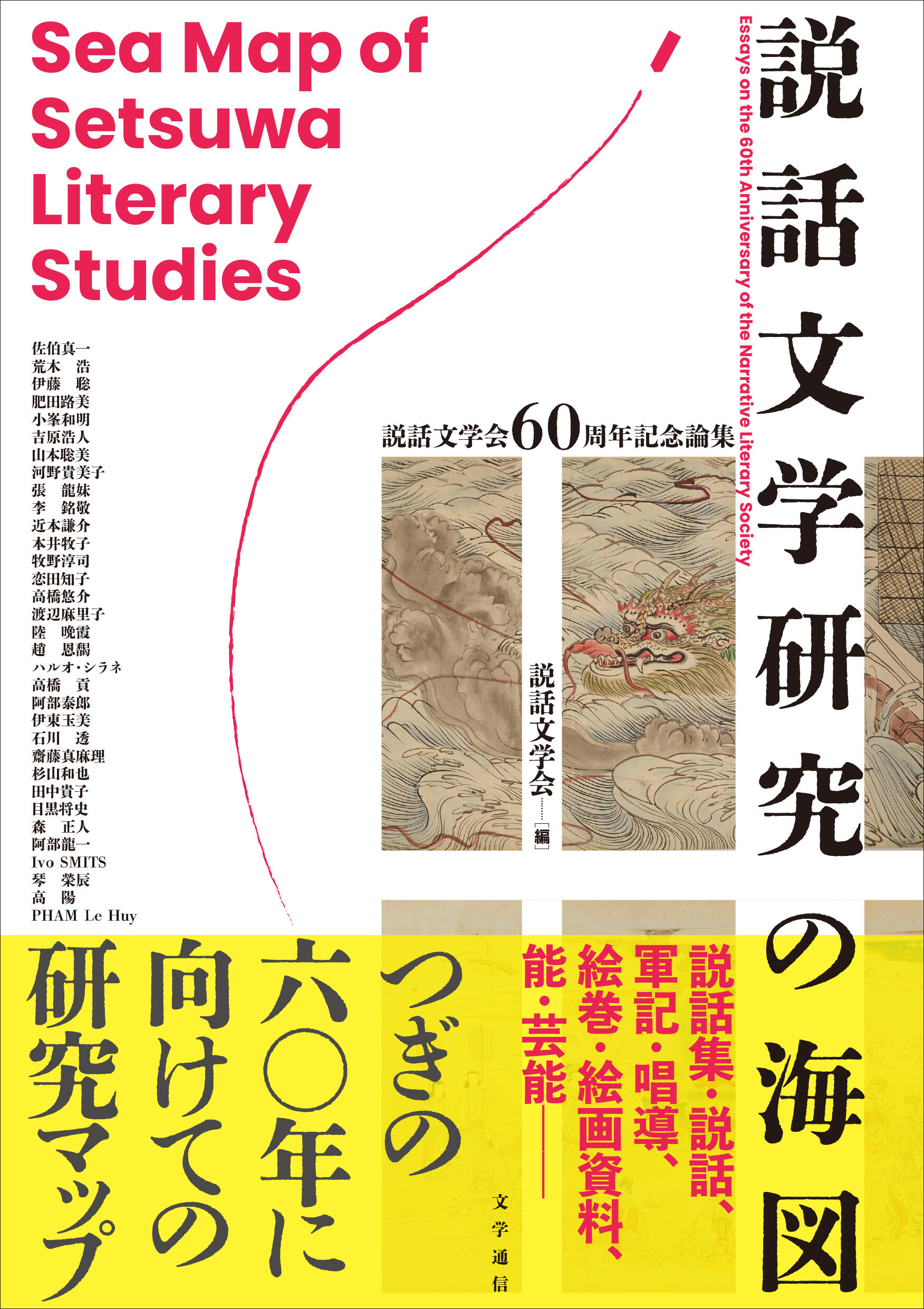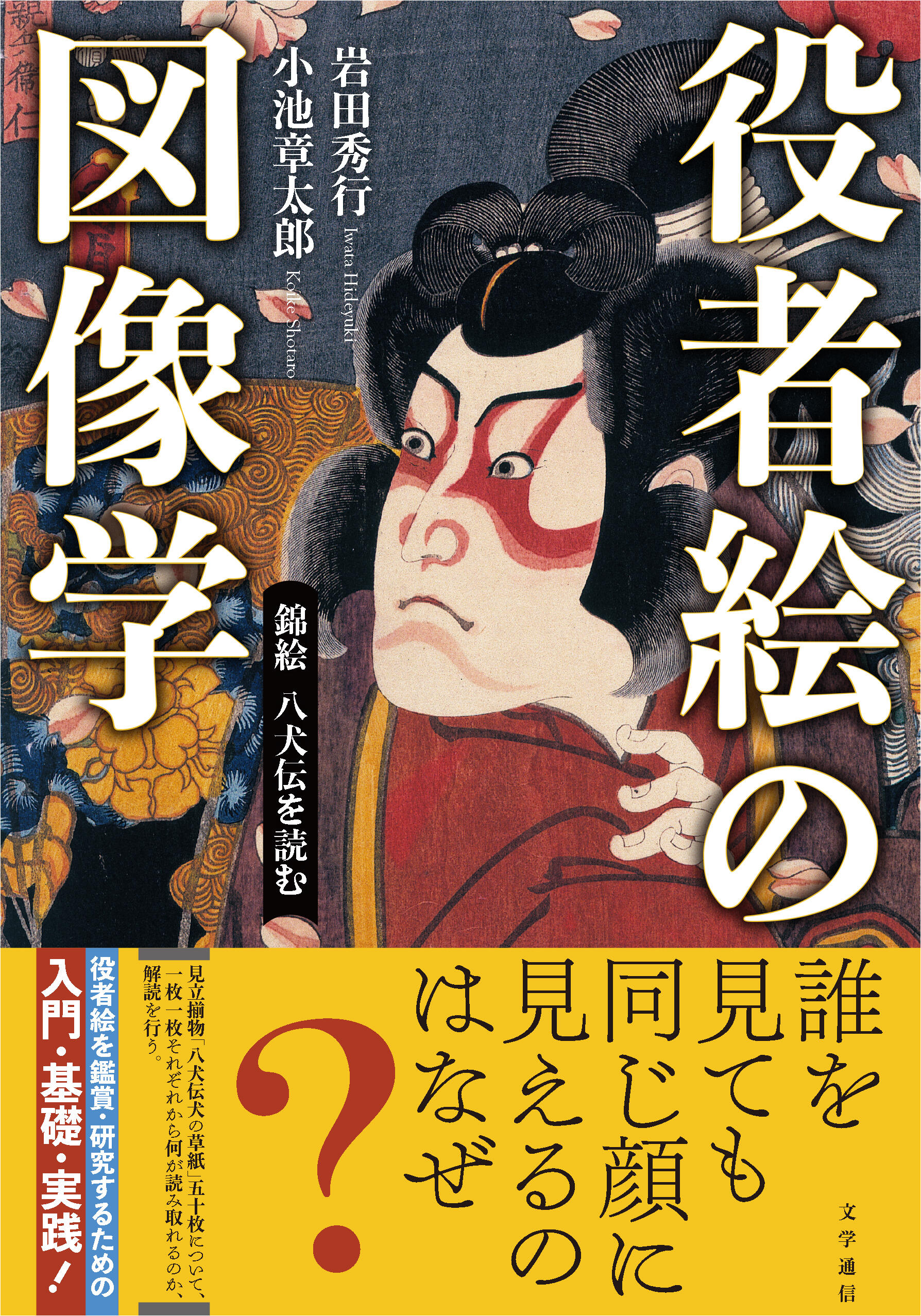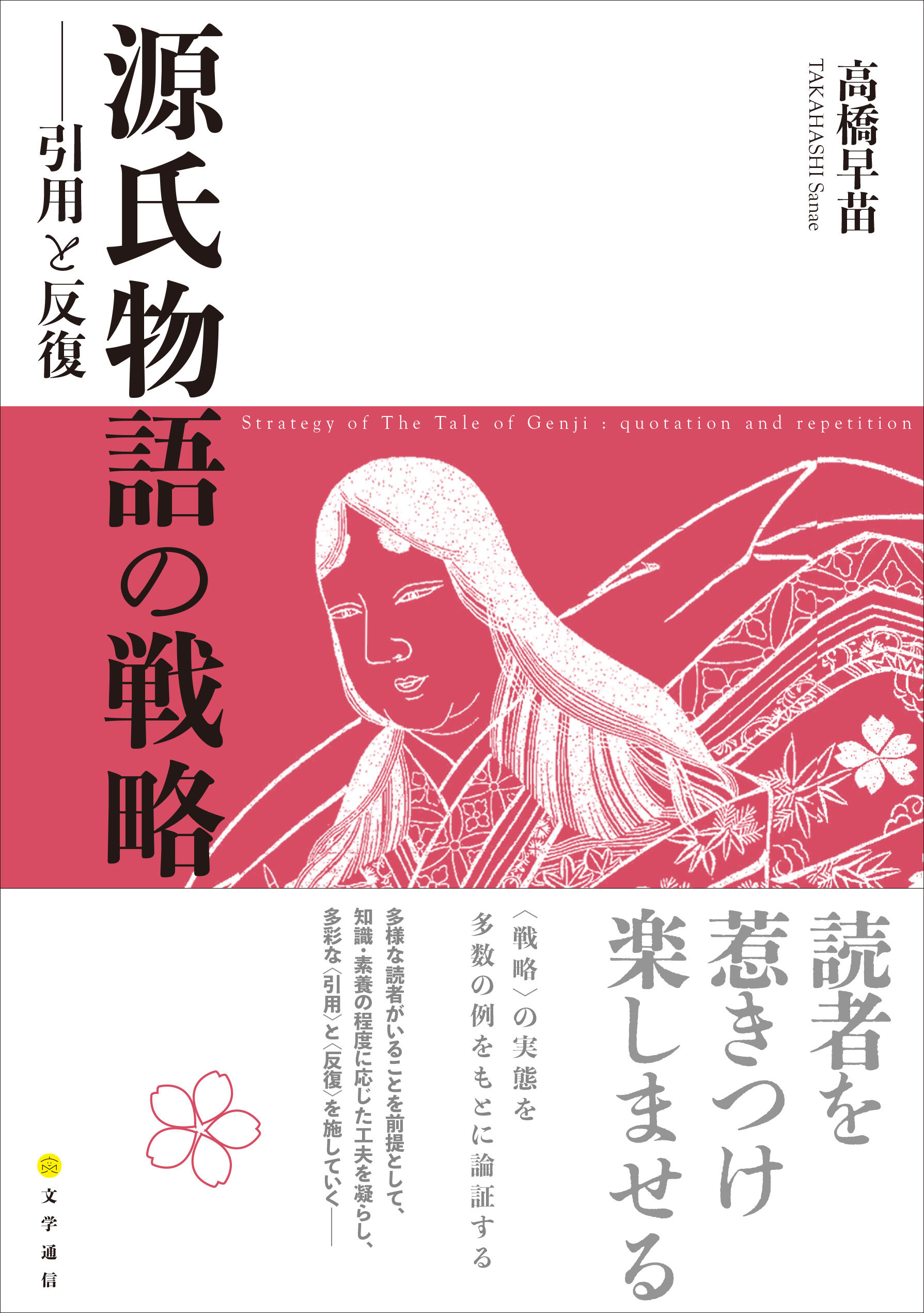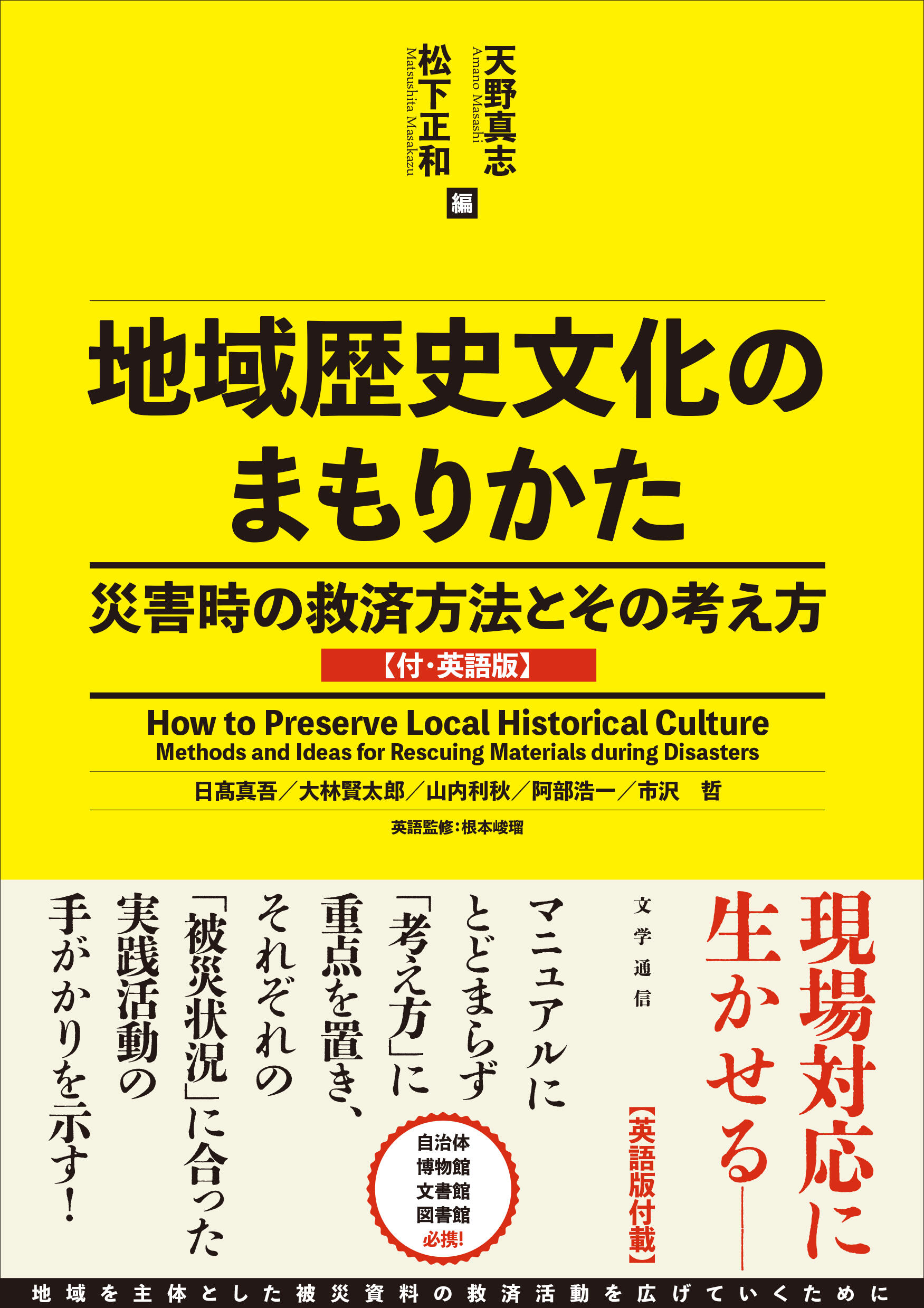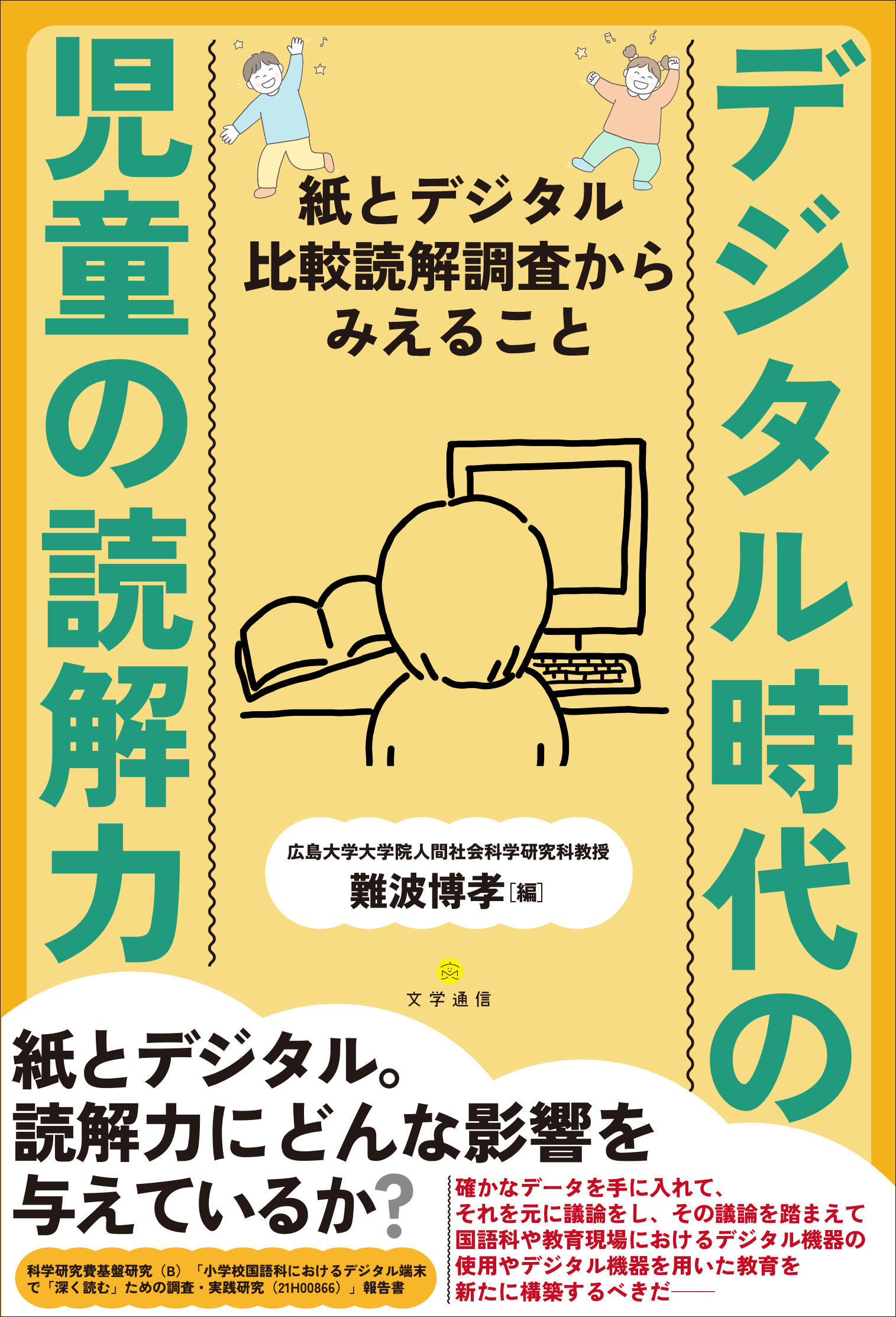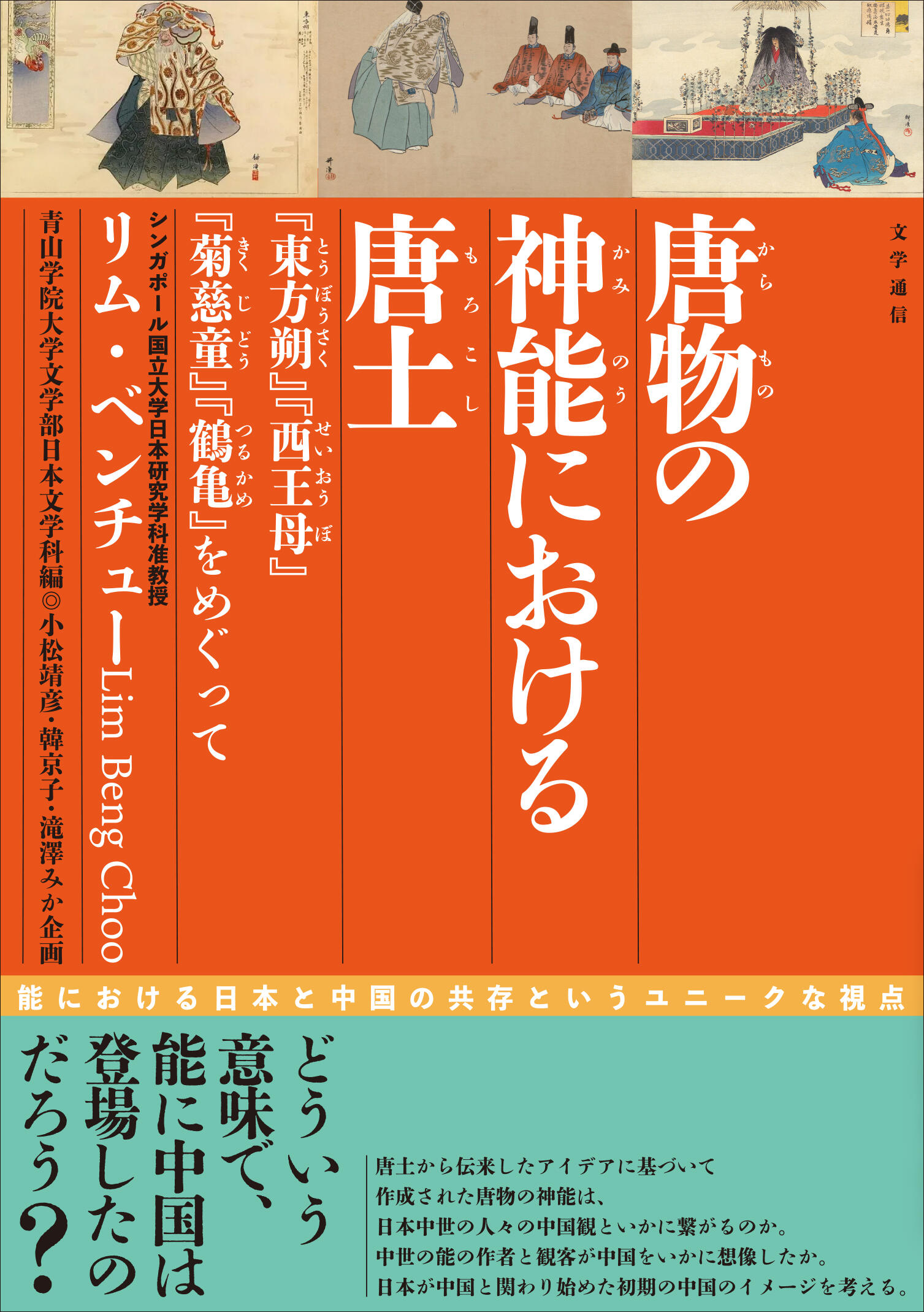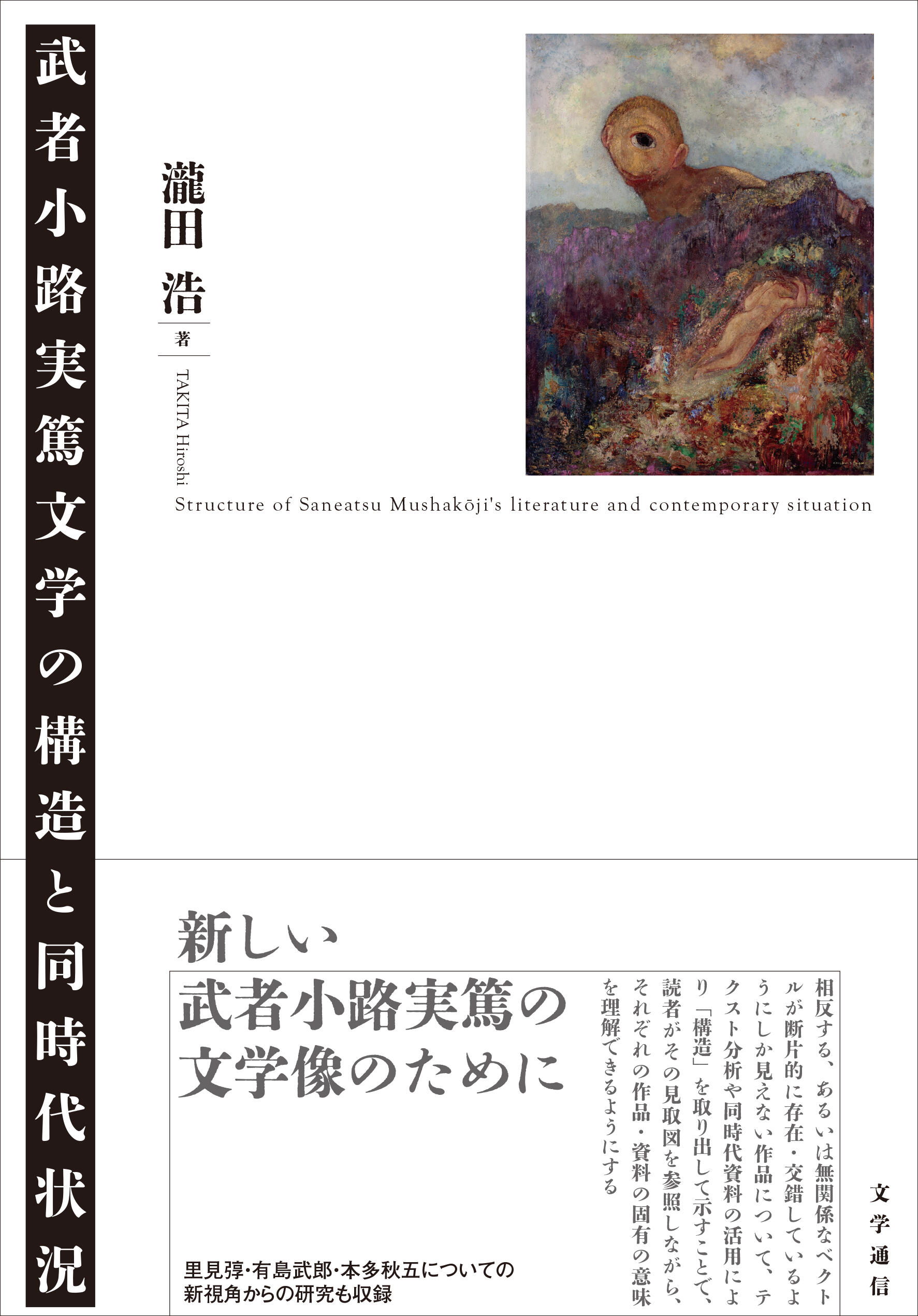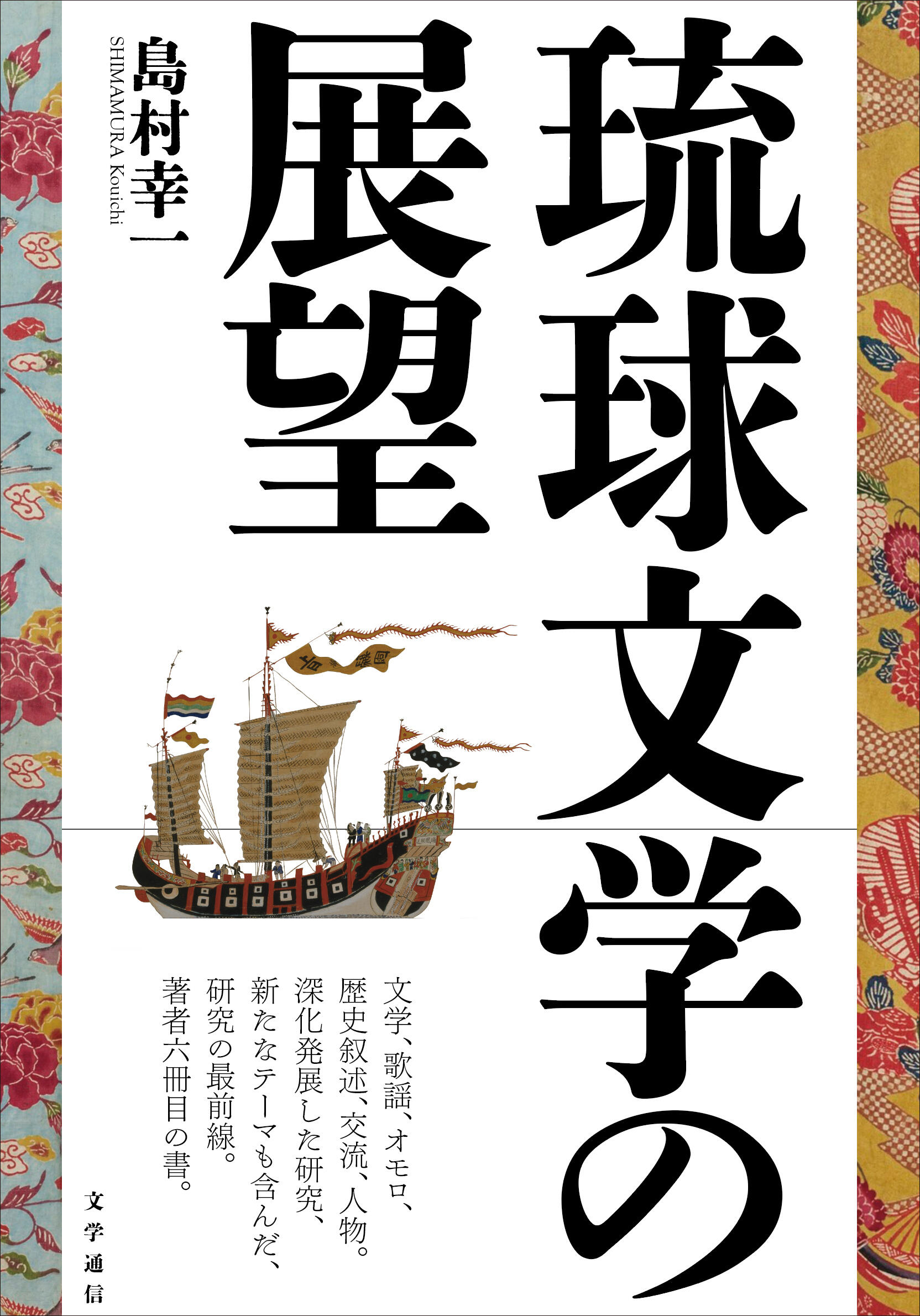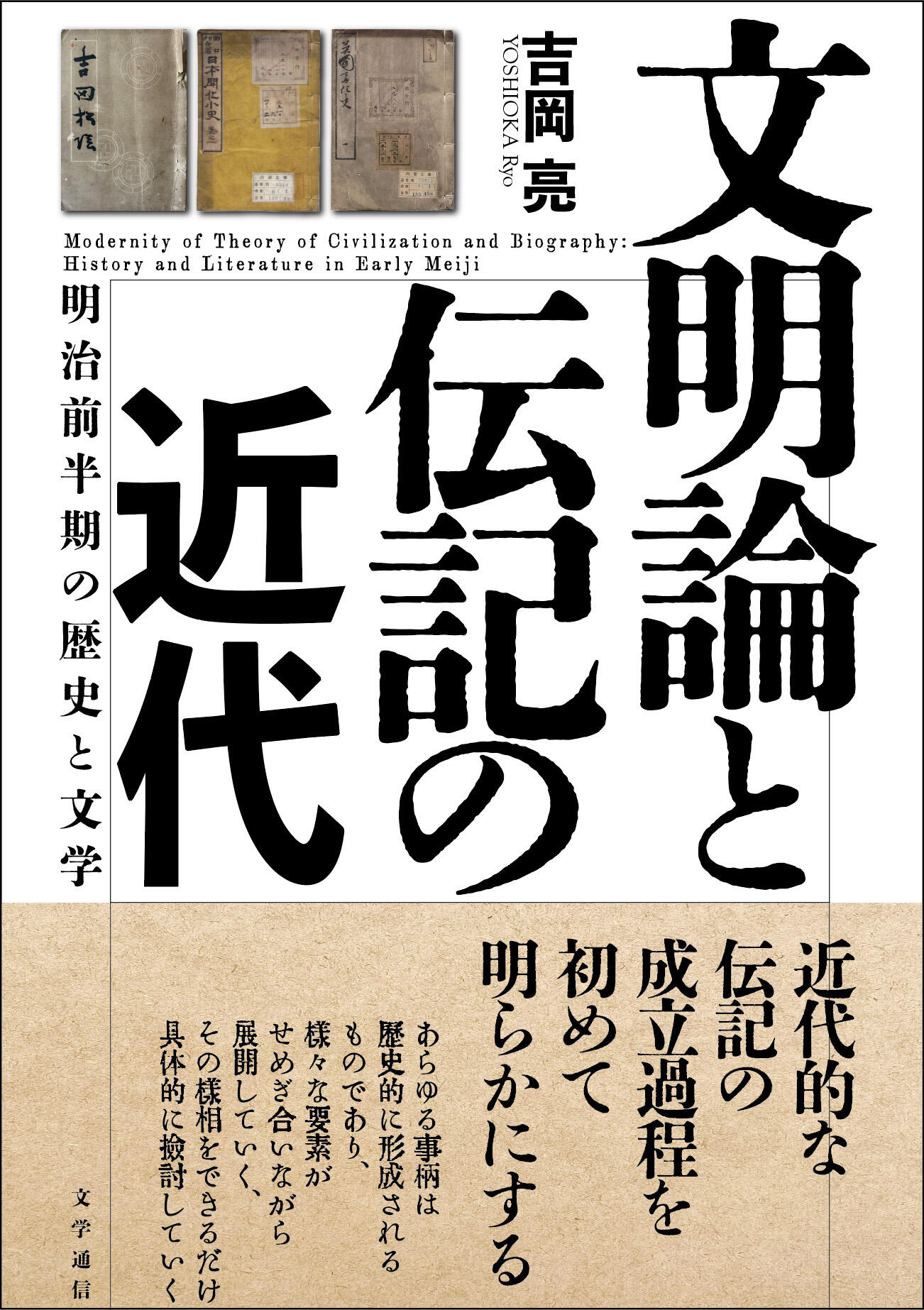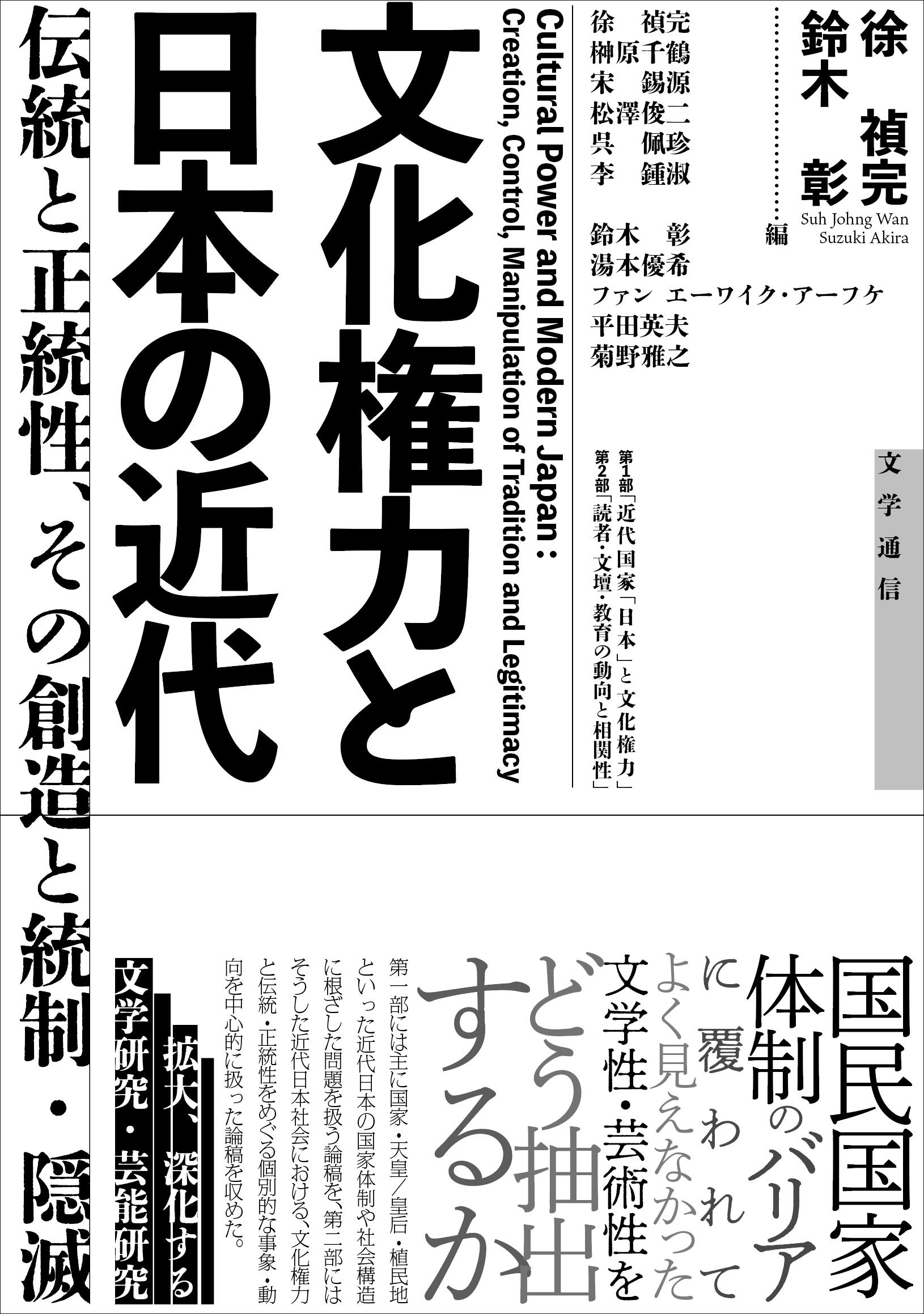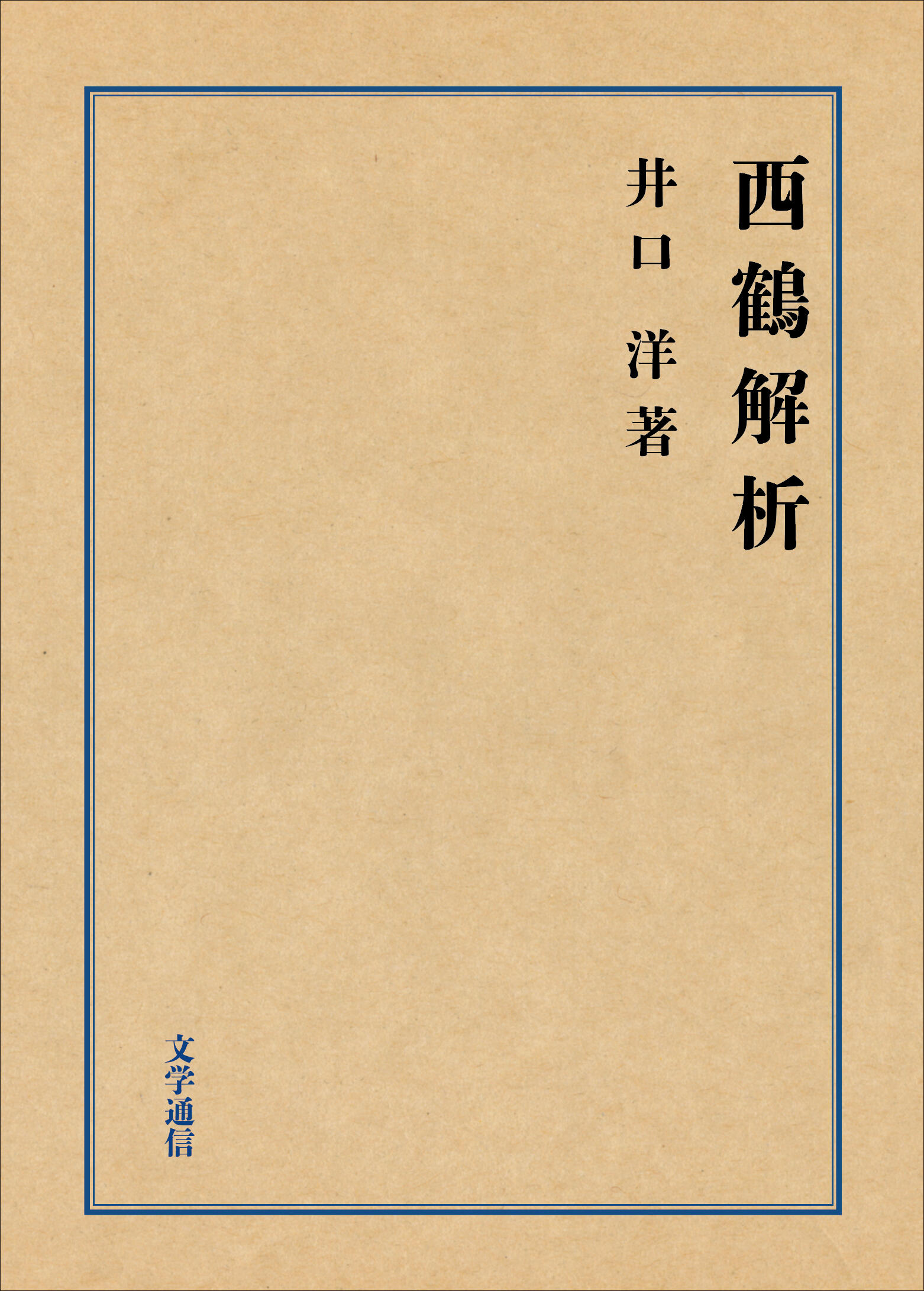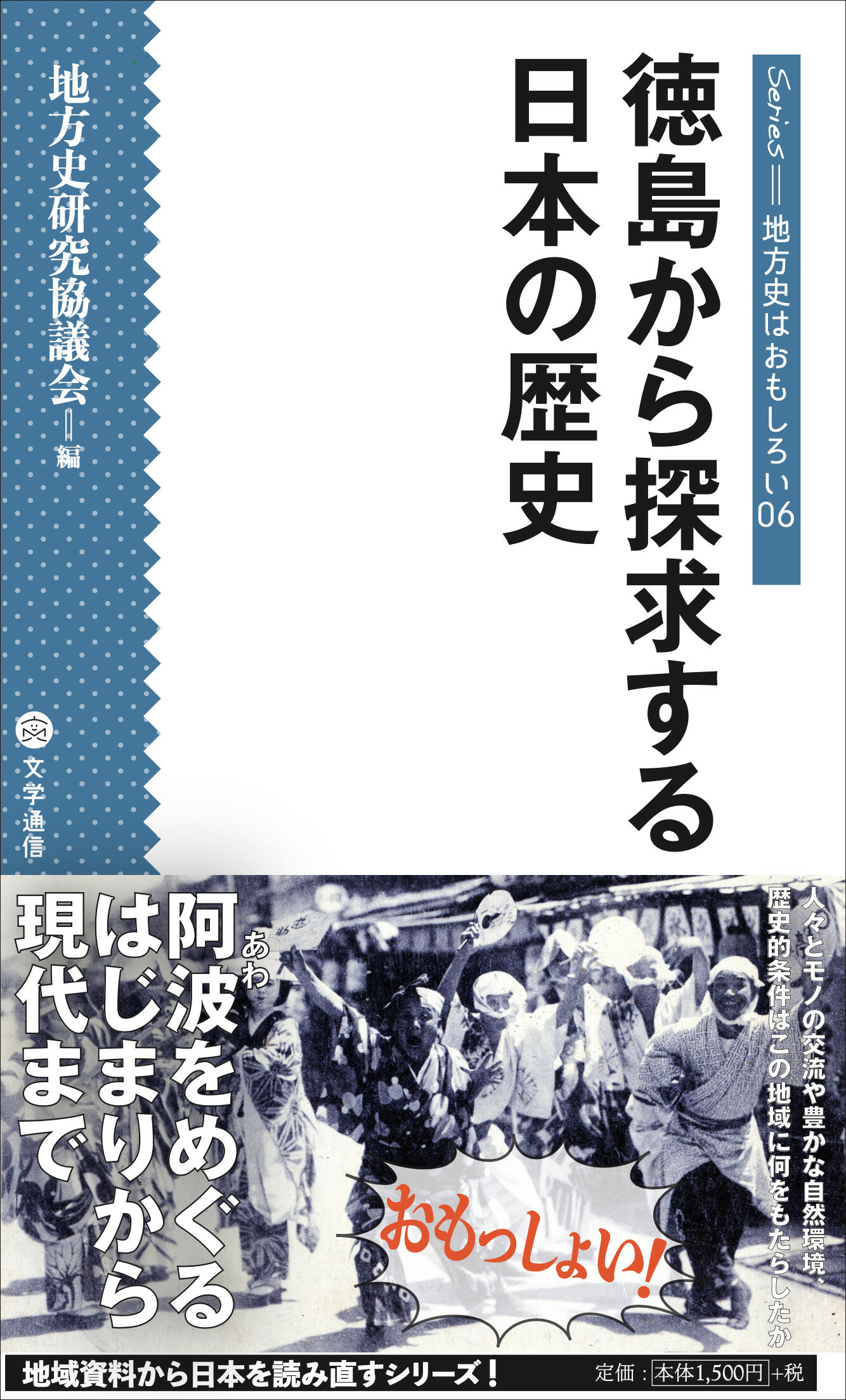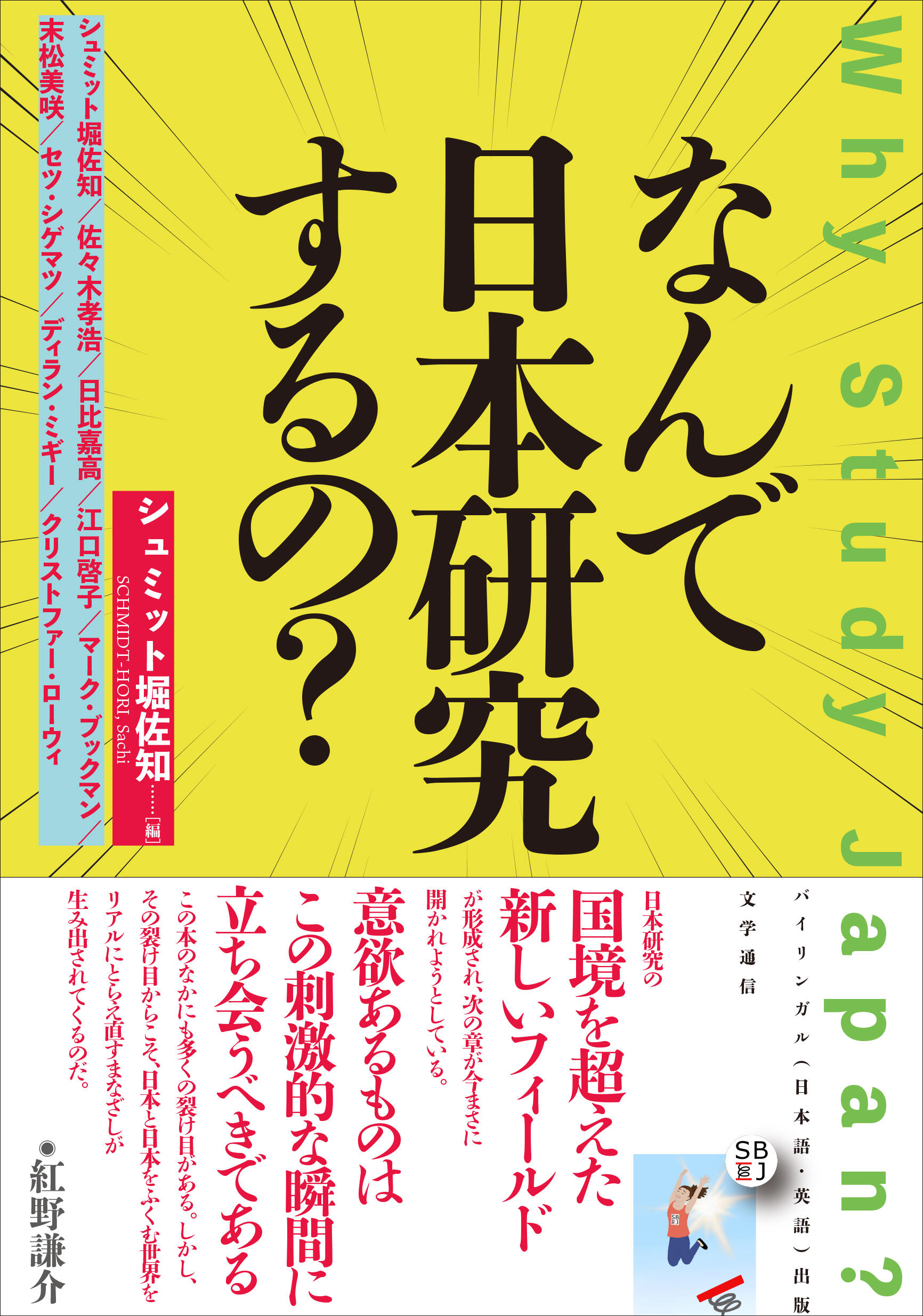飯倉洋一「未来に活かす古典―「古典は本当に必要なのか」論争の総括と展望」(校正中)(荒木浩編『古典の未来学(仮)』文学通信、2020.10刊に掲載予定)
※本テキストは、2020年2月7日に、明星大学日本文化学科公開シンポジウム「古典は本当に必要なのか」の司会者であった飯倉洋一氏に、文学通信で今秋刊行を予定している、荒木浩編『古典の未来学(仮)』にご寄稿いただいたものです。まだ校正中ですが、公開させていただくことにいたしました。なお、2020年6月6日にオンライン開催された、シンポジウム「高校に古典は本当に必要なのか」に関する追記も、末尾になされています(2020年6月6日追記)。
未来に活かす古典―「古典は本当に必要なのか」論争の総括と展望
飯倉洋一
1、はじめに
本稿は、2019年1月14日、明星大学で行われた「古典は本当に必要なのか」シンポジウムとその後のSNSを中心とする議論、さらには当シンポジウムの書籍版『古典は本当に必要なのか、否定論者と議論して本気で考えてみた。』(文学通信、2019年9月。SNS上でのハッシュタグに従い、以下シンポジウムを「こてほん」、書籍を『こてほん』と略す)の刊行とそれへの反響を踏まえ、筆者なりの総括と今後の展望を執筆するものである。古典を過去のものと考えるのではなく、未来において活かすものと考える立場からの試論である。論文というよりもエッセイに近い形式になっていることをあらかじめご了承されたい。なお通常筆者の論文では敬称をつけないが、本論の性格上、「氏」に統一した上で敬称を付すことにした。
まず、簡略に、「こてほん」の経緯を振り返っておく。はじまりは明星大学の勝又基氏によるシンポジウム開催の呼びかけである。
ここ数年、社会的に有用であることを主張しにくいことから、「文学部」や「古典」に対する風当たりが強まる中、それへの反撃として文学部の意義、古典の意義を再考するシンポジウムやワークショップが諸所で開催されたが、それらは多く「身内の怪気炎」(『こてほん』勝又の総括より)であった。本気で古典が不要だと主張する論者を招き、古典必要派と正面から議論する場が必要ではないか、その議論に耐えられない古典必要論は、本物とはいえないのではないか。勝又氏のシンポジウム開催趣旨は以上のようなことであった。どなたか不要派として登壇する方はいないか、 シンポジウムに集う人々のほとんどが古典必要派だと予想される中、登壇する勇気のある人はそういるはずがない。人選は難航していたようだ。勝又氏は打開策のひとつとして筆者に相談を持ちかけた。その時筆者の脳裏に思い浮かんだのが、SNS上で文学部教員のポスト軽減を主張していた某国立大学研究所教授の猿倉信彦氏である。猿倉氏は自ら推薦した、大学の先輩の前田賢一氏とタッグを組み、「悪役レスラー」役を引き受けて下さった。肯定派はやや紆余曲折があったが、和歌文学の渡部泰明氏と、近世文学の福田安典氏に決定した。筆者は不要派ではないが、両手を挙げての必要派でもないことから、司会を務めることになった。
結果から言えば、不要派は手強いどころか、考えられうる最強の論客コンビだった。不要派は、シンポジウムに1ヶ月以上先だって発表タイトルを知らせてきた。猿倉氏のそれは「現代を生きるのに必要度の低い教養である古典を高校生に教えるのは即刻やめるべき」という挑発的なもの。 不要派はさらに、当日の主張の要旨をも数日前に関係者に提示し、必要派もこれに倣わざるを得なかった。不要派は議論のイニシアチブをシンポジウム開催以前に握っていたのである。
シンポジウム当日に行われた議論の詳細については『こてほん』に譲り、割愛する。「ガチ対決」を謳った以上、ひとつの論点をめぐるディベートであるべきだったが、実際はそうならなかった。不要派は、古典を学ぶ必要性は低く、GDPに貢献するところも少ない、むしろポリティカルコレクトネスの観点からは有害であるとした。学ぶとしても現代語訳でよく、国語ではなく選択科目の芸術で教えればよいとした。不要派の論理に対して、必要派は古典の素晴らしさ、有益性を唱えて、正面対決を避けた形に見えた。ディベートとしては不要派の勝利(不戦勝?)という印象となったことは否めない。シンポジウム後のアンケートでは、古典不要派支持は議論以前よりもわずかに増えた。しかし、大勢からみると参加者たちの多くは、古典必要派のままだった。ここから導かれることは、「こてほん」の議論によって、古典必要派の多くは、不要派の論理に同調することはなかったが、上手く反論することもできなかったということである。
本稿は古典の高校必修の是非を論ずることが目的ではない。不要派の高校必修不要の論理を筆者なりに検証することで、古文漢文学習の意味を再考し、未来における古典の活用を提言するものである。
2、古典不要派の主張
「こてほん」は、不要派にとっては、古典(古文・漢文)を必修から外し、理系の大学入試科目からも古典を外すという彼らの所謂「世直し」「文革」実現への橋頭堡であったらしい。高校生に、社会でほとんど使うことのない古文・漢文を学ばせる時間を、社会においては明らかに古典よりも必要度の高い論理国語や英語の学習に割くべきであるというのが彼らの主張である。その主張に反論したり、対案を示したりするのが本稿の目的ではないが、不要派の主張と論拠については、一応相対化しておきたい。
不要派の議論の要点は四つある。
1 国語力の中で大切で、かつ社会において求められている能力は、説明書や報告書の読み書き能力や、プレゼンテーション力・ディベート力である。古典(古語・古文・漢文)の知識や読解力は、現代においても未来において必要度が低く、教育設計においても優先度を低くすべきである。実際、現代における日常生活レベルの国語が使えないレベルの高校生も少なくない。こういう学生に古典を教えるよりも、最低レベルの現代国語をきちんと使えるようにする方が大事だろう。現在必修として割かれている古典の学習の時間は、論理国語に割り当てるべきである。
2 古文・漢文は、現代において読む必要度は低く、書く必要度はそれ以上に低いので、国語の中で学ぶべきではない。学ぶとしたら芸術の一科目として残せばよい。嫌いな人はやる必要がなく、好きな人は存分にやれるのだから、嫌いな人にとっても好きな人にとっても都合がよい。芸術の一科目としての古典では、古典を鑑賞したり、短歌や俳句を創作としてやったりすればよい。
3 古典が大事だとしたらそれは内容である。だから、学ぶとしても現代語訳で学べば十分である。我々は西洋の古典を翻訳で学んでいる。ニュートンの『プリンキピア』はラテン語で学ばないと理解不能であろうか?英語や翻訳で読めば理解できるだろう。日本の古典も、その内容を理解するためであれば、現代語訳で読めば十分だろう。
4 古典には古い道徳観や差別意識が見られ、ポリティカルコレクトネスの観点から見て有害である。現代において、このようなものは排除すべきである。ちびくろサンボが発禁になったように、古い道徳観や差別意識が見られる源氏物語も発禁にすべきである。古い道徳観や差別意識を刷り込むようなテキストを必修科目の教科書に掲載するのはやめるべきである。
3、古典不要派の論理1 優先度
不要派が古典必修を不要とする論拠は、実社会において古典を学ぶ優先度が低いということである。不要派は「優先度」というキーワードをよく使う。「優先度」というのは、複数のものを比較して、どちらがより重要かを相対的に判断するものである。実際、小中高においては、教科・科目ごとの「優先度」を見定めて、授業時間を配分している。この配分を見直すというのであれば、「優先度」という考え方は有効である。同じ必修の中で、古典の時間を減らし、現代文や英語の時間をその分増やせというのであれば「優先度」の議論になる。
現行の高等学校教育の必修科目のうちで、「古典」関係科目が「英語」関係科目よりも多く割り当てられている事例はほとんどないだろう。すでに「優先度」においては、英語が古典より「優先度」が高いという認識で高等学校教育は設計されているのである。必修にするか、必修から外すかという議論は、「優先度」の議論ではなく、教育制度設計の根幹に関わる議論である。必修から選択へ、あるいはその逆を、文科省の学習指導要領のレベルで実現するには、教育制度の設計を根本的に変更しなければならない。必修と選択は「優先度」で議論すべきではなく、「必修であるべきか否か」で議論すべきである。少なくとも、従来の指導要領においてはもちろん、新しい指導要領においても、「言語文化」という必修科目の中で、上代から近現代にいたる伝統的言語文化(すなわち古典)を学ぶものとされている。不要派が古典を否定するのであれば、伝統的な言語文化の理解は高校教育には不要であると言う議論をすべきで、「必要であっても優先度は低い」という議論にすべきではない。実際不要派の中にも温度差があって、「優先度において(現代文や英語より)低い」という認識が彼らの中での合意点だということになるのだろう。
また、「実社会において古典(古文・漢文)の必要性はほとんどない」という論拠もどうであろうか。この論拠については二つの観点から疑問がある。
第一にそもそも、高校教育とは、「実社会において有用なこと」のみを学ぶものなのであろうか。「現代文は社会に有用だが古文漢文は不要」、「論理国語は有用だが文学国語は不要」と古典不要派は言う。しかし、文科省の新指導要領を繙くと、必修科目である「現代の国語」は「実社会において必要な国語の知識や技能を身につける」ための科目であり、古典を含む「言語文化」は「生涯にわたる社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに,我が国の言語文化に対する理解を深める」科目である。前者が主として学業を終えたあとの仕事や家庭生活で必須の知識技能を想定しているのに対し、後者は大学(大学院)での学びやリタイア後やビジネスや家事以外での社会生活での必要性が想定されているのではないか。大学教育は、高校教育を受けている前提で設計されている。たとえば大学の教養科目を学ぶために必要な知識や技能を大学生は持っていなければならない。大学の理系学部の一部が、古文・漢文を受験科目から外していないのも、入学してきた学生が主として文系教養科目を受けるために必要な知識・技能のひとつに、古文・漢文の読解力と見ているからだと考えられよう。古典が不要であるかどうかは、総合大学であれば、理系学部だけの問題ではなく、全学的な判断にならざるを得ない。また、ビジネス以外での生涯学習や、地域振興・文化振興への参画において、古文・漢文読解力が役に立つ場面はいくらでも想定できる。
第二に、実社会においても、古文漢文の読解力を必要とする場面は、さまざまにありうる。行政やビジネスや研究において、好むと好まざるとに関わらず戦前の文書を読まざるを得ない場面は、非常に少ないとは言えないだろう。文化行政に関われば歴史的文書と向き合うことは当たり前であるし、そのほとんどが文語による文章である70年以上前の文書を読む必要性は、ビジネスの世界でも起こりうる。文系の研究の世界で、日本における研究史を繙こうとすれば古文漢文力がないことは致命的であるし、多くの分野で古文漢文の読解力を必要とする文献が研究対象となりうるのである。これは文系にとどまらない。理系でも古文漢文が必要なことがある。地震研究は、数十年・数百年単位のデータを分析するが、その際古文書は貴重な資料である。実際、現在多くの地震学者が古文書と格闘し、古文漢文どころかくずし字を読むリテラシーを身につけている。天文学や生物学・医学でも、古いデータが必要な時、古文書を読まなければはじまらないことがあるだろう。さらに、外交の場においても、領土問題が、古文献をエビデンスとして議論されることがある。政治は、歴史や文化と切り離しては運用ができない。外交政治を左右する生の資料が出た時に、政治家・官僚はその資料を読み解く力を持っていてほしいものである。
4、古典不要派の論理 2 芸術科目
不要派の主張のひとつは、古典は、高校生が全員学ぶ必要のないもので、芸術科目のひとつとして選択科目にすればよいというものである。この主張は優先度の議論とは次元が違う。古典は表現芸術であり、美術や音楽や書道という、一般的には入試科目ではなく、豊かな感性を醸成する芸術科目と同列に並べようとしている。さすがにこれは暴論と言わざるを得ない。
そもそも、芸術科目は実技科目である。もし芸術科目に並べるのであるならば、むしろ「文芸」とし、詩・短歌・俳句・小説・随筆の創作・鑑賞をする科目とすべきであろう。それらは教えられているとしたら、「古典」ではなく、「現代文」で教えられているはずである。すぐれた古典作品を参考として鑑賞することはありうるとしても。
しかし、ここに不要派の「古典」観も現れている。古典の中でも文学的なテキストがイメージされ、論理よりも表現を学ぶもの、鑑賞すべきものと考えられているのだろう。しかし、古典の中には、自然や人間についての思弁的な言説もあり、政治や社会を論じる評論的な言説もある。情緒的なテキストもあるが、論理的なテキストもたくさんある。「古典」といえば、『源氏物語』・『枕草子』・『徒然草』・『奥の細道』の有名な場面を思い浮かべて、現代とは乖離した内容と思い込んでいるふしがあるのだ。現状の古典教材の選択・配列にも問題があることは事実である。しかし、現代の問題に示唆的な古典はいくらでもある。だからこそ時代を超えて、為政者たち、ビジネスのトップたちに読まれてきたのである。
古典すなわち古文・漢文で学ぶことは表現ばかりではない。いな、むしろ現代文に連なる語彙・文法・論理・思考・表現・文体であり、これらの技術・知識の修得は、芸術ではなく、国語力に関わるもの、つまり国語リテラシーである。そういう意味では、現代文を学ぶことと何ら変わりはない。たとえば古典教材の再編成によっては、文学的ではない、非芸術的な教材を並べることも十分ありうるのだ。不要派が、古典を芸術科目にというのは、的外れなのである。
5、古典不要派の論理 3 現代語訳
次に、古典は現代語訳で教えれば十分ではないかという主張。古典が内容だけを教える科目であるならばそれでよい。しかし上に述べたように、古文・漢文は、語彙・文法・表現・文体をも学ぶのである。いや、そちらの方が古典を教える本意である。教科書の載っている古典がスゴいから、古典を学ぶのではない。現代文と同様、古文漢文の例題を学んで古文漢文の読み方を学ぶのである。ちなみにこの世の中に現代語訳が備わっている古文・漢文など、本当にごく一部、どんなに多く見積もっても千分の一以下だろう。未知の古文・文語文に接した時に、辞書を引きながらでも解釈できる力を持っておくには、原文をテキストとして古文・漢文の読み方を学んでおかなければならない。英語の学びと全く同じである。そう言うと、現代日本語の読解力・作文力さえ落ちているというのに、必要度がどんどん落ちている古文・漢文を学ばせるのにどのような意味があるのかという反論がかえってくる。しかし、古文・漢文の語法・文法の知識と読解力は、現代文を読む国語力をつける一助、いや現代国語力そのものである。
現在、契約書・報告書・法律・行政文書という実用的な文章を読む力が求められ、新指導要領に設けられる科目「論理国語」の重要性が叫ばれている。もし、そのような実用的な文章を読む力が必要なのであれば、それらは元々漢文訓読体で書かれていた文語文がベースになっている(法律などは少し前までそうである)ことを思い出すべきだろう。漢文訓読をきちんと学べば、実用的な文章を読む力がつくことは容易に推測されよう。訓読とは、ある漢字の並べをそのまま活かして、日本語として自然な文章に仕立て直す方法である。中国語の文構造を把握した上で個々の漢字を日本語文法に位置づけていくこと、また日本人が漢文の白文を日本語として整合性の取れるようにどう訓読してきたかを考えること、これらの作業が論理的思考を鍛えることに繋がる。そうした訓読文が、長い間日本語の公用的文章の規範とされてきた事実は無視できない。実際、エビデンスになるわけではないが、筆者の知る高校教員の一人は、現場での教育を踏まえ、漢文訓読を学ぶことは論理的な言語運用能力を養うことに資するという感覚を持っていた。どんなに控えめに言っても、英語の読解力や知識よりは、古文・漢文の読解力や知識が現代文を読み書きする技術と知識に直結していることは間違いないだろう。それらは、まだまだ現代文の一部にも直接食い込んでおり、実用的な文章のベースになっているからである。
なお、和歌は、美術をはじめとして、あらゆる表現芸術に大きな影響を与え、日本文化の核心にある文芸様式だが、これだけは現代語訳で教えても無意味だということは、不要派も理解しているようである。和歌の言葉が持つ「連想と記憶」(シンポジウムにおける前田雅之氏の発言、『こてほん』105頁)は、原文でないと説明不能である。踏まえられている本歌、序詞や枕詞そして掛詞などの修辞が和歌の理解には欠かせない。さらに古文全体にも、この「連想と記憶」は散在しており、日本の美術・工芸にさえ浸透していて、それを把握していることが鑑賞の理解を深めるのである。そして「連想と記憶」は、実は現代の文章や会話にも見られるものである。いわゆる「洒落」もそうだが、言葉の重層性は現代においても日本語コミュニケーションの重要な要素である。決して過去の無用のものではない。また「使わなくても済むから教えなくてよい」、というものでもない。車のハンドル同様、「あそび」の部分があって、安定した日本語運用ができるからである。
これから古典教育や古典研究に携わっている者が肝に銘じなければならないのは、古文・漢文は、現代の国語とは切り離された過去の遺物ではなく、現代にも未来にも、何ら活用がなされうるものであるということである。繰り返すが、『源氏物語』や『徒然草』は知っておくべきとか、日本文化の宝だとかいう論理では、とても古典不要派や古典苦手の生徒を説得できない。
なお、不要派が出すラテン語のたとえ----、ニュートンの『プリンキピア』を現代のイギリス人はラテン語で読みますか?(『こてほん』40頁)というのは、一見説得力があるようだが、『プリンキピア』を原著で読むのは、それは『プリンキピア』の理解のみが目的ではない。ラテン語の学習に資するからである。同様に、『徒然草』や『史記』を原文で読むのは、その内容の理解はもちろんだが、古文漢文の読解力を上げるためである。一般人が『徒然草』や『史記』を教養として現代語で読むのは全く問題ない。教育現場において原文で読むのはあくまで古文漢文を学習する教材だからである。
なお、ラテン語を「古文漢文のようなもの」と喩えるのは、この議論の場合は適切ではないことも確認しておきたい。筆者も大学でラテン語初級を受講し、羅和辞典があれば、なんとかラテン語が読めないこともないので、ある程度のことは言えると思う。たしかにラテン語は現代英語とはかなり隔絶している。しかし、古文漢文は、それを構成する古語・漢語のかなりの部分が現代語としてもそのまま生きているのである。つまり古文漢文はラテン語と違い、現代文と切れてはいないのだ。日本を代表する『広辞苑』という国語辞書が、古語を見出しとして載せているのは、今でも現代語として使っているからに他ならない。イギリス人がラテン語を学ばないとしても、日本人が古文漢文を学ばないことを同列に論じるべきではない。
6、不要派の論理 4 ポリティカルコレクトネス
不要派は、古典は旧道徳や男女差別思想を刷り込み、助長させる言説が多いため、ポリティカルコレクトネスの観点から、教科書に掲載されるのは好ましくない、むしろ有害であると主張している。
しかし、この主張は、そもそも事実認識に問題がある。具体的な問題例を挙げることもなく、彼らの古文・漢文イメージを元に述べていると考えられ、高校の教科書を精査して主張しているとは思えない。筆者も全ての教科書を精査したわけではないが、仕事柄、高校の教科書を見る機会が少なくない。現代文の教科書を含めて、国語教科書は、文部科学省の教科書調査官がチェックしているため、ポリティカルコレクトネスの観点から問題になるような本文は除かれているし、教科書会社も十分注意している。戦前の教科書には、親の敵を討った曾我兄弟の話が載っていたが、それを教材として載せる教科書は今では存在しない。現代の価値観から見て相応しくない教材が淘汰されていくのは、古典に限ったことではなく、当然の結果である。
しかし、不要派は、教科書掲載の『源氏物語』もポリティカルコレクトネスの観点から問題なのだという。基準をどのように考えるかという問題が残るが、どうやら不要派は、「やんごとなき」身分の登場人物が存在するだけでアウトだと考えているようである。前近代の身分社会に基づく「高貴な身分」の人を描いたものは全て排除すべきであるという考え方だとすれば、多くは貴族文化から生まれた「日本文化」と称される文化遺産の大部分を否定することになる(これは日本に限ったことではない)。光琳の燕子花図が『伊勢物語』東下りの段を踏まえていることを持ち出すまでもなく、日本画の題材をはじめとして着物の文様に至るまで、前近代の造形美は古典やその美意識と大いに関係があるが、それらも、旧道徳を刷り込む有害物ということになってしまうだろう。
不要派の議論には、年下・女性・外国人(アジア系)の上司ができたらへこむのは、古典教育か儒教マインドの弊害だろう (『こてほん』32-33頁)というが、反論する気にもならない無根拠の主張である。SNSのやりとりの中では某大学の医学部受験が男子優先の不正をしていたことも、古典教育を中途半端に受けた弊害だと強弁していて驚いた。古典を長年研究している我々の間にはそういう発想は微塵も浮かばないのだが、一部の理系研究者の方が、前近代の感覚を当然と思い込むほどに古典をたくさん読み、その影響を強く受けているとでもいうのだろうか。
7、国語力の一部としての古文・漢文
不要派の論理の相対化に紙幅を費やしてしまった。次に、古文・漢文の国語リテラシー(国語力)としての必要性と、より健全に生きるためのサプリメント(教養)としての必要性を説いてゆく。断っておくが、筆者は古典は必修であるべきだという主張をここで展開するものではない。
いみじくも、不要派は「国語にはリテラシーとしての国語と、芸術としての国語がある」(『こてほん』46頁)という。「芸術」というより「教養」というべきだろうが、古典を含め、さまざまなテキストに触れる国語学習の意味にその二面があることは事実である。しかし、一義的にはあくまで国語リテラシーである。
古文・漢文の学習の意義は、将来、読む可能性のある古文・漢文ないしは、古文・漢文的表現を含む現代文に対した時に、それに適切に対応する読解力、さらには実用的な言語運用能力の養成である。または、過去の膨大なテキストを利活用しようとする時に必要な技術の習得である。これについては田中草大氏による明快な解説がある。田中氏は、2019年10月21日に京都女子大学で行われた講演のスライドをtwitterで公開している(筆者自身は講演資料を同大の関係者を通して入手した)。田中氏によれば、古文とは文語文のことで、「平安時代以降、近代に至るまで非常に幅広い書き物に用いられた(文学に限らない)」。また「日本語表記法としての漢文」は、奈良時代以前から例があり、近代まで用いられた」。「つまり古文・漢文(=文語文・漢文訓読)を学習するか否かは、この近代以前の膨大な文字遺産を自分が活用できるか否かに直結する」のであり、「過去の日本に関心のある(将来関心を持つ)全ての人にとって有益たり得る」のである。つまり、古文漢文を学ぶ意味は、現代文の学習や、英語の学習と何ら変わらない。その際、優先度は現代文>英語>古文漢文であってもよい。そこにプログラミングを入れるべきだという向きもあるだろう。入れてもよい。しかし、優先度は低くても、日本の歴史の大部分を占める時代の書記法である古文・漢文を学ばないのは問題である。(編集部注=このときの田中氏の講演は『女子大国文』166号に掲載され、公開されている)
ただし、現在多くの教科書と大学入試問題がそうであるように、古文の教材が源氏物語を中心とする中古文に偏るのは、将来読む可能性のある古文の例題としては、実際的ではないかもしれない。明治大正昭和前期を含めた、論説的・随筆的文章に、やさしめの読み物系文章を交える教材編成にすると、「わからなさ」感がなくなり、親しみやすいものになるだろう。実際、筆者が江戸期の読み物を授業プリントで配布すると、「古文がこんなにわかりやすいとは思わなかった」「高校の教科書もこれくらいの文章なら読む気になるのに」という感想が必ず出てくるのである。そして、彼らが今後の人生で出会う可能性のある古文(文語文)の多くは、中古文的な擬古文ではなく、もう少し読みやすい文語文のはずである。
「風立ちぬ」(小説・歌のタイトル)、「風と共に去りぬ」(小説・映画のタイトル)、「仰げば尊し」(唱歌)などを挙げるまでもなく、文語的表現は今に生きている。少し締まった表現をしようとすれば、あるいは七五調を作ろうとする時に、文語的表現は今でもよく使われる。「急がば回れ」のようにことわざの多くは文語である。これらは、文語とさえ意識されることもないかもしれない。しかし、古典文法を学んでいれば、これらを誤って理解することはない。「仰げば尊し」の「今こそ別れめ」を「今こそ別れ目」と解したり、「ふるさと」の「うさぎ追いし」を「うさぎ美味し」と間違うこともない。
一方、それが正しい使い方をされていない例も見受けられる。CMソングに堂々と使われている歌詞に「住まい選びはたのしけり」というのがあったが、誤りである。ヒップホップの歌詞に文語的表現が使われていることもあるだろうが、文法的に間違っているとカッコ悪い。しかし上手く使っていたら「いい感じ」である。
8、古典知の可能性
ここから先が本題である。リテラシーとしての古文漢文ではなく、文化遺産としての古典について考えたい。現代そして未来において、古典はなぜ必要なのか。必要ではないと主張する人に向けて説得するためではなく、古典を最大限に活かす方法を模索している人々と連携するために、筆者の現時点での考えの一端を述べてみたい(文学部はなぜ必要かの問いとも当然重なってくる)。
そもそも「古典」とは何か。「過去に表現された立派な内容」(『こてほん』17頁)と不要派の前田賢一氏は定義した。異論はないが、どれくらいの「過去」なのかを定義した方がいい。10年、20年前の過去であれば、古典とは言いがたいだろう。筆者は便宜的に100年以上前と定義している。「立派」というのも主観的に過ぎるだろうから、「読まれ続けてきた」としよう。「100年以上多くの人に読まれ続けてきたテキスト」が筆者の定義する「古典」である。多くの人に読まれ続けてきたわけではないテキストは、単なる歴史的典籍であり「古文」である。「多くの人」が曖昧なのであれば、「10万人以上」でもよい。
このように定義すれば、おのずから古典を読む意義は定められてくる。それが、500年、1000年前のテキストであれば、なおさらのことであるが、古典は、時代を超えて読み継がれてきたテキストであり、そのこと自体が読む価値を保証するのである。100年の間には、社会の価値観は大きく変わっている。社会を担う世代も三世代以上変遷している。それにも関わらず読み継がれてきているのだから、「読まざるにしくはなし」、であろう。100年以上読み継がれてきたテキストを、「古くさい」と決めつけ、これからはもう読む価値はないと、数十年も生きていない人間が言うのは、どう見ても愚かしいだろう。断っておくが、今、「原文」で読むかどうかという問題は議論していない。「原文」で読む教育上の意義は、言語運用に資するということであることは、本論で強調してきたことであるが、文化遺産としての古典は、現代語訳や翻訳で読んでも、価値は減じないのである。
では、古典はなぜ100年以上命脈を保っているのか。時代を超えて読まれ続けているのは、普遍的な価値を有しているからである。言い方を変えれば、さまざまな時代の価値観に耐えて読まれ続けてきたのが古典である。『プリンキピア』が読まれ続けているのも、そこに書いていることが今でも有効な真理だからである。また科学的には否定すべき内容に満ちている『聖書』が現代でも読まれ続けているのは、それ以外の部分で多くの人々にとって読む価値があるからである。言い換えれば、今読んでも、これから先読んでも、読む価値のあるテキストが古典である。「やんごとなき」身分の登場人物が称賛されているからポリコレ的に問題であるという「木を見て森を見ない」古典否定論は、古典の古典たる根拠を考えない議論なのだ。
古典の重要性は、普遍的な価値を持っているというだけではない。古典に書かれていることは、その読まれている時代の価値観と異なることがある。それはその時代の価値観を相対化する。今・ここの価値観にどっぷり浸かっている我々は、その価値観を、たとえば海外に行くことで揺さぶられることがある。それと同様、古典を読むことで、現在の自分自身の価値観を再考する手がかりを得られるのである。
「古典」の「典」が普遍性をあらわすとすれば、「古典」の「古」は、書かれた時代がかなりの過去(筆者の定義では100年以上前)であることを示している。今の時代では理解できないことも書かれている。そこで登場するのが、古典研究者である。古典研究者は、現在では通じない言葉や、時代背景や、作者の人間関係等など、テキスト内外のさまざまな手がかりを通して、テキストの意味するところを解明していくのである。インタプリタとしての古典研究者は、いつの時代にも必要とされる。注釈や現代語訳は、その時代に相応しい言葉と形式で更新されていかねばならないからである。
100年以上読み継がれている古典には、さまざまな考え方のサンプルが備わっている。これを、ここでは「古典知」と呼んでおこう(「古典知」という言葉はこれまでも使われているが、必ずしも同じ意味で使われているわけではない)。現代の人間の考えることの大部分は、すでに古典に書かれている。今売れている本を次々と読むだけの読書と、古典しか読まない読書では、後者の方が事に当たって、より正しい判断をする力を獲得する確率が高いだろう。もちろん、古典をたくさん読むだけで誰もが好ましい「古典知」を身につけるとは限らない。正しい判断のできない古典学者だって当然存在するだろう。それだと単なる「古典オタク」にとどまる。英語や数学もそれを活用しないで知識として貯めているだけでは、単なるマニアに過ぎないのと同じである。
大阪大学文学研究科の金水敏氏は、2017年3月22日の卒業式の式辞で、文学部で学んだことの意義を、「人生の岐路に立ったとき、その問題に考える手がかりを与えてくれる」と述べた(金水氏のブログに全文が載る)。このスピーチは大きな反響を呼び、賛同と共感の声が多く寄せられた。金水氏のスピーチは卒業式に、卒業式に向けてなされたものであったので、卒業生とその保護者が納得すればよかったのだが、社会に向けて同様の説明をしても有効だろうかという懐疑的な意見もあった。
同じ大阪大学の経済学者の大竹文雄氏は、金水氏の式辞は、人文学が役に立つという点では説得的な話だが、個人に還元するだけでは、国立大学に公的資金を投入して人文学を教えるべきだという理由にならず、社会への説明責任を果たしえていないという。ではどう考えるべきかといえば、人文学の知は、個々人がよりよい選択ができるだけでなく、社会全体での意思決定を行う際に、よりよい意思決定ができ(公共選択の改善)、その便益は人文学を学んでいない人にも及ぶ。また、間違った選択をしないことで、社会問題や犯罪を減らしたり、社会保障の必要性を減らし、財政支出の削減に貢献することができるというふうに、個人ではなく社会へ還元するような論理であるべきだと言う(「人文学・社会科学の社会的支持を向上されるために」科学技術・学術審議会学術分化会、 2018年8月22日)。もっともな意見である。数値化することは簡単ではないかもしれないが、深い人文知が社会貢献をしたという具体例を人文学に従事する者は収集していく必要がある。
古典を多く読み込むことで、古典をいったん客観化し、自分自身の問題と、現代社会の抱える問題に関与するアイデアをそこから汲み上げる技術を得ることができれば、古典のみならず、さまざまな文書や出来事を的確に分析し、事態に対処することができる可能性が高い。なぜなら、何度も繰り返すように、古典は、古くさく黴臭くて現代に通用しないのではなく、100年以上読まれ続けたものであるから、むしろ逆にさまざまな事態に対応する汎用性を持っていると考えられるからである。言い換えれば、古典はどういう時代にも対応できるという意味で常に新しく、「古典知」は過去の知識ではなく、現代や未来を拓く可能性に満ちているのである。あらためて「温故知新」という言葉が思い起こされる。
もちろん「古典知」は万能ではない。しかし、先の読めない時代である今こそ、思考の安全弁として、新しい事態への免疫力として、「古典知」を保持していることは大切なことではないのか。古典不要を主張する人は、100年・1000年先を見通した上でそれを断言できるほどの教養があるのだろうか。おそらく20年とかせいぜい50年先の社会しか見越していないのではないか。繰り返すが、少なくとも古典は、100年・1000年を生き延びてきているのである。
9、資本としての古典
秋田慧氏は、日本における京都の存在を古典に喩えて、「古典が存在することは見方によっては巨大な資本であって、それがある程度必要とされている限り、出版業や教育業のみならず、筆や紙といったさまざまな高付加価値産業を駆動する「金の生る木」であるはずだったと考えることができる」という(秋田氏が飯倉のSNS投稿に反応したコメントによる)。経済的価値からは一見ほど遠いと思われる古典ではあるが、その市場価値を本気で測定しようとした試みはおそらくなかっただろう。資本としての古典の価値を一度考えることが必要である。
そうすると、すぐに思い浮かぶのが能狂言・文楽・歌舞伎・落語・講談などの、まだまだ根強い人気を誇る伝統芸能である。これらの芸能の各演目は、それ自体が古典文学であることが少なくないが、さらに言えば、多くが有名古典の二次創作である。能の人気演目「井筒」は『伊勢物語』、「葵上」は『源氏物語』、「敦盛」は『平家物語』を典拠としている。文楽・歌舞伎の『菅原伝授手習鑑』は『北野天神絵巻』などを、『義経千本桜』は『義経記』などを、『仮名手本忠臣蔵』は赤穂事件を素材としながらも『太平記』の世界を前提としている。江戸時代中期以降ともなると、これらの古典作品世界のイメージは、古典そのものを読んでいないであろう庶民クラスにまで浸透していたのである。
また古典を素材にしているコミック・アニメ・ゲームも多い。『源氏物語』を原作とする大和和紀のコミック『あさきゆめみし』は中でもよく知られていよう。かつてはNHKで『八犬伝』の人形劇が人気を博していたが、コミカライズやゲーム化も盛んであったことは、内田保廣の「いまどきの八犬士」(『読本研究』第六輯、1992年)が精査している。最近の学生が知っているであろう事例なら『NARUTO--ナルト--』が合巻『児雷也豪傑譚』を利用し、『ドラゴン・ボール』の原型には『八犬伝』がある。現在我々が知る歴史小説やテレビドラマの秀吉出世譚の筋の原型は上方読本の『絵本太閤記』であり、忠臣蔵ものの原型は江戸時代中期の浄瑠璃『仮名手本忠臣蔵』である。江戸の読本や合巻では、まだまだ面白い作品がたくさん眠っている。古典文学の「遺跡」を売り物にする観光産業など、決して馬鹿にできない市場価値を古典は秘めているのではないか。海外に関心の高い日本美術とも非常に親和性が高い。京都という観光都市を軸に考えれば和菓子や日本料理との連携も考えられる。谷知子氏は、2019年、フェリス女学院大学と横浜を代表する和菓子店『香炉庵』とのコラボ和菓子「浜恋路」を開発した。プロジェクト演習の授業で、百人一首をモチーフとした和菓子の開発を行ったのである。全て学生たちのアイデアだという。百人一首のみならず古典本文に著作権はない。原料に一切費用がかからないのである。クールジャパンよろしく、ジャパンクラシックとして古典を戦略的に展開すれば、日本の文化資源として大きな利益を生み出す可能性がある。このようなことは谷氏のように、研究者側(大学側)が積極的に産業界へアプローチすることで活性化するだろう。たとえば文学部出身の企業経営者などをチャンネルにして働きかけることを考えていくべきだろう。
もちろん、古典の原典画像や本文をそのまま提供しても、産業界はそれを活用できない。産業界が利用できるように本文を提供する、媒介者=「古典インタプリタ」が必要であろう。古典インタプリタとは聞き慣れない職業かもしれないが、すでに国文学研究資料館に実在する。国文学研究資料館の近年はじまった事業のひとつに「ないじぇる芸術共創ラボ」がある。これは、国文学研究資料館の古典籍の数々と専門家によるネットワークを研究者コミュニティの外側に開放するというものである。具体的には芸術家や翻訳家を国文研に招き、「古典知」に刺激を受けながら創作や翻訳を行ってもらうというものだが、彼らの活動を支援することをはじめとして、「古典知」を専門外の方に繋げるために、ナビゲータを育成投入するという試みを国文学研究資料館は行っている。そのナビゲータを古典インタプリタと呼ぶのである。
現代社会において古典インタプリタに相当する役割は、主として現職ベテラン大学教員や定年退職した大学教員などが、古典コンテンツを紹介するというやり方で、放送大学やカルチャーセンターらを舞台に務めていて、対象は高齢者が中心であるが、それなりに活況を呈している。古典と親和性の高い、短歌や俳句も趣味人口はかなり多い。俳句添削をエンタテイメントとして提供するテレビ番組も人気を誇っている。今後は、古典インタプリタの人材派遣のような仕組みも考えられてよい。単に古典講座の講師をするだけではなく、古典の活用をさまざまに提案し、あらゆる文化産業や自治体の地方起こし事業への適切な提言をするなど、さまざまな要望に応えることのできるスペシャリストがそこには登録されているわけである。とりわけ古文を現代語訳できる人材が要請されるかもしれない。現在活字化されている古文の校訂本文や現代語訳には著作権がある。しかしオープンアクセス可能な原典画像は、利用自由である。原典のくずし字を解読した上で、正確で読みやすい本文校訂を施し、現代語訳をつけるというスペシャリストである。
10、おわりに―遺産としての古典
日本文学研究者のエドアルド・ジェルリーニ氏は、世界遺産をヒントに古典を遺産として活用することを提案している。単に遺すだけではなく、活用してこそ遺産である。時の彼方にまだまだ眠っている(未翻刻・未紹介)巨大な古典遺産を発掘し、磨き上げ(本文校訂・翻刻)、彩色し(現代語訳・翻訳)、縦横に活用して(二次創作)、文化振興に寄与することが氏の構想だろう。古典を未来に活かす知恵の泉は、こんこんと湧き出てくるはずである。これらを非現実的と笑う人も少なくないだろう。しかし全く不可能な夢物語を述べてきたつもりはない。古典を未来に活かすことに共感する方々のご批正を俟ちたい。
【追記】
2020年6月6日(土)、国際基督教大学高等学校の現役高校生の企画で、「高校に古典は本当に必要なのか」というシンポジウムがオンラインで開催された。閉会に当たっての、本シンポジウムの企画者である高校生の、「古典を学びたいのに現状は・・・」という切実な声に胸を打たれたが、それについての私的感慨は別の機会に譲る。
本稿に関わることで、きわめて有益な示唆をパネリストの一人である近藤泰弘氏の発言から得ることができた。「古典で論理的思考が学べるか」という議論の流れで、近藤氏は、古典の論理は「概念メタファー」を含む論理であるという観点を示され、例として『奥の細道』の冒頭の〈人生は旅である〉という考え方を述べた文章を示した。ある考え方をなんらかの比喩によって認識する方法が古典には非常に多い。古典にしかない認識方法であり、単語の意味や文法を理解するだけでは解釈できないものである。そして、その認識方法は、現代あるいは未来におけるさまざまな場面に応用できるものだと考えられる。古典教育や古典研究に携わるものが、強く意識しておかねばならないことだと痛感した。
ちなみに、ディベートが終わったあと、賛否両論に別れた高校生たちの短い感想戦が行われたが、そこにこそ彼らの本音が垣間見えた。その会話に私は胸を打たれた。それは本シンポジウムが得た賛成派・反対派の合意点でもあった。すなわち「現在行われている古典の授業に問題がある」ということ。おそらく、これでアンケートをとれば、ここに参加した人々(高校生から教員、一般の方まで)のほとんどが賛意を示したことだろう。子どもたちに、限られた時間の中で、どういう教材を使って、何を、何のために教えるのか、このことを常に意識し、議論していくことが、古典に関わるものの使命であることを再認識させられた。