第9回「短歌」が「歌集」になることの可能性――澤正宏『終わりなきオブセッション』|【連載】震災短歌を読み直す(加島正浩)
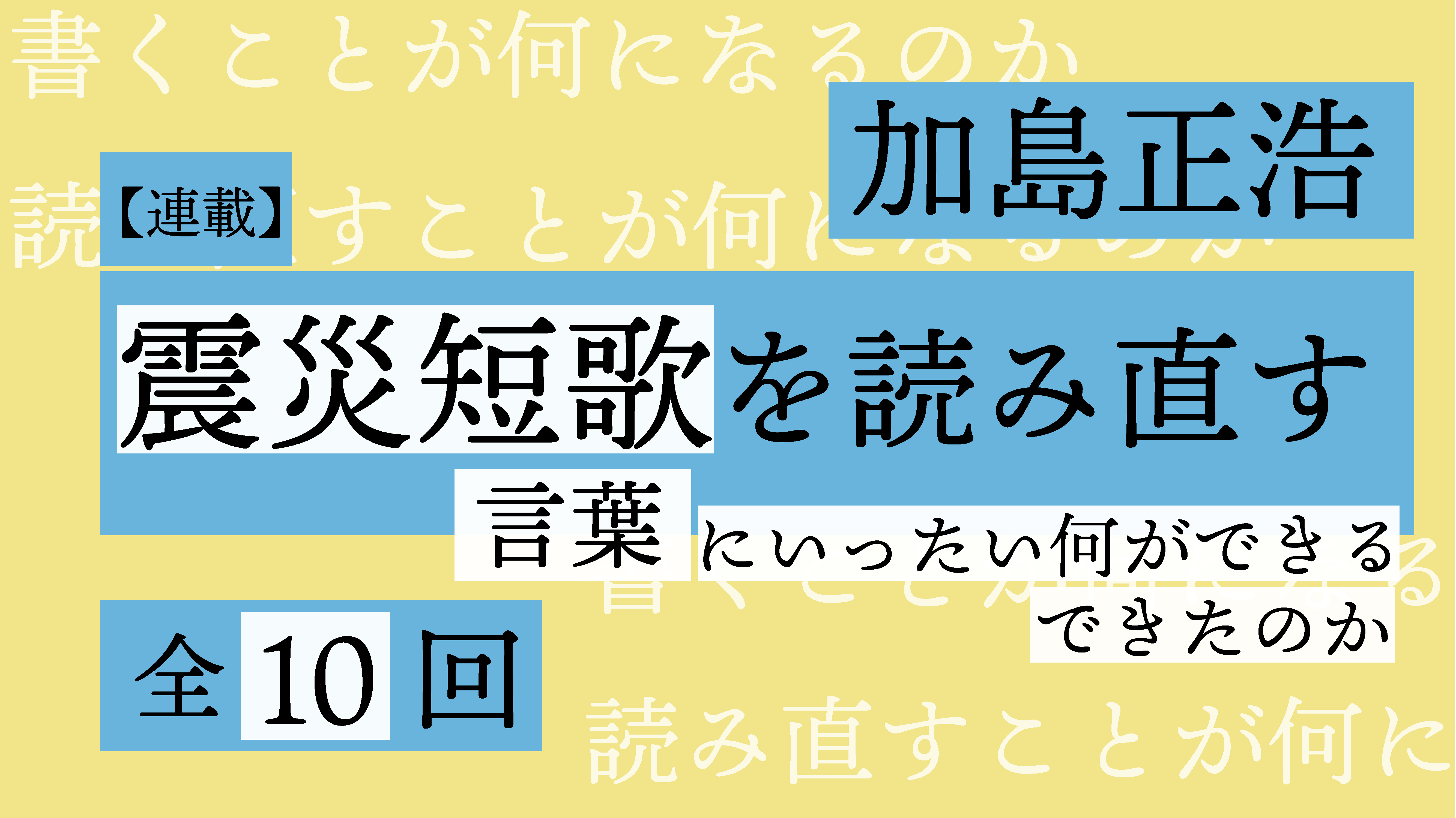
第9回
「短歌」が「歌集」になることの可能性
――澤正宏『終わりなきオブセッション』
■原発「事故」を詠むことの困難さ―「事故」を詠む立ち位置の問題
それまで社会事象や問題を積極的に詠んできた歌人のあいだでも、東日本大震災というテーマを扱うことには慎重な態度を示す歌人が少なくない。
大辻隆弘は社会詠(※社会や社会に対する認識を主題とした歌)を積極的に行う歌人のひとりであるが、東日本大震災を詠むことには積極的でない。2011年を回顧する毎日新聞の記事(大辻隆弘「短歌:2011年回顧 「『記録』としての底力と限界」『毎日新聞』2011年12月18日朝刊)で「リアルタイムの思いを表現するために、31音の短歌は最適の器だった。震災詠の横溢は、生の『記録』としての短歌の底力を改めて知らしめた」と述べたうえで、以下のように記している。
が、「記録」としての短歌は、原発事故と放射能汚染の問題を歌うとき、あまりうまく機能しなかった。放射能は目には見えない。汚染の影響は今すぐには明らかにならない。また、原子力発電による生活の豊かさを享受してきた私たちは、原発の被害者なのか、加害者なのか。その責任のありかも不明だ。そういった目に見えない問題を捉えようとするとき「記録」としての短歌は力不足なのだ。目に見えないものを歌い、現象の背後にあるものを見抜くためには、深い想像力とそれを可能にする言葉の震度が必要なのだろう。
また2016年の段階でも大辻は、他者や被災者へ配慮するがゆえに生じる良心的な葛藤・自己省察を描くと、それが自己弁護に感じられたり、歌うことが誰かを傷つけうることや、自らが「傍観者」に過ぎないことを予め折り込んでいるようにみえる点を指摘している。また、「良い歌」であるかどうかを論じる以前に、詠まれた内容が事実であるかどうか、詠み手が被災者であるのかが問題にされ、あるいは、詠まれた歌が詠み手の経験であると素直に読まれてしまう点に、東日本大震災を詠むことの困難さがあると論じている。(大辻隆弘「戦後短歌のアポリア―3・11以降の短歌の状況について」『龍谷哲学論集』30号、2016年1月)
「被災者」ではないために、または、自らの表現が誰かを傷つけうるかもしれないがために、逡巡や葛藤が生じ、それが歌としての精度を低下させることはあるだろう。
また、原子力工学の専門家である小出裕章が、原発「事故」後に、『騙されたあなたにも責任がある』(幻冬舎、2012年4月)と述べたように、私たちは純粋な「被害者」ではない。しかしその事実を踏まえて短歌を詠めば、その歌が、自分にも責任があることはわかっていると予め批判を封殺するような自己弁護(言い訳)として機能してしまうこともあるのは、事実だろう。
つまり、原発「事故」を詠むための立ち位置は、明確には定めにくいのである。純粋な「被害者」とは言い切れず、「被災者」であっても、置かれた立場・考えは様々であり、何かを断定的に詠むことはできない。「被災者」は一枚岩ではない。そのことを「良心的に」表現しようとすれば、別の考えを持つの人のことも慮っていますという自己弁護のように捉えられる。自己の考え、認識、立場を明確に歌に詠むことは容易ではない。
原発「事故」に向き合う姿勢の定めにくさが、「良い歌」を生み出しうる短歌という「器」を、わかりやすく揺さぶったのかもしれない。
■「業界」を越境して考える
大辻隆弘の社会詠に対する元来のスタンスは、社会を詠むのであっても、短歌である以上、それが良い歌であるかどうかの評価軸を抜かしてはならないというものである。(小高賢、大辻隆弘ほか『いま、社会詠は』青磁社、2007年9月を参照のこと)
大辻が指摘するように、原発「事故」を詠んだ歌が「良い歌」かどうかで判断すれば、原発「事故」という事実の大きさを「記録」した歌というより他にないかもしれない。もちろん、それは「歌人」として、「歌」を評価しようとする倫理的なひとつの姿勢であることは疑いようがない。
しかし、「歌人」ではない文学研究者である私の関心は、周縁化され、顧みられるまでは「何か」と呼ぶより他にない「何か」を適切に可視化/問題化することである。東日本大震災以後の文学研究は、小説を主な対象としており、次いで詩が問題にされてきた。しかし、間違いなく量的に小説以上に存在している俳句・短歌には、ほとんど注目が集まらなかった。それは俳句は俳人が、短歌は歌人が論じるものであるという「業界のあり方」が関係しているのかもしれない。しかし、巨大な複合災害である東日本大震災を真剣に考えようとするならば、「業界のしきたり」を考慮に入れる余裕はないはずである。
歌人には歌人の東日本大震災詠、原発「事故」詠を評価する姿勢がある。しかし、震災文学研究者が必ずしも歌人の評価基準に追随しなければならないということはない。文学研究者に求められているのは、「良い歌」とされるもののみならず、そこからはじかれてしまった歌も介すことで、震災や原発「事故」にどう向き合うかという姿勢を提示することであると、私は考える。
そのように「業界」を越境し、歌を介して原発「事故」と向き合った文学研究者が、澤正宏である。澤は現在、福島大学名誉教授であり、元々は西脇順三郎などの近代詩の研究者である。しかし、原発「事故」を受けて、『詳説福島原発・伊方原発年表』(クロスカルチャー出版、2018年2月)の編者を務め、福島原発の立地、稼働を問題視する裁判記録を丁寧に洗い直すなど重要な仕事を行っている。まさに狭義の「文学研究者」の枠を超えて、原発「事故」に向き合った研究者のひとりである。
その澤には歌人としての側面もあり、彼の出版した歌集が『終わりなきオブセッション―原発事故後七年を詠む』(明文書房、2018年6月)である。澤は、原発「事故」以後を詠むことに対し、以下のように述べている。
事故が起きた二〇一一年三月一一日(この日、既に地震、津波に因り炉心融解は始まっていた)以降、それまでのように短歌を書き、詠むことの意味が私のなかでは空無化し、短歌が生きること、生活などに基盤を置く表現であるならば、核災地である福島を生きる当事者として、事故後の惨状をどう表現すればいいのかという自問に変わってきた。原発の設置から稼働までは言うまでもなく、放射能被害の報告でも隠蔽、改竄が罷り通っている現実を前にして、原発事故七年後も続き、その後も続くであろう絶望的な現実を見つめていると、自分の表現がもの足りないのである。(中略)想像力は現実を超えて行くものというその想像力が、私の場合、現実が重すぎて現実を超えられない事態になってしまったのである。とすれば、核災の惨状を露呈している現実を凝視することから再出発するしかない、自足的で極めて私的な表現を出来うる限り抑えること、私的な考え、感性が自殺を含め強いられた死へと追いつめられた核災の被害者の皆さんにまでしっかり繋がっているかを自分に問うこと、こうした歌作の姿勢が現在できることの唯一の方法となったのである。
原発「事故」以後の福島で「日常」を詠むことが難しいと、澤は述べる。それは「日常」が原発「事故」以後、大きく変容させられてしまったからであり、澤は「フクシマ」の表記を用い〈フクシマの地に刻まれた諦めと怯えと怒りは除染で消せぬ〉と詠んでいる。原発「事故」以後を生きる人々が抱え込まされた「諦めと怯えと怒り」を表現するには、詠み手の生活に基盤を置く日常詠では、足りないということであろう。
また、〈線量が一〇マイクロ出る楢葉町へ「帰れ」は人語か五年目の夏〉という歌もある。人の言葉とは思えない言葉が、原発「事故」の「被災地」に「降りつづいている」のも、原発「事故」以後の現実である。歌人(詩人/俳人......)が問題にしなければならないのは、原発「事故」の「被災地」の悲惨な状況をどう詠むかということに加え、そこに外から「降りかけられた」「人語」とは思えない言葉に、どう抵抗するかということにもある。
澤は「核災の惨状を露呈している現実を凝視する」「自足的で極めて私的な表現を出来うる限り抑えること、私的な考え、感性が自殺を含め強いられた死へと追いつめられた核災の被害者の皆さんにまでしっかり繋がっているかを自分に問うこと」が歌作の姿勢であると述べている。それは原発「事故」以後の「被災地」に起こっていること(どんな言葉が降りかかってきたのかも含め)を明白に「記録」するということでもあろう。そしてそれが、自分個人の表現/感性へと閉塞するのではなく、原発「事故」以後に生じてしまった「フクシマ」を細やかに「記録」する方向に、澤を向かわせたのではないかと考える。それは、以下のような歌からも考えることができる。
■「土地の叫び」を聞いてきたのか『終わりなきオブセッション』には、原発「事故」以後の街それ自体や街で生活する人々の様子を詠んだ歌が散見される。街「と」耐え住むと詠む一首目では、街が詠み手とともに生きて耐えている様子がうかがえる。耐え住んでいるこの歌の主体は、詠み手の「私」と「街」である。地震や津波、放射能、風評が襲いかかる街「に」住んでいるのではないのである。
また二首目で「この地を出ぬと老人は残る」と詠まれる「老人」は、詠み手の「私」のことを指しているようにも、詠み手ではない別の「老人」を指しているようにも読める。詠んだ歌が、詠み手の話に留まらず、その地に住む者たちの思いにまでつながるように詠むというのが澤の作歌の姿勢であった。詠み手の「私」が特殊な人物なのではなく、「フクシマ」となってしまった場所に生活しつづける「老人」のなかに自らを溶かしこむことで、土地に住む者の思いを詠んでいるといえるだろう。詠み手が特権的に看守できた現実を詠むという姿勢ではなく、詠み手である自分の存在を極力同じ「フクシマ」に住む人たちのなかに溶かしていくことで、「私の日常」ではなく「フクシマでの日常」を詠むことを可能にする試みとして読むことができるようにも思う。
また他にも、〈帰路のバス「
特に二首目は、〈地の苦の叫び〉とあるように、この歌の主体は、赤宇木という「土地」である。大辻が述べるように、詠まれた歌が事実かどうかが、震災を詠んだ歌では問題になってきた。しかし一方で、このような歌に対して、土地は「苦」を叫ばない(事実に基づかない)という指摘がなされたとすれば、それは的外れであろう。
歌のなかで「土地」が主体になっているというのが、澤の歌集の大きな特徴のひとつである。確かに放射能汚染の被害を直接に、最も大きく被ったのは、他でもない「土地」なのである。この11年間、私(たち)が土地の叫びを聞いてきたのかどうかは、問われるべき問題のひとつであろう。
そして、土地は問うている。
注意したいのは、ここで命を問うている主体は「福島」であるということだ。「事故」以後に生じた「フクシマ」ではない。澤は〈神主は避難区に残り死者の名を「地脈は切れぬ」と毎朝唱える〉、〈「観光地」めぐりで旅人きょうも来るフクシマ忘れぬバスツァーという〉という歌も詠んでいる。「事故」以後に「フクシマ」は生じたが、その「フクシマ」は「福島」と無縁ではない。「福島」(のある部分)が「事故」によって「フクシマ」に変容させられてしまったのである。「観光地」として「フクシマ」を訪れるとき、「フクシマ」が「福島」であった/でありつづけている部分を見落とす。
〈地脈〉が「事故」によって途切れたわけではないのと同様、「福島」が「フクシマ」へと全てを変えてしまったわけではない。「福島」には「事故」以前からの歴史があり、記憶があり、人は住み続けている。「福島」は「フクシマ」を包含しているが、「福島」が「フクシマ」なのではない。原発「事故」以後の悲惨な「フクシマ」が命を問うなら、それは結局「事故」が起きなければ、悲惨な事態は起こらない、「フクシマ」は生じないという「事故」の有無を尺度に再稼働が判定されるに過ぎない。
そうではなく、「福島」が「フクシマ」に至るまでの全てを踏まえて、私(たち)は再稼働を問わなければならないのである。
本連載の第5回においても、朝日歌壇の常連であった東海正史を扱い、原発立地地域に生きるとはどのようなことなのかを考察した。そのような歴史を「フクシマ」は持っていない。原発「事故」以後に何かを問うためには、「事故」以前を踏まえる必要があり、そのことを最も体現しているのが「土地」という存在なのであろう。「福島」は「フクシマ」以前から、「福島」なのである。
■人間である以上、加害者でもある
澤の歌集に特徴的な点を、もうひとつ挙げておきたい。それは、人以外の「もの」への着眼である。
福島に住んでいたのは、あるいは「フクシマ」に住みつづけている/住みつづけなけれならなかったのは、人だけではない。人以外の動物も、また同様である。ただし「フクシマ」へと変容してしまった地域においては、「福島」のときのような人間との関係が保てなくなってしまった例もある。子熊は迷い感電死し、殺処分の話は(そして殺処分を強制された方々のなかで自ら命を絶った人が少なからずいたことも)多く報道されたところである。
大辻が述べるように、これら動物に対しては、私たち人間は「加害者」の立場にある。澤は以下のようにも詠んでいる。
福島を「フクシマ」にしたことで、殺された動物がいる。一方で「フクシマ」に帰ってくるがゆえに、殺される動物がいる。「フクシマ」となってしまった以後も、殺処分される小動物がいる。私たちは、これらの動物たちにおいて「加害者」の立場にある。しかし、これは「フクシマ」あるいは、原発「事故」以後だけの問題であるのか。子熊が迷い込み、感電する恐れがあるのは、原発「事故」以後だけなのか。殺処分が起こるのは、原発「事故」以後だけなのか。(本連載、第2回を参照してほしい)
高木任三郎は『市民科学者として生きる』(岩波新書、1999年9月)のなかで「原発問題の中にはすべてがある」と述べている。科学技術の問題のみならず、差別も資本主義(新自由主義)も、内的植民地の問題も、原発には存在する。多くの社会問題化しているあらゆる問題が、原発には含まれている。そこでは、大辻が述べるように、「純粋な」被害者は存在せず、あらゆる問題が複雑に交錯している以上、どこかで私たちは「加害者」となってしまう。
しかし、そうであるから、原発「事故」以後が詠めないというのであれば、そもそも複雑化した社会において、社会問題を詠むということがどのように可能であるのかも同時に問わなければならない。ハラスメントなどの加害者が明白に問題である事例をのぞき、「純粋な」被害者という存在が想定しにくい(ある場面では、被害者であっても、ある場面では、知らぬ間に加害者になっているかもしれない)という複雑に様々な問題が絡み合った現代社会において、自らの立場は常に揺らいでいる。一方に肩入れすることが、何らかの(政治的)方向へ誘導する危険性があることも、短歌の歴史を踏まえたときには、注意すべき問題であろう。だからこそ大辻が述べるように、短歌では、原発「事故」は詠めないのかもしれない。しかしそうであるなら、同様に現代社会の問題も、私は詠めないように思う。
ひとつの歌で、原発「事故」を詠むのは、確かに不可能かもしれない。つまり、大辻が述べるような「良い歌」は生まれ得ないかもしれない。しかし歌集であれば、私たちが、ある場面では「被害者」であり、ある場面では「加害者」であることの揺らぎを表現することは可能であろう。そうであるならば、「良い歌」は存在しないかもしれないが、「良い歌集」は存在しうるのではないか。ひとつの歌で、原発「事故」や現代社会の諸問題に向き合うことはできなくとも、一冊の歌集で向き合うことができるのではないか。少なくとも澤正宏の『終わりなきオブセッション』という歌集は、その可能性を示した歌集であると、私は考える。
そして、私(たち)がすべきこととは何か。澤は以下のようにも詠んでいる。
避難に除染に線量に追われることが「日常」となってしまった地域で、「事故」の「根」を問うことには、限界があるのかもしれない。原発「事故」の「根」は、大変に深い。その「根」を「事故」以前にさかのぼり、問うていくことは、「被災者」だけにできる仕事であるというわけではない。むしろ「被災者」だけに問わせることの無責任さを痛感すべきである。
それを歌で成すかどうかは、ひとりひとりの歌人の問題意識や歌の捉え方によるだろう。大辻の考え方に特段の誤りがあると私は主張したいわけではない。
ただ歌によって、福島と「フクシマ」を考えた歌人がいたということを主張したいのであり、それは狭い「文学研究」の範囲に留まらない研究者によってなされているということを主張したいのである。
文学者や文学研究者が、どのように原発「事故」や同時代の社会問題に向き合うか。そのことが、歌人であり文学研究者である澤正宏という人間によって問われていると、私は考えたいのである。
■コーナートップへ




























































































