第2回 災害の普遍性・〈わたし〉にとっての特殊性――伊藤一彦『待ち時間』・道浦母都子『はやぶさ』|【連載】震災短歌を読み直す(加島正浩)
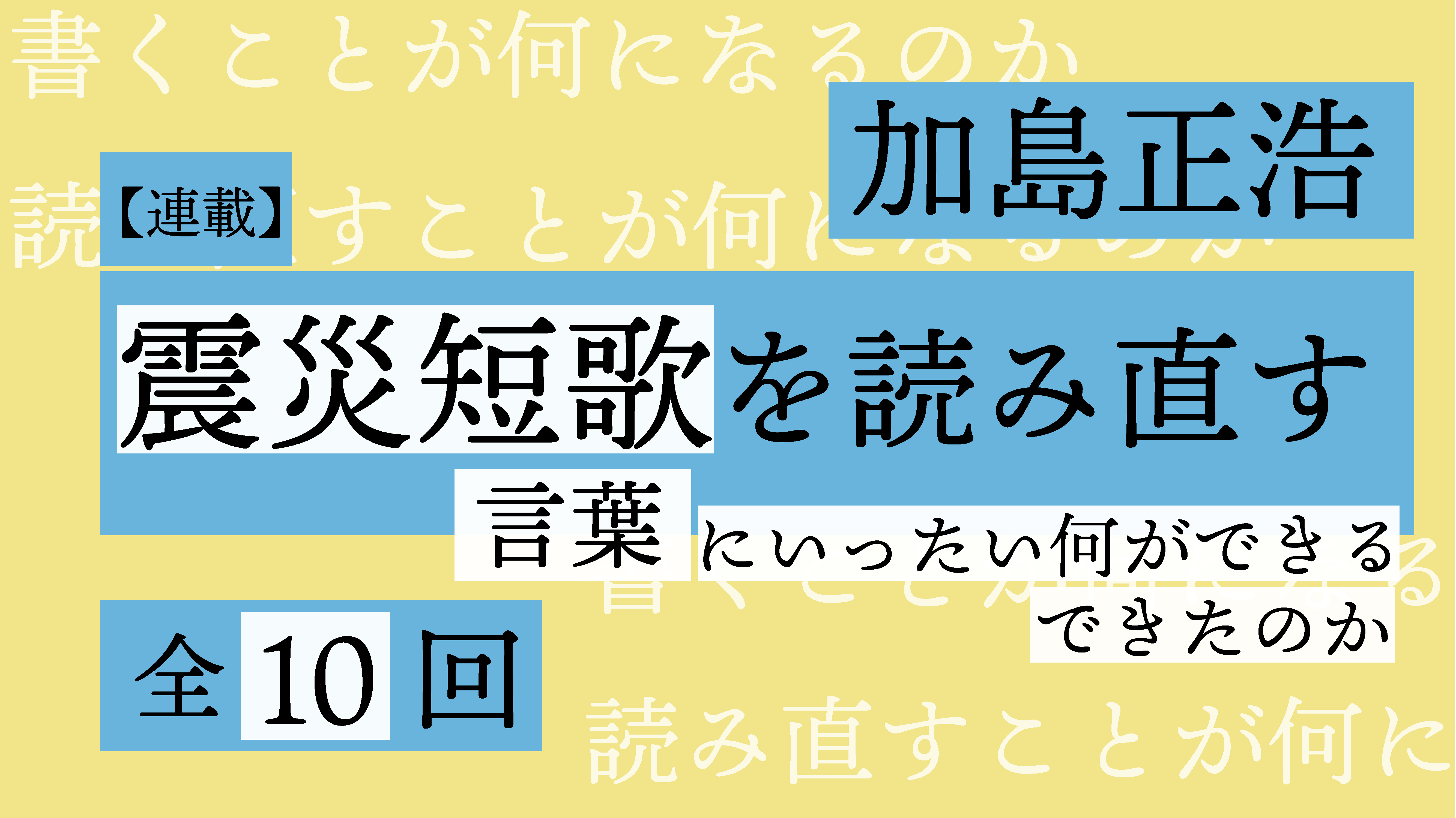
第2回
災害の普遍性・〈わたし〉にとっての特殊性
―― 伊藤一彦『待ち時間』・道浦母都子『はやぶさ』
■〈災害〉に繰り返し襲われながら歌を詠むこと
この一首だけを読む限りでは、コロナ禍で詠まれた歌のようにも思えるが、そうではない。これは2010年に宮崎で発生した口蹄疫を踏まえて詠まれた歌である。詠んだ歌人は伊藤一彦(いとう・かずひこ)。宮崎県出身・在住のベテラン歌人である。上記の歌は彼の第12歌集『待ち時間』(青磁社、2012年12月)に収められている。
ほかにも口蹄疫を詠んだ歌に、以下のようなものがある。
〈いのちの声絶えて聞こえず月光を浴ぶるもこよひ受難のごとし〉
いつもの会場を変更。
〈集会は中止、外出は控へよといふ「非常事態」の中の歌会〉
〈いのちの声絶えて聞こえず月光を浴ぶる〉という歌も、殺処分で家畜が一匹もいなくなった状況を詠んでいると思われるが、「警戒区域」あるいは「帰還困難区域」に指定され、人がいなくなり、動物も殺処分や餓死するなどしてしまった状況を詠んだ歌と受け取ってもしっくりくるように思う。
聞きなれた言葉となってしまった「非常事態宣言」が、都道府県ではじめて発令されたのは宮崎県である。見えないウイルスを封じ込めるために、集会は中止し、外出を控えるように県から指示があり、会場を変更せざるを得なかったというのは、まさにいま、コロナウイルス蔓延のただなかで起っていることである。
■異なる文脈と接続できてしまう歌
ある出来事を詠んだ歌が、別の出来事を詠んでいるようにも受け取れるということを、考える方向は2つあるように思う。ひとつは、〈災害〉の普遍的な側面を詠んでいると肯定的に評価する方向である。〈災害〉が繰り返し襲ってくる国で発達した形式であることも踏まえ、次にくる災害に〈開いた〉秀歌であるという評価である。確かに、〈咎なくて〉や〈いのちの声絶えて〉は大変に優れた歌であると私も感じる。
ただし、もうひとつの方向も考えられるであろう。それは、ある〈災害〉の特殊性を短歌は十全に扱えるのか、という問いを惹起する方向である。しかし、〈災害〉の特殊性を詠むことは可能であるようにも思うのである。
前回、柏崎驍二の〈よい歌でなければ遺らずと人言へど我ら詠む被災現実の歌〉という歌を引き、被災の現実を詠んだ「秀句」は生み出しにくいかもしれないという話をした。
〈災害〉に繰り返し襲われる日本という国では、〈災害〉(→「復興」)→忘却という過程が幾度となく繰り返されてきた。そのため〈災害〉を渦中で詠んだとしても、いずれそれはどのような〈災害〉であったか、多くの場合忘れ去られてしまうということである。
そうである以上、〈災害〉の特殊性を引き受けて詠んだとしても、その歌が〈遺る〉可能性は低い。後にそれを読む人間が理解できるかどうか、不明であるからだ。
そうであるならば、伊藤のように〈普遍性〉に開くように詠んだ方が、後に読む人間からも評価はされやすいと考える。
伊藤は宮沢賢治が、豊沢川で見た幻想(夢)で地獄の様子を詠んだといわれている短歌「青白き流れのなかを死人ながれ人々長き腕もて泳げり」などを踏まえたうえで、
と詠んでいる。賢治は津波を詠んだわけではないが、東日本大震災の津波の様子に重なる歌として読めるということであろう。
未来でも参照される歌というのは、個別の事象の〈特殊性〉を詠む以上に、なんらかの〈普遍性〉を有していることが重要であるということであろう。
しかし、私はそのことの是非を問おうとしているのではなく、災害の〈普遍性〉を詠むべきだとか、災害の〈特殊性〉に着眼するべきだなどと、災害を詠むにあたっての望ましいあり方を提言したいわけではない。
■〈わたし〉にとっての東日本大震災を詠む
では何を述べたいのか。そのことを展開するために、もう1冊歌集に言及したい。道浦母都子(みちうら・もとこ)の『はやぶさ』(砂子屋書房、2013年12月)である。『はやぶさ』には、東日本大震災を詠んだ歌のほかに、彼女がチェルノブイリ((チョルノービリ)を訪れたときの歌、広島で平和祈念式典に出席した際の歌も収められている。
そこでまず注目したいのは、「東北」と別の事件をつなげた歌の存在である。
〈ビン・ラディン殺害されて棄てられし海につながるみちのくの海〉
一見したところつながっているとは思えなかったものが、実は関係しているということを示すのは、(人)文学の仕事のひとつであるし、本来つながらないはずのものをつなげることで、読者に考えさせるのは、文学者の仕事のひとつであろう。そのため歌自体に違和感があるわけではないが、ビンラディンと「東北」をつなげる詠み手の〈わたし〉の「特異性」には気を配ってみたい。
〈今ここに立ちていること奇妙なり福島原発見ゆる護岸に〉
〈弥生三月十一日十四時四十六分それより行方不明となりたるわたし〉
チェルノブイリ原子力発電所を訪ねたのは十六年前
〈からだのどこか噴きこぼれつつ生ききたりチェルノブイリの土踏みしより〉
現在は忘却にさらされつつある東日本大震災だが、発災した当時は衝撃的な災害であったことは、疑いようがない。2011年3月11日14時46分をどこで迎えていたとしても、同時代の災害としてそれを遭遇した者は、もちろん程度の差異はあれ、何かを感じずにはいられないはずのものだったと考える。「東北」に縁のない人であっても、それが何かはわからないが何かを失ったと感じる人はいたはずであり、詠み手の〈わたし〉は〈わたし〉(を形作る何か)の行方がわからなくなってしまったのだろう。
■失った感覚すら失ってしまう日常の前で
あまりにも凄惨な事件に居合わせたり、その傷跡が残る場所を訪れたりした際に、わたしたちは言語化しえない感情に襲われ、絶句することがあるが、その際にわたしたちは、何を失ったかもわからないまま、もしかすると、失ったことにも気がつかないまま、何かを失っているのではないかと歌人は問いかけているようにも思う。
詠み手の〈わたし〉は〈わたし〉を見失ってしまった原因を、おそらくチェルノブイリでの経験に求めている。チェルノブイリの土地を踏んだときから「からだのどこか」が噴きこぼれてしまったと〈わたし〉は詠う。その経験があるからこそ、〈わたし〉は東日本大震災によって自分のなかで何かが失われたことに気がついたのではないか。チェルノブイリを訪れた経験があったから、東日本大震災で何かを失ったと感じたのではない。
誰しもが気がつかないうちに失っていたものの存在に、チェルノブイリの経験があったために、〈わたし〉は気がつくことができたのではないか。
故郷や生活の場所や、大切な人や動物の命を直接に奪われてしまった人たちは、目に見えるもの・見えないものを含め、多くのものを失い、あるいは原発「事故」により奪われたために、失った事実に直面せざるをえなかった。
もちろん次のように述べることで、その人たちのかなしみを蔑ろにしたいわけでは決してなく、いまもなお奪われつつづけている現実を忘れ、発災当時のことを思い返したいわけでもない。
しかし、直接に何かを奪われたわけではないにしても、東日本大震災を目にしたとき、わたしたちは何かを感じたはずであり、そのときに、気がついてはいなかっただけで、何かを失っていたのではないか。失った何かの全体を適切に言語化することもできず、言語化した瞬間に陳腐に聞こえるが、たとえばそれは、政府への信頼であるかもしれないし、無意識のうちに抱いていた科学技術への信頼、明日も同じ生活がつづくはずだと根拠もなく信じることができた感覚といったものなのかもしれない。何を失ったのかは、震災以前にその人が有していた経験によるのだろう。
わたしたちは、自らの意志に反して日常の生活が大きく変えられなければ、凄惨な出来事を前にしたときの感覚を次第に忘れ、日常の生活へと戻っていく。しかし、気がつかなかっただけで、忘れてしまっただけで、わたしたちは何かをおそらく失っている。
圧倒的な日常の前では、失った感覚すら失ってしまう、忘れてしまったことすら忘れてしまうが、そのことを思い出させて、認識させなおすことが「文学」にはできる。道浦が詠んだ歌は、「文学」のそのような可能性を示したのではないかと思う。
おそらく『はやぶさ』に収められた道浦の歌は〈普遍性〉を帯びていない。凄惨な出来事を前にした〈わたし〉の感覚を詠んだ彼女の歌は(学生運動に参加したことを詠んだ歌が代表歌として挙げられることもあるため、ないとは言えないが)おそらく代表歌に取られることはないであろうし、東日本大震災を詠んだ名歌として遺ることもないだろう。
しかし、東日本大震災は「被災地」にいない誰にとっても、震災以前の〈わたし〉とは異なる〈わたし〉へと強制的に変化させるものであったことを示唆する点で、重要な仕事である。秀歌を残すだけが、歌人の仕事ではないという好例であると考える。
また道浦は、以下のような歌も詠んでいる。
〈放射能汚染傘下の地といえど見る限りキエフは美しき街〉
チェルノブイリ原発「事故」を詠んだ歌である。しかしこの歌は、現在に接続して読むことができてしまう。そのような状況に、いまもなおある。この歌が、原発「事故」とは異なる文脈と接続できてしまう現実の前で、わたしたちはいま何を失っているのか。
やはりわからないまま、ただただ失いつづけているように思うのである。




























































































