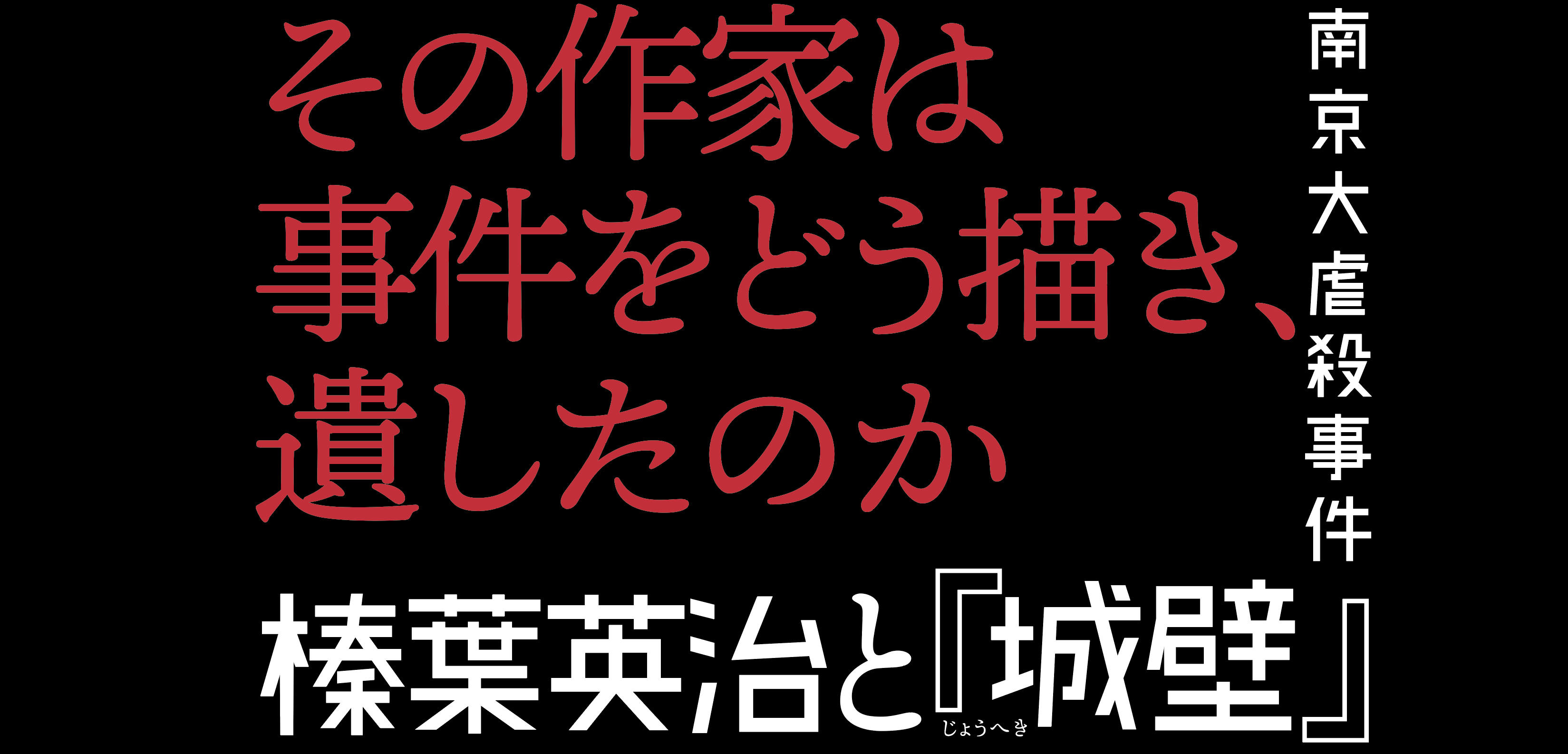2.純文学を希求した直木賞作家として(田中祐介)(2部 榛葉英治という作家)
●2020.06月刊行
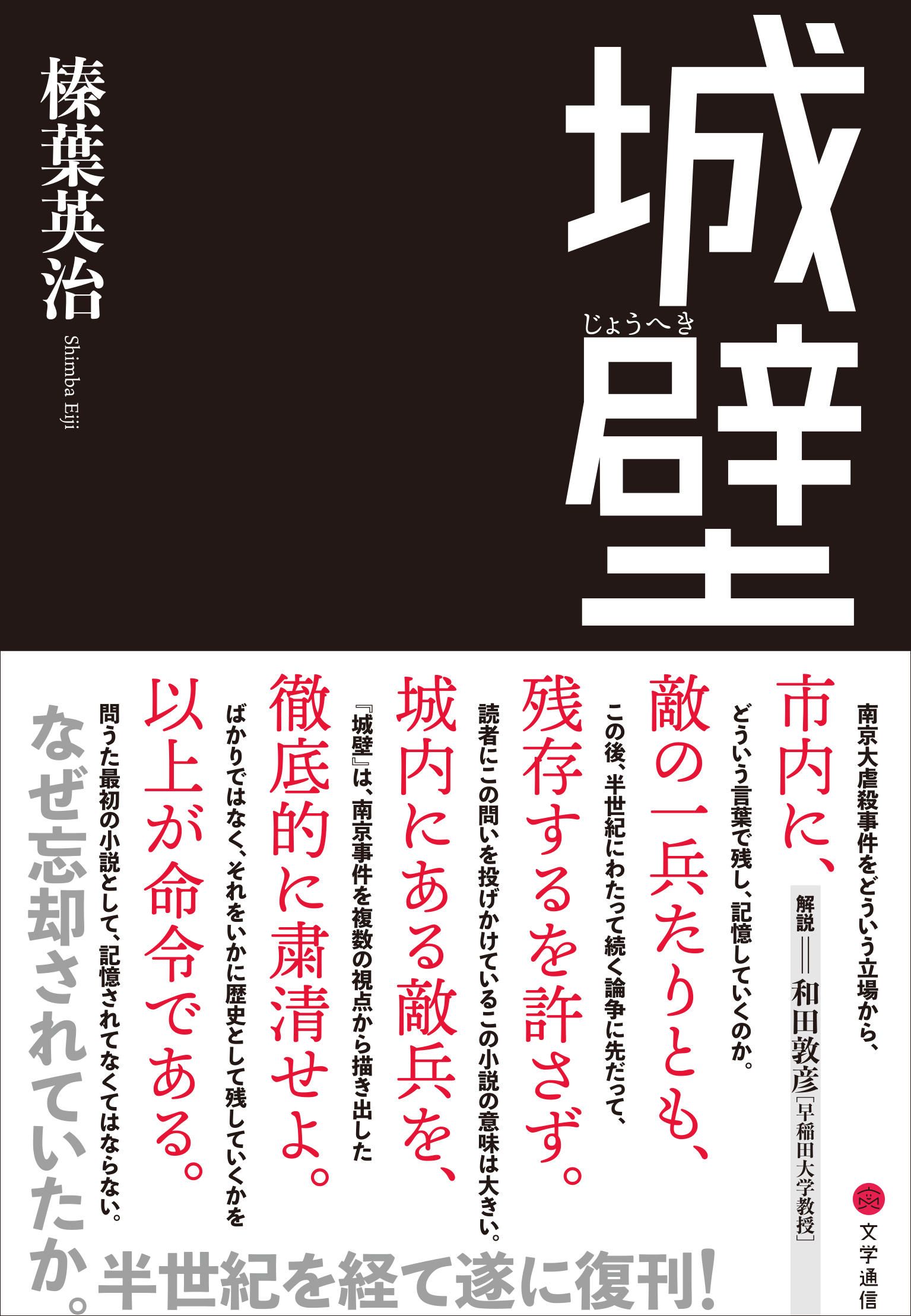
榛葉英治『城壁』
[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)
ISBN978-4-909658-30-2 C0095
四六判・並製・296頁
定価:本体2,400円(税別)
--------
2部 榛葉英治という作家
2.純文学を希求した直木賞作家として
田中祐介
明治学院大学教養教育センター専任講師。編著書に『日記文化から近代日本を問う 人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』(笠間書院、2017年)、論文に「真摯な自己語りに介入する他者たちの声 第二高等学校『忠愛寮日誌』にみるキリスト教主義学生の「読み書きのモード」」(井原あや・梅澤亜由美・大木志門・大原祐治・尾形大・小澤純・河野龍也・小林洋介編『「私」から考える文学史 私小説という視座』勉誠出版、2018)などがある。
●作家生活の理想と現実の乖離
『城壁』の作者である直木賞作家の榛葉英治は、長年にわたり詳細な日記を綴りました。この連載コラムの執筆者は皆、日記の読み解きを2017年から続け、調査研究を続けています▶注[1]。今回のコラムでは、日記から窺える榛葉英治の創作活動の一端をご紹介したいと思います。作家の日記は読者の存在が強く意識されることも多くありますが、それでも率直な、時に赤裸々な私的独白の場であることには変わりありません。
榛葉日記の基調は、創作生活の苦しみです。しかもそれは、純粋な創作の苦しみである以上に、作家生活の理想と現実が乖離してゆくジレンマの苦しみでした。例えば「下らない読物を書いていると、魂まで腐る。しかしそれで生活の宛をつくらないことには、純文を書けない」(1954年1月25日)と書かれるように、純文学作家の「魂」を大切にしたい願望と、純文学以外を多作しなければ生活できない焦燥は、どの活動時期の日記にも頻繁に現れます。
純文学の登竜門である芥川賞を逃したことは、榛葉には痛恨の極みでした。
私としては第二十一回芥川賞をとっていれば、その後の苦労はなく別の道を歩いていたかもしれないとのうらみは残る。佐藤春夫邸のまわりをどなって歩いた太宰治の気持はよく判るというものだ。(榛葉英治『八十年現身の記』新潮社、1993、186頁)
榛葉は敗戦後の1946年に満州から引き揚げ、1948年に上京して創作生活を始めました。戦後初となる第21回芥川賞(1949年)を受賞することは、純文学に身を捧げる新進気鋭の作家生活を歩むために、またとない機会に思われたことでしょう。しかし現実はそうならず、榛葉はその後、戦後の新しい文学ジャンルである「中間小説」、つまり純文学と大衆文学の中間的な小説を書く作家として認知されてゆきます。
●「これからの自分の危険は、中間読物作家にされることだ」
急速に伸長する戦後の出版界において、中間小説や通俗小説の需要も急拡大しました。その需要に榛葉は見事に応えたことになりますが、手を染めるほどに焦燥は高まります。なぜならそうした原稿を量産することは、純文学に費やす時間を物理的に奪うとともに、「非」純文学作家のイメージを世間に植えつけ、みずから培養することになるからです。「通俗雜誌に書いてよいかどうかという大切な問題もあるが、つい断わりきれなくなる」(1949年3月26日)、「これからの自分の危険は、中間読物作家にされることだ」(1950年6月23日)という日記の記述は、榛葉個人の苦悩を如実に示すと同時に、戦後の執筆機会の急増と文学ジャンル再編の力学に翻弄される、当時の多くの書き手に共通した苦悩の存在を示唆しています。
榛葉は時に創作以上に酒を愛し、大いに飲み、飲まれる生活を続けました。痛飲の後悔と断酒の誓いは、30年以上も日記の紙面上に繰り返されます。同様に純文学への専念の決意も長期にわたり現れ、短い時には数週間単位で反復されます。「今日から、当分酒も、外出もやめ、新潮の作品にうちこむつもりだ。これを再出発にして、純文学中心に、そのほかの仕事には眼をくれないつもりだ。何とかして、復活したいと考えている」(1953年6月15日)。しかし、榛葉が反復的に決意する「復活」は、なかなか容易には遂げられませんでした。
そうした純文学への粘り強い憧憬の一方で、榛葉日記には「N賞」受賞への期待が現れるようになります。「「氷河」改作始める。30枚、いいものにしたい。N賞、映画いい」(1956年12月20日)。「長編小説の構想をたてたくなった。現代を書いた自分のすべてを投げこんだ本格小説。N賞もぜったいとらなければ......」(1957年10月24日)。幸いにも榛葉の長編『赤い雪』が、山崎豊子『花のれん』とともに第39回直木賞(1958年)を受賞したことで、期待は現実のものとなりました。
●純文学の「魂」を表現することに成功したのか?
残念なことに、日記は受賞年のみ欠落しており(理由は定かではありません)、当時の榛葉の心の動きを知ることはできません。大衆文学を対象とする直木賞の受賞の喜びと安堵を得ながらも、純文学への復活を常に願った榛葉の心中は複雑だったかもしれません。
『赤い雪』に対しては、受賞後に「所々に見られる文学的ポーズや気負いが少々気にかかったりする」(清水潔「注目される新人たち」荒正人編『大衆文学への招待』南北社、1959年、246頁)との評言も寄せられました。榛葉が大切にした純文学の「魂」は、皮肉にも直木賞受賞作の作品価値を阻害する要因にしかならなかったのでしょうか。
この連載コラムの第一回では、『城壁』の史料改変の問題を取り扱いました。歴史的事実より文学的真実を優先した榛葉は、『赤い雪』から6年後に出版した『城壁』では、史料改変を経てどれほどに、自身の純文学の「魂」を表現することに成功したでしょうか。出版の前年、榛葉は知人からも「純文と通俗小説のあいだで、どっちつかず」(1963年1月10日)と評されていました。史料改変の問題とともに、「どっちつかず」と言われた作風が『城壁』ではどうなったかも、新しい読者となるみなさまにはぜひとも考えていただきたいと思います。
今回のコラムでは、時代に翻弄される榛葉の創作活動の一端をご紹介しました。しかし翻弄を単に翻弄と済ませるのは早計です。榛葉作品はたびたび映画化され、広く鑑賞と消費の機会を獲得し、経済上の恩恵も蒙りました。出版界を凌駕する勢いで戦後に発展し、人々の欲望を駆り立てた映像メディアを榛葉がどう利用し、利用されたかの検証は、次回のコラムに譲りたいと思います。
→つづきを読む。3.映画化に翻弄されて―原作者としての榛葉英治(中野綾子)
注
[1]日記資料に基づく榛葉研究の成果の一部は、「近代日本の日記文化と自己表象」第23回研究会(2019年12月14日)で報告した。また、2020年度日本近代文学会春季大会でもパネル報告を予定したが、新型コロナウイルス感染拡大により大会は中止、報告機会も延期となった。