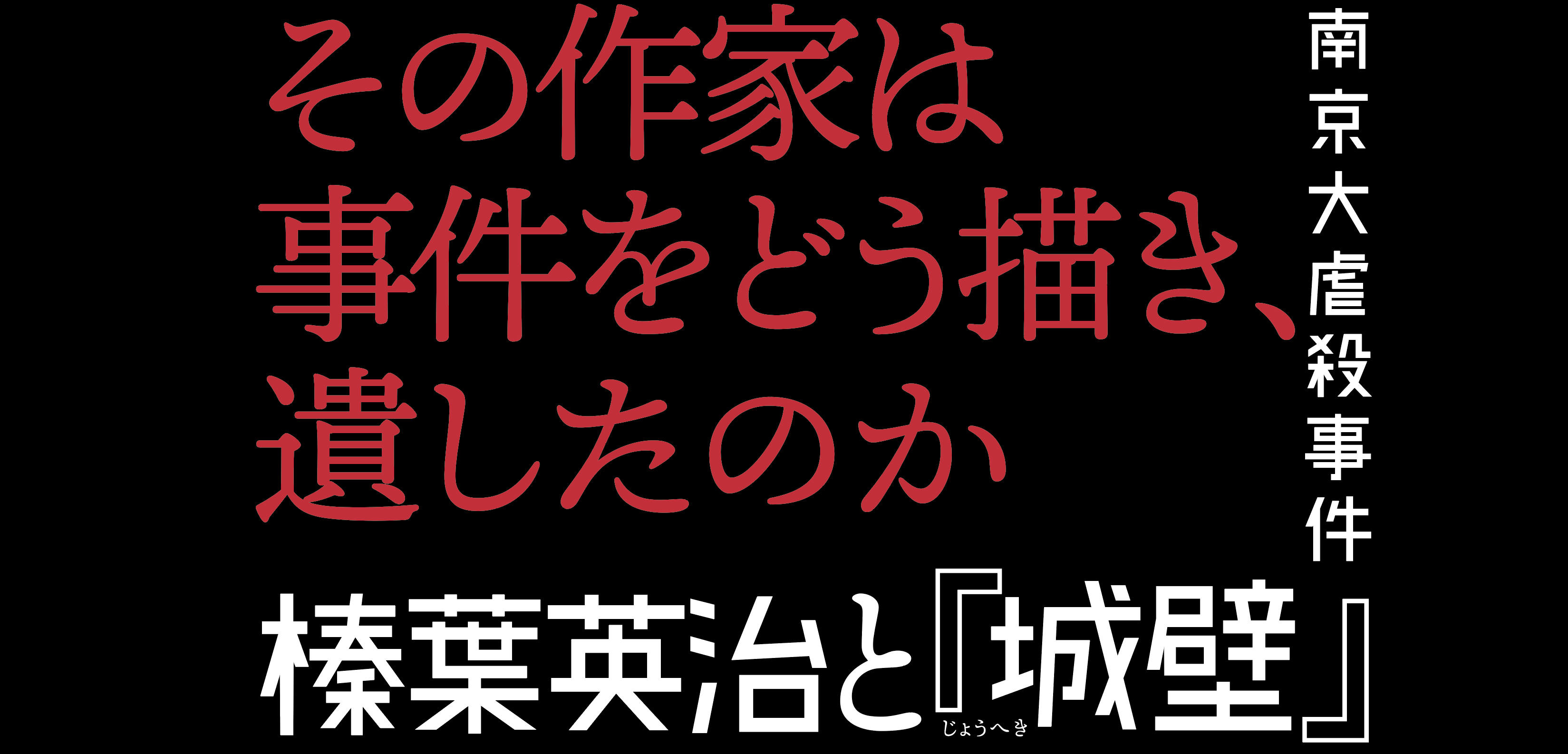1.小説の中での史料の扱い(2部 榛葉英治という作家)
●2020.06月刊行
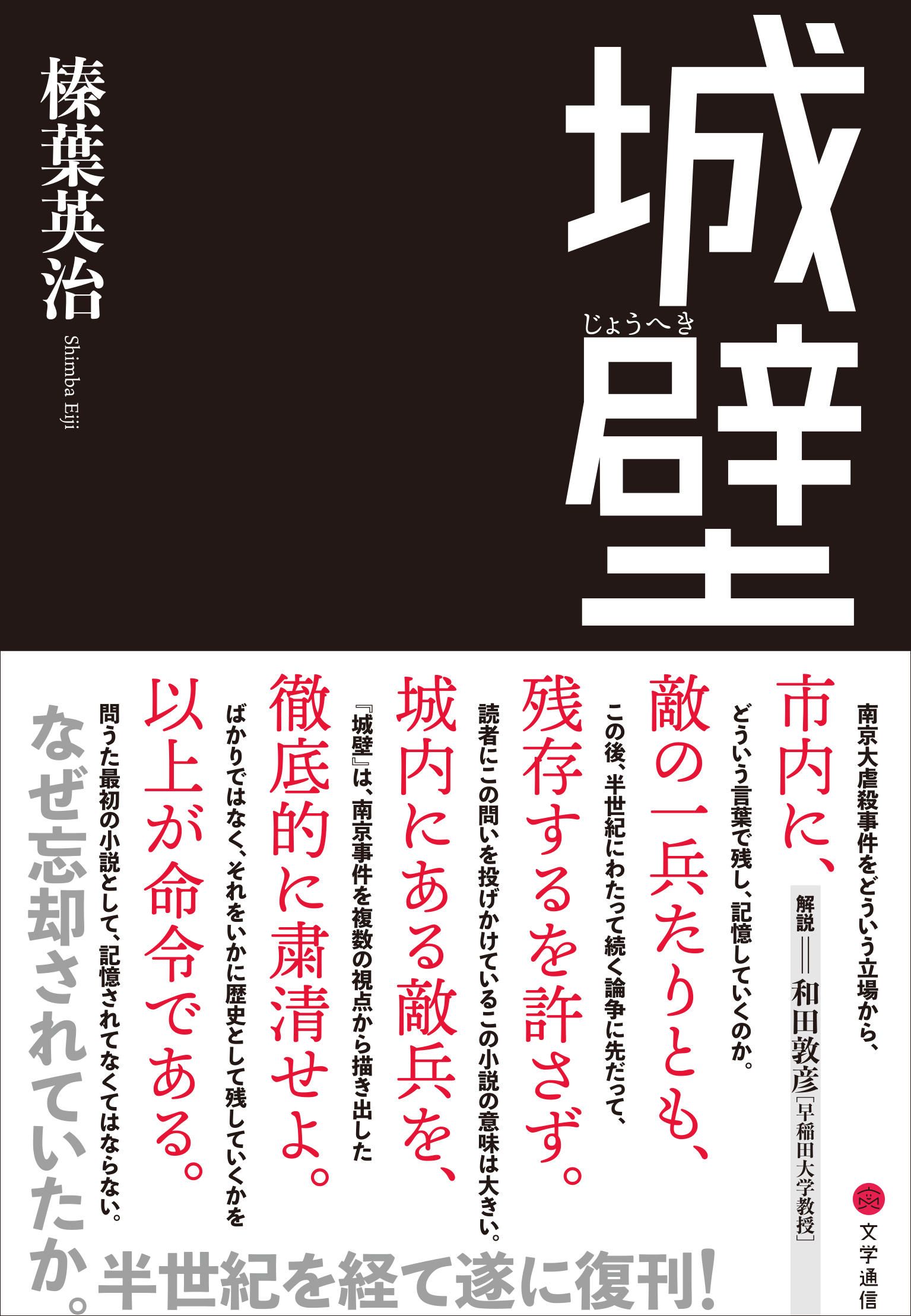
榛葉英治『城壁』
[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)
ISBN978-4-909658-30-2 C0095
四六判・並製・296頁
定価:本体2,400円(税別)
--------
2部 榛葉英治という作家
1.小説の中での史料の扱い
和田敦彦
●作家による史料の改変
「この物語はフィクションです」、あるいは「実話に基づく」小説といった断り書きは、曖昧で、今どき厳密にはほとんど意味をなさない言葉ではあります。ただ、この言葉がそれでも慣行として用いられ続けているのは、物語が本当かどうかの判断を下すのはあなたがた読者や視聴者の側なのだ、と注意をうながしてくれるからかもしれません。
南京大虐殺事件を描いた小説『城壁』を調べている折、考えさせられたことは数多いのですが、具体的にあげると例えば次のような疑問がありました。
実際に存在する歴史資料を小説の中で引用するときに、作家がそれを改変するのは是か非か?
『城壁』作者の榛葉英治は、満州で外交関係の職についているときに、南京事件に関する文書を入手します。それを大幅に引用、下敷きにしながら、戦後、この小説を発表することになります。用いた史料は『城壁』の発表当時はまだ未刊行の知られていない史料でもあり、その点でも『城壁』は重要な意味を持っています。
ただ、細かく史料と小説を比べてみると、大部分はもとのまま史料が使われているのですが、中にいくつか、榛葉英治がもとの史料を改変し、加筆して引用している箇所が見つかりました。具体的にどこをどういう形で変えたのかは、『城壁』解説に対照表を作成して詳しく示してありますので、関心のある方は是非その変更の理由や影響を考えてみて下さい。
さて、研究や教育の場で、史料を引用するときに、特に説明もなくその史料を加筆したり、修正したりして利用するのはむろん御法度で、データの改ざん、ねつ造として厳しい批判や処分を受けることとなります。では小説の場合はどうなのでしょう。フィクションなのだから問題などないと考えるのは早計です。フィクションだと但し書きを入れようが入れまいが、例えば実際に生きているある人物についていいかげんなことを書けば、それによって傷つき、被害を受ける人達が出てくるでしょう。経済的な損失や人命にもかかわりかねないですし、裁判となる事例も少なくありません。
ですから、先ほどの問いの是非について、完全な解答などは実際にはありません。どういう立場から判断するかによって、あるいは用いた史料の種類やそれを改変する目的、その公開の仕方や影響によって是となる場合もあれば非となる場合もあるからです。さらには時代や状況によってもその判断は変わってくるでしょう。単純な是非より、原史料をどう書き換えたかという手段と、何のためにそうしたかという目的をこそ、考えてみる必要があります。
●『城壁』の改変の理由
『城壁』の場合、この手段と目的は比較的はっきりしています。ただ、その手段と目的がずれている、というのが私の感じたことでした。つまり、南京事件を描き出そうという目的と、南京事件の史料に手を加えるという手段との間のずれです。
実際、『城壁』の場合、史料の引用に手を入れている箇所は、例えば虐殺の事実を隠蔽する、あるいは逆にねつ造するといった目的でなされたりしているわけではありません。では何のために、と思うでしょうが、例をあげれば小説内の人物どうし、出来事どうしをより緊密に結びつけるための工夫でそうしています。南京事件に関わった異なる立場の人々が出会う、あるいはその視線が交差しあうような場面を作るための工夫です。
しかし、今日から見れば、南京事件を描こうというときに、そのもととなる史料を都合良く書き換えるということは、その目的がどうあれ過去の出来事を伝えるうえで読者側の信頼性を大きく損なうリスクをおかすことになります。南京事件にできるかぎり近づこうという目的からすれば、そのリスクはあまりに大きい。実際、わざわざ史料自体に手を加えなくとも、この小説を作るうえでは大して困らなかったはずなのです。
●榛葉の小説と歴史資料という二つの表現に対する価値観
では榛葉英治はどうしてわざわざそのようなリスクをおかしたのか、というかそうしたリスクを軽視していたのでしょう。おそらく、小説と歴史資料という二つの表現に対する価値観が、現在と大きく異なっていることがその理由になっているように思います。簡単に言えば、榛葉英治は、小説というジャンルが、歴史資料よりも高度なものであって、小説の出来のためであれば歴史資料の少々の変更などは大して問題にならない、と考えていた節があります。
自身の引揚げ体験をもとに描いた長編『満州国崩壊の日』(評伝社、1982年)刊行の際に、榛葉英治は歴史資料には第三者が手を加えてもいいが、小説の表現には一文字たりとも手を加えてはならない、という趣旨のことを記しています。今から見れば真逆にも思える考え方かもしれませんが、当時の榛葉英治には文学、特に純文学という表現への強い信頼があり、それが、歴史資料を扱う際のある種の傲慢な意識にもつながっていたようです。
ただ、榛葉英治の場合、純文学というジャンルへの過剰な信頼、あるいは信仰は、後々、そこからはずれていく自身の創作を、自ら責め、自身を追い詰めていくことともなっていくのですが。このことについては、この連載コラム第二回「純文学を希求した直木賞作家として」(田中祐介)で取り扱います。
→つづきを読む。2.純文学を希求した直木賞作家として(田中祐介)