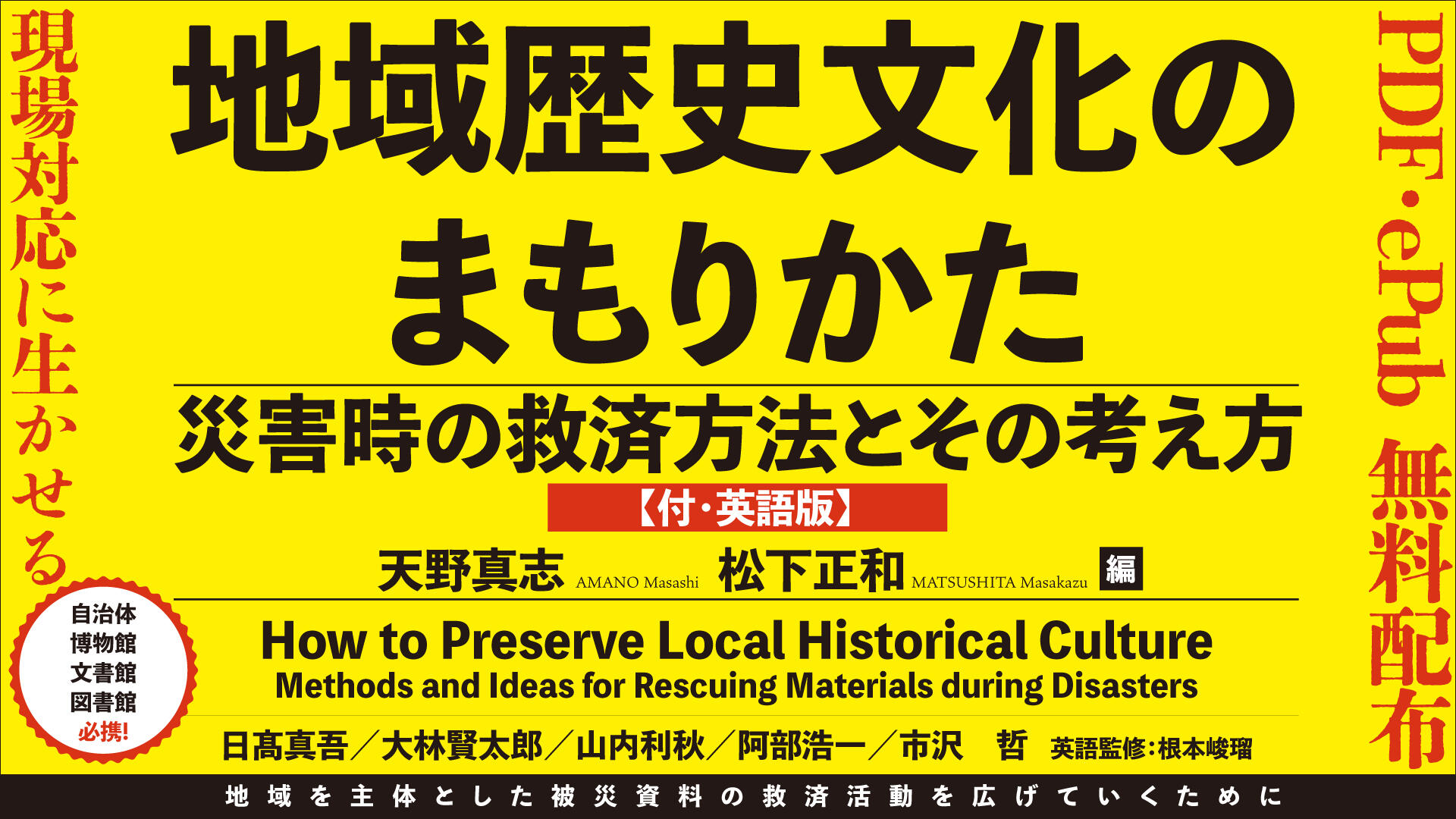第10章 歴史資料保存活動と「専門知」[市沢 哲(神戸大学)]★『地域歴史文化のまもりかた』全文公開
PDFダウンロード
第10章
歴史資料保存活動と「専門知」
市沢 哲(神戸大学)
はじめに
本章では、これまで本書で述べてきた、災害の際に歴史資料を保全するための「知識」「方法」「活動」の意味を問い直す。その際、現代社会における専門知(専門的知識)をめぐる問題を意識して議論を進める。なぜならば、歴史資料保全の活動は、専門知と市民知、市民社会と交差するところで実を結ぶと考えられるからである。専門知をめぐる問題に向きあうためにも、上述の「知識」「方法」「活動」が持つ可能性について考えることにしたい。
1.専門知の現在
2021年に刊行され、同年に人文科学系の賞として権威あるサントリー学芸賞(社会・風俗部門)を授与された竹倉史人氏の『土偶を読む―130年間解かれなかった縄文神話の謎』注1をめぐるやりとりは、現代社会における専門知のあり方を考える上で注目すべき出来事である。すでにこの本については、『土偶を読むを読む』注2で多角的に論じられているが、今一度本章の関心に沿ってこの本がもたらした問題について見直しておきたい。
周知の通り、『土偶を読む』は、考古学の専門的研究者ではない竹倉氏が、考古学者に全く相手にされなかったという自説をまとめた本である。『土偶を読むを読む』で菅豊氏が述べられているように、『土偶を読む』は主たる内容において考古学の専門的研究を正面から批判しているわけではなく、竹倉氏の土偶解釈が開陳された本であった。しかし、具体的内容を越えて、この本は専門知批判の書と受け止められたのである注3。
菅豊氏も指摘しているように、そのことをよく表しているのが、『朝日新聞GLOVE+』の対談記事「『土偶を読む』の裏テーマは専門知への疑問 「素人」と揶揄する風潮に危機感」注4である。記事のタイトルが語るように、竹倉氏の著書は「専門知への疑問」を呈した本、「素人」軽視を批判した本として評価されたのである。
竹倉氏は次のように述べる。
「土偶を読む」をこのようなかたちで世に問うことになった背景には、実は、3.11の原発の問題をきっかけに生まれた専門知に対する不信感があります。
市民がいくら原発の危険性を指摘しても、専門家たちはそれを「素人の意見」としてまともに取り合おうとはしなかった。しかし、絶対安全と言われていた原発はあっけないくらい簡単にメルトダウンにいたった。
専門知も専門家も間違いなく必要です。でも、専門知がわれわれの生活を向上させる実践知に還元されず、既得権益として密室の中で独占されている。このような専門知のあり方が色んな分野で残っている。
専門知がいかに実践知のほうに開かれていくか。リベラルアーツ教育のような形で専門知が一般の人に開かれ、ネットワーキングされ、実践知になり、市民に還元されていく。そういう動きが今後加速するといいなという思いがあります。
僕の研究内容や「土偶を読む」について、すでに色んなジャンルの人が意見を表明しています。この本がそういう議論の着火剤になり、専門家だけでなくいろんな人の意見が交わされ、そこからどの土偶論が最も合理的なのか、広く討議されていくことを願っています。
ここでは専門知の閉鎖的で特権的なあり方が批判されているが、このような専門知批判そのものは決して目新しいものではないだろう。これまでもしばしば言われてきた「専門バカ」批判の一つのバリエーションといえる。また、福島の原子力発電所問題を取り上げて、専門知は市民の意見を無視して原子力発電所を設置したと述べているが、福島についていえば、専門知のなかにもその危険性を主張した意見があったことを全く無視している注5。竹倉氏の専門知に対する理解は粗雑なものであるといわれても仕方がない。目新しくもなく、かつ粗雑な専門知批判が声高になされ、それをマスコミが大きく取り上げたことは、現在の社会における専門知に対する風当たりの強さを示している。
また、対談のなかで中島岳志氏は、次のように述べている。
僕の師匠の西部邁が「世の中のエコノミストがことごとく間違えるのは、経済を知らないからじゃない、経済しか知らないからだ」とよく言っていて、複合的にいろんなことを考えなければいけない、と教えられました。竹倉さんの本を読んでいて、そのことを思いました。
古代について考えるには考古学だけで迫ることはできません。哲学、思想、人類学、いろいろな英知を集結しながら古代と向きあうことによって、私たちの未来も広がっていくと思うのです。そのような古代との向きあい方が、今、縄文を考える際に重要なことだと思います。
考古学だけでなく、あらゆる英知を結集して縄文時代を研究すべきであるという中島氏の意見は、至極まっとうである。しかし、このまっとうな意見が、専門知を粗雑に批判する言説と、知的な媒体において結びつくのも、考えさせられる現象である。
2.「生活」と専門知
ひるがえって歴史資料を保全する現場に立って考えてみよう。歴史資料の保全の場でも、専門知問題が起こることがあるのではないだろうか。
例えば、住む人がいない、住む人がいなくなる住居をボランティアが清掃、整理し、新しい住人に引き渡す「おくりいえプロジェクト」活動を行っているやまだのりこ氏へのインタビュー注6で、次のような話を聞いた。ある旧家の「おくりいえ」を行おうとした際、家屋に大量の古文書が残されていることがわかった。研究者を現場に呼んだところ、調査が必要なので現状変更しないように(つまり手を付けないように)と言われた。しかしその後、研究者の調査はなかなか進まず、結果的に「おくりいえ」は停滞してしまったという。
上記の場合は、研究者のスケジュール感と「おくりいえ」を行う市民の生活感覚が整合しなかったところに問題が生じたと考えられる。このようなギャップについて、心理学者の東畑開人氏は職場のなかに離婚を機に調子を崩した仲間がいた場合を事例に、次のように述べている。
例えば、先の離婚の彼が、しばらくたっても回復しなかったらどうか。仕事が滞り、不機嫌が続く。いつもイライラしていて、周りに当たることもある。すると、世間知は彼を持て余し始める。彼は理解できない存在になり、厄介者扱いされるようになる。孤立していく。
そういうとき、専門知が解毒剤になる。「うつ病じゃないか?」。誰かが言いだす。それが視界を少し変える。仕事の滞りやイライラがうつの症状に見えてくる。すると、周囲は彼に医療機関の受診を勧めたり、特別扱いしたりできるようになる。
この素人判断こそが、心のサポーターに生えたささやかな毛だ。うまく専門家につながれば、そこで適切な理解を得ることができるし、すると彼の不機嫌さが悲鳴であったことがわかる。「厄介者」はケアすべき人に変わる。
これが心のサポーターの背景にある「メンタルヘルス・ファーストエイド」の思想だ。心のサポーターとは、専門知を浅く学ぶことで、とりあえずの応急処置や専門家につなぐことを身につけた素人なのである。専門知が世間知の限界を補う。
ただし、専門知がときに暴力になることも忘れてはならない。「うつ病だ」「不安障害だ」と名指しされることで、本来だったら周りから見守られながら取り組むはずだった人生の課題が、心理学や医学の問題にされる。すると、人はまた別の意味で孤立してしまう。それくらい専門知にはパワーがある。
心理士をしていると思う。私たちは大学院で山ほど専門知を学ぶが、それらは世間知抜きでは運用できない。世間知によってクライアントの生きている日常を想像できないと、支援は専門知の押し付けになり、非現実的になってしまう。だから、心理士もまた、プライベートでは専門家の帽子を脱ぎ、自分の人生をきちんと生きるのが大切だ。そうやって世間と人生の苦みを知ることが、専門知を解毒するのに役立つ。注7
専門知は、本来なら生活のなかで解決すべき問題を、生活から切り離してしまう一面を持っているという警鐘は、生活のなかで守り伝えられてきた歴史資料を取り扱う際に、しっかりと想起されるべきであろう。
また、生活と専門知の関係を考える際には、安東量子氏らによる福島県いわき市末続地区での活動も大きな示唆を与えてくれる注8。福島原子力発電所のメルトダウンがもたらした放射線量をめぐる生活不安のなかで、専門家たちが自説に基づいてさまざまな安全基準を示したり、行政が納得できる説明もないままいったん示した基準を撤回したりした。そのため地域は混乱し、住民同士の意見対立も激しくなった。もちろん専門家に対する不信感も高まった。生活の基盤が動揺するなかで、安東氏は住民自らが放射線量を測定し、生活環境への信頼を取り戻する活動を行った。また、一貫してこの活動に関わり続け、測定値に基づいて専門的助言を行う専門家がこの活動を支えた。安東氏らの活動は、生活環境への信頼―そこには良好な人間関係も含まれる―の再建に向けて、専門知を生活に結びつけた、希有な事例である。
東畑氏の指摘や安東氏の活動は、生活と専門知が取り結ぶ関係を考える際に大きな示唆となる。これらを踏まえて、あらためて本書で述べられてきた「知識」「方法」「活動」の意味について考えてみよう。
3.歴史資料の保全活動が目指すもの
本書で語られてきた「知識」「方法」「活動」は、市民を含むさまざまなアクターと協働した、実際の災害時の歴史資料救出や被災した資料の修復を通じて生まれてきたという特徴がある。そこでは専門知を共有していく、生活の問題と専門知をすりあわせていくことが不可避的に意識されざるを得ない。そういう本質を持っていることをまずは押さえておきたい。
ではその「すりあわせ」を実現するためには、どのような前提に立った、どのような方法があるのだろうか。少し視野を広げてみよう。2022年に刊行された『「専門家」とは誰か』注9は、この問題に正面から向き合っている。
同書が前提としているのは、実際の生活の場、そこで生じる解決すべき課題に接続される場合に露わになる、専門的知識のある種の非柔軟性である。例えば隠岐さや香氏は、専門家が呼び出され意見を求められる場は、科学・技術・社会・政治・経済・行政の規則といった多種多様な要素が交錯する「ハイブリッド・フォーラム」(ミッシェル・カロン)であり、そこに呼び出された専門家は、それぞれの個人の専門研究から逸脱することが求められると指摘している。具体的な問題はしばしば学際的で、判断を下すことに対して強い時間的制約が課されることが多いからである注10。
また、神里達博氏は「諮問と答申」の「軛」、という問題を指摘している。行政が専門家の集まる審議会に諮問を行う。諮問された問題にはその時点の研究では答えられないものもある。しかし、「わからない」と答えるだけでは審議会は役割を果たせない。そこで、できる限りの評価を答申する。これを受けた行政が、そもそも限界があるその答申から都合のよい部分を「つまみぐい」する。というのがその「軛」である。神里氏はこの「軛」の背後には「行政機構の一部である事務局が審議会のアジェンダを決め、専門家を集め、事務局主導で審議会を運営する」構造があると指摘している注11。
では、本来的には限定的な性質を持つ専門知を、現実の問題に即して応用的に使おうとする場合、どのような手立てが取られるべきだろうか。この点について『「専門家」とは誰か』に収録された諸論文は、共通して次のような提起を行っている。
一つ目は、当該の問題に関わる狭義の専門家以外のアクターも、解決のための協議に関わるべきだという考え方である。神里氏は、先ほどの「軛」対策として、エリック・マイルストンの提言を引きつつ、専門家がリスク評価を行う審議会の前段階に、何を専門家にアセスメントしてもらうか、その際にどういう範囲の専門家を集めるか(例えば自然科学だけでなく、人文社会系の専門家や、地域社会の住民代表など)、どれぐらいの期間で答えを出すかを議論する「社会的フレーミング」の段階を置くべきことを提言する。
このような専門家、非専門家(他の分野の専門家を含む)による議論の場の重要性については、菅豊氏も「知のガバナンス」として論じている。菅氏によれば、「専門家と多様な非専門家がネットワーク化し、多元的な観点から知識の品質管理を行い、多元的な知識のあり方を理解し合う」知の「品質管理」のあり方が、「知のガバナンス」であるという注12。
歴史資料の保全の場合を考えると、そもそも歴史資料にはオーナーや研究者だけでなく、さまざまなアクターが関わっている。神戸大学地域連携センター刊行の『Link』では、歴史研究者ではないが、歴史表象や歴史資料に関わる人びとを「歴史研究の隣人」と呼び、インタビューを重ねてきた。家屋の整理を代行する業者の方注13、古書店の店主注14、一般向けの新書などで歴史研究の成果を発信する編集者注15、先の「おくりいえプロジェクト」代表注16、新聞の文化欄で歴史関係の記事を書く新聞記者注17といった方々から話を聞いた。話を聞くなかで、研究者は歴史資料を扱うアクターの一人にすぎないことがよくわかった。
二つ目は、専門知と社会をつなぐファシリテーター、「媒介の専門家」注18、「ある専門分野の、実践についての知識を欠いた、言語についての専門知」注19の役割の重要性である。マスコミと科学技術分野の研究者の間の情報流通を円滑化するSMS(サイエンス・メディア・センター)は、このような媒介的役割を果たす組織として設立されたという注20。さらに、専門知と専門知を結びつけ、他の専門領域で起こっていることを伝える「文化の翻訳家」注21も必要である。
三つ目は、対象に巻き込まれる、参与する研究の活性化である。対象を観察者である自分から切り離して「客観的」に見つめるのではなく、対象に入り込むことで、観察者であった自分を変えていくような研究が求められる注22。このような研究のあり方は、「よそ者」が当事者である地域の人びととともに開発に参加し、自分を新たな当事者へと変えていく、中村尚司氏が唱える参加型開発論注23と課題を共有している。
以上のような専門知をめぐる課題(専門知側が持つ知識の射程、時間的感覚と、求める側とのギャップ)とそれに対する処方箋(①多様なアクターの参加、②専門知と社会、専門知と専門知をつなぐ媒介、③対象のなかに入り込む研究)は、歴史資料の救出、保全の場にもぴったりと当てはまるといっていいだろう。救出と保全はさまざまなアクターの協働なくして実現しないし、現場に臨む研究者は専門知と社会を結ぶ立場に立たざるを得ない。同時に対象となるさまざまな歴史資料の専門家、保存科学の専門家、行政、災害復興に関わる専門家等との相互理解をはからねばならない。さらに、資料を守り伝えてきた人びとや場に深くコミットすることなしに、資料が持つ意味を十分に後世に伝えていくことなどできないだろう。
歴史資料の救出、保全に関わる「知識」「方法」「活動」は、専門知をめぐる問題と深く関わり、問題を乗り越えていく実践という意味を持っている。繰り返しになるが、そもそもこれらは、現場での実践を通して生み出され、新たな現場に持ち込まれて反省的に作り直されてきた来歴を持つ。このプロセス自体が、先に述べた処方箋①~③の実践ではなかっただろうか。
むすびにかえて
以上、専門知をめぐる問題を通して、歴史資料の保全に関する「方法」「知識」「活動」の意味を問うてきた。歴史資料問題は、歴史学、歴史研究の問題であることに立ち返ったとき、当然パブリック・ヒストリーの問題についても触れなくてはならないであろう。
パブリック・ヒストリーについて整理した岡本充弘氏によると、パブリック・ヒストリーは多義的な内容を含むが、「基本的には『パブリックに対する』(to the public)歴史と『パブリックの中』(in the public)にある歴史」に区別できるという。前者は博物館などの社会教育機関、遺跡や遺物、さらには小説、映画、漫画など、専門的な作り手から生み出される歴史である。対して後者は一般の人びとが作り出す習俗、伝承、記憶などを基礎にした歴史で、かつては専門的研究の埒外におかれていた。そして、この両者を、対立的に考えるのではなく、両者の相互性を重視する議論が盛んになっているという注24。
このような整理を参考にすると、歴史資料の保全は、「パブリックに対する」(to the public)歴史、「パブリックの中」(in the public)にある歴史の、双方にまたがる活動であると言える。さらに、時々の場面場面で専門家に限らず、市民を含むさまざまなアクターとの協働がつくられることに注目するならば、歴史資料の保全は、歴史資料にさまざまな関心やスキルに基づいて関わり合う新しいpublicをつくり出す働き(make the public)であるとも言えるのである注25。
現代社会は、誰でも自由に世間に向かって歴史について発信できる時代である。そのようななかで、自分の願望を歴史に仮託するような言説もままみられる。ときには自分が唱える正しい説を専門家たちは知りながら隠蔽しているという陰謀論もある。このような時代にあって、専門家を含めて、歴史を語る資料を残そうという大きな目標で一致し、そのための手立てを考えたり、救出、修復された資料について意見を交わしたりするPublicな空間はきわめて重要な場になるだろう。
以上、先学の引用に終始したが、歴史資料救出の「知識」「方法」「活動」は直接の目的を達成するためだけでなく、専門的研究と市民知、社会を結びつける性質を持つ営みである。今後その意味が一層深められることを期待したい。
注
1 竹倉史人『土偶を読む―130年間解かれなかった縄文神話の謎』(晶文社、2021年)。
2 縄文ZINE編『土偶を読むを読む』(文学通信、2023年)。
3 菅豊「知の『鑑定人』―専門知批判は専門知否定であってはならない」(同上)。
4 The Asahi Shimbun Glove+の該当記事は、https://bungaku-report.com/preserve.htmlhttps://globe.asahi.com/article/14400149から読むことができる(2024年2月15日段階)。
5 添田孝史『原発と大津波 警告を葬った人々』(岩波新書、2014年)、同書は専門知をとりまく諸々の力学を考える上で示唆にとむ。
6 インタビューシリーズ「歴史研究の隣人たち」第2回第2部一級建築士やまだのりこ氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター発行『Link』13号、2021年)。『Link』は神戸大学附属図書館のH.P.の「学術成果リポジトリKernel」から閲覧可能である。
7 『朝日新聞』社会季評(2021年6月17日朝刊)。
8 安東量子『海を撃つ―福島・広島・ベラルーシにて』(みすず書房、2019年)、『スティーブ&ボニー―砂漠のゲンシリョクムラ・イン・アメリカ』(晶文社、2022年)。
9 村上陽一郎編『「専門家」とは誰か』(晶文社、2022年)。
10 隠岐さや香「科学と『専門家』をめぐる諸概念の歴史」(同上)、74頁。
11 神里達博「リスク時代における行政と専門家―英国BSE問題から」(同上)、引用は163頁。
12 菅氏前掲論文、419頁。
13 インタビューシリーズ「歴史研究の隣人たち」(第1回)「家じまいアドバイザー」屋宜明彦氏(『Link』11号、2019年)。
14 同上(第3回)書肆つづらや店主原智子氏(『Link』14号、2022年)。
15 同上(第2回)第1部新書編集者山崎比呂志氏(『Link』13号、 2021年)。
16 注6。
17 インタビューシリーズ第4回として、『Link』15号に掲載の予定。
18 小林傳司「社会と科学をつなぐ新しい『専門家』」(村上編『専門家とは誰か』)、226頁。
19 鈴木哲也「運動としての専門知」(同上)、250頁。
20 瀬川至朗「ジャーナリストと専門家は協働できるか」(同上)、125頁〜。
21 注18小林論文。加えて、藤垣裕子氏はヨーロッパで議論されている「責任ある研究とイノベーション」(RRI)が社会の諸アクターの協業を掲げていることを引きながら、そのためには「隣の領域に口出しすることや、往復による柔軟性は不可欠である」と指摘している(同書所収、藤垣裕子「隣の領域に口出しするということ」、引用は50頁)。
22 注19鈴木論文。
23 中村尚司「当事者性の探求と参加型開発―スリランカにみる大学の社会貢献活動」(斎藤文彦編『参加型開発―貧しい人々が主役になる開発に向けて』日本評論社、2002年)。
24 岡本充弘「パブリックヒストリー研究序説」(『東洋大学人間科学総合研究所紀要』第22号、2020年)。
25 なお、このような「公共」(Public)の考え方については、斎藤純一『公共性』(岩波書店、2000年)参照。