第10回(最終回)福島の言葉を用い続ける歌人――本田一弘『磐梯』・『あらがね』|【連載】震災短歌を読み直す(加島正浩)
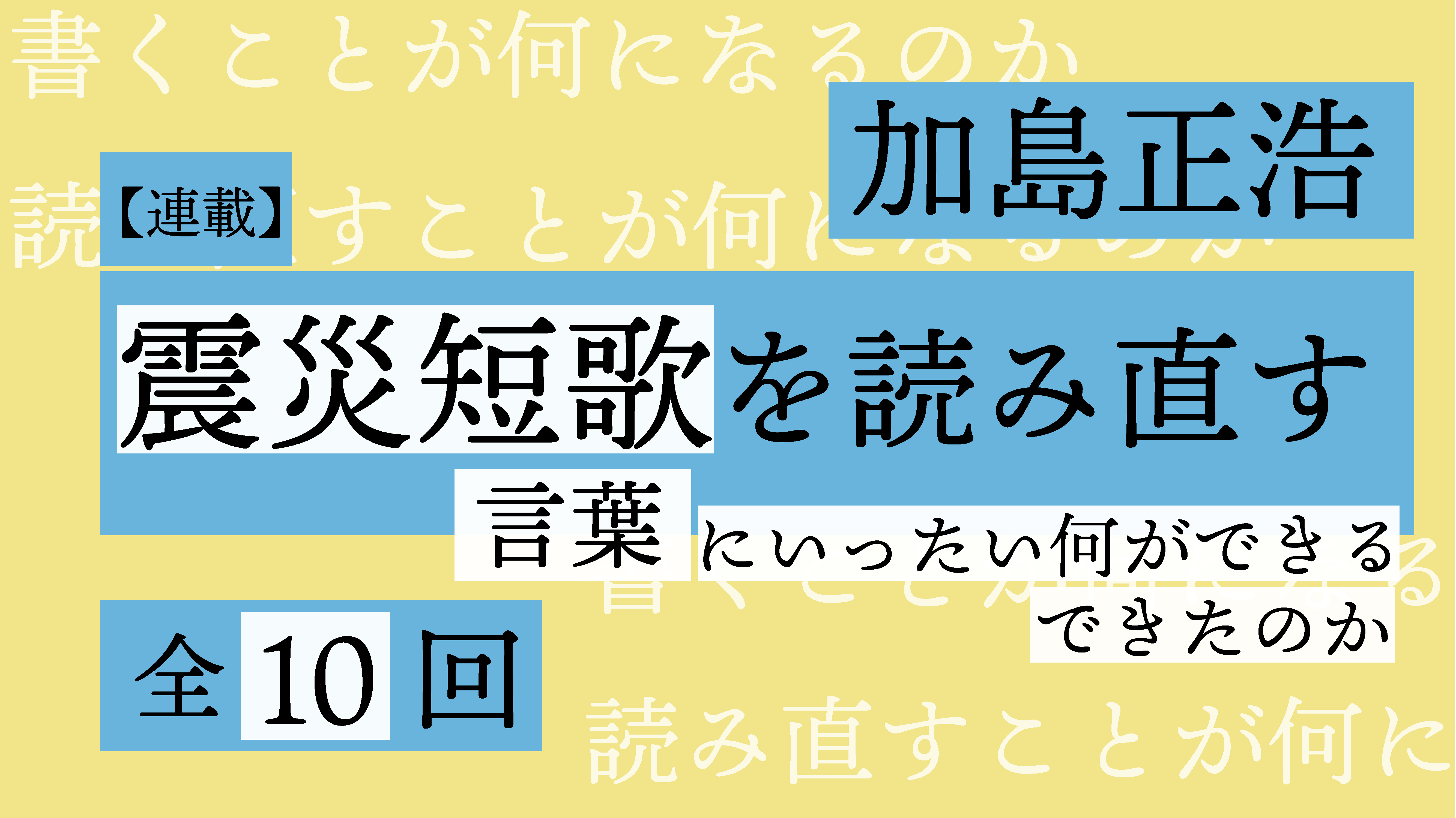
第10回(最終回)
福島の言葉を用い続ける歌人
――本田一弘『磐梯』・『あらがね』
■「事故」を示す言葉も東京=中央が決めている
本田一弘という歌人がいる。1969年に福島市に生まれ、現在は会津若松市に在住する歌人であり、高等学校の国語科教員である。彼は震災後に『
彼の歌の特徴としては、古語や雅語の使用とともに、「方言」の使用が多くみられることである。
〈夫れ雪はゆきにあらなくみちのくの会津の雪は濁音である〉
『磐梯』
福島弁では「かきくけこ」に濁音がつく傾向があるという。それに照らせば、「ふくしま」ではなく、「ふぐしま」が、「ゆき」ではなく「ゆぎ」が、会津や福島の言葉の発音としては適当になるのであろう。「目に見えぬものにおびゆる」のは、福島に住む人々であるのだから、ここでの福島は「ふくしま」ではなく「ふぐしま」が適当であるということであろう。
本田はそのような福島の言葉と、東京を中心に使用される言葉との差異に鋭い反応を示している。たとえば以下の歌である。
〈被災地とふ言葉があれば被災地とよばれ続けるこれからずつと〉
『あらがね』
我々が「被災地」と呼ぶ地域に住んでいる人たちは、果たして自らの住む土地を「被災地」と呼ぶのであろうか、ということを当該歌は考えさせるものである。詞書に、「ばいきんあつかいされて」、「福島の人はいじめられるとおもった」とあるが、福島県内に「避難」していれば、「福島の人」という自称は使わないであろう。福島県外に「避難」した(おそらく子ども)が経験した言葉が詞書に取られ、「被災地」という言葉で福島県が表象されつづけることの暴力性が、ここでは問われているのである。
しかし、「被災地」という言葉を敵視するだけでは、福島が(低線量被曝も含め)原発「事故」被害を被りつづけている事実が不可視化されるおそれが当然生じる。私は、その事実をうやむやに処理する気は一切ない。その事実を踏まえたうえで、原発「事故」被害を被った福島を示す言葉が、東京=中央発信の「標準語」によるものではないかということを考えたいのである。
〈避難区域屋内退避区域計画的避難区域緊急時避難準備区域〉
〈漢語もて双葉のからだ切り分くる避難指示解除準備区域とぞ〉
『磐梯』
東京が制定した「標準語」が、地方の言葉を
東京が福島を(沖縄同様)内的植民地化していた事実が、「事故」以後白日のもとにさらされ、「事故」処理も加害者である行政/東電側が定めていることが問題視されつづけているが、言葉の次元においても、被害の程度を示す言葉が東京で定められているという事実も強調しておくべきだろう。福島で起こされた「事故」にもかかわらず、「事故」やその程度を現す言葉もまた、東京由来のものなのである。
■「土」が育んだもの
先の引用歌の3首目の「双葉のからだ」という表現に着眼したい。本田は震災以前から〈みちのくの体ぶつとく貫いてあをき脈打つ阿武隈川は〉(『磐梯』)など、土地を体に見立てた歌を多く詠んでいる。なかでも注目したいのは「土」である。
『磐梯』
『あらがね』
「除染」された土を「なきがら」や「むくろ」と、本田は言い表す。「なきがら」や「むくろ」であるということは、「除染」され「死体」となる前の土には、「魂」が宿っていたはずである。その「魂」とは何か。
〈福島のつち疎まるるあらがねのつちの産みたる言の葉もまた〉
『あらがね』
「あらがね」とは、発掘されたばかりでまだ精錬されていない金属のことを示す言葉であるそうだ。「あらがね」は、おそらく「つち」に係るのであろう。本田は、土には言葉が、まだ精錬されていない言葉が宿っていると引用歌によって示している。土がなければ、言葉は生まれないが、土が宿す言葉はまだ精錬されていない。だからこそ、歌が言葉を鍛えるという流れがあるのであろう。
福島の土には、福島の「生」の言葉が宿っている。福島の土が疎まれるとすれば、福島の言葉も同様に疎まれるのではないかというのが、2首目である。ただ「言の葉もまた」で歌が終わっているように、福島の言葉が疎まれるという結論が提示されているわけではない。「あらがねのつち」が含むのは「あらがねの言の葉」である以上、それを歌人が鍛えることは可能であるわけである。では、本田一弘という歌人は、なぜ歌によって言葉を鍛えようとしているのだろうか。
■言葉がある限り、消えない
〈復興は何をもていふふくしまのからだは雪の声を抱けり〉
〈たましひを信ぜずといふその人に福島に降る雪を見せばや〉
〈垂直に雪はふりつつ現し身の肩にし触れむ死者の手の平〉
〈ふくしまに生れし言葉はふるさとの土を奪はれさまよふらむか〉
〈亡きひとの言葉と記憶うけつがむために訛りてゐたるわれらは〉
『あらがね』
「復興」という言葉があるが、いったい何がどうすれば「復興」といえるのか、的確に答えられる人がいるとは思えない。「復興は進んでゐます」(「標準語」であろうか)という言葉には、セシウムが付着しており、絶えずそこからセシウムが漏れ出ている。最低でも「復興」という言葉から、セシウムを「除染」することなしに、「復興」は果たされないであろう。
未だ「復興」がなされえない福島/ふくしまは、「雪の声」を抱いていると本田は詠む。そして福島に降る雪には「たましひ」があり、垂直にふる雪に死者の手の平を感じるとも本田は詠む。土は「除染」されてしまう。山も田畑も、もとをかえせば土である。土をもとにした「自然」は、「除染」によってかたちを変えてしまうかもしれない。行政が決定する政策によって。しかし雪だけは奪えない。そこにセシウムが含まれようとも、会津や福島市には、雪は降り続けるのである。そこに「たましひ」や「死者」を感じると詠む本田の歌からは、「死者」を行政によって奪わせないという意志を読み取ることも可能だろう。
ただし、「死者」は雪にだけ存在するわけではない。我々が思うところに「死者」がいるというのは、原理としておかしい。生者の思い通りに「死者」がなるわけがないからだ。『磐梯』においても本田は、〈山鳥はこゑひくく啼く三年をまだ見つからぬ死者をよぶこゑ〉、〈忘れえぬこゑみちてゐる夏のそら死者は生者を許さざりけり〉、〈偶然に死ななかつた中年の俺のめだまが
そして、見なければ聞こえないものの代表が「言葉」であるのかもしれない。福島/ふくしまで生まれ、話されていた言葉は、避難区域に指定された場所では長らく話されることがなかった。福島/ふくしまを離れた「避難」先では、福島の言葉が話される機会は激減したであろう。福島の土が「汚染」され、多くの人々が福島を離れなければならなくなったとき、福島の言葉は帰着する場所を見失い、本田が詠むように、さまよったのかもしれない。
だからこそ本田は、「亡きひとの言葉と記憶うけつがむために訛」るのだと詠む。福島/ふくしまの言葉は、本田が生まれる前から育まれ、本田へと手渡され、また次の世代へと継承されていくものである。だからこそ、本田は歌に「方言」を折り込み、福島の言葉を鍛えようとしているのであろう。言葉がある限り、福島/ふくしまに住んでいた人たちの「記憶」は消えないのである。
それは逆も同じである。「避難区域」などの言葉が消えない限り、「事故」は終わらないのである。東京=中央主導でなされている「事故」処理であるために、「事故」以後を現す言葉も東京の言葉=「標準語」であるという話は先にした。しかしその言葉を、福島/ふくしまの言葉で表現「しなおす」べきだという話を私はしたいわけでもない。現状では福島の言葉に置き換えた瞬間に、東京=日本が「事故」以後の問題を自らの問題と捉える視点を欠落させ、福島を見捨てて、撤退する姿が目に見えるからである。
せめて「事故」以後に出現した「避難区域」「除染」などの言葉が、現実に飛びかうことなく「死語」になるまで、行政は徹底して「事故」処理に取り組むべきであるとだけ、ここでは主張しておきたい。「事故」以後の現実が覆い隠されようとするとき、言葉もまた覆い隠されている。しかし、覆い隠されたとしても、「事故」以後の「汚染」された現実が消えることなくして、言葉が消えることはないのである。また言葉を使う仕事をしている人間が、現実より先に言葉を消すこともない。だからこそ福島の言葉を用い続ける歌人の仕事は重要なのである。福島の言葉が消えない限り、福島は消えないのである。
■私(たち)は何も知らない
私たちは言語によって現実を認識しているというが、現実を適切に認識するというのは、難しい。私たちは知らないもの、経験していないものを認識することはできない。
『磐梯』
そこに家があったことを知る人だけが、この場所で何が起きたかを認識することができる。震災以前にそこにいなかった者は、よすががなければ、そこを単なる「くさむら」としか認識することができないであろう。
本連載においては、主として津波や原発「事故」の被害を被った「当事者」の短歌を多く取り上げた。それは「当事者」が、東日本大震災について発言できる「特権」などを有しているという考えが私にあるからではない。
ただ私は、地震や津波に居合わせなかった。原発「事故」の被害を強く被ったわけでもない、「事故」被害が大きい地域に居住し続けている/た人間でもない。しかし私は、東日本大震災以後の文学を研究する研究者と名乗り、偉そうにいくつかの論文を書き、連載を持たせてもらっている。私は何も知らないのにかかわらずである。震災によって「何が」奪われたのか。私はそれを、「被災地」に赴き、具体性をもって明確に何かを指し示して語ることはできない。
私は、何も知らない文学研究者として、震災を「経験」した人の言葉をよすがにしようとしたのみである。それ以上の特段の意味はない。「当事者」以外の人が震災について語るべきでないとか、事実に基づかない詩歌(フィクションとしての「文学」)を評価しないという態度を表明しているわけでもない。
ただ私たちは、震災や原発「事故」に関して、いったい何を知っており、知ろうとしてきたのかを、私自身をも含み、問いたかっただけである。
本連載10回だけでは、私の力不足もあり、多くの歌集や歌人、同人雑誌(一冊も触れることができなかったが、福島・宮城・岩手には膨大な文芸同人雑誌が存在する)に触れることができなかった。しかしそれと同時に記しておきたいのは、震災から11年が経過し、震災後の文学研究が一定の盛り上がりをみせているにもかかわらず、歌人以外の人々には、大量の短歌がほとんど触れられることなく放置されていたという事実である。本田が詠むように、「被災地」での言葉は、さまよっていたのである。
しかし、多くの言葉を「さまよふ」ままにしてしまっているのは、私の力不足である。「被災地」で詠まれた言葉をよすがに、「被災地」を知ろうとした私の試みが、読者の方のなんらかの思考のよすがになっていれば、望外の喜びである。
ひとまず連載は、ここで終えさせていただく。10カ月間お付き合いくださった読者のみなさまに深くお礼申し上げる。
=================================
本連載は2023年夏に書籍として刊行予定です。
ぜひお楽しみにお待ちください。(編集部より)
=================================
■コーナートップへ




























































































