第4回 幾度も「戻されながら」詠うこと――梶原さい子『リアス/椿』|【連載】震災短歌を読み直す(加島正浩)
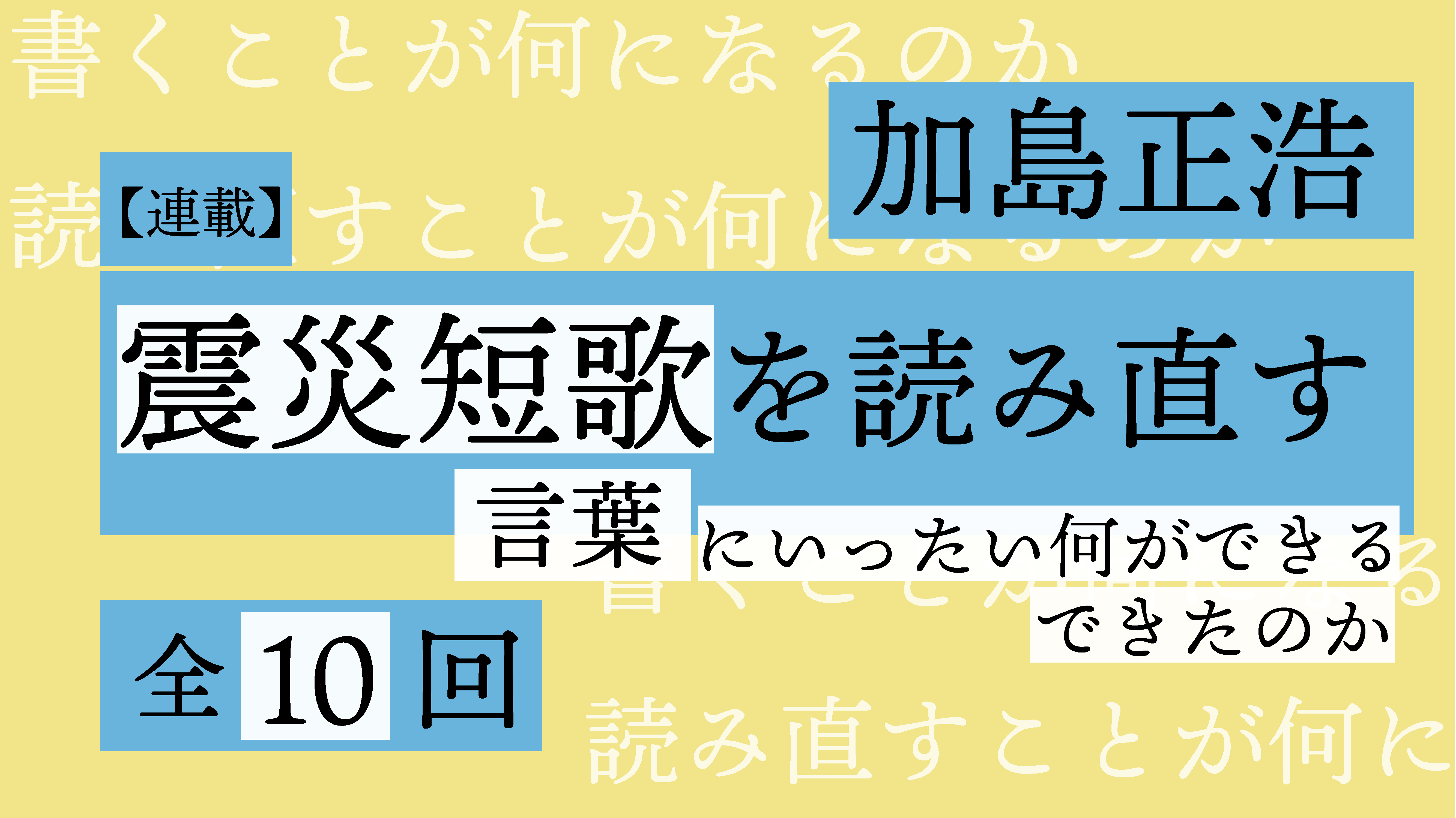
第4回
幾度も「戻されながら」詠うこと
―― 梶原さい子『リアス/椿』
■暮らしつづけることでしか、わからないもの
宮城県仙台市在住の歌人、佐藤涼子に〈見た者でなければ詠めない歌もある例えばあの日の絶望の雪〉という歌がある。(佐藤涼子『Midnight Sun』書肆侃侃房、2016年12月)
私も、佐藤が詠む通りであると思う。見た者でなければ、経験したものでなければ、詠めない、わからないことはあるはずである。さらに付け加えるならば、そこに暮らしつづけていたものしかわからないこともあると考える。
気仙沼市の神社が実家である梶原さい子の『リアス/椿』(砂子屋書房、2014年5月)は、そのことを読むものに示す歌集であると、まずはいえる。たとえば、以下のような歌である。
〈跡形も無き町筋のまぼろしの間口を思ひ描かむとして〉
〈津波がどこまで来たのか、というのは津波襲来後に訪れた人にも伝えることができる基準である。しかし「誰までを、来たのか」と問え、またそれを理解できるのはそこに誰が住んでいるかを知っている地縁のある人でしか、ありえない。
津波が襲来した後の町をしか知らない私(たち)のような人物には、眼前に映る津波後の景色しか見えないが、津波以前から住んでいた人たちには、眼には映らない「まぼろし」の景色を思い描いてしまうこともあるのだろうと思う。以前と以後の景色が織り交ざるように見えるときもあるのかもしれない。
地震/津波/原発「直後」には注目が集まるが、記憶の風化が問題視されることはあれ、その後の変化に注目が集まることは少ない。アメンボがびっしりと増えたという光景などは、まさに地震以後もその土地に住みつづける人でなければ、わからない、詠めない歌であるといえるだろう。
■「津波以前」から暮らしているということ
梶原の歌集の特徴は、それにとどまらない。『リアス/椿』は、2009年から2013年までの歌が収められたⅡ部構成の歌集であり、Ⅰが以前、Ⅱが以後となっている。そのⅠには、2010年2月に発生したチリ地震津波に遭遇した際に詠まれた梶原の歌が収められている。
〈おとうとを奪ひし海を
〈皆誰かを波に獲られてそれでもなほ離れられない 光れる
名取市の閖上地区・石巻・気仙沼は、そもそも津波の常襲地域であった。小母ちゃんたちが話す50年前の津波とは、1960年に襲来したチリ地震津波のことであろう。50年のサイクルで、再度同じ場所を震源地に津波が押し寄せる地域に居住しつづけること。それは、親族や大切な誰かを失うことと常に隣り合わせであるということであり、誰かを波に獲られる経験を現にしているということであり、それでも海と生きていくことを選び、離れられない思いが、さまざまにあるということなのであろう。
水底に死者が根を降ろしている地域から離れられないのは、地上で生き延びた人と水底に住む死者とが縁によってつながれていた/ることも意味するのかもしれない。そこに住んでいる人間にしかわからない、人と土地とのつながりが存在するのである。
■言葉を寄せつけない「大震災」であったということ
しかし、津波の常襲地域とはいえども、東日本大震災は桁違いの「大震災」であった。「東日本」大震災という名称が定着し、震災に関する言及がこれまで以上に多かったのは、単に震災が広域に及んだからというだけではなく、地震と原発「事故」による放射性物質の飛散が「東京」にまで至ったからである、と断言してしまっても、もはや差支えはないように思うが、「大震災」の中心地となってしまった場所においては何が起きていたのか。
〈腕に名を書きしを言はる流されて
朝日新聞の青木美希記者が、福島第一原発から4キロの住宅で、原発「事故」が起きた12日後に、75歳の男性が「餓死」して亡くなっているのが見つかったというツイートを2022年の3月9日に行っている。(https://twitter.com/aokiaoki1111/status/1501437773651210240)
「想像を絶する現実」は、報道には乗らず人口に膾炙しないという現実がある。
上記に引用した梶原の歌も、そのような「現実」を示すものでもある。
私は、ここに言葉を連ねていくことにためらいを感じる。この歌の前に、何を述べてもそれは「間違っている」ように思う。蛇足になることを承知のうえでいえば、それが「想像を絶する現実」ということなのだろう。言語(これまでの秩序)のなかに取り込めない「現実」が、そこでは起こっていたわけである。
■想像されることや、飛び交う言葉のうえでの断絶
ほかにも、梶原による以下の歌をみてほしい。
〈DNA鑑定といふ言葉ありて暮らしのなかに滲むがごとし〉
〈ただ一人生き残れるを語る子の私があの場所にいて波にのまれていたかもしれないという想像は、「私個人」のことであるからできなくもないが、隣にいた人が「流されて死んでゐたかもしれない」という想像は、津波に襲われた地域でなければ起こらない想像であろうと、私は感じる。大津波が襲った地域とそれ以外の地域では、想像の度合いが大きく異なるように思う。
それは想像のみの話ではなく、飛び交う言葉においてもそうである。「DNA鑑定」という言葉が、暮らしのなかに滲んだ地域は、津波で多くの人が亡くなった地域でしかありえないだろう。「震災以後」に使われる言葉においても、大津波が襲った地域とそれ以外では、大きく違いがあったのである。
そして、大津波が襲った地域の「現実」を私(たち)が知るのは、報道を通してであるが、そこで語る人々の言葉を「文字通りに」私(たち)は理解することはできない。「東北」という、共通語と(されている)言語からは距離がある言葉を用いている地域に大津波が襲い、そこでのいわゆる「方言」が理解しにくいために「字幕」というわかりやすい形式でその事実が示されているが、そもそも、私(たち)は被災した人の語る言葉を「文字通り」に理解できているのか、自分の理解できる枠組みに矮小化(「方言」の翻訳などはまさにその好例であろう)して事態を理解しているのではないか。
大津波の際にそこにいなかった者が、またそこで暮らしつづけていない者が、そこで起こったことを語る人々の言葉を十全に理解することはおそらくできていないと、少なくとも私は理解できていないと、思っている。
■最も遠く隔絶された「死者」という存在
梶原は〈あまたなる死を見しひとと見ざりしひとと時の経つほど引き裂かれゆく〉という歌も詠んでいる。津波襲来時から多くの死を見ざるをえなかった人と、そうでない人とのあいだには断絶があるのは、事実であろうと思う。しかし、最も大きな断絶は、生き残った者と波にさらわれた「死者」との断絶である。
〈奔る奔る船の
死者は「彼ら」と呼ばれ、発話能力を有する人たちと区分されるが、その下に「彼ら」がいることは誰も口にしない。そして、船と海とのあいだには境界があり、海は「彼ら」のものであるという。夜の浜にも「死にたることを知ら」ないものが漂っているという。
梶原は「死者」がいることを、海が「死者」のものであること、「死者」が辺りを漂っていることを口にするが、それ以上のことには踏み込まない。生き残った者たちとは、隔絶した存在だからである。「彼ら」のことはわからない。「彼ら」の思いはわからない。しかし、梶原は「彼ら」の存在を仄めかすだけで、とどめているわけではない。
■その瞬間に、幾度も戻されていく
〈暖かき午後の授業の只中を日々行き過ぎる二時四十六分〉
〈この浜に起こりたることふつくらとめかぶを解けば泡にじみ出づ〉
〈泡の間にあまたの息の溶けゐるを思ひつつをり 一途に啜る〉2011年3月11日の空模様に似ていれば、あるいは、普段は行き過ぎていく時間であっても、ふと2時46分という時刻を意識すれば、津波が襲来してきたその瞬間へと、戻っていく。めかぶの泡に、そこに息を溶かしていった「彼ら」のことを思う。多くの死を見て生き残った人は、大津波が押し寄せてからいくら時間が経過しようとも、その時と、それ以後の記憶が消えていくということは、おそらくないのであろう。
そこには当然、環境も関わってくる。〈けふはもう出掛けられざり大潮が舗装道路に迫り上がり来て〉〈真夜中に咳止まらざる幼子のほとりに潮の満ち満ちて来て〉忘れようにも、海は、すぐそばにある。多くの人をさらっていった海がそこにある以上、忘れられはしないのであろう。
〈震災の後にも死ありあのときを越えられたのにと誰もが言ひて〉
〈可愛がりくれしひとらの死んでゆく浜から遠き仮の住まひに〉それに忘れるどころか、むしろ「死者」へと近づいていくのではないか。生きている以上、私たちは常に死に一歩近づき、周囲の人もひとり、またひとりと亡くなっていくが、そういうことではない「死者」への接近があるということが(だけは)、梶原の歌からわかる。〈幾たびも繰り返し来し生き死にの打ち寄せてうちよせて花びら〉〈たつぷりと失くせしのちの中空をアキアカネ打ち寄するいくたび〉という歌も梶原は詠んでいる。
本来あったはずのものが失われ、そこに新たななにかが「打ち寄せて」くる。しかし、重要なのは、ぽっかりとあいた場所へと新たなものが「打ち寄せる」ことで、それ以前の喪失が思い出されるということなのだろうと思う。時間の経過は新たなものと生を生み出すが、その度に失われたものや生を思い出すということが、「震災/津波以後」を生きるということなのかもしれない。つまりそれは、生が奪われた震災・津波の時点に幾度も幾度も「戻されて」しまうということなのではないか。
■理解はできなくとも、津波の瞬間に戻っていく
梶原が詠んだのは、死者の内面や考えを理解するためにではなく、多くの死が生まれてしまったその瞬間にただ「戻されていく」大津波「以後」を生きる人の暮らしの姿であった。〈大風のちからに打ち寄せられしかと捜索隊が浜に集ひぬ〉という歌も梶原は詠んでおり、私たちの行為には理由も意志もなく、ただ大風によって「打ち寄せられる」だけの存在であることを、示しているかのようでもある。
理解もできず、戻りたくもないのに死者が生じたその瞬間に、潮が引くように戻されていくこと。その心的な負担を、〈あまたなる死を見ざりしひと〉である私が(本当の意味で)理解することはできない。そこには断絶がある。
しかしこのように述べるのは不遜ではあるが、死者のことを理解できないままに大津波が人を呑みこんでいった瞬間に戻されていく梶原のあり方と、そこで生きつづける人たちのことが理解できないままに、震災のことを考えようとして接近していく営みは、類似していないことはないだろう。
梶原さい子『リアス/椿』が大変優れた歌集であるのは、死者の方へと何度も引き戻される「震災後」を生きる人の生活と圧倒的な「現実」を詠むと同時に、読むものに震災のことを安易に口にさせることを封じ「考えさせざるをえない」強度を持っている点にある。歌集を読んでいる瞬間、読者は「震災」の方へと引きずり込まれていくはずである。無自覚に。意志の力ではなく。
読者が「震災」に引きずり込まれていくことに、何の意味があるのか。それはわからないが、死者の方へと引きずり込まれながら、死者のことを詠んでいる梶原が、それを詠むことの意味を提示しているわけでもない。「意味」ではない。ただそうせざるを得ない圧倒的な力が、梶原の住む場所にはあり、梶原の歌集にはあるのである。
東日本大震災以前の歌を収めたパートに以下のような梶原の歌がある。
歌/詩は、死者のためにあるのか。だとすれば、死者のことを理解できぬままに、何もわからぬままに、歌/詩を介して、そこに「打ち寄せられて」いくのは、「意味」はわからなくとも、間違ってはいないように思うのである。
■コーナートップへ




























































































