第1回 言葉にいったい何ができた(る)のか――吉川宏志『燕麦』・柏崎驍二『北窓集』|【連載】震災短歌を読み直す(加島正浩)
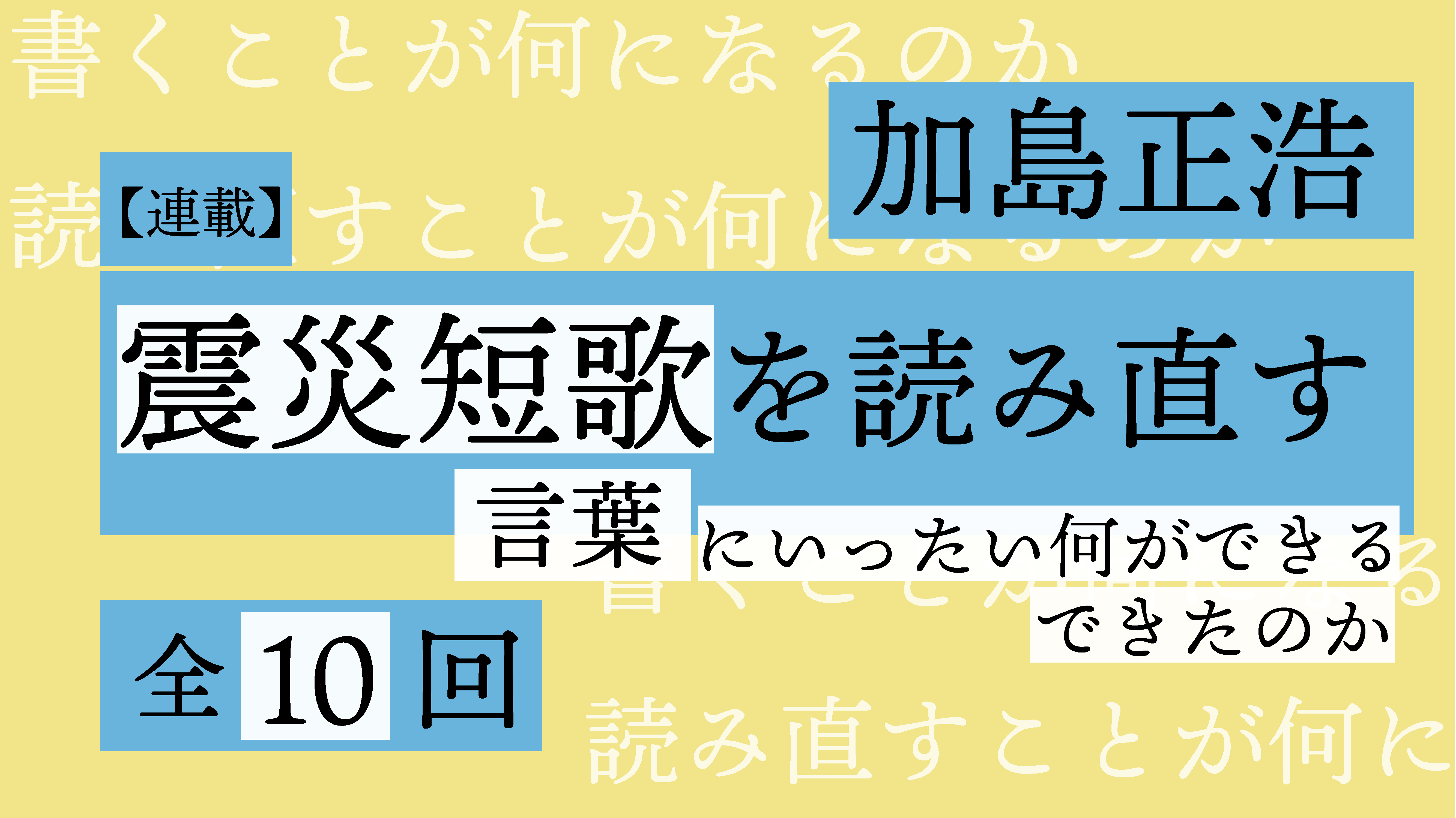
第1回
言葉にいったい何ができた(る)のか
――吉川宏志『燕麦』・柏崎驍二『北窓集』
2011年3月11日から11年が経った。この11年、言葉に何ができたのだろうか。
そのことを考えるために、今回は震災直後に詠まれた歌を収める二冊の歌集を取り上げたい。
■「見えにくい」存在である原発
吉川宏志(よしかわ・ひろし)は、『京都新聞』の「京都歌壇」の選者も務めるベテラン歌人であり、近年は社会派の傾向を強くもつ歌人でもある。『燕麦』(砂子屋書房、2012年8月)は吉川の第6歌集であり、2008年から2012年までに詠まれた歌から成っている。
吉川は原発というものが、原発周辺に存在するものによって、また原発それ自体によってその存在が覆い隠され、見えにくくされていることを喝破している。
〈原爆ドームに似ておれどそこに近づけぬものが映れり雪かすめ飛ぶ〉
〈顔を淡く消されていたり原子炉に働きし人はテレビに語る〉
〈二十キロの鉛の板を運びしとボカシのなかに泣いている人〉
〈貧しきを原子炉に働かせいるさまを貧しからねばテレビに見たり〉
〈誰か処理をせねばならぬこそそれは分かる私でもあなたでもない誰か〉富岡町の多くの場所で原発の排気塔が見渡せる福島第二原発というごくわずかな例外をのぞき、ほとんどの原発はその存在を覆い隠すように立地される。根強い抵抗運動が続けられているにもかかわらず、中国電力が上関原発の建設をあきらめようとしないのは、立地の予定場所となっている長島の西端部分が、本州から原発の存在を覆い隠すような山林が存在するからではないかという話もある。
都市部から離れた場所に建設し、都市部の住民にその存在を意識させないように立地される原発は、そもそもが「見えにくい」存在であるが、原発内部にある〈原子炉〉はそこに働く人以外、ましてや「事故」以後は、目にすることは難しい。また、そこで働く人の〈顔〉そのものも(もちろん、テレビに「ボカシ」が入るのは、そこで働く人のプライバシー保護のためでもあるが)生活のなかで目にすることは難しい。
11年経過した現在でも、原発「事故」以後は続いており(日本は現在でも、原子力緊急事態宣言が発令されつづけている)福島第一原発の「事故」をテレビ映像ではあれ、実際に目撃した世代のみではおそらくは片付かず、それを処理してもらうのは―もしかすると処理への道筋をつけてもらうのも―次の世代の人たちになる。「私たち」はその人たちの〈顔〉を見ることができない。
原発は都市部の人たちからその存在を隠し、そこで働く人たちを隠し、あらゆるものを見えにくくさせたうえで、いまは見えない、存在しない人たちに難事を押し付ける。もちろん直接には放射性廃棄物やプルトニウムの処理をどうするかという難事であるが、処理できるかどうかわからないものを延々と生み出し続ける原発自体が難事のはずである。原発自体が難事であること自体も「見えにくく」させられている。
■どの言葉にどのように反論すればよいのか見えない状況
〈くちびるをあやつるごとき声ありて原発をなお続けむとする〉と吉川が詠むように、「事故」以後にも原発を進めようとする大元がどこにいるのか、誰が原発を維持したがっているのか、その存在が見極められないということである。原発が国策であるために多くのお金が動くという新自由主義的な理由など、原発維持を望む人間にも様々な理由があり、複数の利害関係が絡み合い、社会が複雑化し、誰もその全体像をとらえられず、「誰を」止めれば原発が止まるのかわからないということがある。そもそも特定の何かを止めて止まるようなものでは、もはや、ない。
しかし原発を維持しようとする言葉を〈くちびる〉を〈あやつられるように〉動かし発している人間が、どれだけ本気で原発を維持したがっているのか、それもよくわからない。原発以上に利益をあげられる「何か」があれば、そちらに簡単に動くのではないか。つまり「事故」以後、様々に原発が必要であることを主張する言葉はよく耳にするが、なぜ原発維持を求める言葉が発せられるのかの動機が不明瞭なため、どの言葉にどのように反論すればよいのかが、見えにくくなっているということである。あるイデオロギーに対して「それは正しい/間違っている」と述べるのみでは、相手は説得されにくい。相手と本当に対話しようとすれば、なぜ原発を維持する必要があると考えるのか、その動機を知ることが必要なはずである。
しかし、その動機が見えにくい、いやもしかすると〈あやつられたように〉見える〈くちびる〉から発せられる言葉には動機などないのかもしれない(なぜならそれは仕事だから...)。そのような状態では対話することは難しい。原発〈反対〉以上の言葉を紡ぐことは、そこからは困難であると考える。
■数値に還元できない「私たち」の身体と生活
「事故」以後に用いられたさまざまな言葉によって、様々なものが覆い隠されてきた。たとえば吉川は以下のようにも詠んでいる。
〈死亡率わずかに上がるのみと言う死にて数字となりゆくいのち〉
〈数値へ数値へ議論は入りゆく違うのだ数値のために生きるのではない〉〈被曝〉には、ここまでは〈被曝〉してよいとされている値(しきい値)が定められている。しきい値以下の〈被曝〉量で、発ガンなどがあった場合は〈被曝〉との因果関係が「科学的」には明確でないため、〈被曝〉による発病とは認定されない。(このような低線量被曝の問題については、中村征樹編『ポスト3・11の科学と政治』(ナカニシヤ出版、2013年1月)がわかりやすいため、そちらを参照のこと)
重要なのは、定められているしきい値以下の低線量の〈被曝〉と発病の因果関係が「科学的」に明確ではないというだけで、しきい値以下の〈被曝〉であれば発病しないとは必ずしも断言できない点である。放射線は目に見えないため数値に頼るしかないが、数値に「私たち」の身体が還元できるわけではない。その時々の数値を参考に、「事故」以後に線量が高い地域となってしまった場所に居住し続けるか、帰宅するか、避難するか、働くかを個々人で決めるしかないのである。
〈数値へ数値へ議論は入りゆく違うのだ数値のために生きるのではない〉と吉川が詠むように、「事故」以後に考えるべきことは、「専門家」だけがわかるような細かい数値の話ではない。数値を基に自分で「事故」以後の生活を選ばなければならなかった人たちのことであり、そこでどのような生活が選ばれたのかということである。
「事故」以後に生活を変えることのなかった「専門家」(そうでない人たちももちろんいるが)が使用していた「専門的」な用語、ベクレルだとかシーベルトなどの言葉で、数値は表される。しかし、それが示す放射線量に人々の生活は還元させられない。その言葉に還元できない生活と人生を「文学」は示す必要があるはずなのだ。ただしそれは、線量が高くとも故郷に戻りたいと思っている人・実際に戻る選択をした人と、しきい値以下で生活するのには問題ないと「科学的」には認定されながらも、その地域での生活を選ばなかった区域外避難者とよばれる人々の両方の生活を考える必要があり、片方のみを考えればよいということではない。
■11日が過ぎればまた忘れ去ることをただ繰り返す
そのとき、まず振り返りたいのは〈東北〉の人々の言葉に「私たち」は向き合ってきたのだろうかということである。
柏崎驍二(かしわざき・きょうじ)は、岩手県に生まれ、震災後の岩手に居住していた歌人である。『北窓集』(短歌研究社、2015年9月)は彼の2010年から2014年までの歌が収められた彼の第7歌集にあたる。彼が2013年に詠んだ歌に以下のようなものがある。
その通りである。〈東北がこのままでいい訳がない〉と震災から11年経った2022年に同様のことを私は思う。〈なにか〉は東北に〈吹き荒れ〉たのか。3月に入ると思い出したかのように震災の特集を組んで、11日が過ぎればまた忘れ去ることをただこの11年間繰り返し、結局〈東北〉を「見えにくい」土地のままにとどめおいたのではないか。いまだ「私たち」は〈東北〉で〈吹き荒れ〉るのに望ましい〈なにか〉の外縁すら取られないまま、ただ〈このまま〉を吹き飛ばしてくれる存在に〈なにか〉と言葉をあてがいつづけることしかできていないのではないか。柏崎は以下のようにも詠んでいる。
〈此処がいい此処に住みたいとなほ言へり住み着くといふいのちの力〉
〈我ら〉は誰に〈荒れはでだ浜の様子〉であれ〈見どぐべし〉と述べているのだろうか。震災時に〈東北〉には住んでいなかった、そしてもしかすると震災がなければ〈東北〉とかかわることがなかったかもしれない「私たち」のような人間に、その言葉は向けられているのではないか。「それでも」〈此処に住みたい〉という人たちの思いに「私たち」は向き合ってきたのだろうか。
■「震災後文学論」が取り上げてこなかった文学を考える
東日本大震災以後に、大手商業文芸誌で震災を陰に陽に扱った「小説」が多く書かれたことを踏まえて、「震災後文学」というカテゴリーが現在成立しているようにみえる。もちろん「小説」が多く書かれたのは事実であり、時折「震災後文学論」のなかで戯曲にも言及されるように、震災を扱った演劇も多くある。ただしそれ以上に、詩も俳句も短歌も、書かれ、詠まれてきた。小説と戯曲のみを取り上げ、詩歌を排除しておきながら「文学論」を名乗ってよいのか。
ただし震災や社会問題を詠んだ歌は、「秀歌」にはなりにくく残りにくいため、論じる必要はないという考えもあるだろう。柏崎も以下のような歌を詠んでいる。
〈表現の技法以前のこととしてよき歌を生む作者のなにか〉
〈歌の作者を知るゆゑ配慮あるらしき批評も聴きぬ被災地の歌会〉
〈よい歌でなければ遺らずと人言へど我ら詠む被災現実の歌〉経験したことのない津波に襲われた後、〈表現の技法〉を駆使して「秀句」を生み出すのは、難しいのではないかと推察する。これまでに研鑽してきた〈技法〉が想定していない事態に巡り合ったとき、それをうまく言葉にするのは難しいのではないかと考える。だからこそ津波後に行われた歌会でよい歌を生み出したものは、〈なにか〉と呼ぶしかないものなのではないか。歌会の〈批評〉も平時に生み出された会の「技法」ともいえるだろう。平時のように十全に機能しないのは、当然である。
だからこそ〈被災現実〉を詠んだ「よい歌」は、存在しにくいのかもしれない。しかし「よい歌」を生み出す基盤も、またその評価基準の大部分は、「平時」において研鑽されてきたものである。〈被災〉時には、〈被災〉時の歌があり、歌の詠み方があり、評価のされ方があるはずである。
「よい歌かどうか」という基準のほかに、短歌を詠むことでどう〈被災〉を乗り越えたのか、どのような言葉が生み出され、それによりどのような思考が可能になったのかという評価の方向や、〈被災〉時に歌を詠むことで何を訴えようとしたのか、なぜ〈被災〉時にも人は歌を詠むのかなど考察すべき問いがそこから派生するかもしれない。
■書くことが何になるのか。読み直すことが何になるのか。
私は本連載において、「よい歌かどうか」という基準以外から〈震災詠〉を考えていきたいと思っている。ただし、それがいまの「現実」に有効なのかどうかは、よくわからなくなってしまった。
3月4日にロシアは、ウクライナ南部の欧州最大級で稼働中の原発である、ザポリージャ原発を攻撃した。攻撃のニュースを耳にした後では、いまのロシアであればやりかねないとそう感じたが、私はロシアがそこまでの暴挙に出るとはまったく考えていなかった。それは、原発「事故」の危険性を認識はしながらも、日本で大型の「事故」が起こるとは思ってもいなかったと述べていた人々の思いにも重なるものであったかもしれない。吉川の『燕麦』には以下のような歌もある。
原発の危険性を訴え続けていた科学者のひとりである高木仁三郎(たかぎ・じんざぶろう)を読むことは、その危険性を知ることは、読まないときよりも、知らないときよりも何かを変えうると私は思ってきた。ただ、ザポリージャ原発攻撃のニュースを耳にしたとき、私が感じたのは〈けっきょくは読むだけだった〉という思いだった。この11年はなんだったのだ、という絶望であった。
書くことが何になるのか。読み直すことが何になるのか。私はそこから問い直していく必要があるのかもしれないと考えている。
■コーナートップへ




























































































