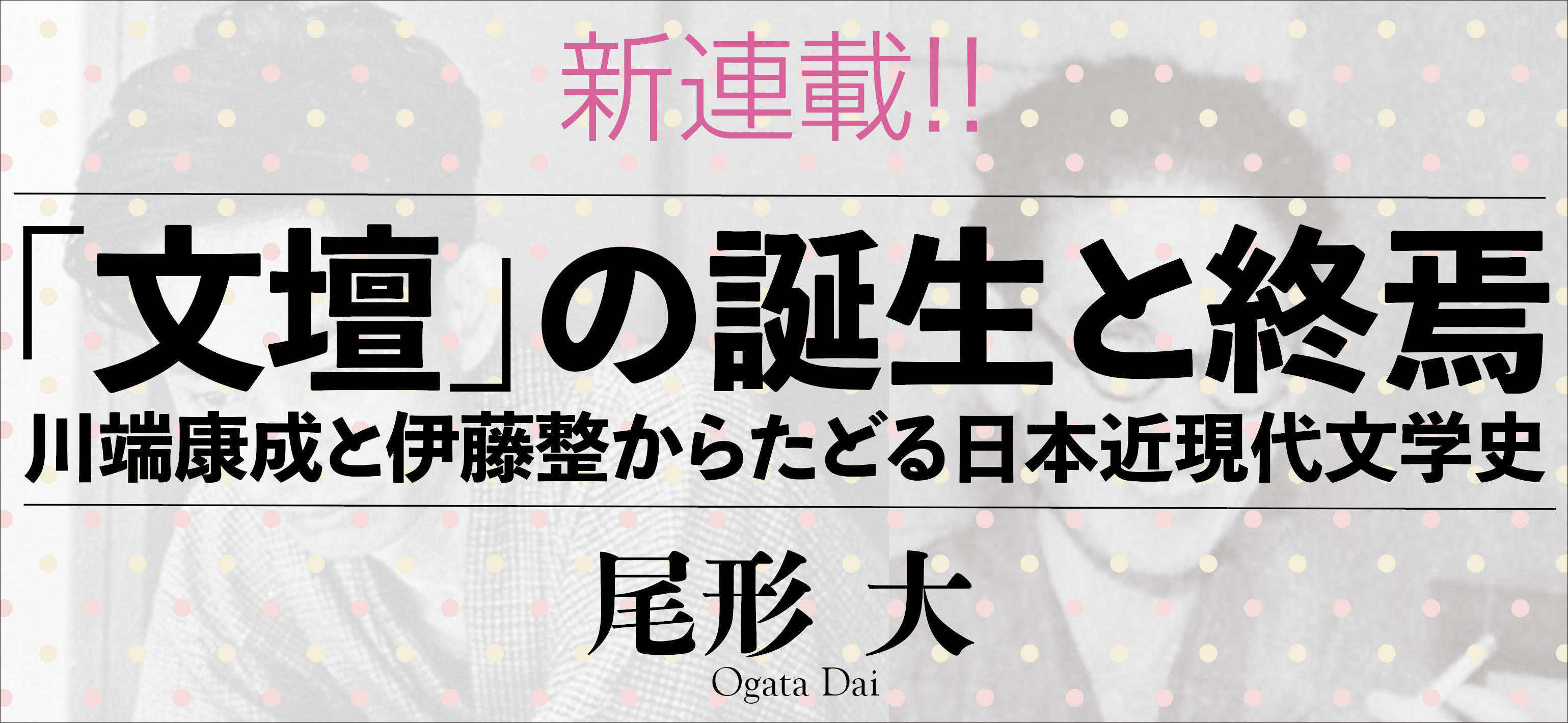第2回「文壇」に登録される―『感情装飾』と『雪明りの路』の作者たち●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史
第2回「文壇」に登録される―『感情装飾』と『雪明りの路』の作者たち
尾形大
▶︎それぞれの文壇参入
大阪出身の川端康成(1899-1972)は北海道出身の伊藤整(1905-1969)より6歳年長にあたる。1917年に第一高等学校入学のために19歳で上京した川端に対して、伊藤は東京商科大学入学のために1928年に24歳で上京を果たした。この11年という時間(年齢差6歳に加えて上京時の5歳の差)は、二人の「文壇」参入に大きな違いを生じさせた。
1920年9月に東京帝国大学文学部英語英文学専攻(後に国文科へ転科)に進学した川端は、まもなく今東光らと同人雑誌の計画を立てる。第三、四次『新思潮』のメンバーだった菊池寛と芥川龍之介に挨拶を済ませ、第六次『新思潮』創刊の許諾を得、第二号に「招魂祭一景」(4月)を発表し好評を博す。こうして川端は菊池寛ら先輩作家連中と接点を持ち、菊池をとおして横光利一と知り合い、1923年には『文藝春秋』の同人に、翌24年には横光らと『文藝時代』を創刊し、千葉亀雄によって「新感覚派」と命名された若手作家の一員と見なされる。1926年6月に第一作品集『感情装飾』、1928年2月に『伊豆の踊子』をそれぞれ金星堂から刊行し、1929年には『文藝春秋』誌上で「文芸時評」を断続連載、『新潮』にも文芸時評「新人才華」を掲載するなど活発な創作活動・批評活動を見せると同時に、反プロレタリア文学をうたった十三人倶楽部に参加し「月に一度新潮社の会議室で四方山話に耽」り、翌30年には新興芸術派に参加。さらに文化学院の文学部長に就任した菊池寛の依頼を受けて教鞭をとるようにもなる。こうして川端は「文壇」に参入し着実な位置を獲得していく。
▶︎川端の〈孤児意識〉
この前後の川端の小説群を読み進めていくと、いわゆる〈孤児意識〉を描いたものに多く出くわす。幼年時に父母を失い、次いで姉、祖母、ついには祖父を失い天涯孤独の身となった川端の〈孤児意識〉は、たとえば戦後川端の代表作へと祭り上げられていく「伊豆の踊子」でも、「二十歳の私は自分の性質が孤児根性で歪んでいると厳しい反省を重ね、その息苦しい憂欝に堪え切れないで伊豆の旅に出てきているのだった。」と旅の目的に据えられている。三十五篇の掌編小説が収録された第一作品集『感情装飾』の巻頭を飾った「日向」でも、「幼い時二親や家を失つて他家に厄介になつてゐた頃に、私は人の顔色ばかり読んでゐたのでなからうか」と自己を嫌悪し、盲目の祖父との生活の記憶が呼び起こされている。また、後に「日向」に代わって川端の「掌の小説」集の巻頭を飾る「骨拾ひ」も、祖父の火葬前後の「私」の心境を記した掌編で、祖父を亡くしたことに深く傷つき、「唯一人になったという寄辺なさ」が描かれている。戦後になって発見された「骨拾ひ」は、加筆の上『文藝往来』(1949・10)最終号に掲載されて、十六巻本版『川端康成全集』(新潮社、1950)以降「掌の小説」集の巻頭に据えられる。
川端の〈孤児意識〉は小説内で語り直され掘り下げられていく。「油」(『婦人之友』1925・10)では「顔も知らない父母の死のために流す甘い涙は幼稚な感傷の遊戯なのだ。しかし痛手にはちがいない。この痛手は自分が年を取って一生を振り返った時に初めてはっきりするだろう。その時までは、感情の因習や物語の模倣で悲しむものかと思った。」と突き放して扱っている。川端は文学をとおして自らの〈孤児意識〉の内実を問いつづける。このことを敷衍すれば、〈孤児〉というプライベートな境遇を繰り返しあつかうことで、川端は大正後半の「文壇」に参入したという見方もできるだろう。
▶︎伊藤の〈捨児意識〉
伊藤整もその文学上の出発期に、自己を〈捨児〉に見立てた印象的な詩を発表している。小樽で友人らと発行した同人誌『信天翁』創刊号(1928・1)に「海の捨児」という詩が掲載された。伊藤の没後、同詩は郷里小樽市塩谷に建立された文学碑に刻まれる。
私は波の音を守唄にして眠る。
騒がしく 絶間なく
繰り返して語る灰色の年老いた浪
私は涙も涸れた凄壮なその物語りを
つぎつぎに聞かされてゐて眠つてしまふ。私は白く崩れる波の穂を越えて
何時私は故郷の村を棄てたのだらう。
漂つてゐる捨児だ。
私の眺める空には
赤い夕映雲が流れてゆき
そのあとへ 星くづが一面に撒きちらされる。
ああ この美しい空の下で
海は私を揺り上げ 揺り下げて
休むときもない。
あの斜面の草むらに残る宵宮の思ひ出にさよならをしたのだらう。
ああ 私は泣いてゐるな。
ではまたあの村へ帰りたいといふのか。
莫迦な。
もうどうしたつて帰りやうのない
遠いとほい海の上へ来てゐるのに。
(「海の捨児」)
詩人としての将来を夢見、東京への憧れを抱いた1928年当時の伊藤は、12人兄弟の長男として病床の父に代わって家族を経済的に背負わねばならぬ立場にあった。夢と現実の間で思い悩む伊藤が生み出したのが、詩の世界での「私」の〈捨児意識〉だった。現実を直視するのではなく情緒の衣に包みこんだ「物語り」として仮構する伊藤と、自らの境遇と向き合い繰り返し問い直しつづける川端。出発期の文学上のモチーフの類比性とその相違は、彼らの後の文学のあり様を物語るように思えてならない。
「海の捨児」の一年前、1926年12月に第一詩集『雪明りの路』(椎の木社)を上梓し詩人としての第一歩を踏み出した伊藤は、当時小樽市中学校教諭として奉職していた。13歳の時に島崎藤村『藤村詩集』(春陽堂1904)を読んで詩の世界に魅了され、生田春月『新しき詩の作り方』(新潮社1918)などを手引きに詩作をはじめ、それから約十年をかけて北海道の自然・風物に繊細な心情を投影した抒情詩集『雪明りの路』を完成させた。伊藤は22歳になっていた。
▶︎詩壇から評価される伊藤
アイルランドの象徴派詩人イェイツの詩集『葦間の風』の一篇"He wishes for the Cloths of Heaven"をエピグラフとして掲げた116篇の口語自由詩から成る『雪明りの路』は、モダニズム文学、プロレタリア文学の盛り上がりに揺れる当時の「詩壇」の動向に比してあまりにも古風だった。しかし、詩集は高村光太郎や小野十三郎、『椎の木』同人らの高い評価を受ける。その理由の一端は、詩集の「序」の次のような言葉に求められるかもしれない。
私は詩壇に一人の先輩も知友もなかつた。私が敢てそれを求めもしなかつたのは、たゞでさへ自分を捉へることの面倒な詩の世界で、当然被るべき影響の為に、自分自身を失ふのを何よりも恐れたのである、私が詩を書き始めたころから詩壇そのものは、すでに一時代を経過してゐる。私はそれを遠く横目で見ながら、どうしたら、何時になつたら自分自身を捉へられるのかと、それのみの為に苦しんできた。(中略)此の詩集の大部分を色づけてゐるのは北海道の自然である。北海道の雪と緑とである、私の故郷は小樽市の西二里、高島と忍路との間の塩谷村である。(中略)――此処が大体私の詩の背景である。(『雪明りの路』「序」)
「北海道の自然」に囲まれた「小樽市の西二里」にある「塩谷村」。「雪と緑」に囲まれた「故郷」が強調され、物理的距離のために「詩壇」との交友、師事関係を一切持ち得ず、ただ「遠く横目で見」ることしかできないという点が前面に押し出されている。「詩壇」との距離の遠さの強調は、純朴な詩人イメージを醸成し、自然のなかでひたむきに自己と向き合う若き詩人・伊藤整像を「詩壇」に提出しようとする意識(戦略)を物語っているように思われる。発行所を引き受けた椎の木社の百田宗治は、『椎の木』第三号(1926・12)のなかで、「既成の詩壇に関係なくひそかに僕の抱いてゐたこの隠れた刻苦のひとを紹介し得るのは何よりの歓びである。最近詩壇の弊害はいたづらに付焼刃の感覚多彩に走つて、言葉の綺羅を飾ることのみを以て豊富なる詩想と解するごとき浅見者の排出であつた。」(「雑筆」)と既成の「詩壇」に自省を促すような、「詩壇」の喧騒から離れた領域に生み出された詩集という性格付けに一役買っている。
私の周囲の事件については、此処に集められたすべてが私の現実の責任にされては困るものもあるのである、それにしても私は此処ではじめて物を言ふ様な気がする。私は長い間身ひとつに秘めておいたこと、私の青春がむざむざと踏みくだかれた時にも、皆に愚かしい私を笑はれた時にも黙つておいた事を今始めて、すつかり言ふ様な気がするのだ。(中略)此処に集められたものを見てゐて私は涙ぐんでしまつた。何もかもが其処から糸をひくやうに私に思ひ出されるのである。之が今までの私の全部だ。なんといふ貧しさだらう。幾年もの私がこんな小さな哀れなものになつて了つた。(『雪明りの路』「序」)
詩の「私」と作者自身とを重ね合わせる鑑賞に対して予防線を張る一方で、「私」が「秘めておいたこと」を告白している「様な気がする」とほのめかしてもいる。「自分自身を捉へ」ようとひとり苦心してきた「私」に比べて、詩のなかに「捉へ」られた「私」は「小さな哀れなもの」として立ち現れる。現実の作者と詩の「私」との境界をすり抜けるような絶妙な位置取りがなされている。
高村光太郎は「或る名状しがたいパテチックな感情に満たされました。チエホフの感がありますね。」という葉書を書き送った(『信天翁』創刊号広告欄に掲載、1928・1)。小野十三郎は『若草』誌上で「あなたは全く純真な、そして純粋な曇りのない透明な性格の人です」と評した(「『雪明りの路』の著者へ」1927・5)。また、『椎の木』(1927・2)掲載の「『雪明りの路』合評」のなかで丸山薫は、「詩集『雪明りの路』をば繙いている間、その肩にいっぱいの林檎いろの雲をば積らした著者が寒い風と一緒に這入って来て、黙って私の傍に坐っているように思ひました。」と記し、同時期の「詩壇」を「粗暴な気象」と言い表した三好達治は、荒れ果てた「詩壇」に現れた「憧憬に顫える青空のような、ややにチエホフ先生式な厭世思想と(その為めに、君は正しい憤怒を洩らしている)犀利な観察。(それによって、ともすれば忘られ勝ちな些細な出来事の美しさを、君は巧みにノートして呉れた)」を高く評価した。
いずれの批評も作者と詩集が「詩壇」のアクチュアルな動向から遠く離れていたことを好意的に受け止めている点は注目される。その意味で伊藤が「序」に記した言葉は、彼の思惑以上の効果を発揮したと言えるのかもしれない。「詩壇」から遠く離れていたがゆえに「詩壇」に対して強い憧れを抱き、「詩壇」に参加しなければならないという焦燥に駆られていた伊藤にとって、みずからを「詩壇」に登録させるための戦略は不可欠だったと考えられる。伊藤がそうした意識を持っていたと見なし得る根拠として、同詩集が東京の椎の木社を発行所にしていたことが挙げられる。
▶︎同人雑誌『椎の木』に集った文人たち
1926年9月の『日本詩人』に掲載された同人雑誌『椎の木』創刊の予告および同人募集を見た伊藤は、ただちに百田宗治に手紙を書き送ったという。伊藤は後年この時のことを次のように振り返っている。
民衆派詩人として出発し、この一二年前から急に俳句的な枯淡な詩を書いていた百田宗治の作品に私は心服していたわけではなかったが、私はこの雑誌に加わろう、と思った。その頃私は、誰かの仲間になるか、何かの結社に加わらなければ、「詩壇に出る」ことは出来ないことが分って来ていたので、これから出来るこの結社に加わった方がいいと判断した。(『若い詩人の肖像』新潮社1956)
引用が事後的な回想、小説である以上、当然当時の伊藤の心情を正確に写したものではない。ただ、前述した『雪明りの路』「序」に表れた伊藤の「詩壇」に対する意識を鑑みれば、「詩壇に出る」ための経路を『椎の木』参加に見いだしたという点に関して、事実からそう大きく外れてはいないと思われる。
1926年10月に創刊された『椎の木』(第一期、~1927・9)は、東京中野坂上町二七五六番地の百田宗治方を発行所とする同人雑誌だった。第一期の同人は丸山薫、三好達治、坂本越郎、伊藤整らで、室生犀星や春山行夫らが寄稿者として加わった。第二次『椎の木』(1928・11~1929・9)は発行所を同人の坂本越郎方に移して、第一次の同人に加えて乾直恵や伊藤の親友・川崎昇らが同人に加わり、寄稿者として野口米次郎、佐藤一英、安西冬衛、滝口修造、北川冬彦、堀辰雄、飯島正らが参加した。
1926年11月号で『日本詩人』が廃刊した後、「詩壇」の中心のひとつになった百田のもとには、当時東京で活動しはじめていた若い詩人や作家連中が多く出入りしていた。伊藤が同人に加わり、自身の第一詩集の発行所として名を借りた椎の木社という百田を中心とする詩人・作家コミュニティは、その後の『詩と詩論』に集う主要なメンバーが参集した場でもあった。この線上で伊藤と川端の間に次第につながりができはじめる。
1928年4月に念願の上京を果たした伊藤は、一年間休学していた東京商科大学本科に復学する。上京した伊藤に下宿先を紹介したのは北川冬彦だった。二人は同月14日に伊藤の上京祝いとして催された『信天翁』の会の席上ではじめて出会ったという。丸山薫・三好達治ら『椎の木』同人と親しく交際し、しばしば百田のところに出入りしていた北川は、その縁で『信天翁』の会にも出席し、ちょうど下宿を探していた伊藤を麻布の飯倉片町の下宿に連れて行った。その下宿は、第三高等学校出身の若い小説家や詩人たち、北川・三好達治・梶井基次郎・淀野隆三・中谷孝雄・外村繁らの雑誌『青空』(1925・1~1927・6、全28冊)の元発行所でもあった。伊藤があてがわれたのは梶井と三好が使っていた部屋だったという。こうして伊藤は『椎の木』と旧『青空』系の文学者との接点を得、次第に詩から翻訳・評論・小説にその活動領域を移しながら、東京での文学活動を開始する。
▶︎梶井基次郎との出会い、そして川端への執筆依頼
1928年5月上旬、伊藤は伊豆から帰ってきた梶井基次郎とはじめて出会う。肺結核の療養のため伊豆に長逗留していた梶井は、1927年頃に当地で川端と知り合い、3月に刊行された小説集『伊豆の踊子』の校正を手伝った。
梶井君は大晦日の日から湯ヶ島に来てゐる。「伊豆の踊子」の校正ではずいぶん厄介を掛けた。「十六歳の日記」を入れることが出来たのは梶井君のお蔭である。私自身が忘れてゐた作を梶井君が思ひ出させてくれた。(中略)梶井君は底知れない程人のいい親切さと、懐しく深い人柄を持つてゐる。植物や動物の頓狂な話を私はよく同君と取り交した。「青空」の同人が四五人も入れ替り立ち替り梶井君の見舞ひに来て、私はそのみんなに会つた。今は三好達治君がゐる。淀野隆三君はいいお茶を送つてくれた。(川端康成「「伊豆の踊子」の装幀その他」1927・5)
新感覚派と『青空』周辺の文学者たちとの交流は、1925年頃から伊豆の湯ヶ島に移り住んでいた川端を中心に当地で深まっていった。川端は1929年10月に堀辰雄編集の第一書房の同人雑誌『文学』(~1930・3、全六冊)に編集同人として参加する。『文学』には横光利一・深田久弥・永井龍男といった同人に加えて、梶井や北川、春山、三好らも寄稿し、淀野隆三訳「スワン家の方―失ひし時を求めて」や小林秀雄訳「地獄の一季節」の翻訳連載はとくに注目を集めた。言うなれば、『文学』は新感覚派と『青空』、『椎の木』、『詩と詩論』周辺の人々たちのコミュニティとしての一面を持ち、まもなくそこに伊藤整を中心とする『文藝レビユー』(1929・3~1931・1、全20冊)周辺に集った若い文学者たちが加わることになる。英仏を中心とする海外の新しい文学を、その高い語学力を駆使して翻訳し、研究し、受容する彼らのスタイルは、川端と異なる文学との向き合い方でもあった。
『文学』創刊の半年前、伊藤は自身が編集人をつとめる『文藝レビユー』を創刊し、1929年5月15日、「私は「文藝レビユー」のものでございますが」と同誌への執筆依頼の手紙を川端に出す。これが二人にとって最初の交流だった。