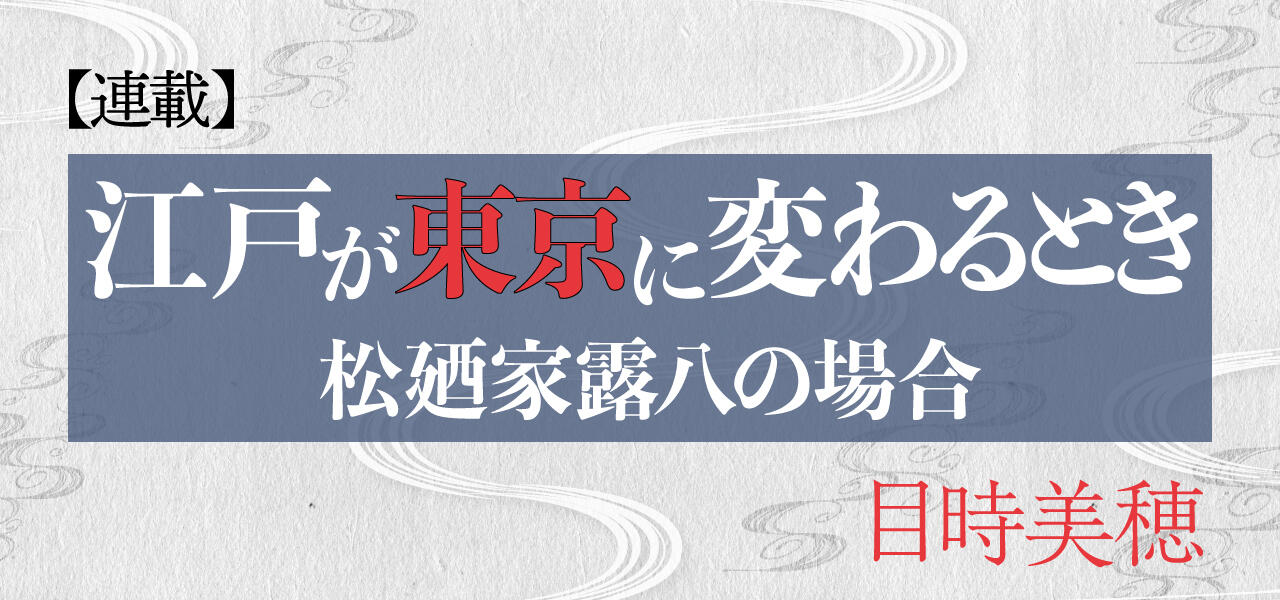01 江戸いまだ敗れず|【連載】江戸が東京に変わるとき――松廼家露八(まつのやろはち)の場合(目時美穂)
01 江戸いまだ敗れず
彰義隊に身を投じるということ。それは本当に確実な敗北と死を見据えた自殺行為だったのだろうか。上野にたてこもった当事者たちにとって、勝つ見込みのない戦いに身を投じることで、みずからの命でもって江戸の武士の誇りを示し、江戸文明に殉じるという、滅びの美に徹したありかたであったのだろうか。またそれを見守っていた当時の江戸民衆にとって、本当に、彰義隊は死に花を咲かせるために集まった集団であったのだろうか。
松廼家露八こと土肥庄次郎も家督を継いだ長弟からまだ10代の末弟まで、本人を入れて5人の男の兄弟全員と、土肥家に仕えていた侍まで、文字通り一族郎党引き連れて、必敗を覚悟で上野へ行ったのだろうか。土肥家の男たち全員の命を捧げることで徳川政権や、江戸文明に報いようとしたのだろうか。
徳川政権と心中するために死に場所を戦場に選んだ人もいただろう。だが、露八・土肥庄次郎には、滅びの美にみいられた、ある意味耽美な生き方がそぐわない。だから、敗けると決まった戦場にあえておもむくとは思えないのだ。勝つ気ならば、あくまでも抵抗を貫きたいのなら、上野でなくとも合流できる戦場はまだいくらでもあった時期だ。
彰義隊イコール死を覚悟した集団のイメージは、彰義隊が一日の戦闘で、戦闘部隊としては全滅ともいえる被害をだして壊滅してしまったから、つまり結果ありきのイメージではないか。
こんなことを考えたのは、上野戦争があった慶応4年の江戸で、さかんに佐幕派の新聞が発行され、戦況を案ずる江戸庶民に多いに読まれていたという事実があるからだ。
しかるに、江戸で佐幕派の新聞が闊歩したのは、新政府と幕府勢が拮抗していたというよりも、後者の勢力の方が依然として強かったことを示唆している。いや、幕府権力が風前の灯でありながらもかろうじて存続している一方、新政府の権力が浸透していない時期、つまり確固たる権力の不在期、空白期という特殊な時期であったからこそ、この種の新聞が誕生したともいえよう。ともかく佐幕派新聞の活動は負け犬の遠吠えではなかった。(山本武利「新政府を批判した旧幕臣」『歴史読本』1985年1月号)
たとえば、開成所頭取であった幕臣柳河春三が江戸で創刊した「中外新聞」は慶応4年2月24日から同年6月8日に新政府に発行を禁じられるまで、佐幕派の立場から戊辰戦争の戦局を報道しつづけた。この新聞は、最盛期1500部の発行部数を数え、号外まで出された。おなじく慶応4年、閏4月3日に福地源一郎(桜痴)や、条野伝平(採菊)らによって「江湖新聞」が創刊されている。人々は、固唾を吞んで戦局を見守っていたのである。

「別段中外新聞 戊辰五月十六日」表紙。
前日、5月15日払暁に勃発した上野戦争について報じる。おなじく「江湖新聞」でも上野戦争について別号を刊行したとある(5月18日付、第20号)。この「中外新聞」の内容は早稲田大学古典籍データベースで全文読むことができる。
実際、旧幕府軍は、総大将である徳川慶喜が先んじて敗北を演じ、率先して武装解除を行ったため、色濃い敗北色がただよっているが、兵力でいえば、まったく新政府軍に劣るものではなかった。そして、新政府軍は、江戸城を明け渡されたからといって、江戸を支配していたわけではないのだ。むしろ、新政府軍の兵士らにとっては無傷な軍隊を保持しているにもかかわらず、首府をあえて武力の空白地にして、降伏した奇妙な占領地に駐留しているようなものだった。さらに住民感情も最悪だった。毎日のようにテロがあった。現場としては、けして勝利に酔うどころの状況ではなかっただろう。
江戸庶民は、彰義隊となった江戸武士たちが、西からきた「蛮族」を打ち破ってくれることを期待して、ハラハラ、いちめん、わくわくしながら開戦の日を待っていたにちがいないのだ。
もし彰義隊が勝利すれば、戦況はどのように転ぶかわからなかった。江戸の各所、周辺には、いざ戦闘となれば彰義隊と呼応あるいは合流して戦おうと幕臣や佐幕派諸藩の兵士たちが武装を整えて集結していた。勝利しなくとも戦闘を長引かせれば、勝機がある戦いだった。
これまで、彰義隊は、たった一日で敗れた弱兵、烏合の衆という印象で語られてきたが、この印象は結果論にすぎない。期待していたのにあっけなく敗れてしまったという民衆の失望もあるだろうが、もっといってしまえばこのイメージは、戊辰戦争終結後、旧幕府軍がもろかったと思わせ、一刻もはやく支配体制を盤石のものにしたい新政府の心理操作の賜物であろう。
むしろ、一日で破らねば新政府軍の勝利が揺らぐ、という危機感のもと、天才大村益次郎が一日で破ることができる作戦を練りに練った。といえるのではないだろうか。
上野の山王台、ちょうど彰義隊の墓に背を向けたかたちで、西郷隆盛像が建っている。この西郷像は、恩赦により許されたとはいえ国に叛逆をした男ということで、皇居のまえに建てることを却下され、「縁の深い」上野公園に建てられることになったのだ。では、どう縁が深いのか、といえば、べつに縁などないのだ。唯一の縁といえば、慶応4年の5月、薩摩藩兵を率いて、激戦地であった上野の黒門を破り、新政府軍勝利のきっかけを作ったというだけだ。日常着に兎狩り姿でやわらげられているとはいえ、彰義隊にとっては墓のまえに立った征服者であることに変わりはない。銅像といえば、靖國神社にある大村益次郎の銅像も、江戸城富士見櫓から上野の戦況をうかがっている姿を現したものだという。
江戸を征服するということにおいて、彰義隊を壊滅させたということがいかに大きな意味があったのか、「敵将」たちの銅像が明かしているようなものだ。
上野戦争は江戸地方の局所戦、小競り合いのように考えられているが、当時、当事者にとっては、戊辰戦争の戦局を決めた重要な戦いであったということだ。参加した者たち、もちろん露八も、最初から負けるつもりなどなかっただろう。勝利に寄与するため、勝つために参戦したのだ。
=========
■連載トップ 江戸が東京に変わるとき
https://bungaku-report.com/rohachi.html
■本書の詳細はこちら。

目時美穂『彰義隊、敗れて末のたいこもち 明治の名物幇間、松廼家露八の生涯』(文学通信)
ISBN978-4-86766-020-1 C0095
四六判・並製・376頁
定価:本体2,500円(税別)