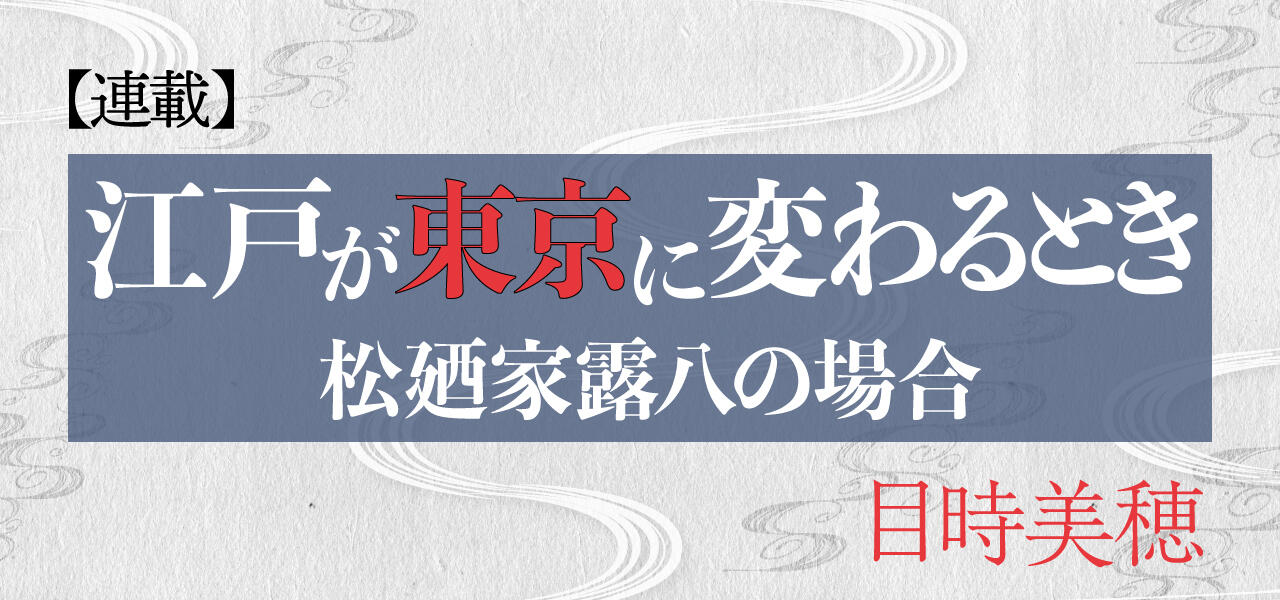00 露八の気持ちは霧のなか|【連載】江戸が東京に変わるとき――松廼家露八の場合(目時美穂)
00 露八の気持ちは霧のなか
松廼家露八(まつのやろはち)は明治の吉原で名高い幇間(ほうかん)であった。ところで、幇間芸といえば、ひっぱられたり、しかられたり、屏風やふすまのむこうの架空の人物と攻防を演ずる一人芝居(屏風芸)などはご存じかもしれないが、そうした芸は幇間の役割のほんの一部でしかない。幇間芸の真骨頂は、遊廓に来た客を、御茶屋で花魁の到着を待つあいだ、いかにすこぶる楽しく遊ばせるかにある。酒にもつき合えば、日常会話も、噺家のまねごともお手のもの、即興の芸も披露する。そうして客は極上の気分で登楼してゆく。もちろん、色事を挟まない、慶事にも葬儀の露払いにも、人がつどって酒を呑むいかなる席にも呼ばれる。場の空気をよみ、客が望むであろう最良の周旋をするのが幇間である。
かつて幇間は宴席になくてはならない芸人だった。需要があったのだから供給のほうも当然豊富であったにちがいなく、そのなかでかなりの人気を博していたのだからもちろん、酒席を盛りあげる芸も、客のとりもちもよかったにちがいない。どんな持ち芸があって、客に喜ばれたかは記録にある。だが、どんな味わいをもった芸人であったかは、積みあげたエピソードから推測するほかにないのである。
松廼家露八の前身は武士である。本名の土肥庄次郎(どひしょうじろう)を、芸名の松廼家露八としても、(職業スイッチは入るだろうが)人間の本質のなにが変わるというのでもない。露八の父、土肥半蔵(どひはんぞう)はもの堅い武士だった。露八が自分の教養や素養についてどれだけ軽く語ったとしても、こどものころから父にたたき込まれた「武士」なるものを、みずからの内から消し去ることはできなかっただろう。
客に漢語幇間(かんごほうかん)とよばれ、馬で吉原入りしたときの姿は立派であり、日ごろの運動に槍をしごく姿、のこされた数葉の写真の表情の厳しさから、武士の風格を保った人だっただろうと思う。どれだけ幇間として洒脱にくだけても、ちらりと垣間見える、肉体に、魂に染みついた武人の面影、芯にたたき込まれた武士の節度。それが幇間露八の持ち味であり、魅力のひとつであったのではないだろうか。だからこそ、ほかにも旧彰義隊士(きゅうしょうぎたいし)の幇間がいたにもかかわらず、「彰義隊あがり」は露八の専売となったのだろう。

露八の肖像画
(藤井宗哲『たいこもち(幇間)の生活』雄山閣、1982年より転載)
松廼家露八こと土肥庄次郎は、江戸が終焉をむかえようとするころ、御三卿の一家、15代将軍徳川慶喜(とくがわよしのぶ)を輩出した一橋家の家臣の家の長男として生まれた。幼いころから体格にめぐまれ、武芸の稽古にも熱心で、とくに槍術、馬術、砲術には熱心に取り組んだ。本人はあまり関心がなかったというが、漢学を中心に学問もきちんと身につけていた。しかし、長じて、酒と女の味をおぼえて、悪友とつるんで問題行動を起こすようになり廃嫡される。やがて吉原に身を置くようになり、ついに武士を捨てて幇間になる。ところが、当時の身分制では賤(いや)しいとされていた幇間をしていることが父親にばれて斬られそうになり、逐電して西国で気ままな生活を満喫する。
しかし、時代はのんきな放蕩(ほうとう)生活をつづけている場合ではなかった。禁門(きんもん)の変、長州征伐(ちょうしゅうせいばつ)、そして鳥羽伏見(とばふしみ)の戦いの敗北。主君徳川慶喜の生命さえも危うくなった。 そのころ、江戸で、旧一橋家の家臣が中心になって彰義隊が結成された。上野で謹慎している慶喜の名誉と命を守るために作られた組織だが、次第に薩長、新政府軍への報復を目するようになっていった。
このとき、庄次郎は四人の弟をひきつれ、彰義隊にくわわり、上野にたてこもった。
これが土肥庄次郎、松廼家露八の前半生である。
これだけみると、それまでみるからに「軟派」な人生を歩んできた庄次郎の突然の変わりように少々違和感があるのではないだろうか。
吉川英治の『松のや露八』では、京にいた露八は、鳥羽伏見の戦いの後、長州藩に与している弟(長弟・八十三郎は、吉川英治の小説では長州方についたが、現実の八十三郎は兄とともに幕府側で戦った)にひとめ会おうと陣中に忍び込み、兵に間諜と思われて攻撃されて負傷し、気を失っているあいだに弟に救われ、籠に乗せられる。弟が気を失った自分に土肥家の紋のあるみずからの着物を着せ、金と印籠まで持たせてくれていることに気がつき、「会いたかった」と涙するのであったが、その後、突如として怒りがわきあがる。「彼は、這い摺っても、江戸へゆくぞと思った。江戸へゆけば人間という人間はみんな味方であり親類のようなものだし――と思った」。そして、その次がすぐに上野の戦いの場面になる。戦いにおもむくほどの怒りはなぜ、いつわいたのか、痛む体を籠にゆられながら生じた怒りだけで彰義隊に加わるものだろうか、と考えてしまう。がそんなことは、吉川英治にとっての主題ではないからか、庄次郎の感情はいつもぼんやり、もやがかかってみえる。
拙著では、本人や親しい人の証言があることを別として、主人公の心情をあまり書いていない。行動から推測することしかできない他人の心を、本当であるかのように書いてしまっては、創作と評伝の一線を越えてしまう。くわえて、本当に考えたかどうかわかりはしないことを、創作ではなく評伝としてまことしやかに書くことは、当人に対し非礼であると考えるからだ。
だが想像してみることは自由だ。以下、江戸から明治の転換期、松廼家露八こと土肥庄次郎がなにを思い、どう考えて戦い、また、幇間になったのか、若干のメディア史と、岡本綺堂の戯曲にことよせて推測してみたいと思う。
=========
■連載トップ 江戸が東京に変わるとき
https://bungaku-report.com/rohachi.html
■本書の詳細はこちら。

目時美穂『彰義隊、敗れて末のたいこもち 明治の名物幇間、松廼家露八の生涯』(文学通信)
ISBN978-4-86766-020-1 C0095
四六判・並製・376頁
定価:本体2,500円(税別)