第7回 独自の韻律を生きる――三原由起子『土地に呼ばれる』|【連載】震災短歌を読み直す(加島正浩)
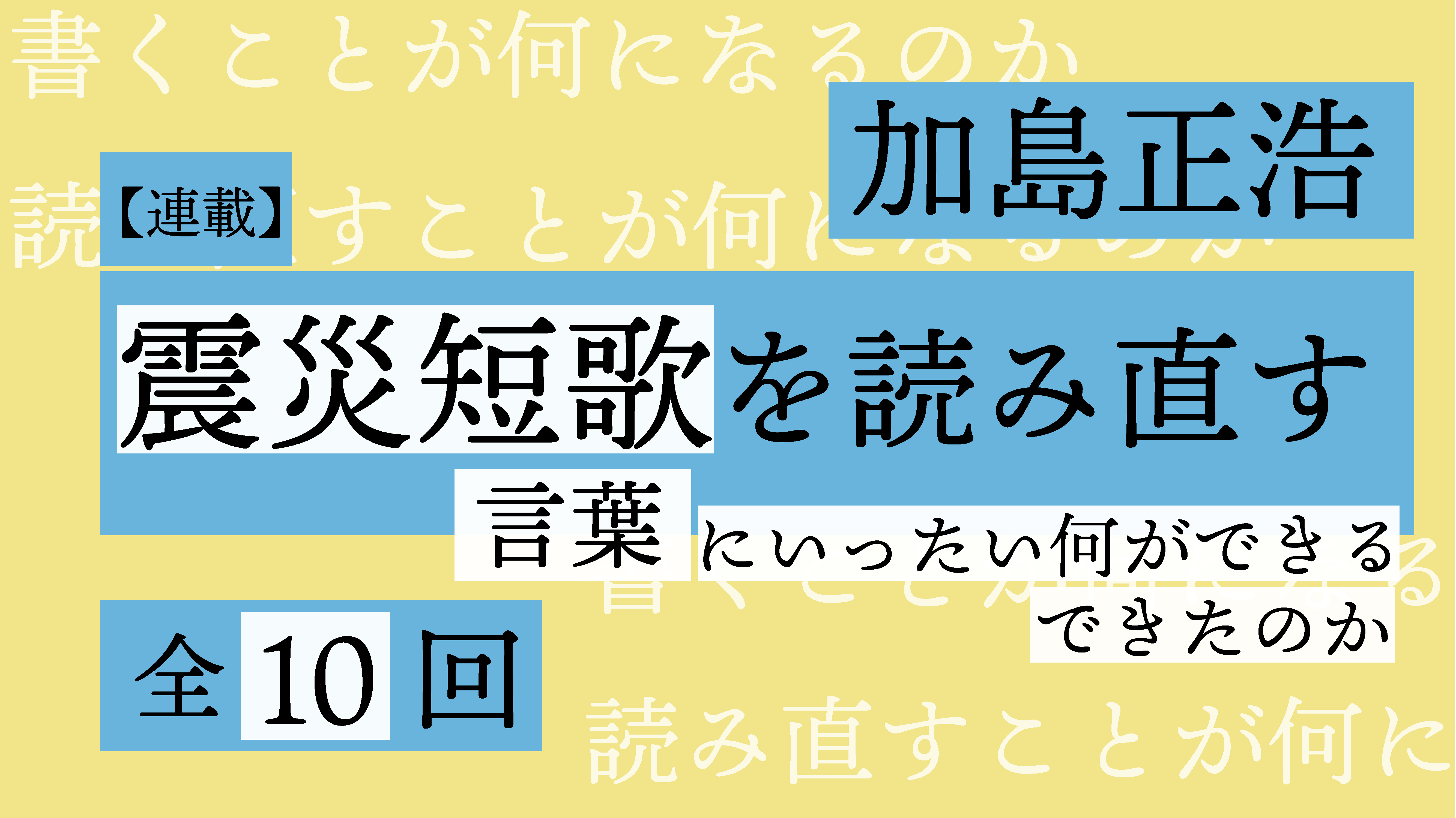
第7回
独自の韻律を生きる
――三原由起子『土地に呼ばれる』
■韻律にはまらない言葉の出現
三原由起子は、原発「事故」以後に警戒区域などに指定された福島県浪江町に生まれた。第一歌集『ふるさとは赤』(本阿弥書店、2013年5月→新装版、2021年6月)には、三原が16歳から33歳までに詠んだ歌が収録されている。原発「事故」を挟んで収録された歌からみえる作風の変化から、原発「事故」が、ひとりの歌人の人生を変えたことがうかがえる。その点については、以前述べたことがあるので、ここでは繰り返さない。(https://sectpoclit.com/shinsai-2/ならびにhttps://sectpoclit.com/shinsai-10/を参照のこと)
『土地に呼ばれる』(本阿弥書店、2022年8月)は、三原の原発「事故」以後の歌を収録した歌集である。本歌集の特徴として挙げておきたいのは、「破調」(5・7・5・7・7の31音の短歌の定型を外す)や「句またがり」(句をまたいで文が成立する。破調の一種)の歌が多いという点である。それが意味することを、今回は順を追って考察したいと思う。
そもそも、原発「事故」は、言葉の世界に「新たな語句」を定着させてしまった。
居住制限区域とは、「除染」を行い、将来的に居住可能にすることを目指すために、居住を制限し、一時帰宅のような限定を(行政の判断で)もうけたものである。浪江町は2017年3月31日まで、居住制限区域の制限を受けていた。一首目は、自ら死を選んだ三原の友人「やっちゃん」(〈掴み合いしたやっちゃんが自らの死を選ぶ四半世紀のあとに〉という歌でも詠まれる)のことを詠んだ歌と推察される。
「浪江に住みたかった」という「やっちゃん」の無念を読者に伝えるためには、浪江に住むことができない時期があったことを伝える必要がある。浪江の指定されていた区域名が時期によって変わることを踏まえれば、「居住制限区域」という言葉を用いることは、「やっちゃん」がどの時期に自ら死を選んだのか、そしてなぜそれを選んでしまったのかを読者に考えさせるうえで有効であると考える。
しかし「居住制限区域」は「きょ・じゅ・う・せ・い・げ・ん・く・い・き」の10音であり、短歌の韻律に組み込むのは難しい。しかし行政がそのような区域名で浪江を呼ばせていたという事実は、浪江と関りが深い人たちにとっては特に重要なのであり、三原も韻律より、その言葉があったという事実を優先すべきと捉えたのではないか。三原は、〈あることをなかったことにする国の民として生きるのはもういやだ〉という歌も詠んでいる。ある時期に存在し、将来には消し去られることが目論まれるであろう言葉を、短歌の韻律が消し去ってしまうのであれば、三原の思いとは逆に歌が働いてしまう。そのため、韻律よりも「言葉」を重視したと思われる歌が、歌集にはみられる。
他にも「マ・イ・ク・ロ・シ・イ・ベ・ル・ト」(9音)などの言葉は、韻律にはうまくはまらない。しかも「/毎時」がつけば、どのように音のリズムを取ればいいのかも、よくわからない。しかし三原がそれでもその語を歌に組み込んでいるということが重要なのであり、このように韻律のリズムを狂わせたのが、原発「事故」であるのだと述べることも可能であるだろう。原発「事故」で、短歌もまた「被災」したのである。
■「あえて」韻律を外していく
『土地に呼ばれる』は、使用語句が韻律のリズムを崩しているだけではない。三原自身が、「あえて」短歌の定型のリズムを外している歌も多くある。
そもそも短歌の定型とは、なんのためにあるのだろうか。木下龍也は以下のように述べている。
助詞を入れることによって定型をはみ出し、それが字余りという技法とまで呼べないのであれば、やはり言葉の選択、語順の変更をして五七五七七に収めよう。声に出してみて普段の話し言葉に近づけ、31音の流れをなめらかにしよう。読み手に無駄なひっかかりを与えないように。
木下龍也「助詞を抜くな。」『天才による凡人のための短歌教室』(ナナロク社、2020年11月)
木下の説明に基づけば、短歌の定型は「読み手に無駄なひっかかりを与えない」ためにあるということである。では、裏をかえせば、定型を外せば、読者は句に「ひっかかり」を覚えるということである。たとえば以下の歌をみてみよう。
「ど・う・し・ん・え・ん・に/か・こ・ま・れ・る/ち・ず・の・な・か・に・あ・る/ひ・と・り・ひ・と・り・の/に・ち・じょ・う・を・も・ど・せ」と仮に音を区切ってみる。4句が7音である以外は、定型の韻律ではない。定型の韻律を用いず、三原は独自のリズムをこの歌に持たせることで、スラスラと読むことができないよう読者に「負荷」をかけている。以下の歌もそうである。
「スーパーの/ちゅうしゃじょうの/いっかくで/」とすれば、短歌のリズム感を損ねることなく、歌を詠めたはずである。それをあえて「とある一角で」としていることの意味を、われわれは読まなければならない。「とある」で読み手を立ち止まらせようとするのが、この歌である。スラスラ読んではならない、考えろと、歌は定型の韻律を崩すことで、読み手に求めているのである。
そして、このような定型の韻律を「あえて」破る歌があることで、以下のような定型を守った歌が読者に響いてくるということもある。
このような歌を読む者がひっかかりを覚える「破調」で詠んでしまうと、日々を「淡々」と生きる両親の姿がうまく伝わらない。リズムの「ひっかかり」と「淡々」という言葉が相容れないからである。この場合は、定型の韻律を守った方が「淡々」という言葉の意味が生きるように思われる。しかし、定型のリズムで心地よく読める歌の上の句で詠われているのは、「生業をある日突然奪われし」というなめらかに読むことのできない内容である。なめらかに読んでしまった歌が、何を詠っていたのかと読者がふりかえるときに、この歌の「重さ」に気がつくということがあるのかもしれない。読者につっかえさせる歌と、一度なめらかに読ませる歌を上手く取り交ぜることで、『土地に呼ばれる』は、原発「事故」以後の「重い」現実を読者に伝える歌集となっているといえる。
■別のリズムを作っていく
しかし定型の韻律をはみ出していくことの意味は、これだけではなく、もうひとつあるように思う。
原発「事故」以後に福島県に住んでいる人だけが、「事故」の影響を被ったわけではない。福島にいま住んでいる人だけが、福島県の現在に意見を述べることのできる「権利」を持っているわけでもない。福島第一原発立地地域に近い相双地区を故郷に、様々な場所で生活を営んでいる人は原発「事故」で故郷を「失い」、強制/区域外を問わず「事故」以後に福島県からなくなく避難した人は大勢いる。その人たちが意見することは許されないのかと、問うのが引用した一首目である。
三原は〈「僕たちは反対じゃない」と告げられて僕たちの「たち」を考えている〉・〈「町のためにがんばっている人もいるのだから」と思えばわれは再び黙す〉という歌も詠んでいる。「僕たち」のなかに含まれない自分、「町のためにがんばっている人」のなかに含まれない自分というのを三原は自覚せざるをえない状況に追い込まれている。
(付言するが、三原は下北沢で「いりの舎」という出版社をパートナーの男性とともに営んでおり、そこから国文学研究資料館教授の西村慎太郎著『「大字誌浪江町権現堂」のススメ』(いりの舎、2021年9月)という浪江の歴史を辿る本を刊行している。また三原は、定期的に西村らとともに、浪江の過去/今後を考えるシンポジウムを企画しており、このような活動が「町のために」もあることは、疑いようのないことであると私は思う)
ただ現実として「たち」に含まれない自分というのを自覚せざるをえないためか、〈SEALDsにもママの会にも当てはまらぬわれも「緊急行動」にゆく〉というデモに行く際の歌も詠まれている。しかしデモに参加した結果、そこにいた多彩な顔ぶれに励まされている様子もうかがわれる。先の二首目で「老若男女という語しっくりくる」と三原は詠っているが、短歌の韻律からすれば「ろ・う・にゃ・く・な・ん・にょ」(7音)は扱いづらいようにも思う。「老若男女」の歌は、定型からみれば「破調」である。
しかし「定型」に当てはまらない多彩な顔ぶれに「しっくりきた」ことを示す歌が、「定型」にはまっているのも、おかしい。「定型」にはまらなくとも「しっくりくる」語やリズムはあるはずなのである。三原はそれを〈それぞれのリズム感を持ちそれぞれの言葉を持って声を発する〉という歌で、素直に示しているのではないか。そして土地を選んで生きることも「型」にはまっていくことなのではなく、自分自身の「形」を作っていくものなのだと。
三原は以下のようにも詠んでいる。
この歌は「句またがり」である。
そとからの/かぜをふきこむ/やくわりと/してとうきょうに/すもうわたしは/
自分は「外からの風を吹き込む」者だと決意する歌が、定型の韻律からは逸脱するリズムで、詠まれていることが重要であると考える。われわれは誰かが定めた「型」に、わざわざはまっていく必要はない。自分の立つ場所から、自分のなせることを、自分のリズムで行えばよいのであるし、またそうすべきであるということを、三原の『土地に呼ばれる』はわれわれに教える。
ただし、独自のリズムで向き合うことが苦しいのは言うまでもない。〈「辛いならやめろ」と父に言われおり錠剤飲みつつ向き合う故郷〉とも三原は詠む。「孤独」のなかで戦わざるをえない場面があることも、三原の歌からは推察される。
ただそれでも三原は、「短歌」で故郷と原発「事故」に独自の向き合い「形」を探りつづけている。原発「事故」以後という時間の区切りが存在しないかのように振る舞いつづける世の中(と「故郷」)に対峙するということの厳しさを三原は示す。
しかしそれでも向き合う三原由起子という歌人がいることで、忘却の荒波に消されることのない希望が言葉として生まれている。その希望/言葉をなんとか増幅できるよう努めることが、書かれた言葉がなければ何もできない無力な研究者としての私に課された仕事なのだろうと思っている。
■コーナートップへ




























































































