第6回 農業と原発――佐藤祐禎『青白き光』|【連載】震災短歌を読み直す(加島正浩)
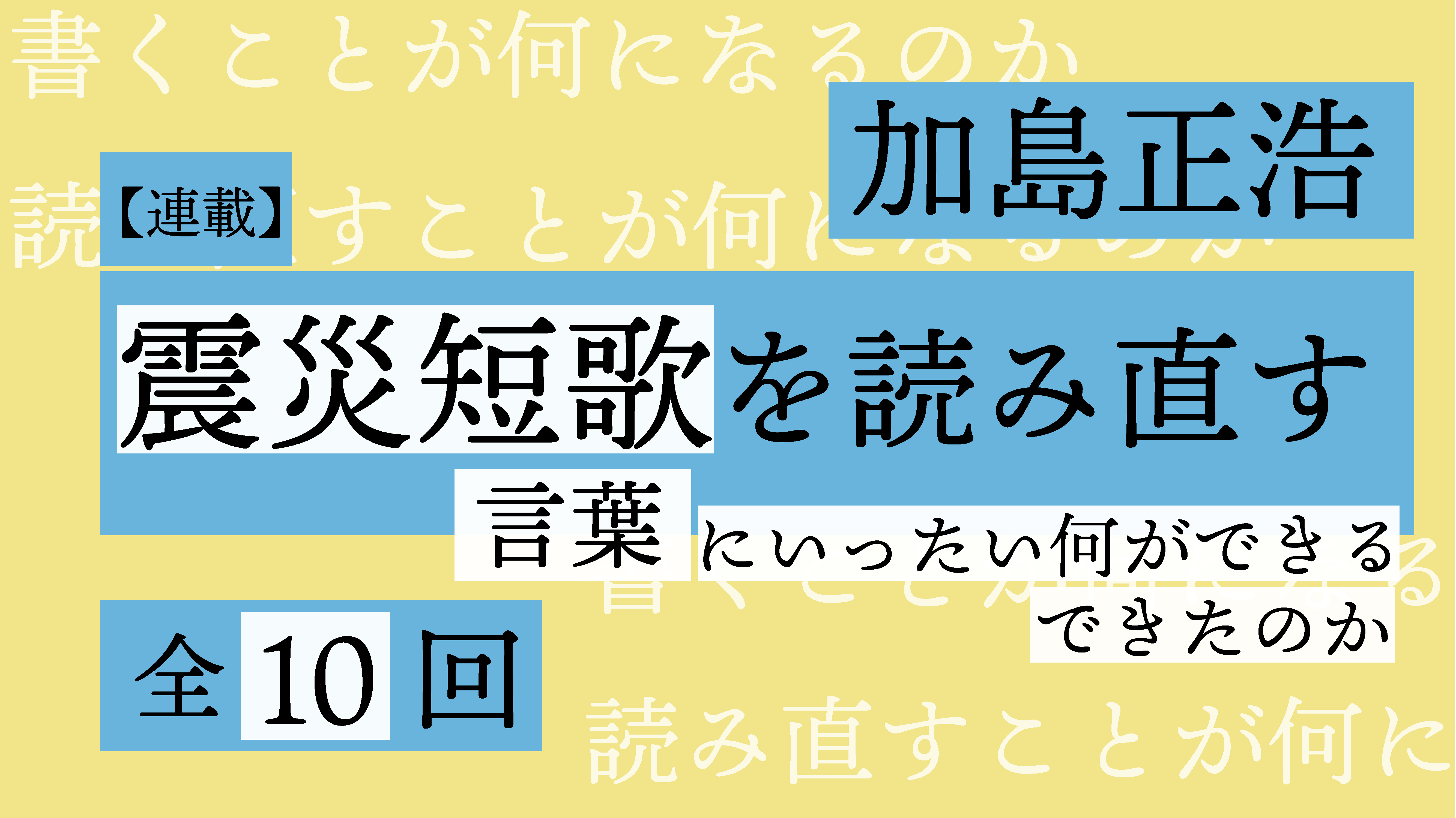
第6回
農業と原発
――佐藤祐禎『青白き光』
■佐藤祐禎という歌人がいた
前回、原発「事故」以前に原発を問題視していた歌人として東海正史を取り上げた。しかし、「事故」以前に原発を詠んでいた歌人は、東海だけではない。今回取り上げる佐藤
佐藤は、彼が後に〈日々に見る線量わが地のみ減らず原発四キロ圏内われら〉と詠むことになる福島県双葉郡大熊町に生まれる。福島第一原発の六基の原子炉を持つ大熊町である。佐藤は農業を生業としながら、52歳(1981年)のときから短歌をはじめる。翌年「アララギ」に入会し、1998年には新アララギ福島会を立ち上げる。
2004年に反原発への想いを詠んだ歌を多く収める『歌集 青白き光』(短歌新聞社→2011年12月に文庫版として、いりの舎より復刊)を刊行。2013年に亡くなるが、佐藤が立ち上げた水流短歌会が中心となり、「事故」以後から2012年8月までに佐藤が詠んだ歌を選歌し『歌集 再び還らず』(2022年3月、いりの舎)が刊行される。
■縁遠い人間は、その言葉の重さのままに理解できるか
『青白き光』を一読した際、目を引く主題の一つは原発であるが、もうひとつある。彼が「農民歌人」であるという点である。
しかも、上記4歌を読んでもらえばわかるように、佐藤が農業を続ける大きな要因には、子や孫に農地を継承しようとする意図があることがわかる。
東北南部は「ハヤマ信仰」が強い地域であるといわれる。「ハヤマ信仰」はいわゆる山岳信仰のひとつであるが、祖先の霊魂がやがて神となり、子孫を守ってくれるという祖霊信仰と共通点を有する。大熊の近くでは、双葉郡富岡町にある
つまり、かなり乱暴なまとめではあるが、大熊で生活する人々は、農業の神と、神となった祖先に守られて生活を営んでいたのである。
それを踏まえて、佐藤の歌に戻りたい。佐藤が耕している農地は、(神となった)先祖から継承した土地なのであり、それは自分の代で安易に終わらせられるものではない。だからこそ子が継承してくれるのかと悩み、子は継承せぬとも孫が継承するかもしれないと期待し、もし継承者がいないとしても田を荒らすわけにはいかないという思いが生じるのである。
佐藤は「事故」後、『再び還らず』に〈五代目にして故郷を捨てて来ぬ原子炉爆発といふ奇襲受け〉、〈先祖より伝ふる田畑売らず来しされど放射能に捨てねばならず〉という歌を残している。この無念さを、大熊や大熊が属す地域区分である浜通りと縁遠い人間が、その言葉の重さのままに理解できるかどうかが、ひとつの問題になるのだろうと思う。
また、『青白き光』には〈農村の実情知らぬ学者らの片腹痛き論を聞きおり〉という歌が収められている。歌集の文脈から読めば、原発を「推進」しようとする学者が、農村の実情をわからず話している内容を揶揄している歌であると解釈するのが妥当であろう。しかし、東日本大震災以後の文学や文化について論を述べてきた研究者が、どれほど農村の実情や、そこで紡がれた思想、言葉に関心を寄せ、理解しようとしてきたのだろうかと考えると、決して全ての研究者がそのような努力を行ってきたとは、思えない。もちろんそれが「本当の意味で」可能であるかは、別の課題ではある。しかし、少なくとも原発立地地域のことを知ろうと試みたうえで立論しなければ、それは世相の(あるいはアカデミズム内の)「流行」におもねる以上の意味を持つのであろうか。どうすれば原発立地地域に住む人や住んでいた人、あるいは福島県のみならず様々な場所から避難した人々に「片腹痛い」と一蹴される以上の論を示すことができるのであろうか。
〈五代目にして〉とわざわざ頭につけた佐藤の意図が、自分の代で田畑を捨てなければならなくなった佐藤の無念さが、理解できるかどうかが、ひとつの問題となるはずである。
■農業と原発の関係
そのうえで、佐藤が『青白き光』で、以下のように詠んでいることにも注目したい。
くどいが繰り返す。佐藤(大熊に住む人)にとって農地は、先祖から継承した大切な土地なのであり、自分の代で終わらせることはできないものである。しかし、その農地を継ぐ重要性以上に、原発「事故」が続くこの町で暮らす方が問題だと佐藤は捉える。佐藤が原発をどれほどに問題視していたか、その想いの強さが、詠まれた背景を踏まえることでみえてくる。
『青白き光』は、1983年から2002年までに佐藤が詠んだ歌によって編まれている。この間、東北で農業に従事していたものに大きな問題がふたつ降りかかっている。ひとつが、「平成の米騒動」ともいわれる1993年に起きた記録的な冷害である。そしてもうひとつが、「平成の米騒動」のような大規模な冷害がある年をのぞいて行われ続けていた減反政策である。
冷害が襲えば、資金繰りは厳しくなる。冷害と無縁の時期は、米が余っているとして、減反政策を強要される。減反せねば米価を下げると脅され、細かな制約がつき、作るほどに赤字となる。そのため、子に農地を継げとも言えない。ただ政官財が一体となった「国策」によって、農業が滅びるのではないかという予感に怯えるという佐藤の真率な気持ちが吐露されている。
では、農業が滅びると、どうなるのか。
冷害で稔らない稲田のつづくはてに、原発があり、そこの夜空は「明るい」。お金にならない、生活できないために、何もなくなった稲田の果てに「明るい」原発がつづいている。生活のためにその明かりを求めていくことを責められるはずもない。〈危険なる場所にしか金は無いのだと原発管理区域に入りて死にたり〉、〈子の学費のために原発の管理区域に永く勤めて友は逝きにき〉と佐藤は詠む。冷害や減反政策(=「国策」)によって農業で食べていけなくなったとき、原発=「国策」で食べていくしかないのだという現実がある。しかし、原発が生み出すその明るさは、人間の「命を燃やす」ことで保たれている。
どちらが、何が「正しい」とも言えないが、ただ「国策」に振り回されて、大熊の人は生きていたとはいえるだろう。減反政策が終わるのは、2018年である。それは原発「事故」後であり、佐藤が亡くなった後なのだ。
■農業は農作物だけをつくるのか?
減反政策を踏まえて、佐藤は〈飽食ののちに飢餓なしと言ひ得るや休耕田は年ごと荒るる〉とも詠んでいる。米が余った飽食の時代に、米を作るなというが果して飢餓の時代はこないと言えるのかという歌の前半部に目が行きそうだが、ここでは後半部に注目したい。〈休耕田〉は、手を入れないために、年を経るごとに荒れるのである。冷害で稲が稔らない風景がつづいたように、休耕田が増えれば風景は「荒れていく」のである。
農作物を作らない休耕田(それが生じたのは「国策」のためであろうが)、しかも農地を継ぐ者がいなければ、それを遊ばせておくよりかは、廃棄物処理場(これも「国策」によるもの)に貸した方がよいという判断は利にかなっている。佐藤も沢地を貸したと詠んでいる。そこには処分場の看板が立ったと詠う。土地を貸すことで、風景は変わってしまうのである。
佐藤は、そのことを理解していたのだろうと思う。だからこそ「茅葺きの家」を彼は残そうとした。軒が傾いている家である。今後も住み続けるために、残したということではないだろう。茅葺きの家があるという「風景」を残すために、茅葺きの家を残したのだろうと思う。
田畑を耕し、農作物を作ることは、農作物が実る田畑という「風景」を残すことでもあったのだろう。農業は農作物だけを作るのではない。「風景」を同時に創り出していたのである。
風景は時代とともに変化する。田畑が、原発に。産業廃棄物処分場に。そして現在はメガソーラーパネル(https://fukushima-power.com/blog/351/)へと変化していく。
それが時代の流れということなのかもしれない。もしかすると「事故」がなくとも、休耕田は増え、メガソーラーパネル地帯へと、あるいは原発関連の施設が立ち並ぶ風景へと変貌したのかもしれない。その是非をここで問うつもりはない。
ただ最後に佐藤が以下のような歌を残していることにだけ、触れたい。
佐藤が行おうとしたのは、子に自らの家が所有する田畑を継承することだけだったのか。佐藤が「耐へて譲」ろうとしたのは、先祖から受け継いだ家と田畑だけだったのか。先祖から受け継いだものは、それだけではなかったのではないか。
彼が反原発の歌を詠み続けたことは、そのまま「ひたすらに耐へて譲る」行為に直結するものであったのではないか。
1929年生まれの佐藤は、大熊に原発が建設される様を、当然目にしている。『再び還らず』によれば、佐藤が反原発の思想を宿したのは、一号炉建設に好奇心で携わったときであるとのことである。彼が先祖から受け継いだ田畑を子孫に受け渡す以上のことを意識していたかどうかはわからない。
しかし、彼が「ひたすらに耐へて譲」ろうとしたもののひとつは、原発のない大熊の「風景」だったのではないか。先祖から受け継いだのは、田畑だけでなく、田畑のある「風景」だったのだから。
■コーナートップへ




























































































