第3回 分断は超えられるとする思考への苛立ち――逢坂みずき『まぶしい海』・近江瞬『飛び散れ、水たち』|【連載】震災短歌を読み直す(加島正浩)
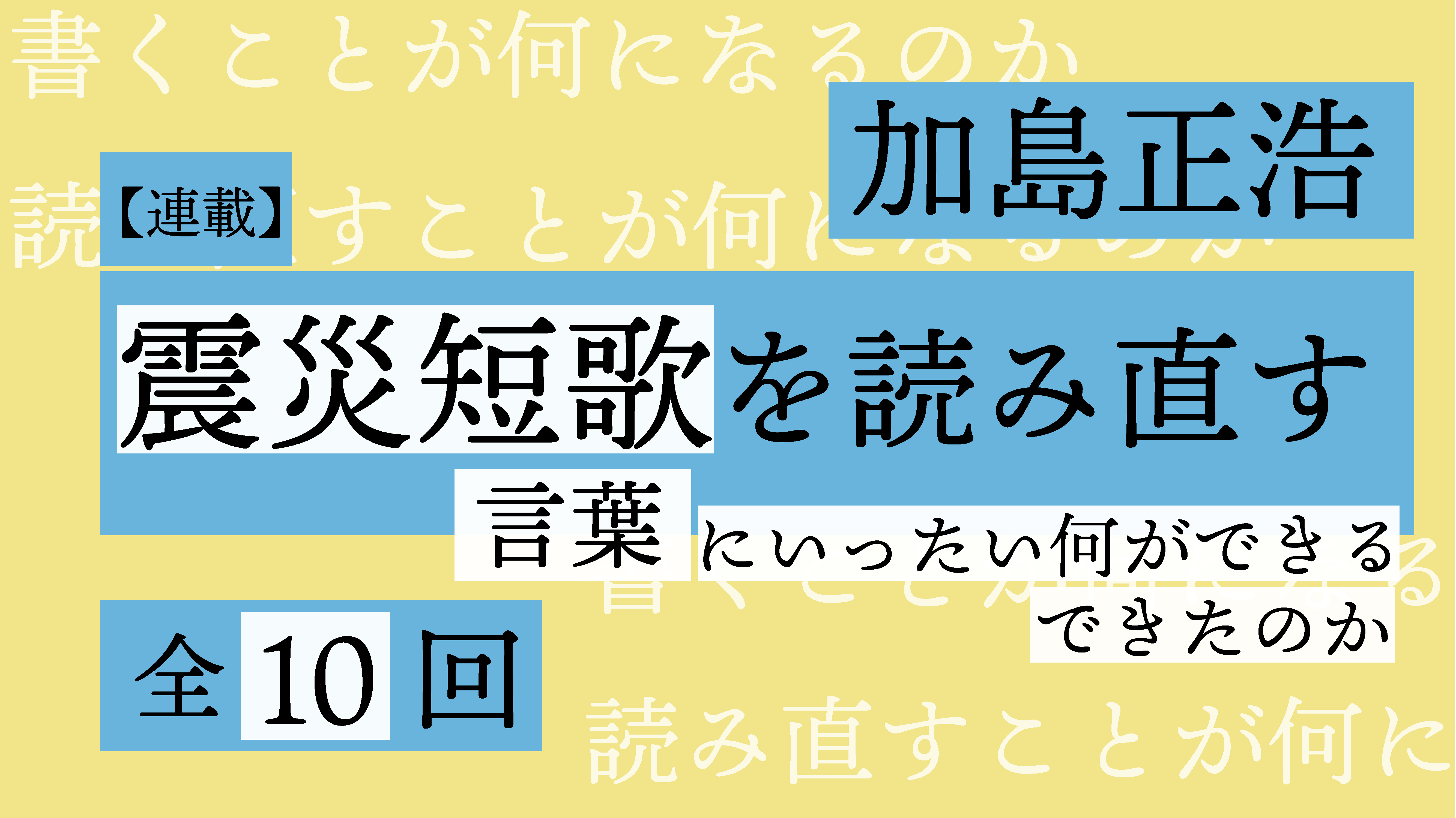
第3回
分断は超えられるとする思考への苛立ち
―― 逢坂みずき『まぶしい海』・近江瞬『飛び散れ、水たち』
■東日本大震災は終わってはいない
小説家の高橋源一郎と、文芸評論家の斎藤美奈子がその年を代表すると思われる小説や評論を俎上に載せた2011年以降の対談を収録した『この30年の小説、ぜんぶ―読んでしゃべって社会が見えた』(河出書房新社、2021年12月)は、読み応えのある良書だが、東日本大震災と文学の関係を考えている人間にとっては、一点気になる発言があった。
斎藤 (前略)2011年に対談したとき、高橋さんはすぐに作品で答えることが大事だとおっしゃってたじゃないですか。高橋さんの『恋する原発』、川上弘美さんの『神様2011』、古川日出男さんの『馬たちよ、それでも光は無垢で』(すべて2011)、東日本大震災後、というか福島第一原発の事故後につぎつぎと作品が発表された。
高橋 そうですね。
斎藤 コロナ文学も、もっと書かれるべきだと言う人がいるんだけど、そんなに急がなくていいと思うんですよ。だって、まだ終束 していないわけで。
この後、高橋が「震災とはちょっと性質が違いますよね」と発言し、斎藤も「違うと思いますね。瞬発力で行ける範囲は限られている」と応じ、震災とコロナの性質の違いがあるため、文学者の反応も震災直後と現状のコロナ禍での対応も異なることに言及されており、この点が主意なのだろうと考える。そのため、揚げ足取りではあるのだが、しかし思わずにはいられないのは、東日本大震災も終息してはいないだろうということである。
原発「事故」がいまだ終息していないことは述べるまでもないが(現在もなお原子力緊急事態宣言は発令されたままである)津波を被った地域に住む人々は、いまもなお「津波以後」を生き延びている。そのことを示すのが、逢坂みずき『まぶしい海―故郷と、わたしと、東日本大震災―』(本の森、2022年1月)である。
■震災は「忘れる」ようなものなのか
逢坂は、津波で町の中心部が壊滅的な被害を受けた宮城県女川町の出身である。当該書籍には東日本大震災以前や以後に書かれた詩や日記、エッセイなどと一緒に、2013年以降に詠まれた短歌も収録されている。
〈夢の中なんども津波押し寄せてなんども失くす今はなき家〉
上から2015年、2017年に詠まれた歌である。
私は、本連載の前身にあたる「震災俳句を読み直す」『セクト・ポクリット』の初回の連載時(https://sectpoclit.com/shinsai-1/)に、人々は震災を忘れたのではない、罪悪感から解放されるため、忘れようとしたのだということを述べた。そして東日本大震災で被災し、被災以後を生きることを強制された人々は、震災を「思い出す」という行為とは無縁であり、常に以後を生き続けざるを得ないと記した。
「被災地」では紙コップにまで、震災以後を示す「復興」の文字が刻まれ、その文字を(局外者は看過するかもしれないが)逢坂は見逃すことができず、「逃れられない」と感じる。逃れようにも逃れられない圧倒的な受動性のなかに逢坂はおかれている。それは、二首目の何度も津波が押し寄せ、生家が失われつづける夢を詠んだ歌にもみられる。自分でコントロールしようにも、夢は自分の制御できる範囲の外側にある。それに幾度も襲われつづけているのである。
上記に挙げた以外にも、逢坂は2019年に〈震災のこと話さねど春毎に忘れたいとのみ呟く友あり〉という歌を詠んでいる。「忘れたい」と思うということは、私が言い換えるまでもなく、言葉にしなくとも震災のことが、頭から離れないということである。
逢坂は〈この歌は震災詠ではないのだが日常の歌のつもりなのだが〉という歌も詠んでいる。「被災地」では、震災は年に一度「思い出す」特別なものなのではない。いまもなお「震災以後」を生き続けざるをえず、それが「日常」となってしまったのである。震災に浸食された「日常」を生きざるをえないのが、「震災以後」という意味なのであり、「震災」を想起したり忘却したりするサイクルのなかにおかれた、私も含む局外者が「震災以後」という時間を「生きている」のかどうかは疑わしい。私を含め局外者は、逢坂が詠むように〈翌日は震災の話題なくなってゴーヤチャンプル食べたとツイート〉できてしまう/してしまうのである。
■震災を「特別視」することが、分断を招く
加えて逢坂が、前書きに以下のように書いていることには注意したい。
高校一年生の終わり、二〇一一年三月に発生した東日本大震災では、生家が全壊となり、故郷の町も壊滅的被害を受けました。とてもつらい経験でした。でもわたしにとって、それは例えば、病気になって入院するとか、大切な人が亡くなるとか、誰の人生にも起こる出来事の一つという認識です。/しかし、東日本大震災を直接的に詠んだ歌を目にした読者は、特別なつらい経験をした可哀そうな人の歌だ、と少なからず思うのではないでしょうか。だから、多くの人に共感される本になってほしいと願っていた『虹を見つける達人』には、そうした作品を載せませんでした。
「日常」となってしまった「震災以後」を生きざるをえない人びとにとってみれば、「震災以後」は「特別」なことではない。しかし、私のように震災を切り出して問題化するのは、どこかに震災が「特別」であるという意識があるからである。そうでなければ「震災」を読み直すという企画自体が成立しない。ただしそうすることが、「震災以後」を「日常」として生きなければならない人たちとのあいだに分断を生むのも事実である。
逢坂は第一歌集の『虹を見つける達人』には「共感される本になってほしい」という願いから、震災を直接に詠んだ歌は収録しなかったという。局外者である「私たち」が、自らの理解を超えた震災の被害を「特別視」し、遠ざけようとする傾向にあることを、〈「震災は大丈夫だった?」「二階まで津波来ました」引くなら聞くなよ〉と詠む逢坂は鋭く見抜いているといえる。
津波が襲い来るその場に居合わせなかった人間には、そのときの恐ろしさやその後を生きなければならない苦悩は想像するしかないが、それらは「私たち」の乏しい想像力をやすやすと超えるものでもある。震災のことは安易に尋ねられるものではなく、また想像を超える被害とその後を生きなければならない現実に、たやすく共感できるわけもない。
しかし想像を超えた共感できないものとして震災と震災以後を捉える「特別視」が、分断を生じさせることも事実である。逢坂は〈崖に咲く躑躅の赤さ 当事者であること強みにはしたくない〉とも詠んでいるが、「当事者であること」を強みにさせてきたのは、「当事者」である彼女ではなく、局外者である「わたしたち」なのではないか。「わたしたち」が震災を「特別視」することで、それを経験した人に「当事者」性を付与し、彼女たちに何かを語らせ、そのうえで自分たちとは違う経験をした人として(敬して)遠ざけてきたのではないか。それが適切なことであったのか。しかし、津波が押し寄せる瞬間に居合わせなかった「わたしたち」に何ができるというのか。そのあいだを行き来しながら、思考をめぐらせる必要があるはずである。
■「被災地」における分断
ただし、やすやすと超えていけないから分断は生じるのであり、それを超えていけるかのように接することが逢坂を苛立たせ、〈引くなら聞くなよ〉という言葉を招き入れているのだろうと思う。(安易に)分断を埋めようとすることが、結果的に分断を深めるということを真摯に考える必要がある。
逢坂の苛立ちをより先鋭化させたのが、近江瞬『飛び散れ、水たち』(左右社、2020年5月)であると考える。当該書籍はⅠ・Ⅱ・Ⅲの三部からなり、Ⅰ・Ⅱには〈僕たちは世界を盗み合うように互いの眼鏡をかけて笑った〉、〈何度でも夏は眩しい僕たちのすべてが書き出しの一行目〉、〈まだ割れることを知らない空中の瓶だよ僕らの今は例えば〉などの鮮やかに青春を詠みあげる歌が収められているが、Ⅲでは「被災地」となってしまった故郷石巻での生活が詠まれ、歌の雰囲気が大きく変わる。
〈生きられれば良かった日々も七年が過ぎれば全教室にエアコン〉
〈被災地視察に新大臣が訪れる秘書の持つ傘で濡れることなく〉
〈図書館も被災してれば国の金で立派にできたのになんて言葉も〉冷徹に「被災地」の以後を見つめ、歌にしているといえるが、二首目などは現実を捉えた歌とはいえども、手厳しい。一首目もその土地で生きていれば、ある程度は仕方のないこととして看過する向きもあるかと思うが、近江はそれを見逃さない。鋭敏な感覚は当然、政治家の訪問の姿や、生活者の「失言」も当然見落とさない。
そして近江は「被災地」での人々の姿を鋭敏な感覚で捉えるだけではなく、自分自身に向けられる視線にも敏感である。
近江は「当時の記憶を持たないことの劣等感が消えることはこの先もないだろうと思う」、「大学卒業後に2年間働いた都内の前職時代、東京の人々は石巻を故郷に持つ僕を被災者の一人として気遣ったけれど、石巻に暮らせば、あの日を知らない僕はやはり被災者ではなかったと知った」ということも述べている。「石巻に暮らせば、」「やはり被災者ではなかったと知った」という部分が近江の置かれた立場を示しているように思う。そこで生活する人々を捉える視線と、人々が自分を捉える視線に敏感であるからこそ、自分が「被災者」としては見られていないことを把握し、「劣等感」すら抱かされてしまうのである。
近江は〈僕だけが目を開けている黙祷の一分間で写す寒空〉とも詠んでいる。「目を開けている」のは近江だけではないだろうという野暮なコメントをさしはさむこともできる。阪神淡路大震災においても、避難所で寝泊りしたものの、発災時に崩壊した自宅にいなかったことで「被災者」ではないと感じた劇作家の深津篤史や、避難所で生活していたものの当時は「子ども」だったために、何もわかっていなかったと引け目を感じる詩人の最果タヒなどの存在もあり、そこに居合わせていても、震災を「目撃」しなかったことや「理解」できなかったことで、「被災者」と自らを位置づけられない先達者がいたことの指摘もできる。しかし、そこに本質はなく、重要なのは歌人に〈僕だけ〉と思わせる力学が「被災地」にも働いているということを詠んでいる点であろう。「被災地」においても、2011年3月11日にそこに居合わせたのかどうかで、線引きが行われうることは念頭におく必要がある。
■安易につながろうとすることへの苛立ち
しかしそれで終わるわけではない。近江は〈普通という暮らしの中に物言わぬ311のうるささは満ち〉という歌につづけて、以下のように記している。
その無音のうるささと対照的にSNSではある種の決意や回想が封を切ったかのようにあふれ出る。(中略)「つながっていよう」「忘れないでいよう」「覚えているよ」。口には出せないかわりSNSでたくさんの心がうるさい。「マスコミはこういう時だけ」と、こういう時だけいう人。「忘れちゃいけない」と言う人の前日の投稿にあるディナーの肉がおいしそうだった。忘れてもいいし、つながってなくてもいい、普通でいてほしいけれど、それは本当に難しいことなんだと思う。
SNSでのうるささと対照される「普通」の暮らしのなかにある〈無音のうるささ〉とは、「被災地」での生活なのであろう。「被災地」での「普通」の暮らしには、取り立てて「特別」に取り出さなくても、「震災以後」は「うるさい」ほどに刻印されているということだと思う。一方SNSでは、3月11日という「特別」な日が近づくにつれ、あるいはその日だけ騒がしくなり、「普通」ではなくなる。ただ「特別」は継続しないから「特別」なのであり、その日が終わればまた静かになる。そうであるならば、3月11日も〈普通〉に過ごせばいいのにということだと思う。3月11日にだけ、震災を思い出し、新たにする決意にどれほどの意味があるのか。それは「震災以後」から逃れられない人たちを苛立たせるだけなのではないか。
近江は、自らは「被災者」ではなかったと知ったと述べるが、「被災地」となり「震災以後」が刻まれた故郷石巻で生活しつづけている以上、「震災以後」という時間からは逃れられない。だからこそ〈サイレンを無視して笑う人のいて何に怒っているんだ僕は〉という歌も詠まれる。「被災者」ではないが、「震災以後」の時間とも無縁ではいられないからこそ、震災との距離の取り方が安定せず、複雑化する。〈何に怒っているんだ僕は〉と歌い、自らの感情を相対化する近江はそのことにも自覚的なのだろう。
そのような複雑さを抱えながら、「何と」つながろうとし、「何を」忘れずに覚えておこうとするのかも明示されない、深くは考えていないであろう型通りの言葉の羅列を見れば、「普通」でいてほしい=何も言わなくていいという気持ちになるのは、無理もないことであろうと思う。
■では、分断されたままでよいのか
しかし、震災に関する安易な言葉への拒絶は、局外者が震災に関わることへのハードルを高くする。局外者が震災に関わることを辞めれば、震災は「被災地」の〈彼ら/彼女ら〉の問題として局所化される。そうなれば、震災への関心は薄れていく。記憶の「風化」を招く。もはやそうなっているのかもしれないが、その流れに拍車をかける。
もちろん、それでいいということなのかもしれない。「被災地」の問題なのだから、「よそ者」は口を出すなということなのかもしれない。近江はあとがきにて以下のように記している。
靴紐が切れたり、ビニール袋が風に膨らんで飛んだり、打ち寄せる波の半分が砂浜にしみ込んだり、君と眼鏡を交換してみたり、開けっ放しのペットボトルを投げ渡してみたり、悲しくて海に来てみたり、うれしくて海に来てみたり。僕らはいつだって無意味で、だからこそ美しい。誰かにとっての意味ではなく、ただ僕らにとっての意味にあふれる世界を生きている。
短歌は、世界の無意味を僕らの意味へと変えてくれる。
「僕らにとっての意味にあふれる世界を生きている」と述べるように、近江の短歌は〈僕ら〉の世界を詠むものであり、彼が範疇化した〈僕ら〉以外の人間を寄せつけない雰囲気がある。〈僕たちは世界を盗み合うように互いの眼鏡をかけて笑った〉のなかに、外側にいる眼鏡を交換できない人間は入っていけないし、〈何度でも夏は眩しい僕たちのすべてが書き出しの一行目〉も、〈僕たち〉にとっての世界で完結している。
近江は短歌が「世界の無意味を僕らの意味へと変えてくれる」と述べている。彼は自覚的に〈僕ら〉の世界を詠んでいるのであり、そのために〈僕ら〉ではない人は入り込みにくくなっているとはいえる。Ⅲ部では、〈僕〉にもその視線は向けられるとはいえ、基本的には〈僕〉の外側にいる人びとへの冷徹なまざなしが向けられるが、〈僕〉(たち)ではない人たちを詠んでいるという意味で、Ⅲ部は、Ⅰ・Ⅱ部とは作風が変わっているというよりは、表裏を成すものとして捉えた方が的確であるかもしれない。
もちろん〈僕〉(たち)と、〈僕〉(たち)の外側をわけて震災を詠むとき、それが分断線を強固にすることは言うまでもない。しかし近江はおそらくわかっていて「普通」でいてほしい=関わらないでほしいと言っているのである。
そして、その流れは加速するだろう。人/文学は、渦中にある問題にはほとんど無力であるが、それが終息した時点から、強みを発揮する。ロシアによる侵略戦争が終息した段階から、人/文学は、ロシアやポスト冷戦の問題、グローバル主義の問題、現代における戦争の問題へとリソースを割くことは、ほとんど間違いがない。
もちろんそれは必要なことであり、当然である。しかし、そうなれば震災は、それ自体を「特別に」取り上げられる機会は大きく減少し、グローバル化による内的植民地の構造的な問題のひとつとして、震災も存在したという言及のされ方へと変わっていくだろう。そのとき言及される震災の側面は、日本社会の問題としてや世界の構造的問題としての震災というものになるだろう。人/文学において、「被災地」のことが「特別」なものとして問題化される機会はおそらく大きく減少する。「被災地」とは関わらなくなっていくだろう。
それで良いのかもしれない。3月11日前後のマスメディアの報道やSNSの人の反応に苛立っているだけで、人口に膾炙しない人/文学はどうでもよいのかもしれない。「もういい加減、お前も忘れろよ」と私のような人間に対しても思っているのかもしれない。
ただ本当に「忘れられ」誰も「特別」に問題視しなくなったとき、どう思われるのか。
2022年5月6日、富山市は西本郷企業団地の造成の際に余った土の一部から、環境基準を最大で2倍上回るヒ素が検出されたと発表した(https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/732567)。この土はカドミウム汚染田の復元事業で、表層の土を除去した後の下の土を建設用に用いたものとのことであった。イタイイタイ病もまだ「終わってはいない」のである。しかし、このニュースが富山県外でどの程度報道されたのか、イタイイタイ病を「終わっていない」ものと認識している人がどの程度いるのか。
東日本大震災が、イタイイタイ病と同様の事態となるのかどうかはわからない。しかしそこへと向かう流れになっているのは、事実であろうと思う。そのときに、「普通」でいてほしい=関わらないでほしいという思いを基に、歌人は歌を詠むのであろうか。
そのことには注視しつづけたいと思う。
■コーナートップへ




























































































