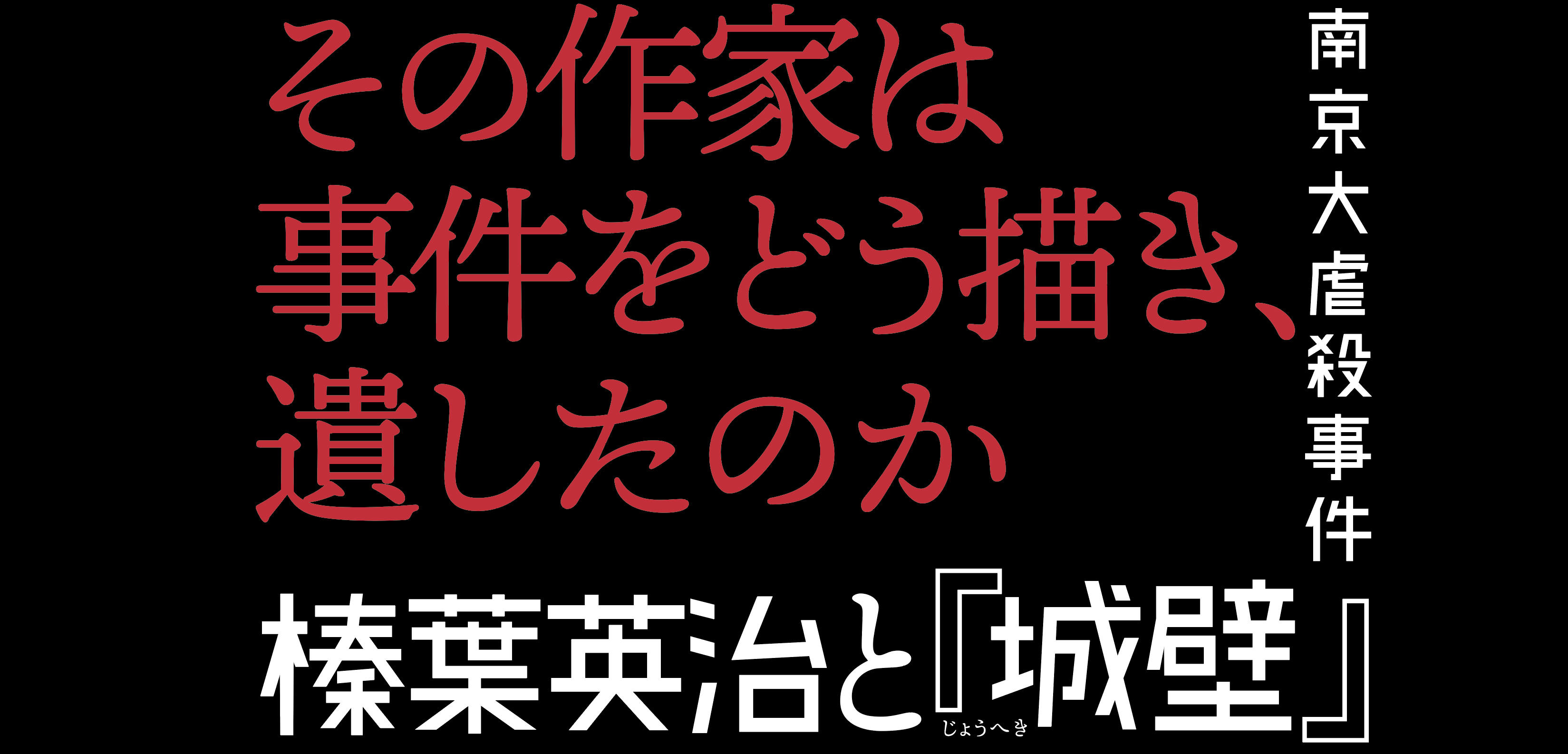5.戦争文学としての『城壁』(五味渕典嗣)(2部 榛葉英治という作家)
●2020.06月刊行
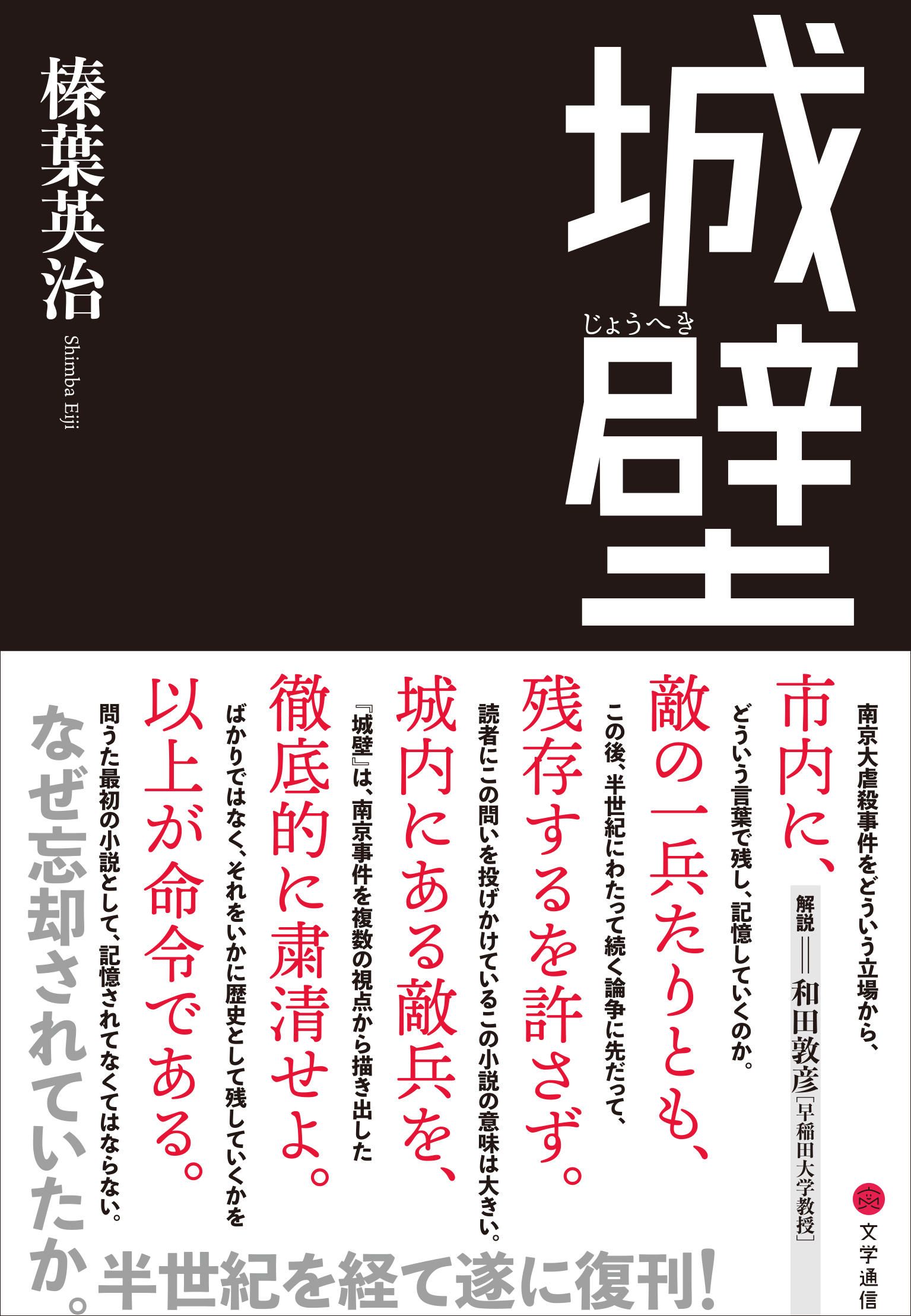
榛葉英治『城壁』
[解説・和田敦彦(早稲田大学教授)](文学通信)
ISBN978-4-909658-30-2 C0095
四六判・並製・296頁
定価:本体2,400円(税別)
--------
2部 榛葉英治という作家
5.戦争文学としての『城壁』
五味渕典嗣
早稲田大学教育学部教授。慶應義塾大学大学院文学研究科国文学専攻博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。専門は、近現代日本語文学・文化研究。著書に『プロパガンダの文学――日中戦争下の表現者たち』(共和国、2018年)、『言葉を食べる――谷崎潤一郎、1920~1931』(世織書房、2009年)、『谷崎潤一郎読本』(共編、翰林書房、2016年)、『漱石辞典』(共編、翰林書房、2017年)などがある。
文学通信から榛葉英治『城壁』が復刊されると初めて聞いたときに感じた驚きと昂奮は、いまでもよく憶えている。これで、現在の日本語の読者は、辺見庸が『1★9★3★7』(金曜日、2015年。のち角川文庫から『完全版 1★9★3★7』上下が刊行)で取り上げた堀田善衞『時間』(岩波現代文庫、2015年)と、中国文学研究者・関根謙による全面的な補訳・改訳を経て刊行された阿壠『南京 抵抗と尊厳』(五月書房新社、2019年。▶注1)と合わせ、1937年12月から翌年にかけて、南京城内外で起こった日本軍による惨虐な加害行為をめぐって、異なる視座から描いた3つの小説を書店で手にできるようになったわけだ。
文学通信版『城壁』「解説」の執筆者である和田敦彦氏は勤め先での同僚だが、わたし自身は、榛葉英治資料にかんする研究会には参加していない。そこでここでは、本連載コラムの他の執筆者とは違う観点から、日中戦争を描いた戦争文学として『城壁』を読みなおす可能性について、わたしなりの補助線を引いてみたいと思う。
『城壁』の冒頭近く、江藤清少尉率いる小隊が上海から南京へと侵攻を続けて行く途中で、次のようなシーンが書き込まれている。
田のなかをながれるクリークにかかった土橋のそばに、ひとりの女が死んでいた。そばに荷物が散らばっている。逃げる途中で、流弾にやられたのだろう。晴れた日で、黄色いクリークには雲が映っている。
「おい、女が死んでるぞ」
二列縦隊の先の方で、兵隊がいった。隊列はそこでとまり、後ろからきた兵隊もかたまった。一人が珍しいものでもみつけたように後ろに教えた。
「おい、女だ。赤ん坊を抱いてるぞ」
「ばかな女だ。こんなとこをうろうろ歩いてやがるからだ」
うつ伏せに倒れた母親の腕のしたで、赤ん坊が手をうごかし、大きな眼をあけていた。男の子か、頭を剃り、両耳の上にだけ毛の房を残している。(一章)
じつは、日中戦争初期の戦線を描いたテクストには、これに類する場面が多く書き込まれている。石川達三『生きてゐる兵隊』(『中央公論』1938年3月=発売禁止)では、やはり上海から南京に向かう追撃戦の中で、クリークの土手近くで仰向けになって死んでいる若い母親の横で「まだ這ふこともできない嬰児がうつ伏せになり枯草のなかに鼻を突つ込んで泣きわめいてゐた」場面が記されている。『城壁』の江藤小隊と同じ杭州湾上陸作戦に参加した火野葦平『土と兵隊』(改造社、1938年)には、1937年11月11日の出来事として、夜陰にまぎれて戦場から逃げようとした住民たちが中国軍側から射撃され、瀕死の母親が懸命に「道に転がつてゐる赤ん坊の方に手を差し延べて何か口の中で歌ふように呟きながら、赤ん坊をあやして居る」姿が印象的に書き留められている。このあと母親は、最後の力を振りしぼって赤ん坊を抱き寄せていくのだが、そんなことは分からない赤ん坊の泣き声が、戦場の夜の闇の中を響きわたる。いたたまれなくなった「私」=玉井伍長は、危険を省みずに壕を飛び出し、「殆ど身体をむき出しにしてゐる」赤ん坊を蒲団でぐるぐる巻きにし、母親にも蒲団をかぶせて壕に戻った、と記されている。このあと、この赤ん坊がどうなったかを火野葦平は語っていない。
『土と兵隊』の挿話については、坂口博が、火野と同じ部隊(第一八師団第一一四連隊第二大隊第七中隊)所属の安田貞雄による戦記『戦友記』(六芸社、1941年)に同じ場面があることを指摘、「ほぼ描かれた通りの出来事が起こったに相違ない」と考証を加えている(▶注2)。敗戦後に刊行された村田和志郎の従軍記『日中戦争日記(一)杭州湾上陸』(鵬和出版、1984年)にも、1937年11月の戦闘にかかわる記憶として、「道路脇の畑の中」に、死んだ若い母親のそばで「まつわりついて遊んでいた」赤児の姿が点綴されている。ちなみに村田は、「誰かが見兼ねて、その赤ん坊を抱いて行軍して行ったということを後できいた」と書きつけている。
もちろんわたしは、彼らが同じ場面に出会っていた、と言いたいわけではない。「もっぱら給養は掠奪に依存する作戦」(▶注3)だった南京攻略戦は、中国の現地住民たちの生活と生命を日本の戦争のために搾取し尽くすことによって行われたから、乳呑み児を抱えたまま逃げ遅れた母親たちが、こうした無惨な死を死なねばならなかった出来事はあちこちで起こっていたはずだ。だが、ここでわたしが問題にしたいのは、描かれた出来事の事実性だけではない。日中戦争の同時代から敗戦後にかけて、戦場の惨酷さを伝えるエピソードとして、同じような情景がくり返し想起され、テクストに書き留められてきたことをどう考えるか、ということである。
例えば、こうした場面が、作中でどんな意味を与えられていたかを確認してみよう。明らかに日中戦争期のプロパガンダ的意図を担って書かれた『土と兵隊』では、「悲しげな赤ん坊の泣き声」から「故郷のことを思い出」し、「全くどうにもいやな気持」になって、半ば自棄的にあてもなく発砲をくり返す兵たちの様子が書き込まれている。作中の「私」=玉井伍長は、そうした兵たちの思いを代表するかのように、中国軍が銃を構える壕の外に身をさらし、せめてこれくらいはと人間的なやさしさを発揮してみせる。こうした場面が書き込まれたことが、銃後で『土と兵隊』を読む読者たちに、戦場の「ヒューマニズム」という評価を生んでいったことはよく知られる。
では、ひるがえって『城壁』はどうか。大学の法科出身で、いわゆる「甲幹」(甲種幹部候補生)上がりの小隊長である江藤少尉は、現役志願の叩き上げである倉田軍曹が、赤ん坊だけを「生かしといても仕様がないぞ」とこともなげに口にしたことに、「半ば肯定しながら、相手を非難する」ような視線を向けずにはいられない。一方、軍隊生活にいちはやく適応した寺本伍長は、そんな倉田軍曹以上の残虐さを発揮して、躊躇なく赤ん坊を射殺し、軍曹に向かって「髭面の白い歯をみせて笑」ってみせる。一連の情景を見つめていた鈴木上等兵は、「これが戦争というものだ」と自分自身に言いきかせていく。
短いカットの積み重ねによって小隊の面々の戦争観とキャラクターとを浮上させた見事なシーンと言えるが、わたしにとって興味深いのは、この場面で内面の揺らぎを書き込まれ、相対的に良心的な将校という位置を与えられていく江藤少尉について、『城壁』の語りが、ある種のひ弱さ・頼りなさというだけでなく、男性的な強健さを一貫して強調していく点である(彼は大学時代ボート部の選手だったと設定されていて、彼のたくましい身体を兵たちがうらやむ場面がある)。『城壁』には、日本軍の兵士対中国の民間人、日本軍の兵士対難民区の外国人たち、日本軍内部でも強姦や暴行を行う兵士たちとそうでない兵士たち、という複数の対立が書き込まれている。日中戦争を描いた戦争文学として『城壁』を読みなおすうえでは、群像劇としてしつらえられた舞台の上で、男性どうしのホモソーシャルな関係性が、こうした対立の構図をどのように上書きし、ズラしていくのか、その「ズラし」にどんな意味を読み込み、評価していくかが問われることになる。
和田氏の解説が詳細に論じているように、『城壁』は、「南京事件を歴史知識にもとづきながら想像可能な物語にして広く発信していった小説」として、歴史的な価値を有している。そして、『城壁』が小説である以上、南京事件を「どういう立場から、どういう言葉で残し、記憶していくのか」(「解説」)という問いは、このテクストで榛葉が誰に・どんな場面を経験させ、どんな思いや言葉を語らせていたか、という表現にかかる問いへと折り返されていくはずである。
戦争文学として『城壁』をどう読みなおすのか。この問いは、現在の読者として、榛葉の描いた南京事件をどう評価するか、という重たい課題とつながっている。
(▶注1)『南京 抵抗と尊厳』の解説によれば、同書は、関根によって1994年に刊行された『南京慟哭』を全面的に改訳し、当時割愛した章の翻訳を補った「完全版」である。
(▶注2)坂口博『校書掃塵――坂口博の仕事Ⅰ――』(花書院、2016年)。
(▶注3)藤原彰『南京の日本軍 南京大虐殺とその背景』(大月書店、1997年)。