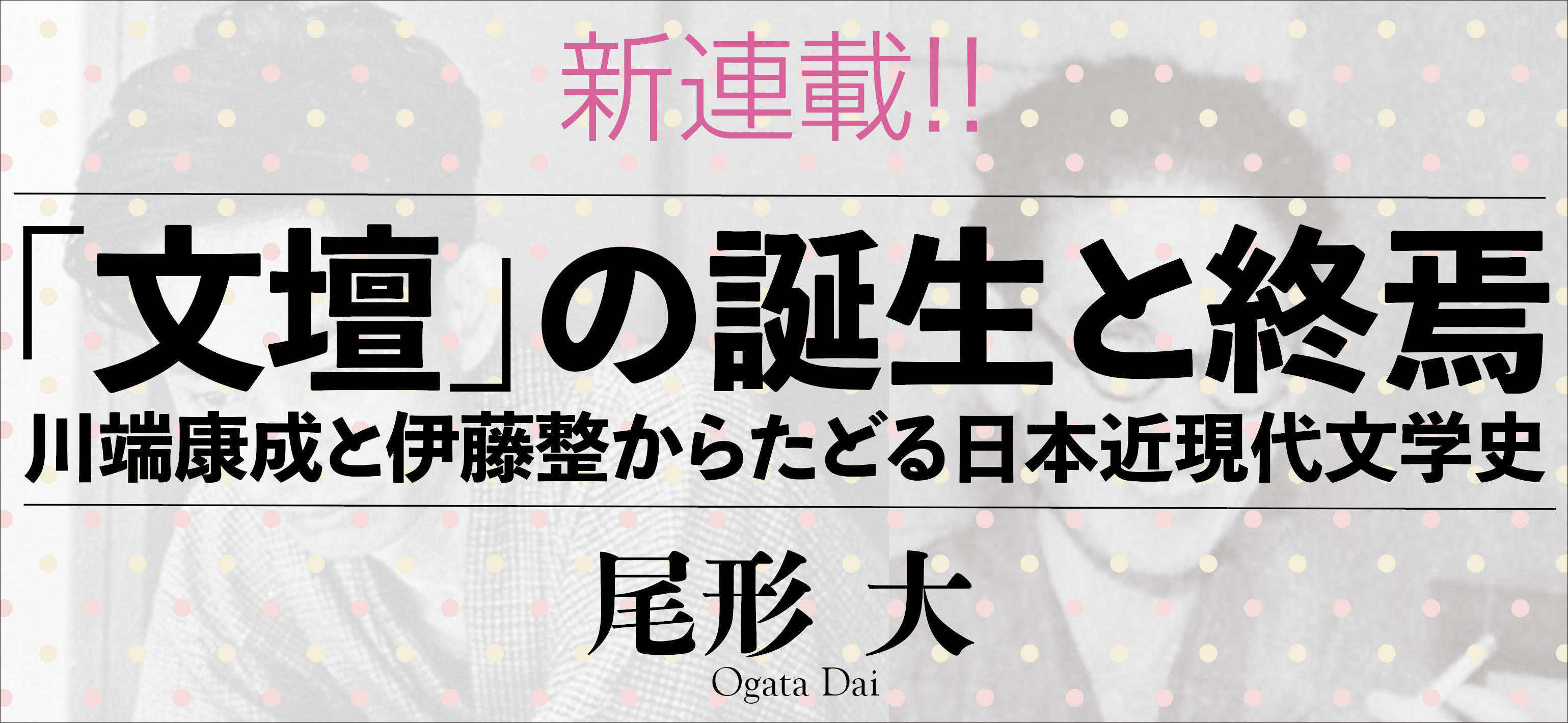第1回 はじめに―「文壇」は作られた●【連載】「文壇」の誕生と終焉―川端康成と伊藤整からたどる日本近現代文学史
第1回 はじめに―「文壇」は作られた
尾形大
▶︎「文壇」という言葉の定義
「文壇」という言葉がある。一部の人にはノスタルジーを感じさせるこの言葉を耳にする機会は、近年ほぼなくなった。「文壇」という言葉を辞書でひいてみると、「文筆活動をしている人たちの社会。作家・批評家などの集団。文学界。」(『大辞林』第3版)と記されている。この定義にしたがって文学の作り手たちの社会を「文壇」と呼ぶとすれば、市場は縮小したものの「文筆活動」をする「作家」たちは現在も生き残っており、必然的に「文壇」も存在しているということになるだろう。しかし、今日の社会に「文壇」は存在しないと思われる。辞書で定義された「文壇」と、年に二度の芥川賞・直木賞の選考・発表が報じられる際に私たちが想起する「文壇」とは微妙にずれている。そのずれは、辞書の意味する「文壇」という言葉に、本来付随するはずのある特殊性が抜け落ちていることに起因する。
1977、78年に刊行された『日本近代文学大事典』(全6巻)の第4巻「事項篇」のなかで、瀬沼茂樹は「文壇」を「広狭二義」に分けて解説している。「古くからの用途として「文学界」または「文学者の社会」全体を漠然と呼ぶ広義の文壇」と、「特殊な気質または倫理、さらには芸を養成するような小集団を形成する」「狭義の文壇」である。このうち「狭義の文壇」が、「文壇」という言葉が内包する〈特殊性〉を説明する。独自の価値観を共有し「芸」を磨く「文士」という特殊な人々の修業・交友機関としての「文壇」は、世間一般とは隔絶した社会と見なされてきた。こうした〈特殊性〉を有した社会としての「文壇」は、今日すでに存在しない。
『日本近代文学大事典』が刊行された1970年代まではたしかに「文壇」が存在した。川西政明は『新・日本文壇史』第十巻(岩波書店2013)のなかで、1970年前後を「文壇」の一区切りと見なしている。その理由として、「日本の近代文学・昭和文学が抱えていた重く苦しいテーマ―「私」「家」「性」「神」「戦争」「革命」「原爆」「存在」「歴史」」が概ね書かれ終わったこと、「文壇」がそうしたテーマを「抱えた文士たちの共同体」だったこと、そして高見順(1965年没)、伊藤整(1969年没)、三島由紀夫(1970年没)、志賀直哉(1971年没)、川端康成(1972年没)、平野謙(1978年没)といった「文壇」の中核的なメンバーの相次ぐ死去などを挙げている。
▶︎『日本文壇史』のなかの文壇像
1970年代まで「文壇」という言葉は敬意をこめて用いられ、そこに所属する人々は最高の知識人として社会的に認められていた。「文壇」は明治以降の日本文学を生み出した歴史と伝統に彩られた場として権威を持ち、世俗的な価値基準に縛られることのない芸術家の領域と見なされた。こうした「文壇」イメージが形成された要因のひとつに伊藤整の『日本文壇史』(『群像』1952-1969)があった。
伊藤は第1巻「開化期の人々」(講談社文芸文庫、1994)の「はしがき」で、「ある時代の文士や思想家や政治家の行動が、みなつながりのあるものと考え、そのつながりや関係や影響を明かにすることに全力をつくした。」と述べている。『日本文壇史』では個別の作家ではなく、個々の作家の生活・生き方と人間関係に焦点が当てられている。個人の思い付きや行動、小さな人間関係が、水面に生じた波紋のように遠くまで及んで影響を与えるさまを物語風に記述することで、「文壇」の歴史が立ち上げられていく。『日本文壇史』は「文壇史」というジャンルの嚆矢となり、巌谷大四や近藤富枝、大村彦次郎や川西政明らによる多くの「文壇史」が発表される土壌を作った。
ただ、ここで注意したいのは、伊藤や瀬沼らによって具体的な姿形を与えられた(かに見える)「文壇」とは、あくまでも特定の個人・集団・メディアを事後的に〈中心化〉する「文学史」的な尺度の内側で語り直されている点である。再び『日本文壇史』第1巻に眼を向けてみれば、その第七章の1、2節で明治十四年の銀座に焦点を当てた伊藤が、3節で銀座に集った3人の少年を取りあげる点に『日本文壇史』の性格の一端が表れている。「明治十四年の九月に、長野県木曽の山の中の馬籠という峠の頂に近い村から、島崎春樹という十歳の少年が上京し」、「銀座の数寄屋橋のそばにある泰明小学校」に入学する。そして「この同じ年、その泰明小学校に、小田原から来た北村門太郎という十四歳の少年が入学した。」と「泰明小学校」を梃子に二人目の少年に接続され、さらに「またこの明治十四年、同じ京橋の南伝馬町の有隣堂という書店に、十一歳の田山禄弥という少年が小僧に入っていた。」と、やはり銀座という場所に集った「文壇」の萌芽を描写してみせる。互いの存在さえ知らずに東京銀座周辺に集った三人の少年は、後の島崎藤村・北村透谷・田山花袋である。この三人を中心に「文壇」の形成が語られはじめる構成は、『日本文壇史』が本質的に「文学史」的な尺度をもって試みられた「文壇史」であることを物語っている。
このように考えてみると、伊藤によって「文学史」の枠内で遡及的に形成された「文壇(史)」と、その時々の文学者がアクチュアルな形で向き合っていた「文壇」とは、けっして同義ではないことに思いいたる。1970年代まではたしかに存在した「文壇」は、明治期との連続性を持ちながら同時に非連続的な場でもあった。両者は事後的に「文壇」という言葉で貫かれ、ひとくくりにされたのではないか。
▶︎文壇へ参入するには
そもそも瀬沼の言う「文学者の社会」の範囲は一様ではなかったし、「文学者」の〈資格〉も実に曖昧だった。多くの「小集団」が離合集散を繰り返し、特定の「小集団」は先輩諸氏にとって代わろうと野心を燃やす。いつの世も「文壇」は賑やかに存在したが、そこに参入するための方法・経路は、基本的に手探りするしかなかった。時々の「文壇」のアクチュアルな状況・情勢を見極め、参入のために適切に対応できた文学者がはたしてどれだけいたことか。それでも硯友社時代から大正中期頃までの「文壇」は、特定の作家と特定のメディアとの結びつきや地縁・学閥・師弟関係等を土台とする「ギルド」(大宅壮一)的性格を有していたため、比較的分かりやすい面もあった。
『新小説』に「芋粥」、『中央公論』に「手巾」を発表した芥川龍之介が友人の原善一郎に宛てた書簡のなかで、「この頃僕も文壇へ入籍届だけはだせましたまだ海のものとも山のものとも自分ながらわかりません」(1916・10・24)と記したことはよく知られている。芥川が「文壇」に参入するための戦略を練ることができた背景には、夏目漱石や滝田樗陰といった先輩作家・文学関係者の「社会」として、「文壇」が可視的だった幸運もあっただろう。
転機は大正後期に訪れる。大正末以降のジャーナリズムの大規模化にともない、「文壇」は大きな変革期に差し掛かった。当然「文壇」への参入も新たな局面を迎える。幸運にも参入のかなった芥川や菊池寛らは、まもなくその中心に食い込み、若き舵取り役として「文壇」の動向を左右するようになる。
▶︎戦後文壇の中心:川端康成と伊藤整
ちょうどこの前後に新人作家として活動を開始した二人の文学者、川端康成と伊藤整に注目してみたい。川端は1920年に東京帝国大学文学部英語英文学専攻に入学し、翌年創刊の第六次『新思潮』に「招魂祭一景」(4月)を発表する。伊藤は1926年12月に北海道小樽の片隅で第一詩集『雪明りの路』(椎の木社)を上梓し、詩人として出発をはたした。この後彼らは各々の経路で「文壇」に参入し、とくに戦後の「文壇」において中心的な役割を担っていくことになる。
このことを象徴するようなテレビ番組がある。特別番組「川端康成氏を囲んで」(NHK総合、18日21:40~22:10放送)である。川端のノーベル文学賞受賞の報を受けて日本中がおおいに沸いた翌日の1968年10月18日、鎌倉長谷にある川端康成邸の庭先に3人の男が腰を掛けていた。中央に主役の川端(70歳)が和装で座し、画面右に三島由紀夫(43歳)、左に伊藤整(63歳)がスーツ姿でひかえる。この番組が2003年11月30日に再放送されることを伊藤整研究者の曾根博義先生から知らされた私は、当日あわてて録画した。現在NHKアーカイブスでこの貴重な映像と肉声を冒頭数分間視聴できる。
番組は伊藤を司会役に進行する。三島は川端個人に焦点を当てながら西洋/非西洋という尺度で川端文学の特徴を説明し、日本文学のなかでもっとも「洗練」された結晶と川端文学を言い表す。俳句・連歌の韻律を模したような『山の音』の文体や、「どこがはじまりか終わりかわからないような」非西洋的な作品構成について歯切れよく語る三島に対して、受賞を「国の喜びでもあり、われわれ文壇全体の喜び」と言い表す伊藤の見解はやや異なる。
伊藤「川端さんがここに今立っていらっしゃるけども、その前にも後ろにも人が繋がっていましてね、明治時代から鷗外とか藤村とか、それからあのまあ...、とくに私があげたいのが秋声ですね。秋声の...今三島君の言われたような川端さんの生き方に秋声だけがいくらか近いようなところがあるわけでして、...それから鏡花は私ども前から言っていたことですが。川端さんより前の人の仕事が厚みをなしていると。で川端さんが前に立っていられると。そのあとにも若い人が、三島君をはじめつながっていると。そういう、ちょうどいま川端さんが全体を代表してこれをお受けになったという感じがするんです。」
川端の文学を明治以来の日本文学の系譜のなかに置き直し、さらに同席する三島のような若い世代まで含めることで、今回の受賞を川端個人の功績ではなく、川端の「前にも後ろにも」「繋がって」いる日本の文壇全体の功績として意味づける伊藤の言葉は印象深い。
番組は当時の「文壇」を可視化するような場として作られている。当時の文壇の長老格、脂の乗り切った若手作家、そして文芸評論家という三者が一堂に会した図は象徴的だ。なかでも伊藤は番組内でひとり「文芸評論家」の肩書を付され、作家と学者を股にかけて、世間と「文壇」を媒介する役割を担っている。こうした伊藤の立ち位置は、有志の文学者と文学研究者とによって1962年に設立準備会が結成された日本近代文学館の開館および同館理事長という当時の役職とも深くかかわっている。
▶︎ノーベル文学賞を受賞した川端の戸惑い
番組全体をとおして、司会役の伊藤の問いかけに対する川端の反応はどこか鈍く、あまりかみ合っていないような印象さえ受ける。前日からのお祝いで少々疲れ気味の様子の川端が、やや唐突に次のように問いかける。
川端「伊藤さんに聞きたいんだけど、今度の受賞でですね、あのー、審査...翻訳でやってますね。だから僕は翻訳者には、...(翻訳者-引用者注)のおかげが非常に多いわけですがね。おそらくいい訳だったんだろうと思うんですがね。翻訳者ばかりじゃなしに、まあサイデンステッカーとかキーンとか、フランスの作家なんかもそうですが、私にかなり応援してくれる人もあるんですね。だからまあ翻訳者が半分貰ったのか、あるいは三分もらったのか分かりませんけどね。日本語で審査されてない。非常に良心的に、厳密に言うと、辞退するのが本当かもしれんと...。どう思いますか。」
伊藤「...そうですね。しかしですね、それはもう私賛成するわけにはいきませんですね。私どもやっぱり、あのー、外国の諸国の文学を日本語でほとんど読んでおります。私なんか英語を商売にした人間でも日本語で読んでおります。それでやっぱり分かったつもりでおりますから、いい翻訳ということもですね、なんて言いますか...、なんて言いますか...、やっぱり原作の再現をできるだけ忠実にやるということですから、また日本語で読んでもらうチャンスはなかなかしばらくはないでしょうから、これはもうそういうこと...辞退するなんていうことを考えていただくと困ると思うんですね...。」
自身の受賞を自嘲気味に語る川端に対して、受賞を「文壇」全体の功績と位置付ける伊藤は困った表情を浮かべながら懸命に回答する。生真面目な伊藤の反応に川端は「まあね、そんなに深刻には考えないんですけどね。」「まあ、しかしそういう考え方もたしかにあるんじゃないかというね。」と悪戯っぽく応答してみせると、安心した様子の伊藤は優しい声色で「ああ、そうですね、そうです。」と相槌を打つ。
おそらく川端の真意は、「僕のようなのが日本文学の代表だと思われると、これは困る」、「僕はこれから書くとしたら、西洋人にもっと分かりにくいものを書くと思います」という番組終盤での発言にあったと思われる。自身の文学に「日本文学」という衣を被されることを迷惑がる様子が見え隠れしている。伊藤と三島は、「川端さんが一番にわかりにくいわけです。日本文学のなかで。(中略)その分かりにくい川端さんが受け入れられることがですね、分かりやすい人が受け入れられるのと違った意味がある」と、受賞は川端の創作を規定したり束縛したりするものではないと懸命にフォローするものの、川端の真意をとらえ切れてはいない。
その二か月後、スウェーデン・アカデミーでの記念講演「美しい日本の私-その序説」で日本の文化・伝統・美について講じた川端は、その系譜の上に自身の文学を位置づけ、自身にしばしば冠せられる「虚無」の内実を説明した。講演を番組と結び付ければ、講演は伊藤と三島の期待にこたえる内容であり、日本的な美と伝統の世界を明治以降の「文壇」が共有し継承し練磨してきたとする文壇論として解することもできる。川端のノーベル文学賞受賞は、まさに日本の「文壇」がもっとも輝いた瞬間でもあった。
しかし、それから約25年後、1994年に大江健三郎がノーベル文学賞を受賞した際の記念講演「あいまいな日本の私」は、大江がすでに日本や「文壇」といった枠内で仕事をしていないことを物語っている。少なくとも1994年の時点で、「文壇」はその役割を終え、衰退し、あるいは終焉を迎えていたのかもしれない。
▶︎川端と伊藤が向き合った「文壇」
さて、番組の翌年中旬に末期の胃がんが発見された伊藤は(本人には告知されず)11月15日に没した。19日には日本近代文学館・日本文芸家協会・日本ペンクラブによる合同葬が青山斎場で執り行われ、川端が葬儀委員長が務めた。葬儀での川端の挨拶は参列者の心を打ったという。平野謙はその時の川端の言葉を次のように書きとめている。
伊藤整の死によって、作家としての私のある部分も確実に死んでしまった。伊藤整は私の作品を批評しながら、つねに私自身にも未知の部分をひきだし、そのことによって、私の作家的可能性をてらしだしてくれたが、もはやそういうことはなくなってしまった。伊藤整の死とともに、私の残り少ない作家的可能性も死にたえたのである。おそらくこれは私一個の感慨にとどまらず、おおかたの作家のそれでもあるだろう。/口ごもるような語調でのべられたこの川端康成の言葉は、聞くものにふかい印象を残した。(平野謙『昭和文学私論』毎日新聞社、1977)
川端康成と伊藤整。二人の文学者の関係は長く深い。川端の言葉からは、作家としての自分にとって〈半身〉のような存在であった伊藤への深い哀悼の念が伝わってくる。彼らの文学活動は実に多くの場面で接近し離合し重なり合いながら互いの文学を形成した。そして「文壇」の変革期にその片隅で出会った彼らはそこに参入し、モダニズム期・文藝復興期・戦時期・戦後の「文壇」と向き合い、「文壇」をけん引し、そして明治期から連続する場としての「文壇」を作り上げていくことになる。