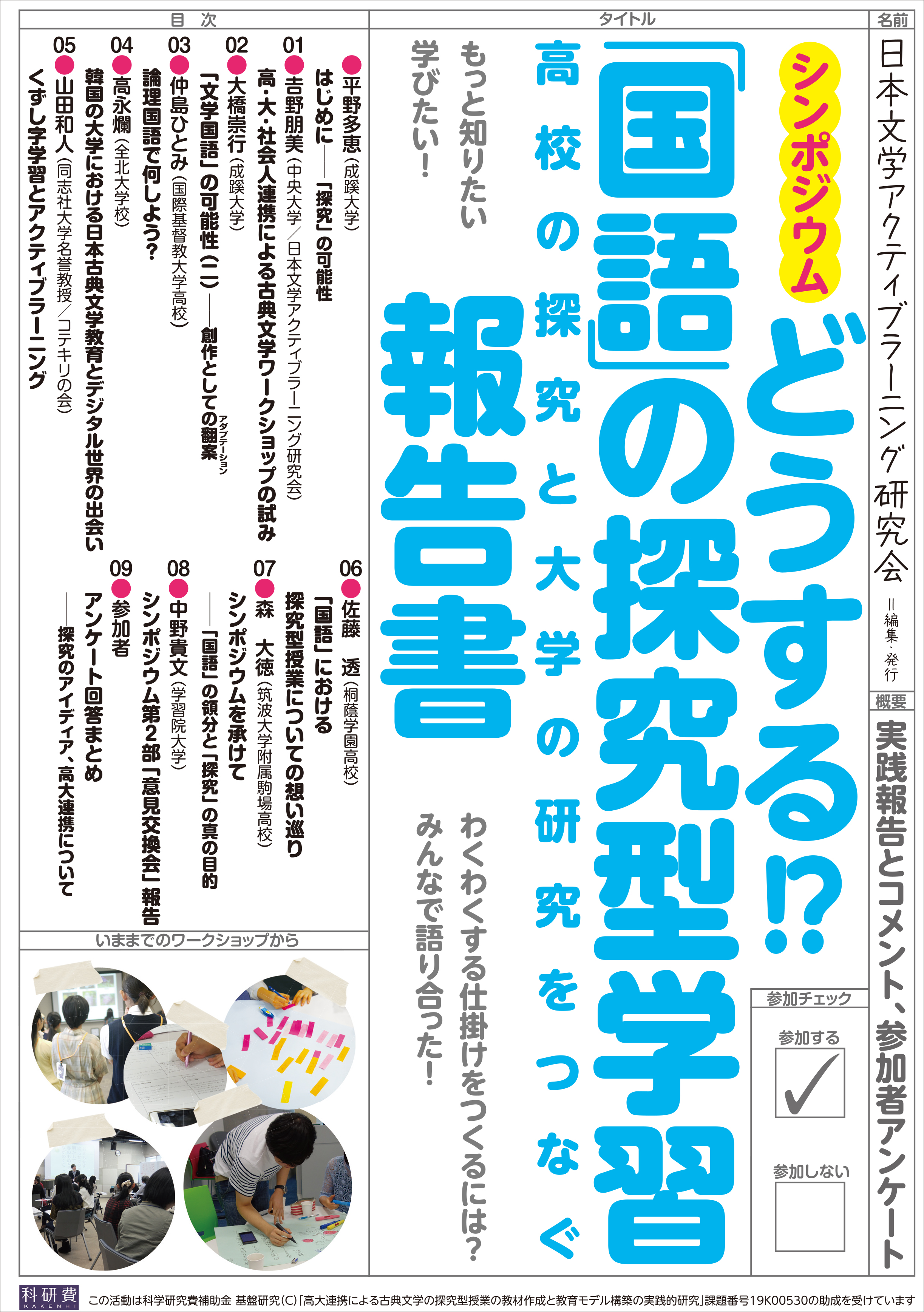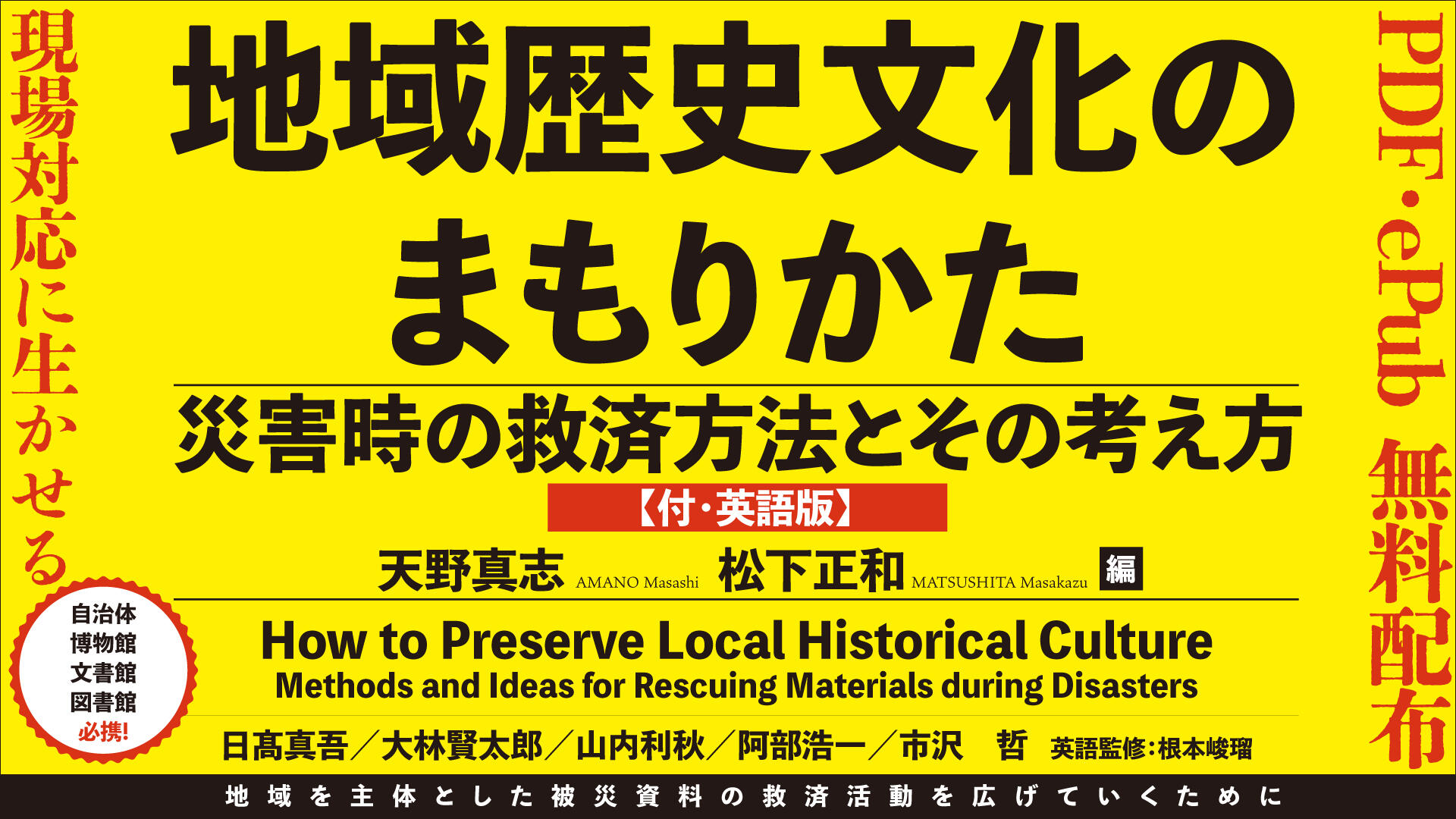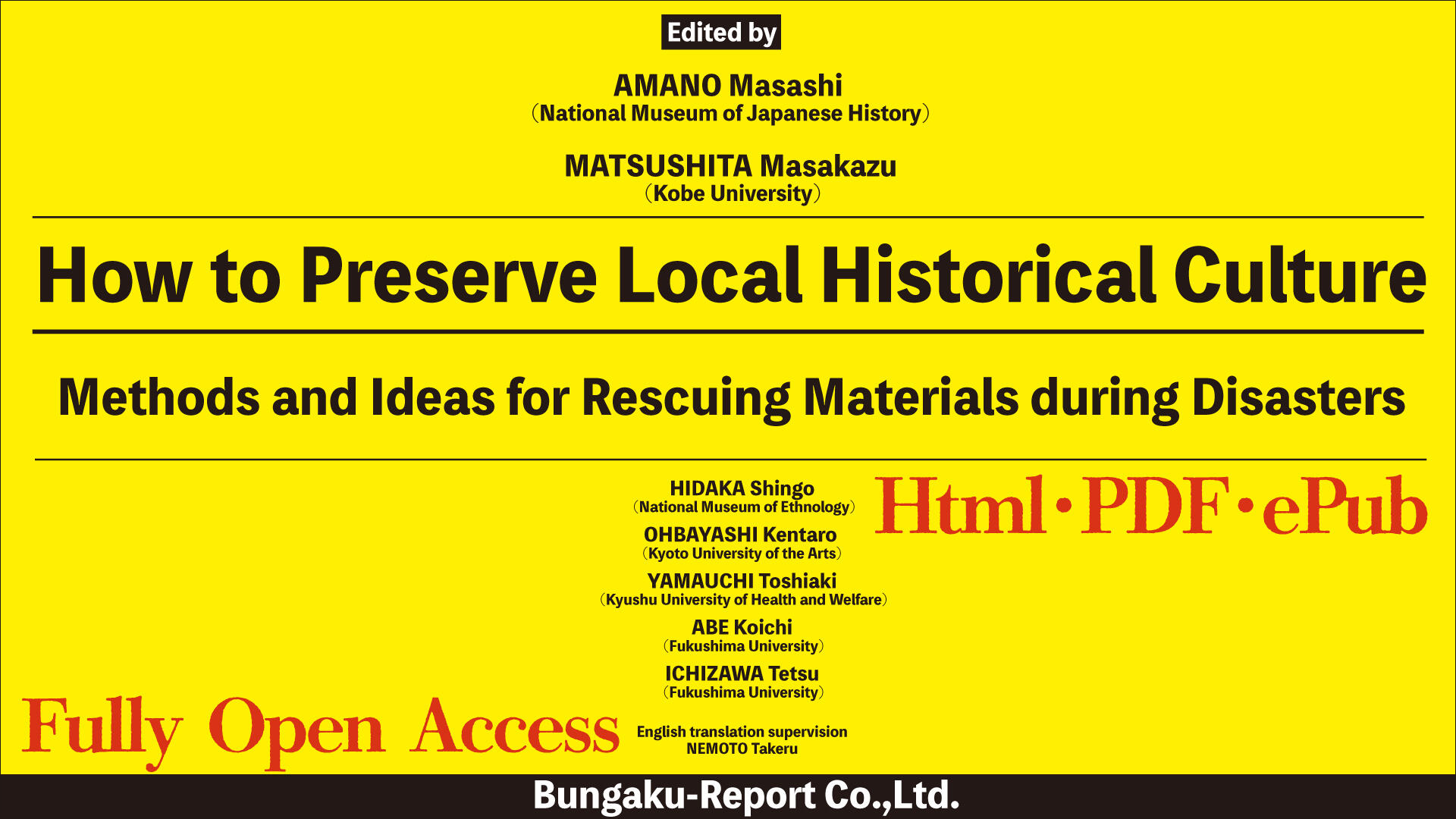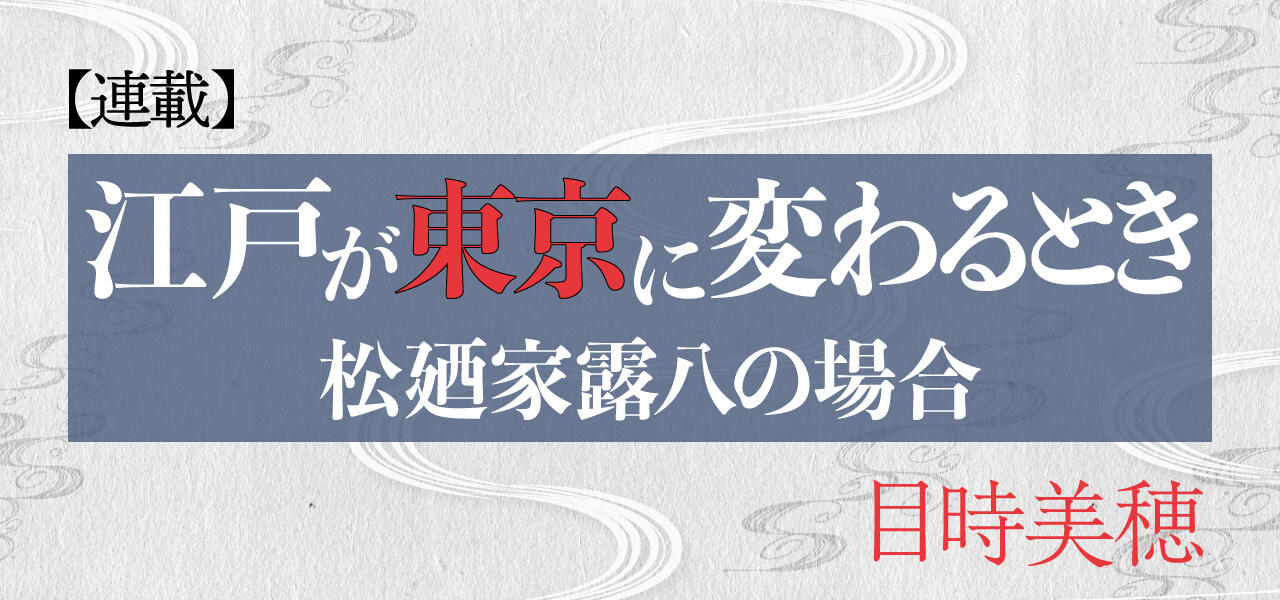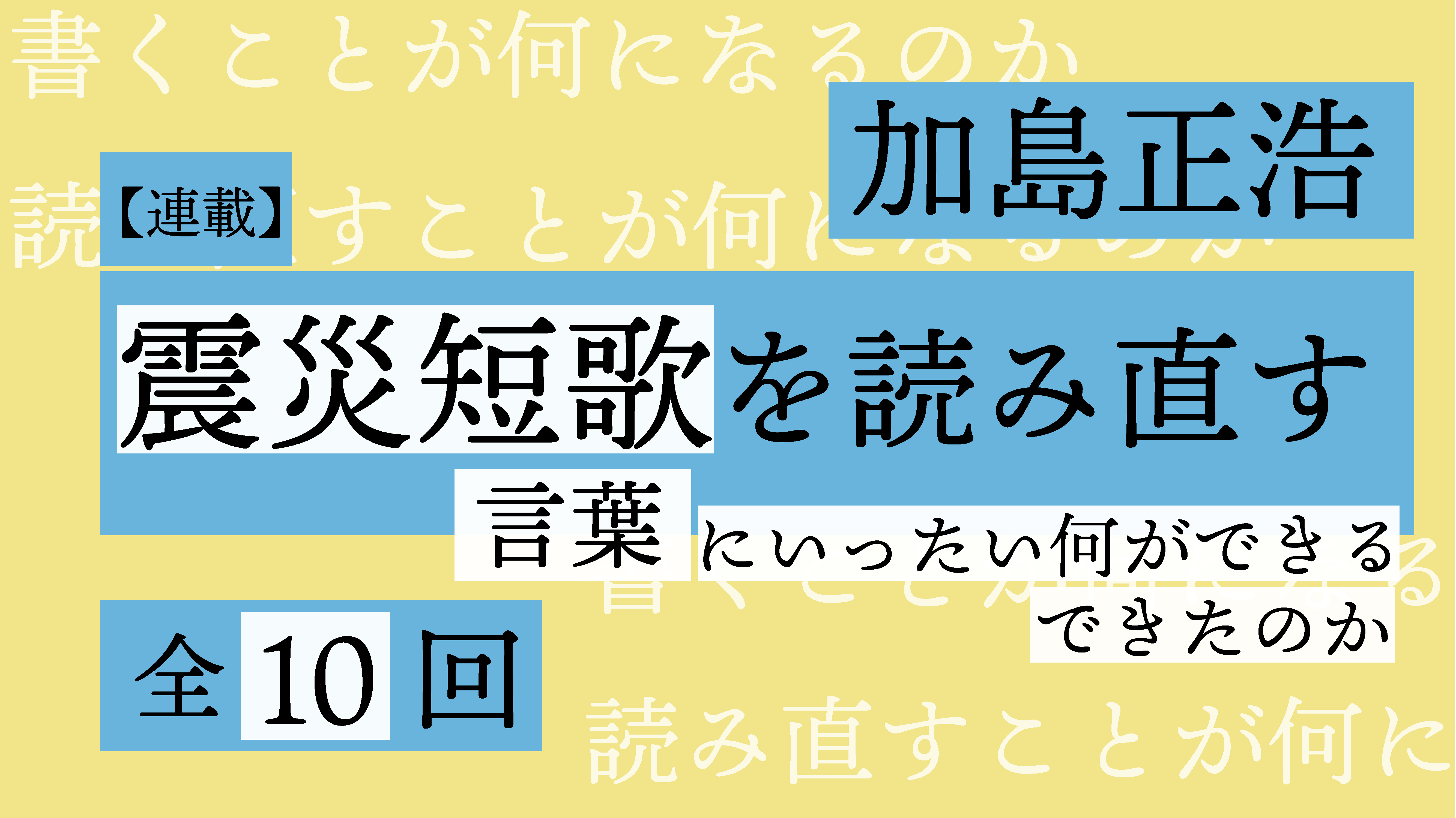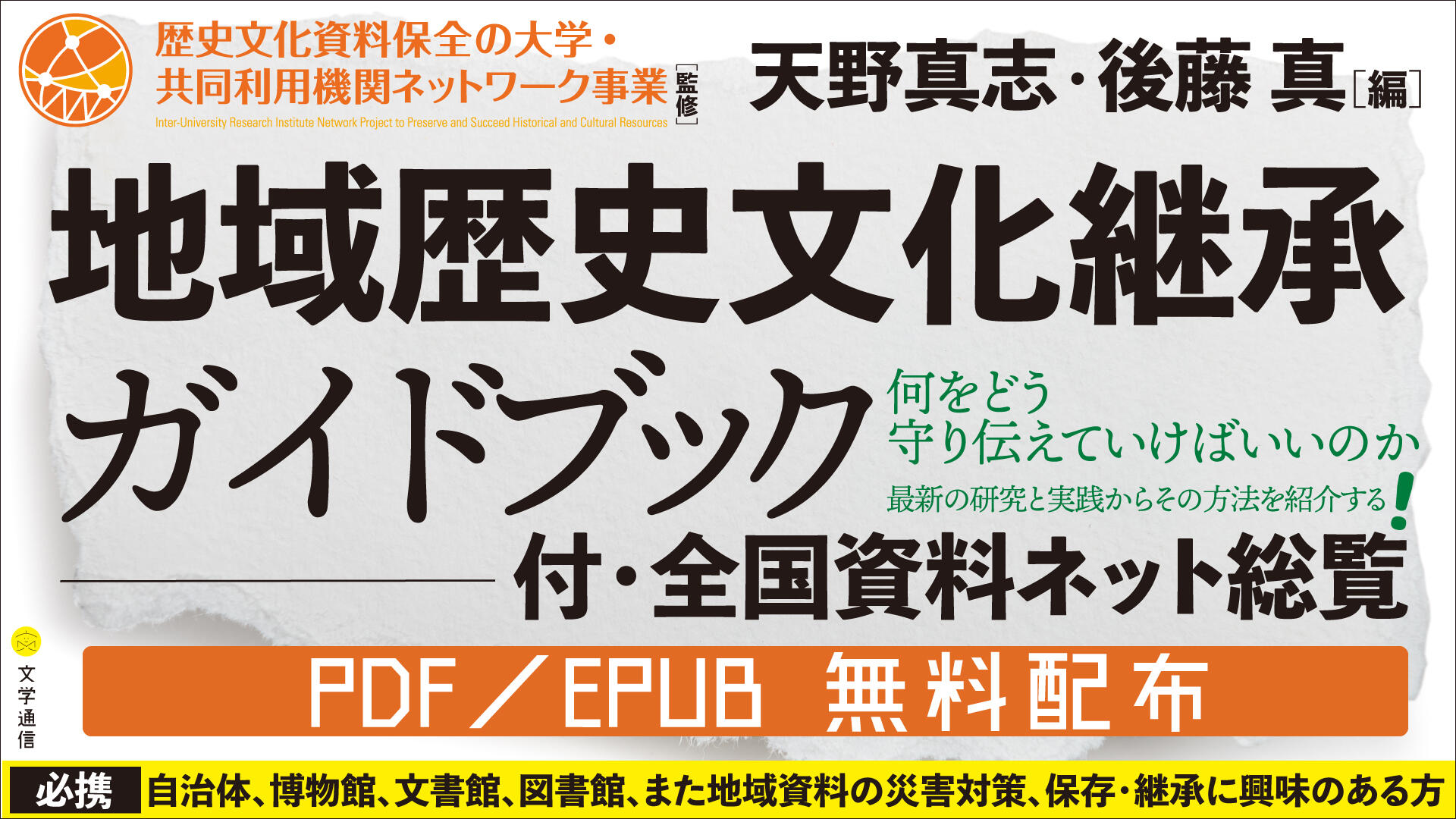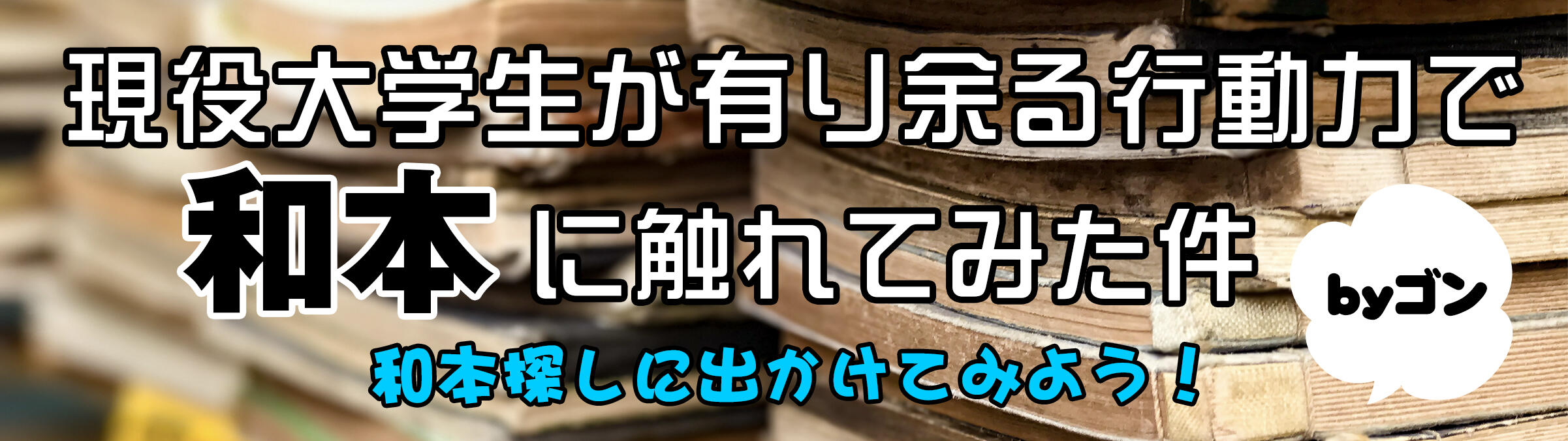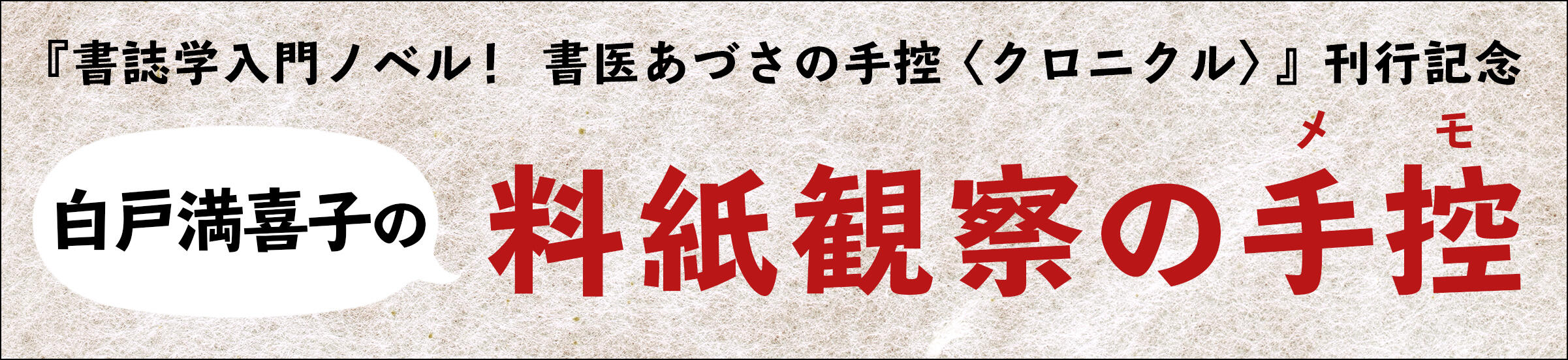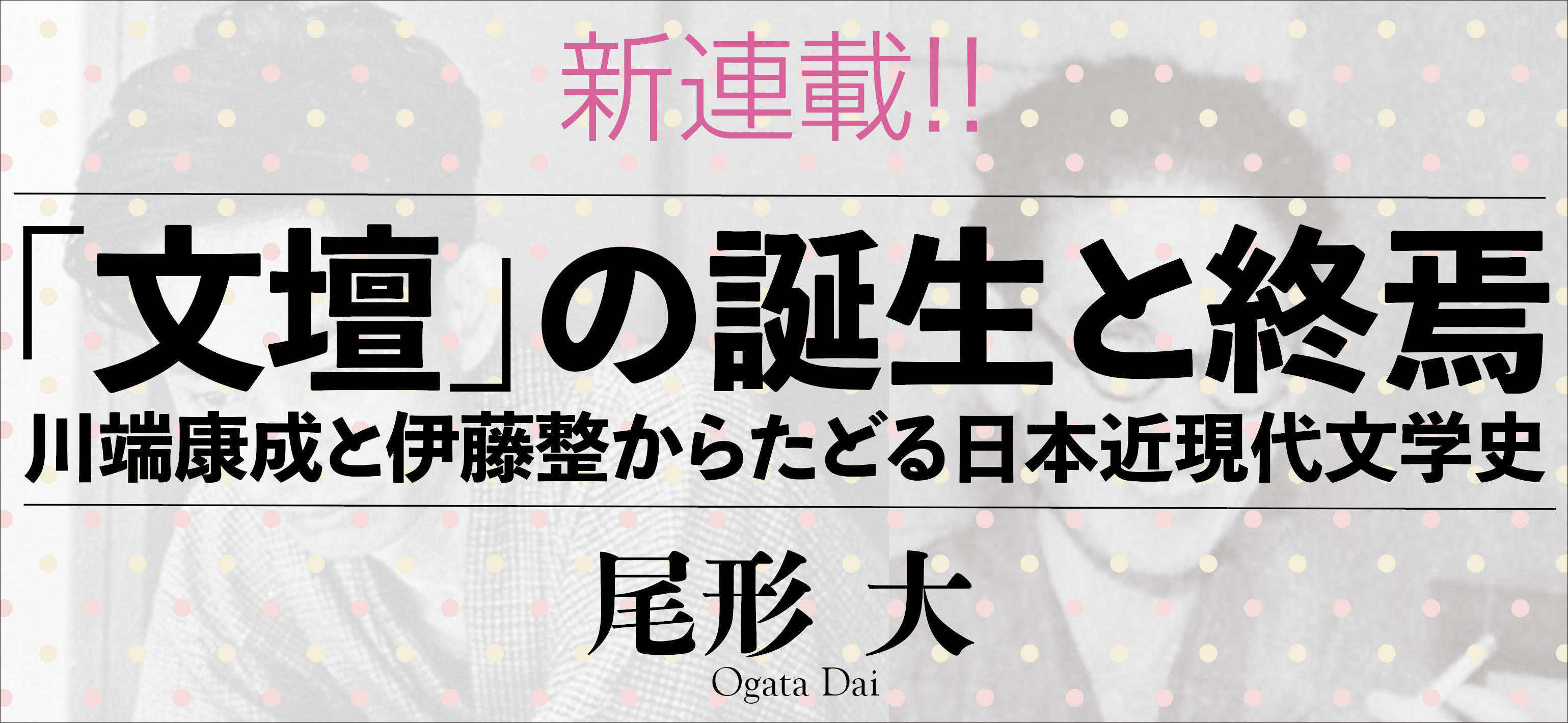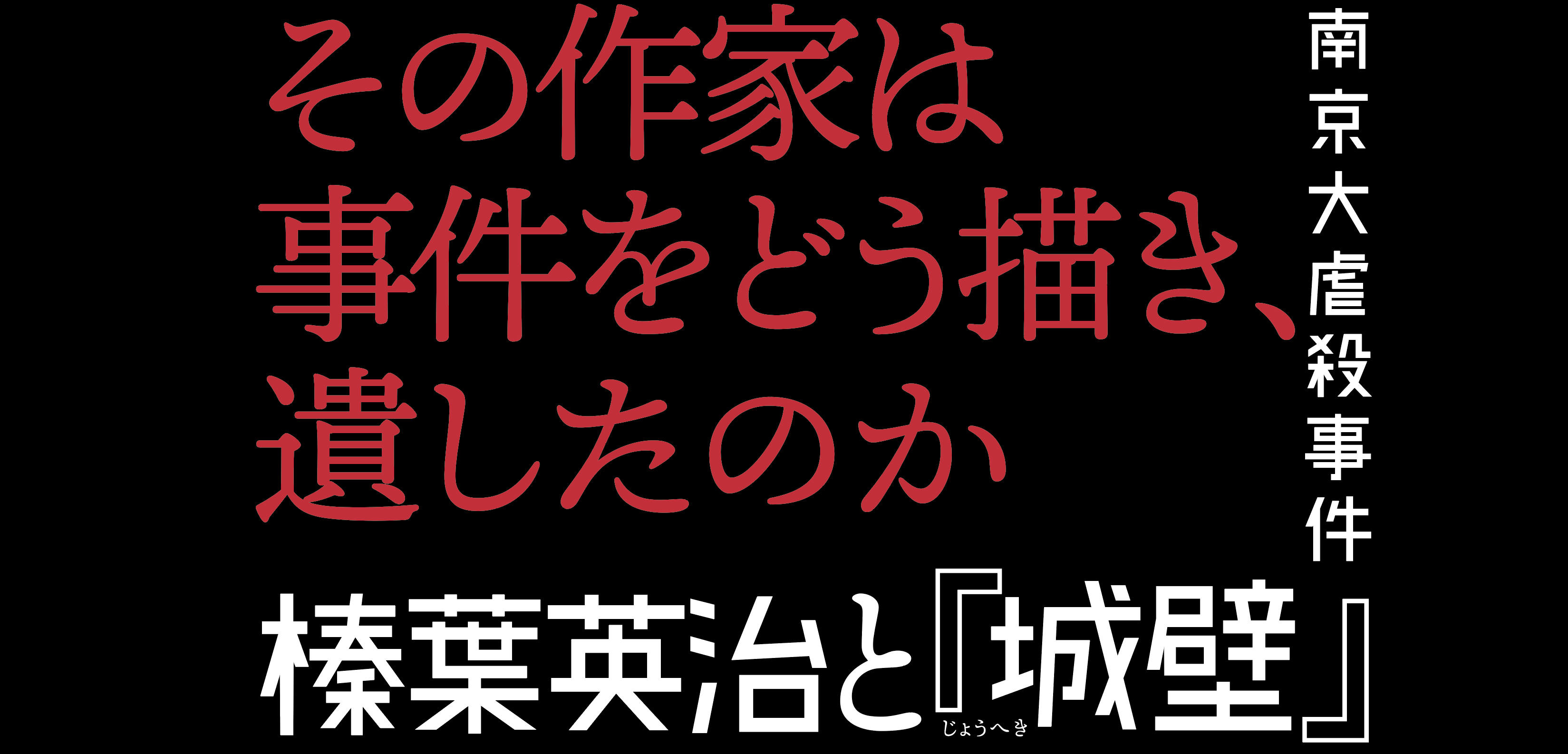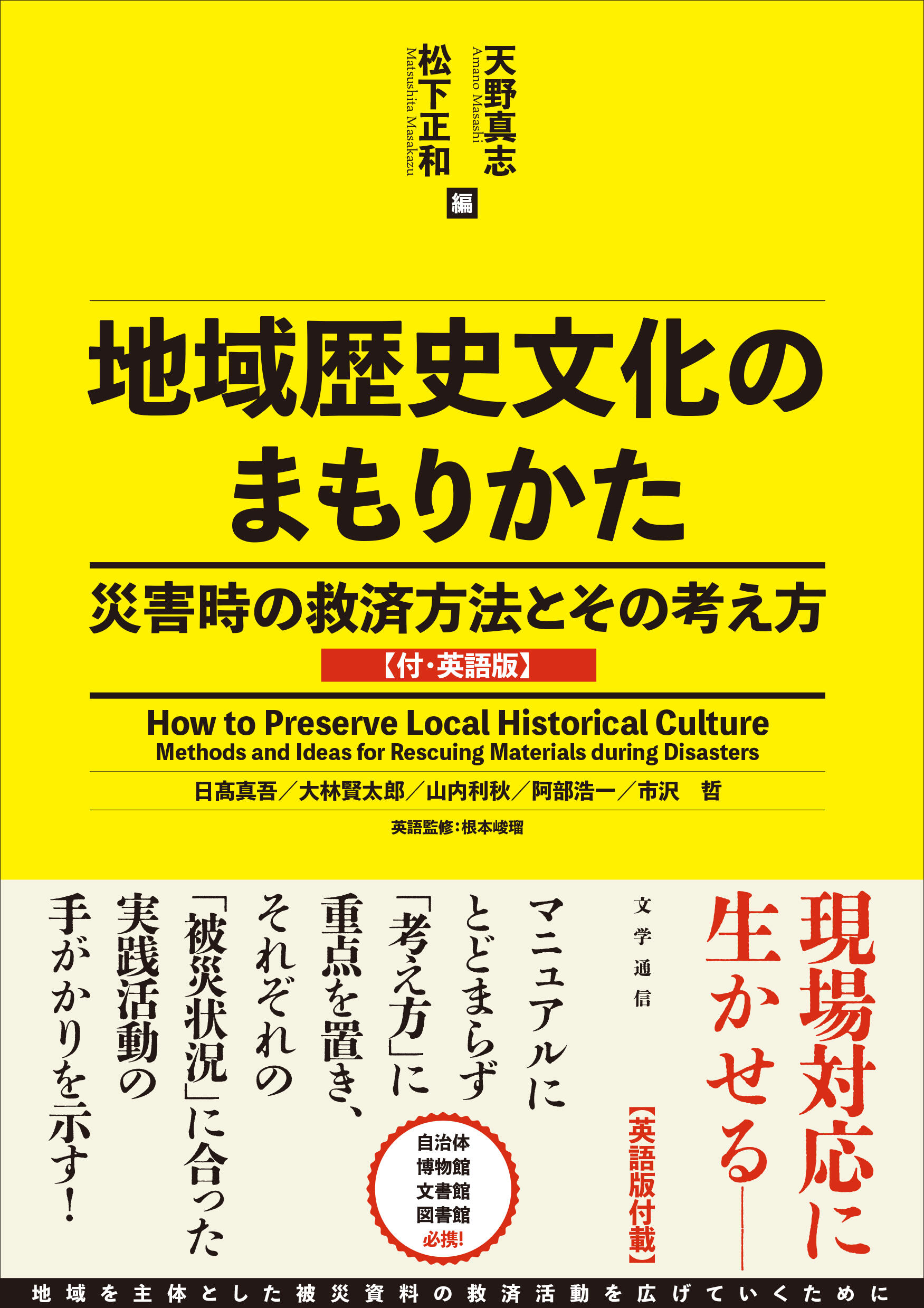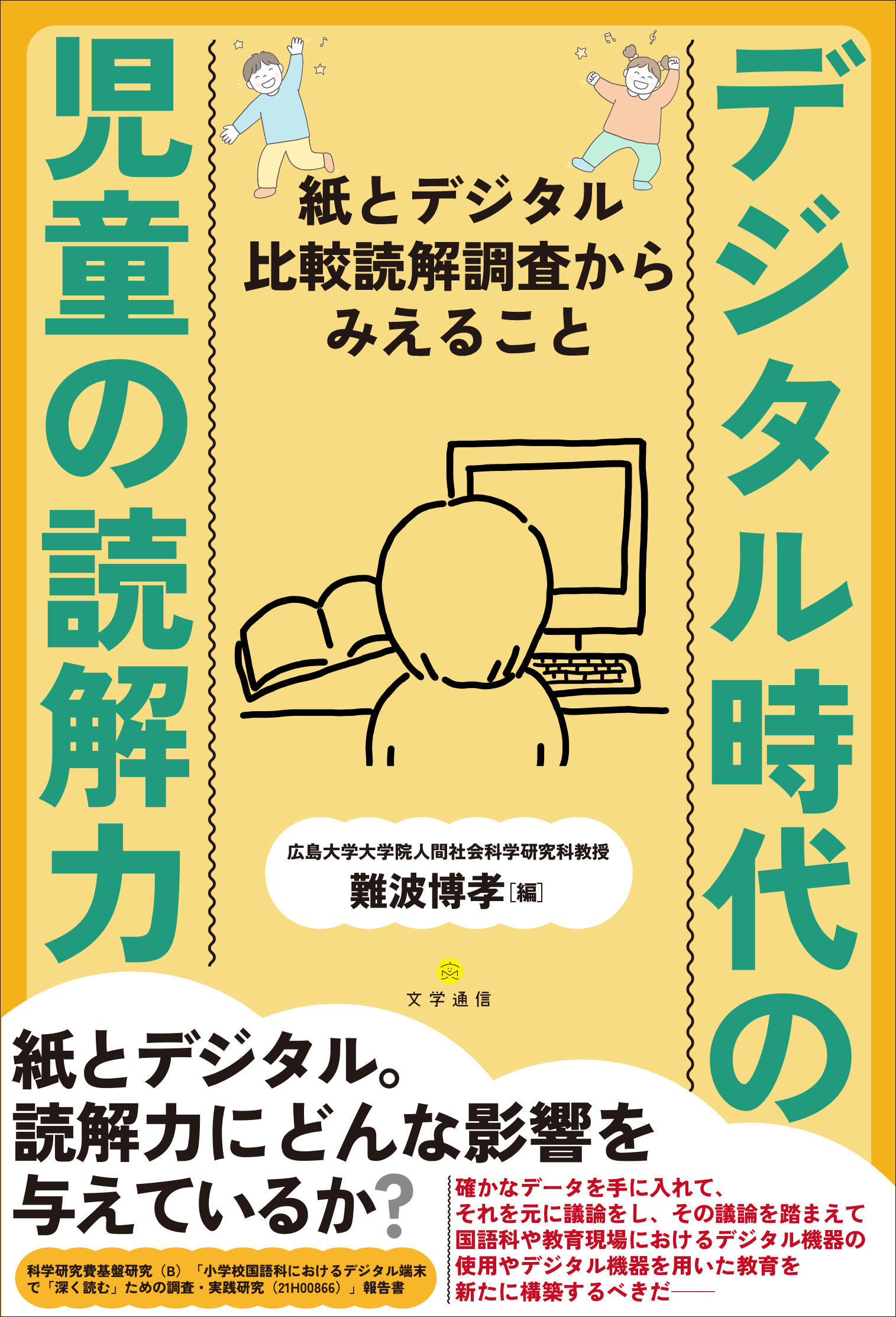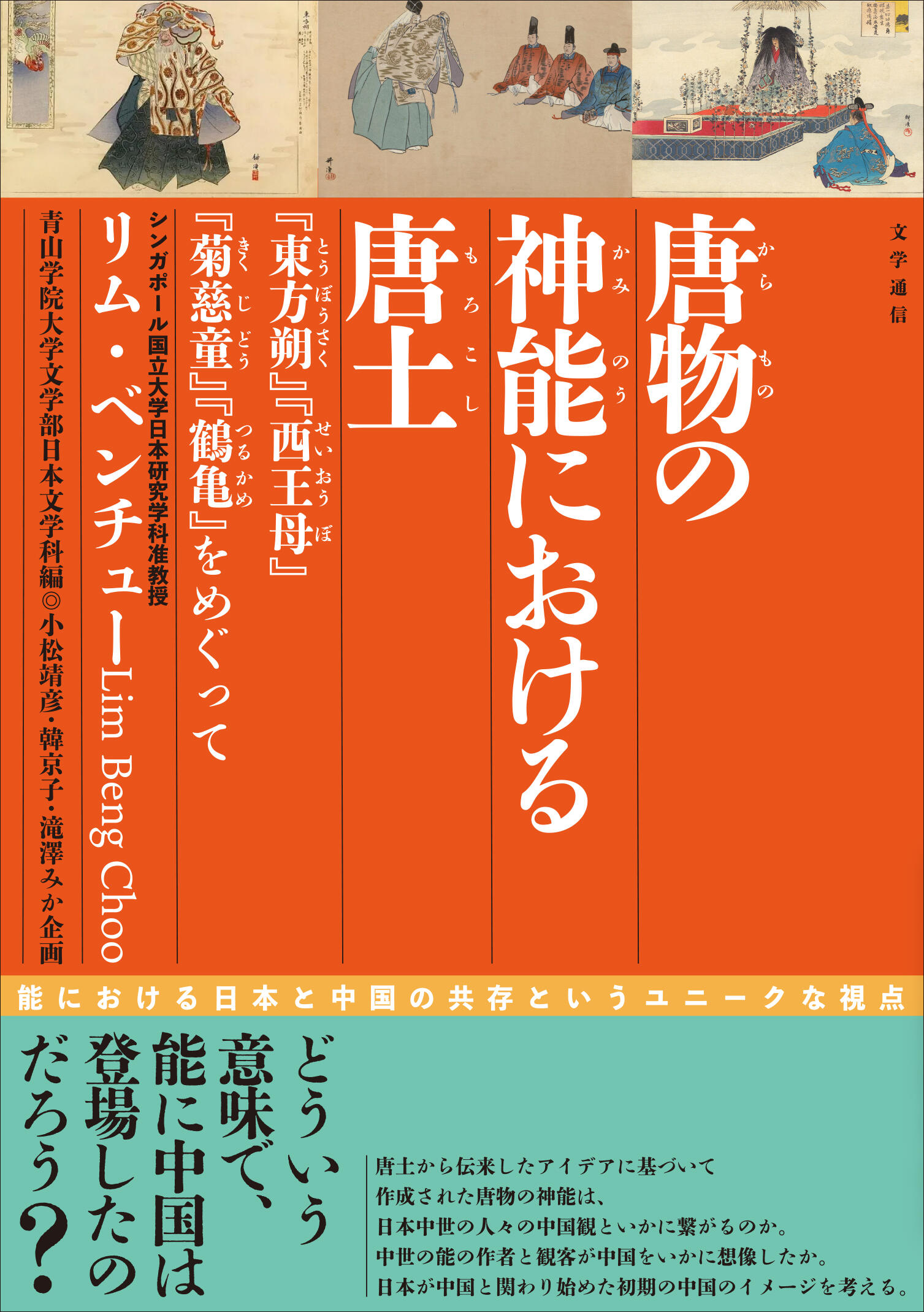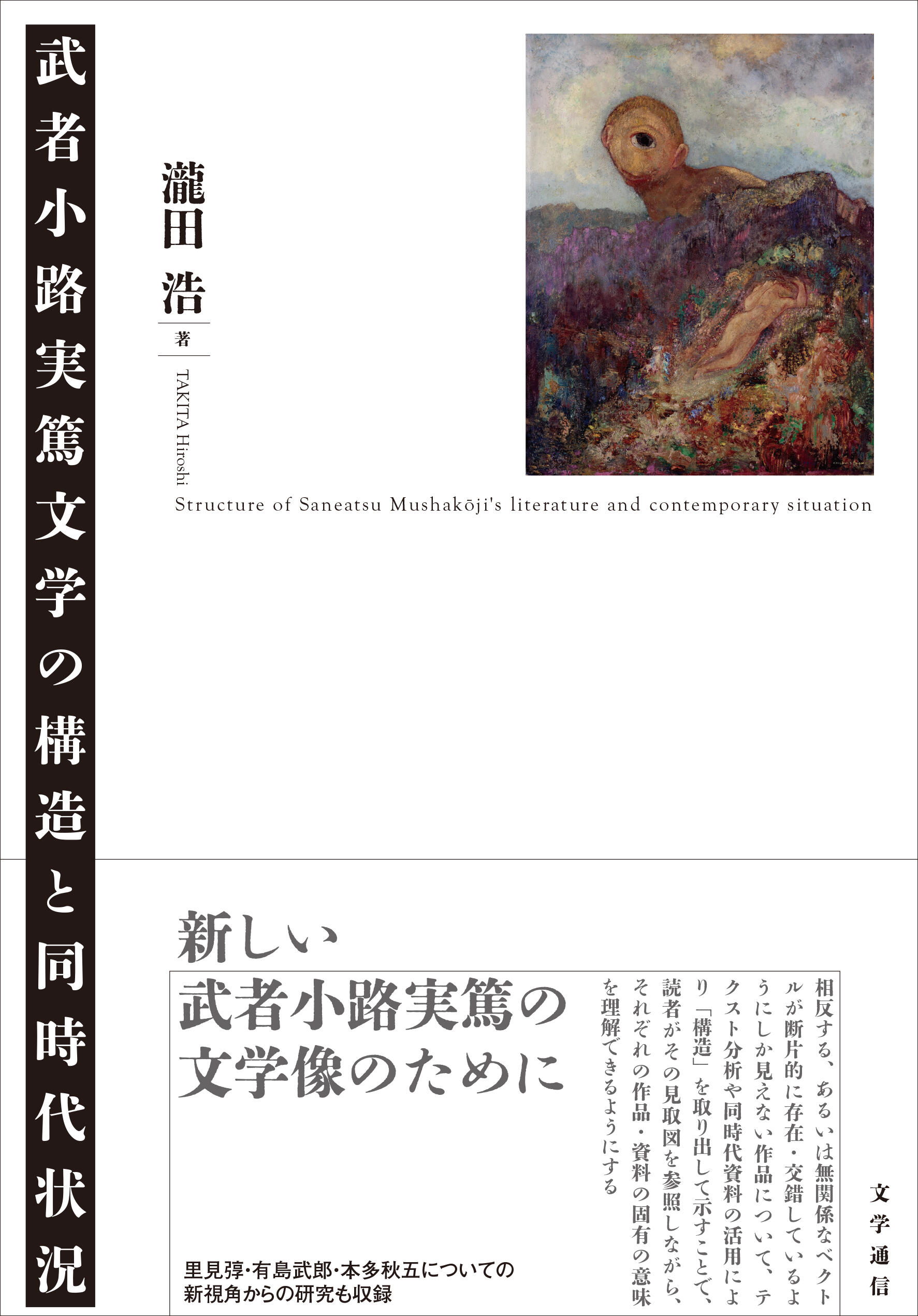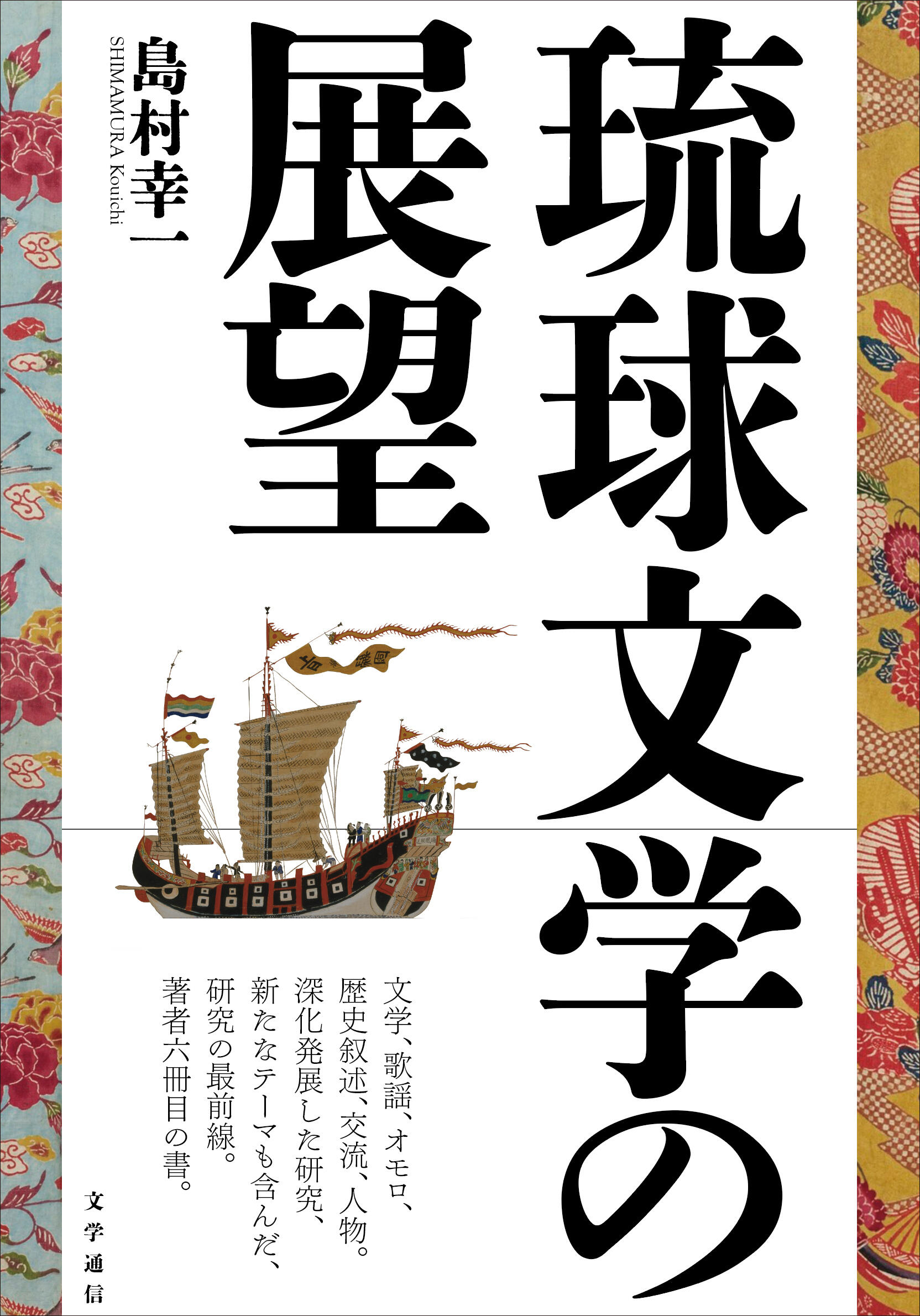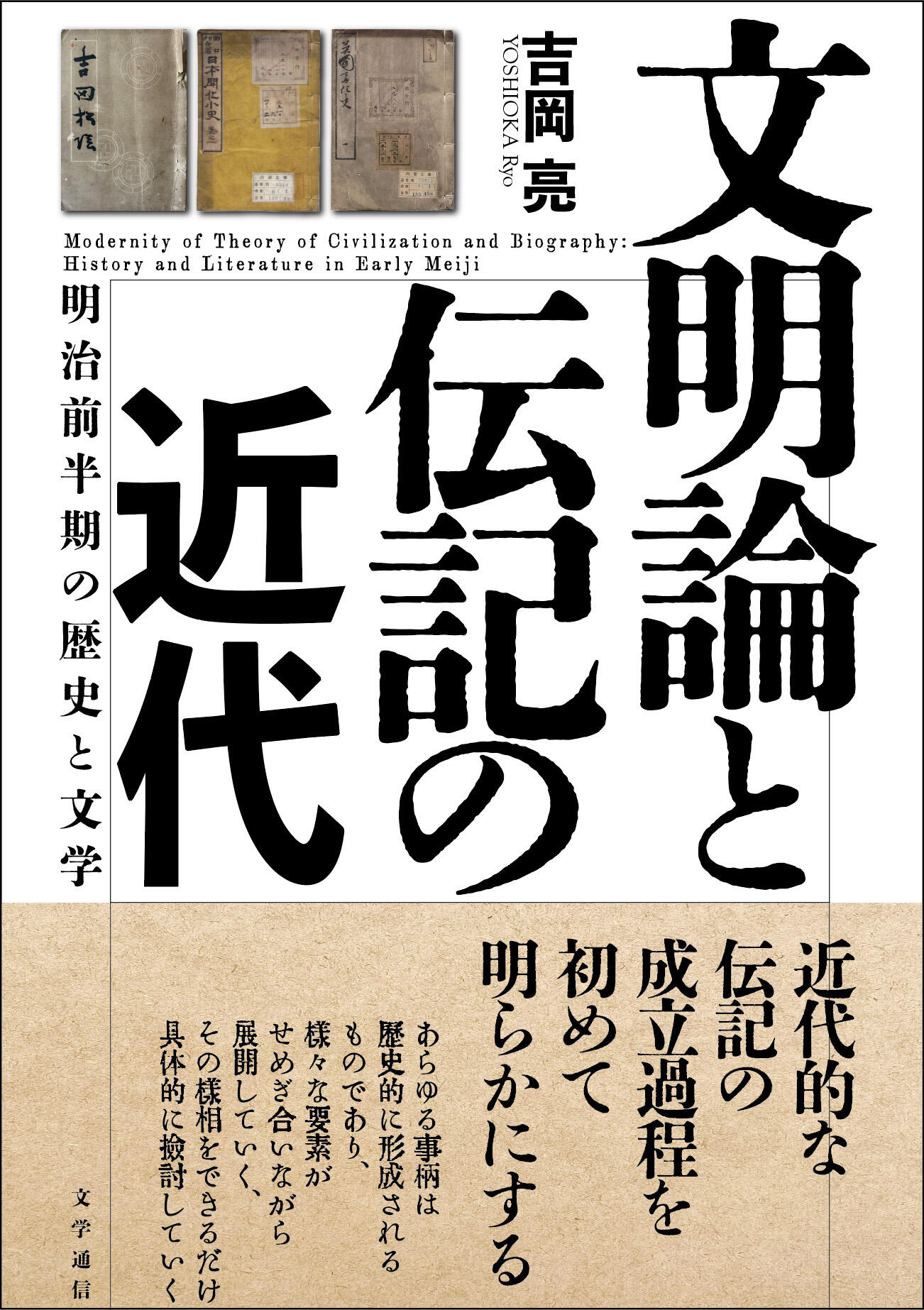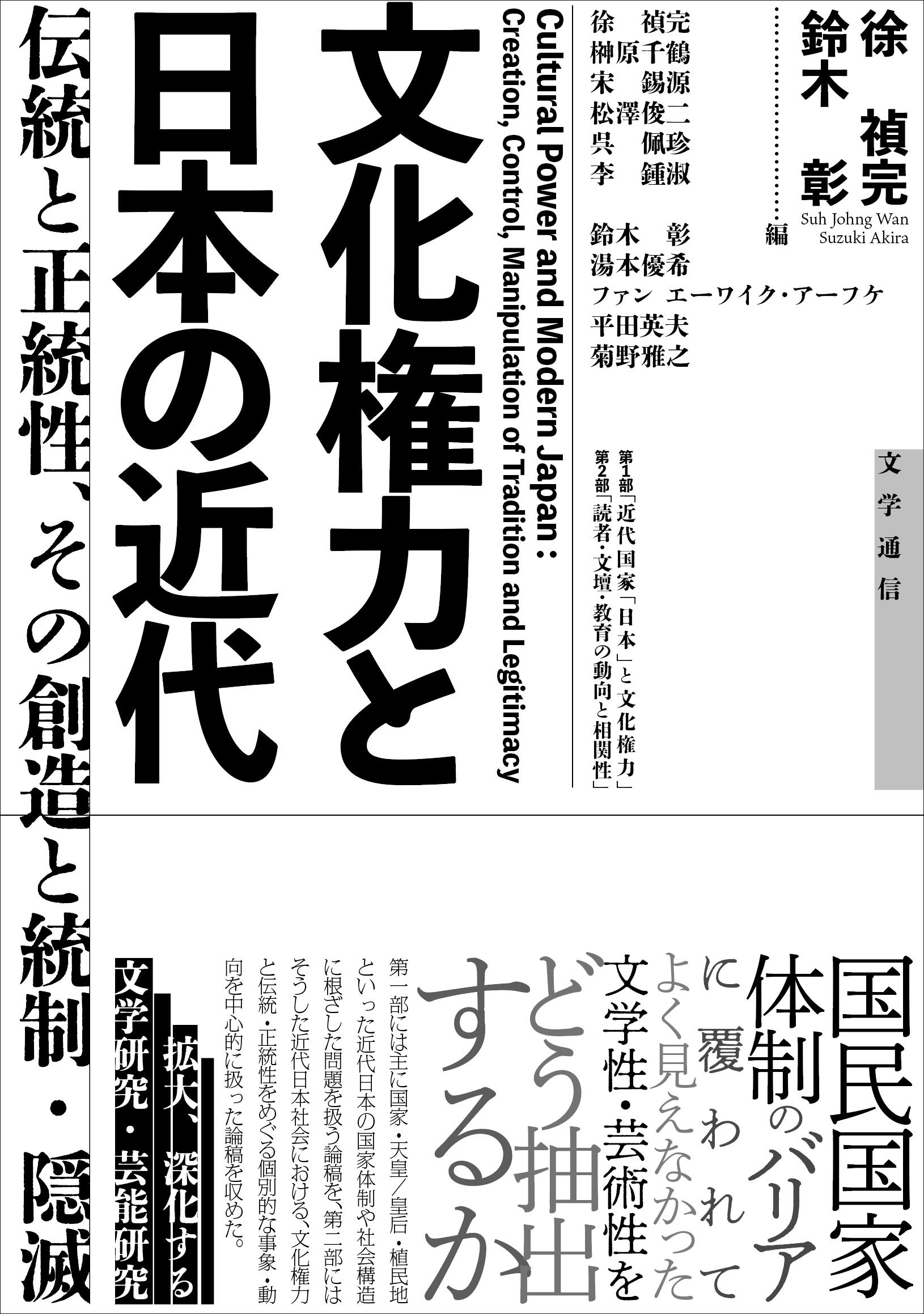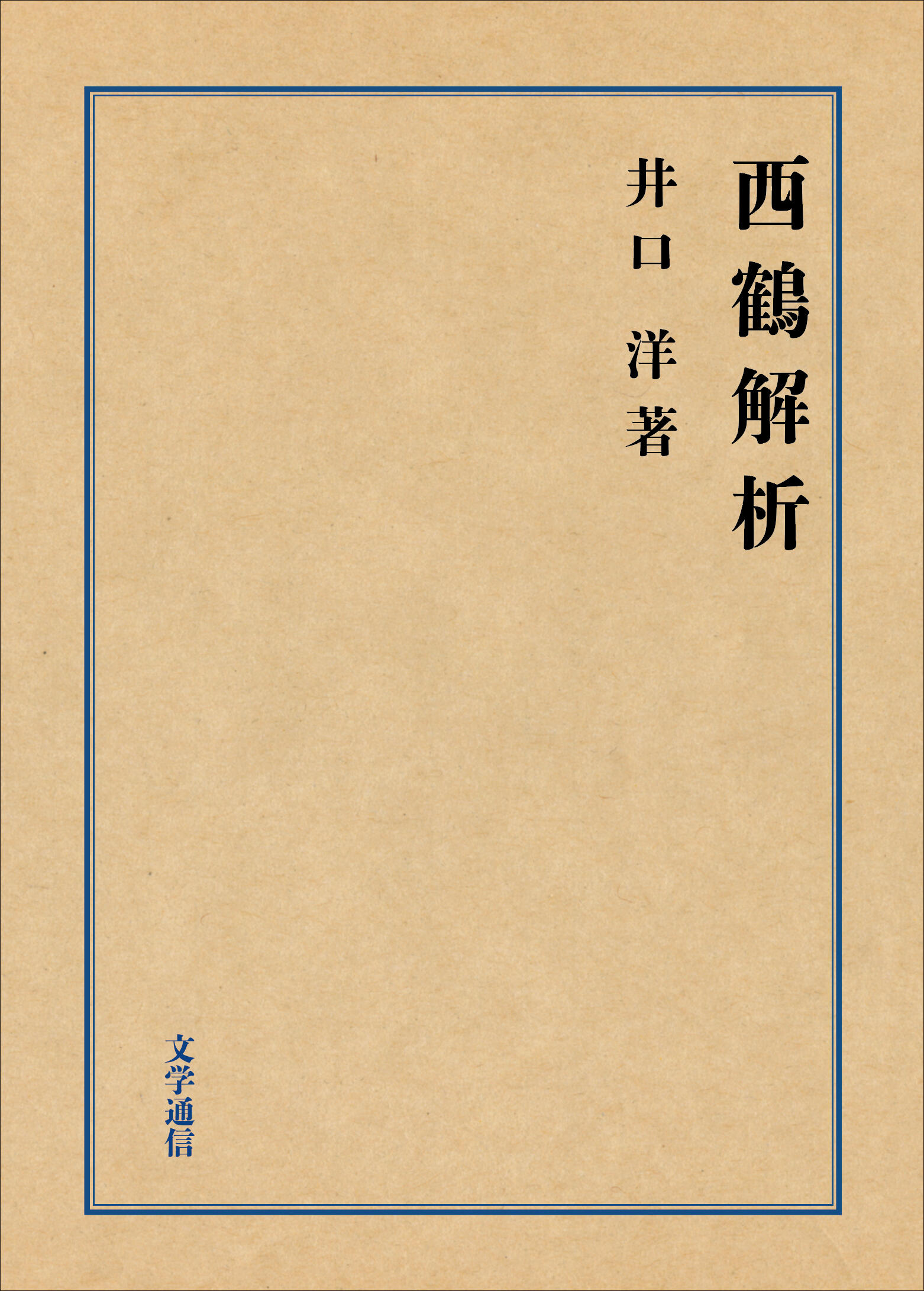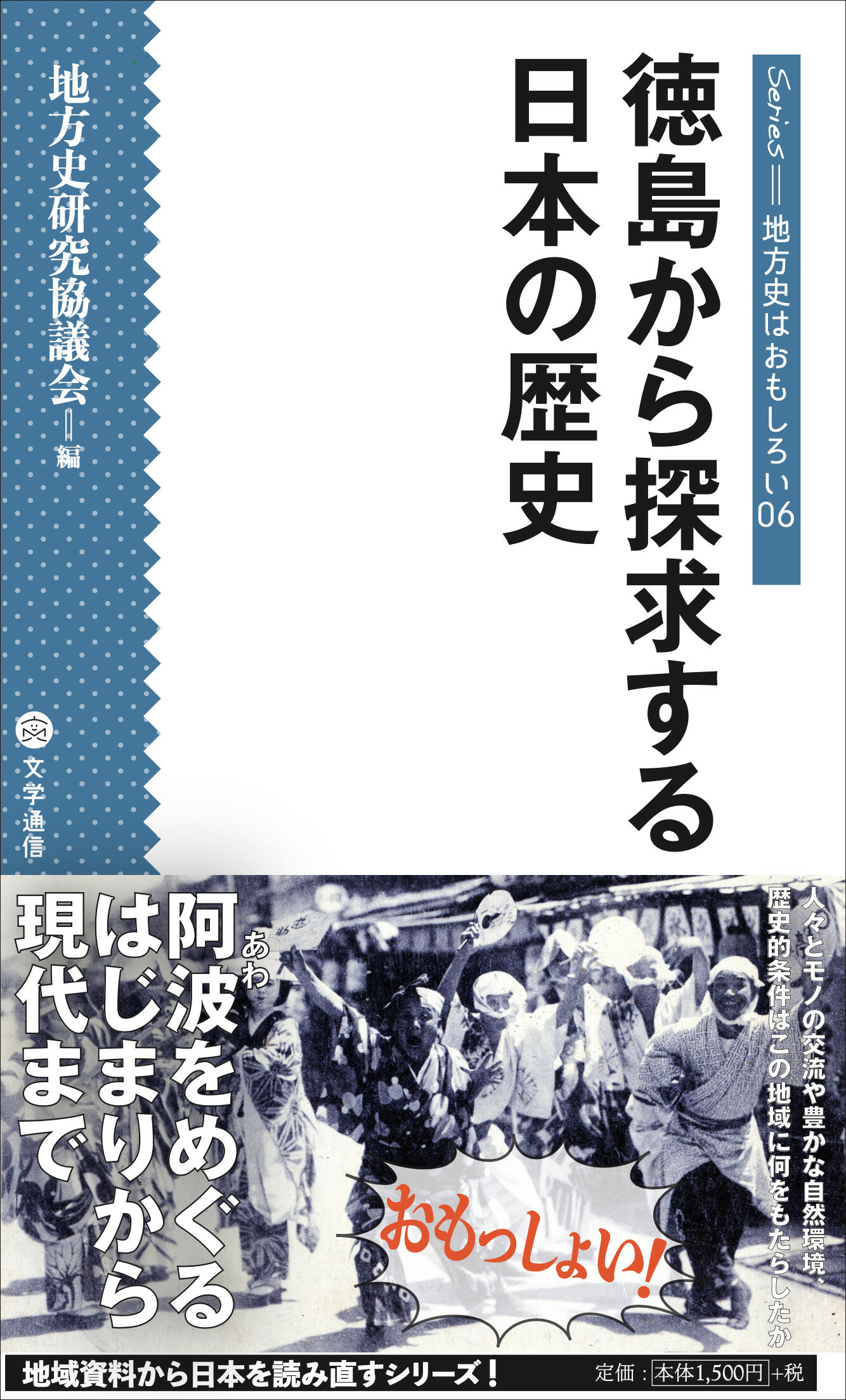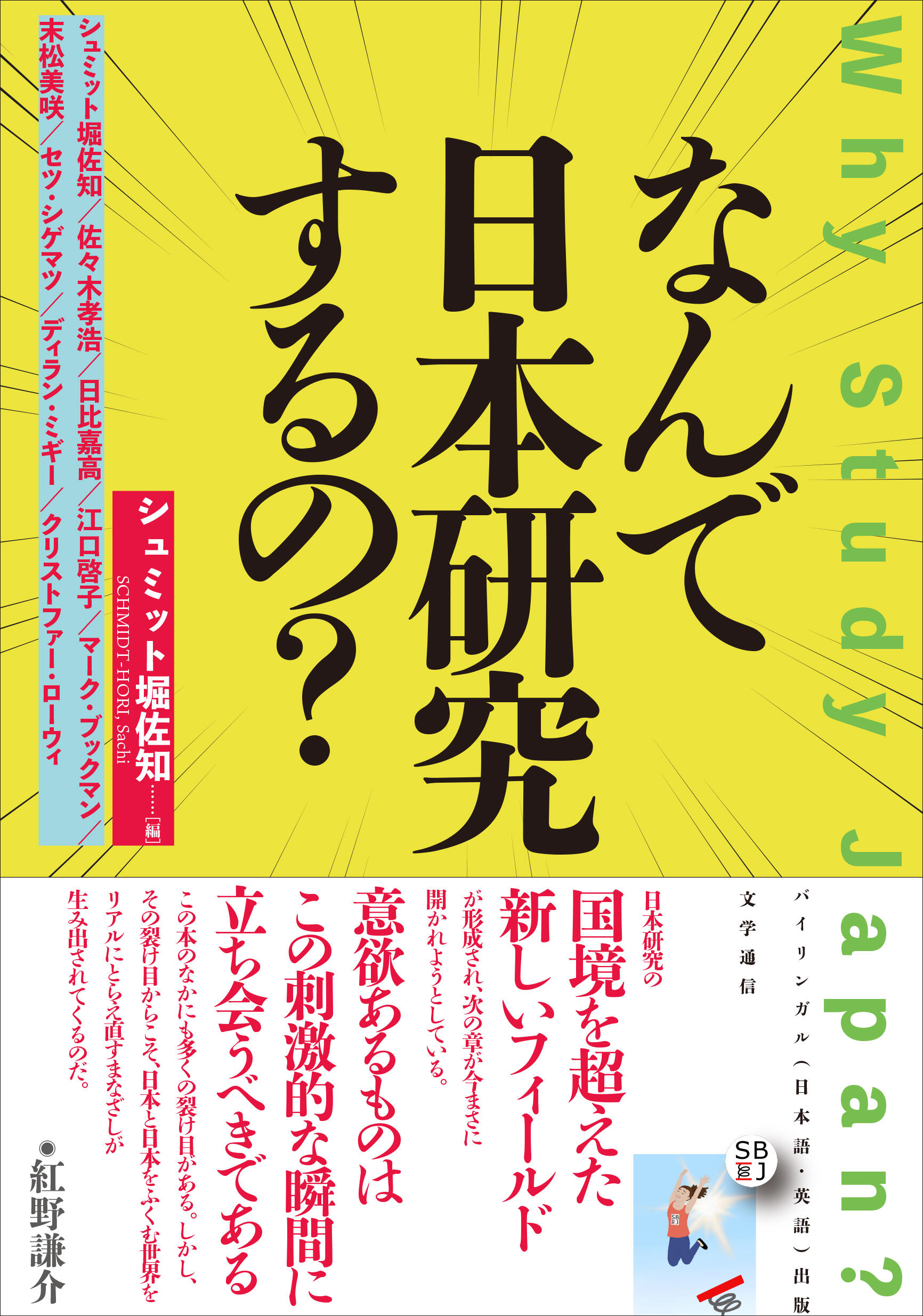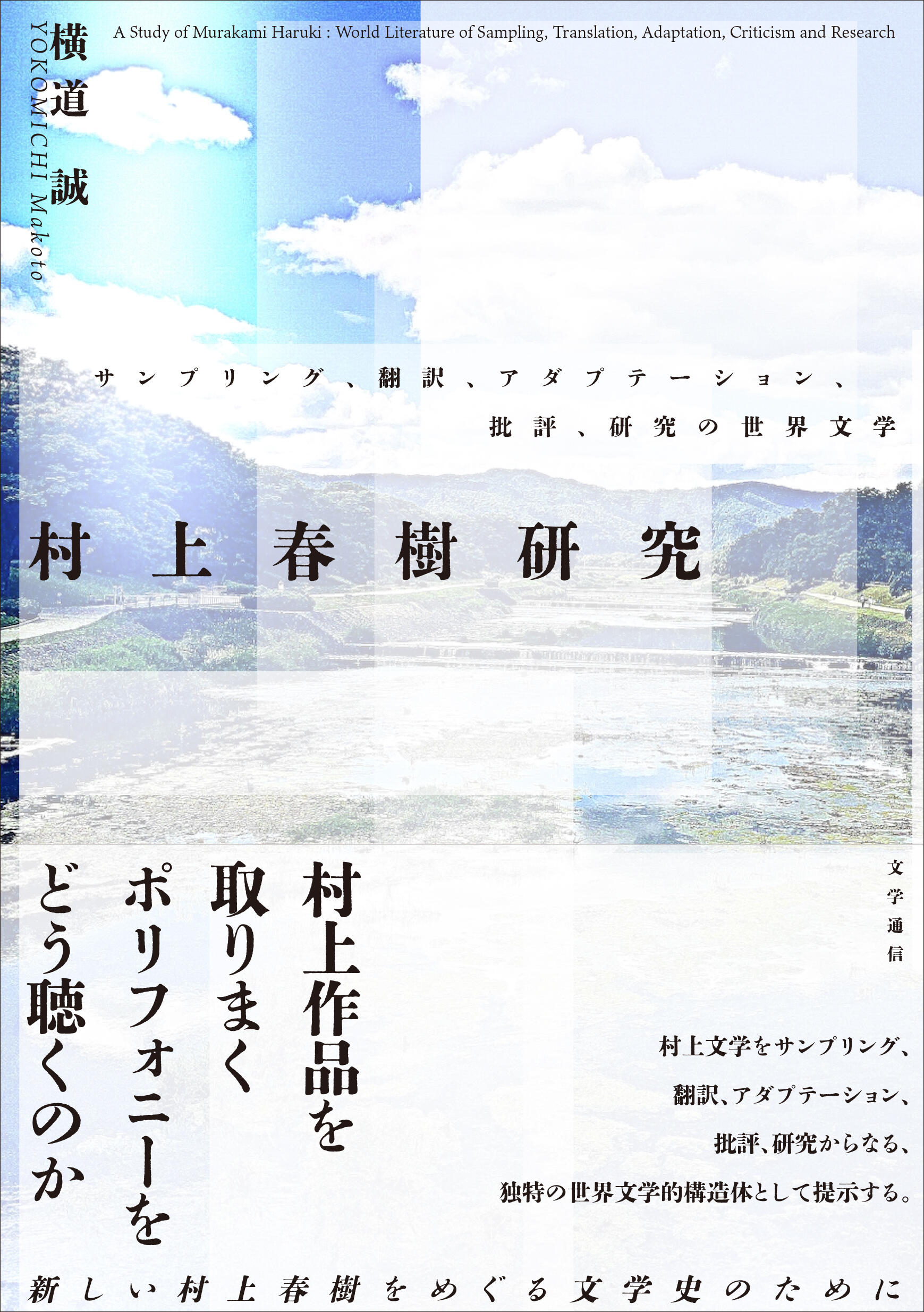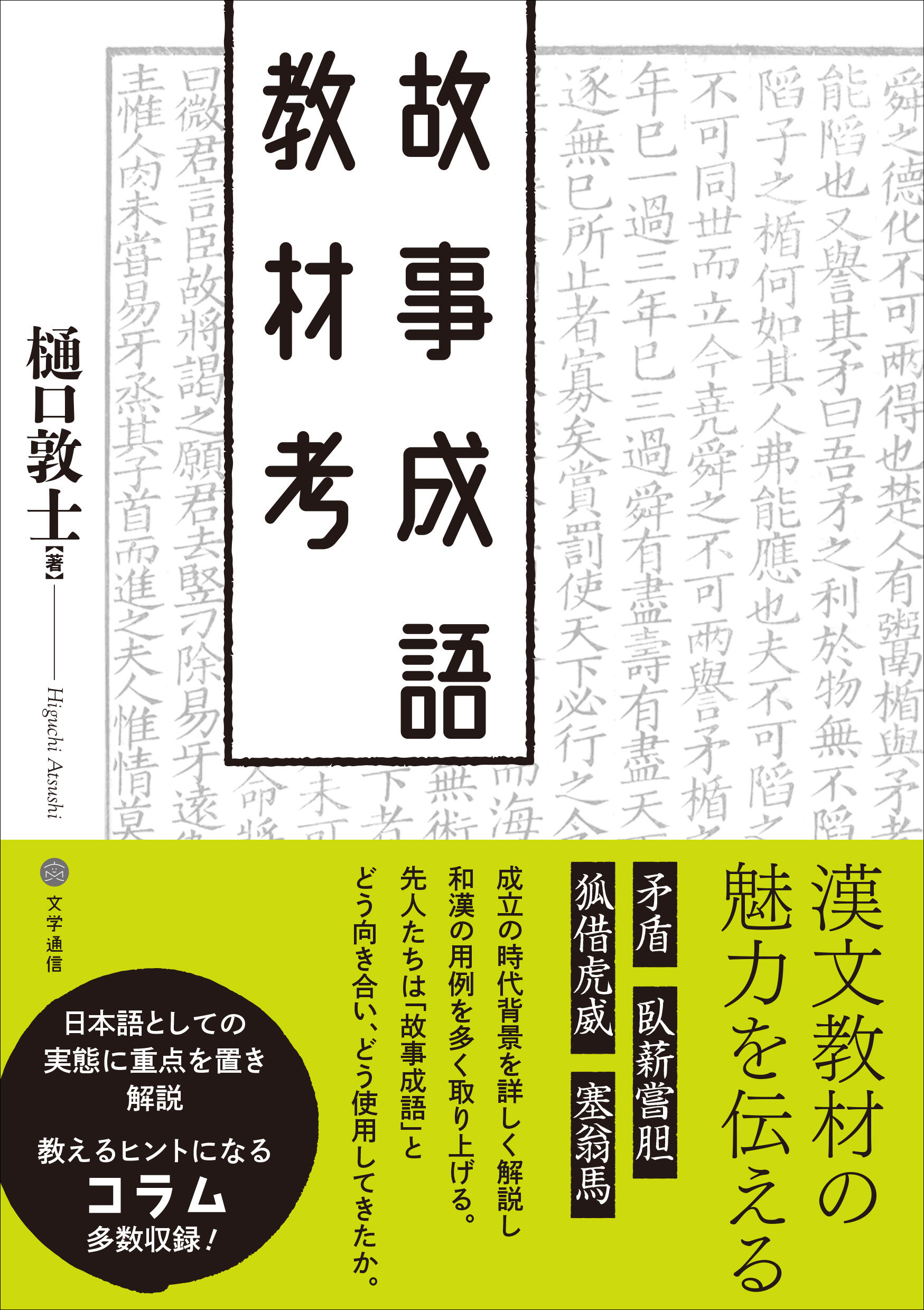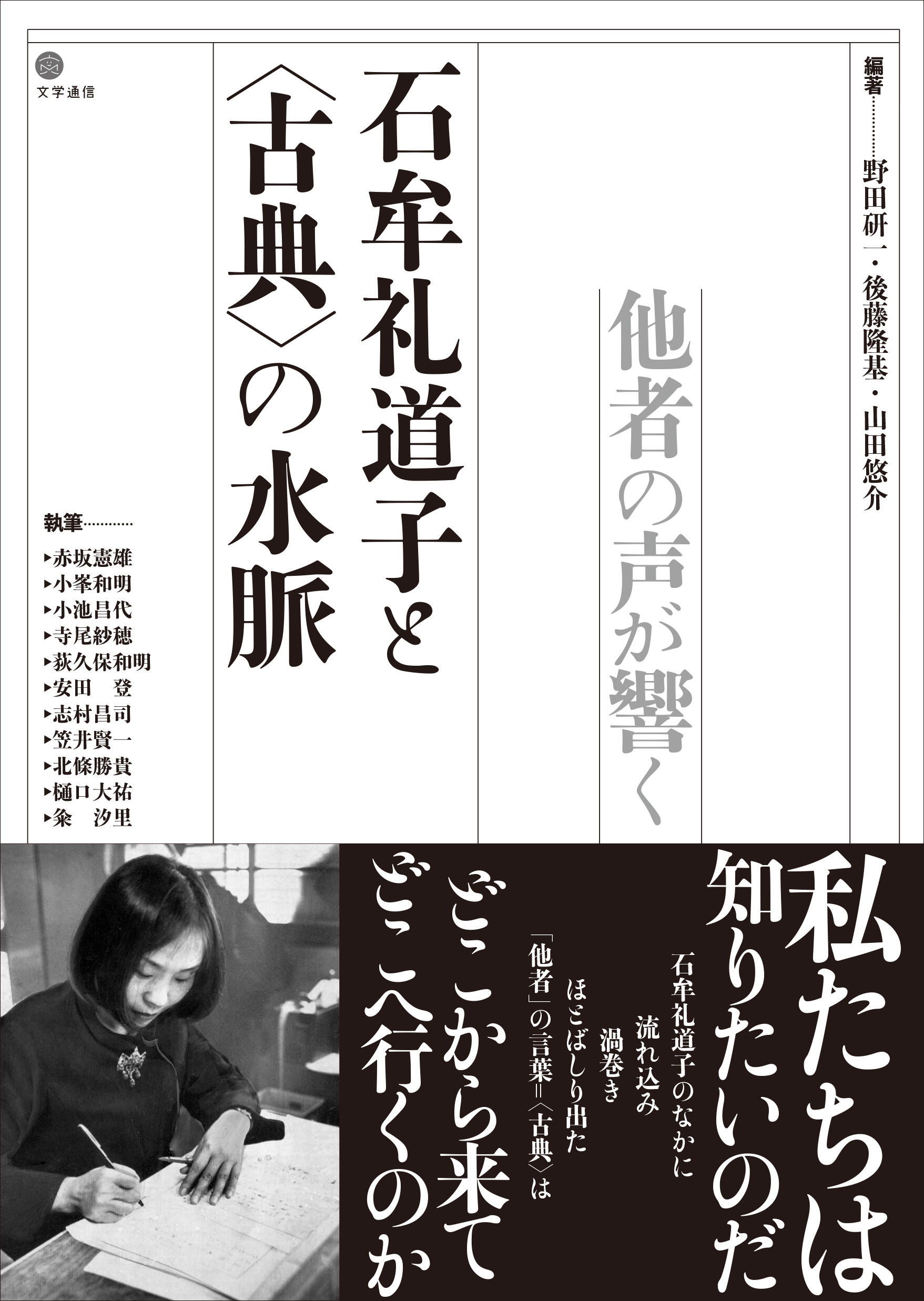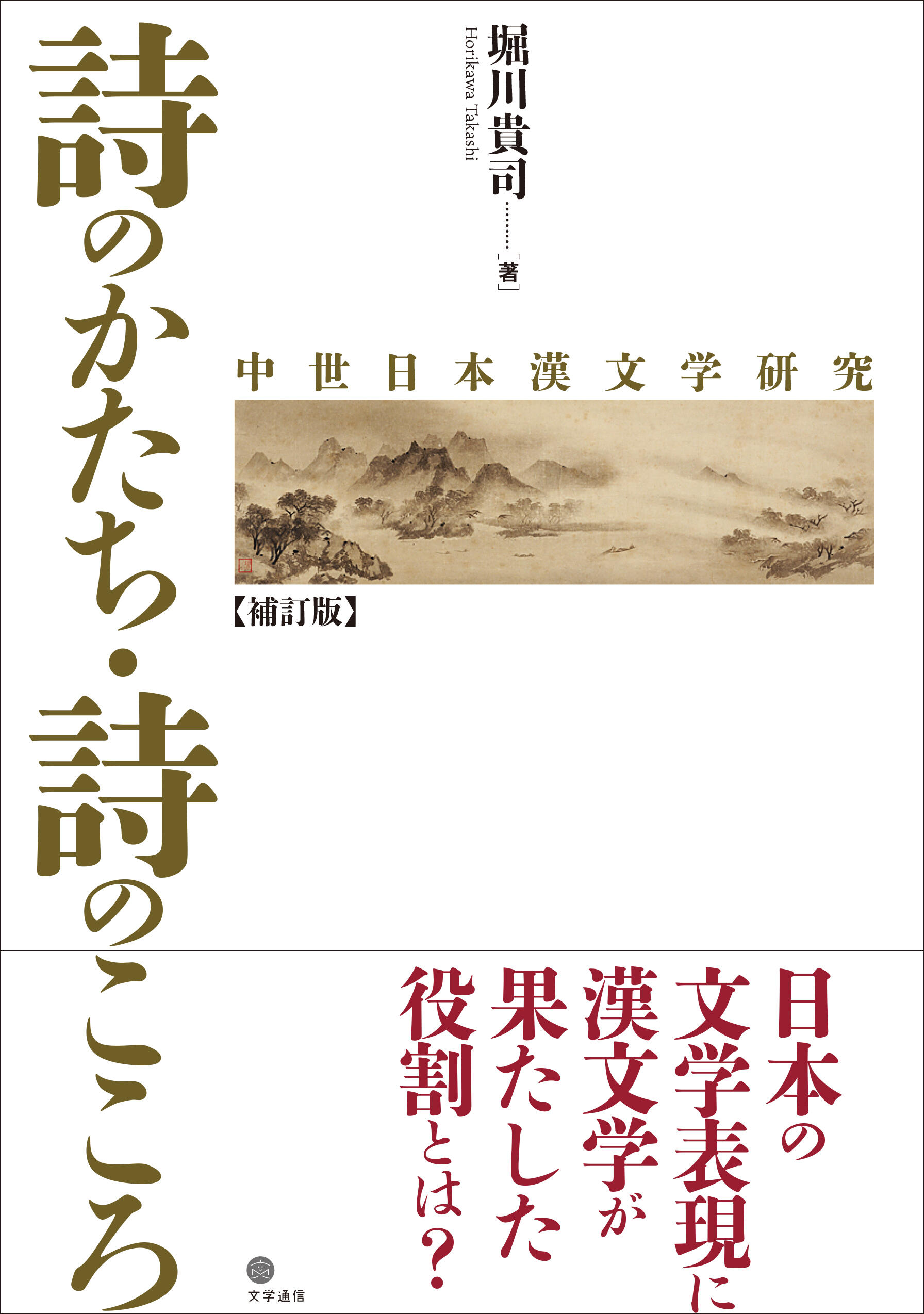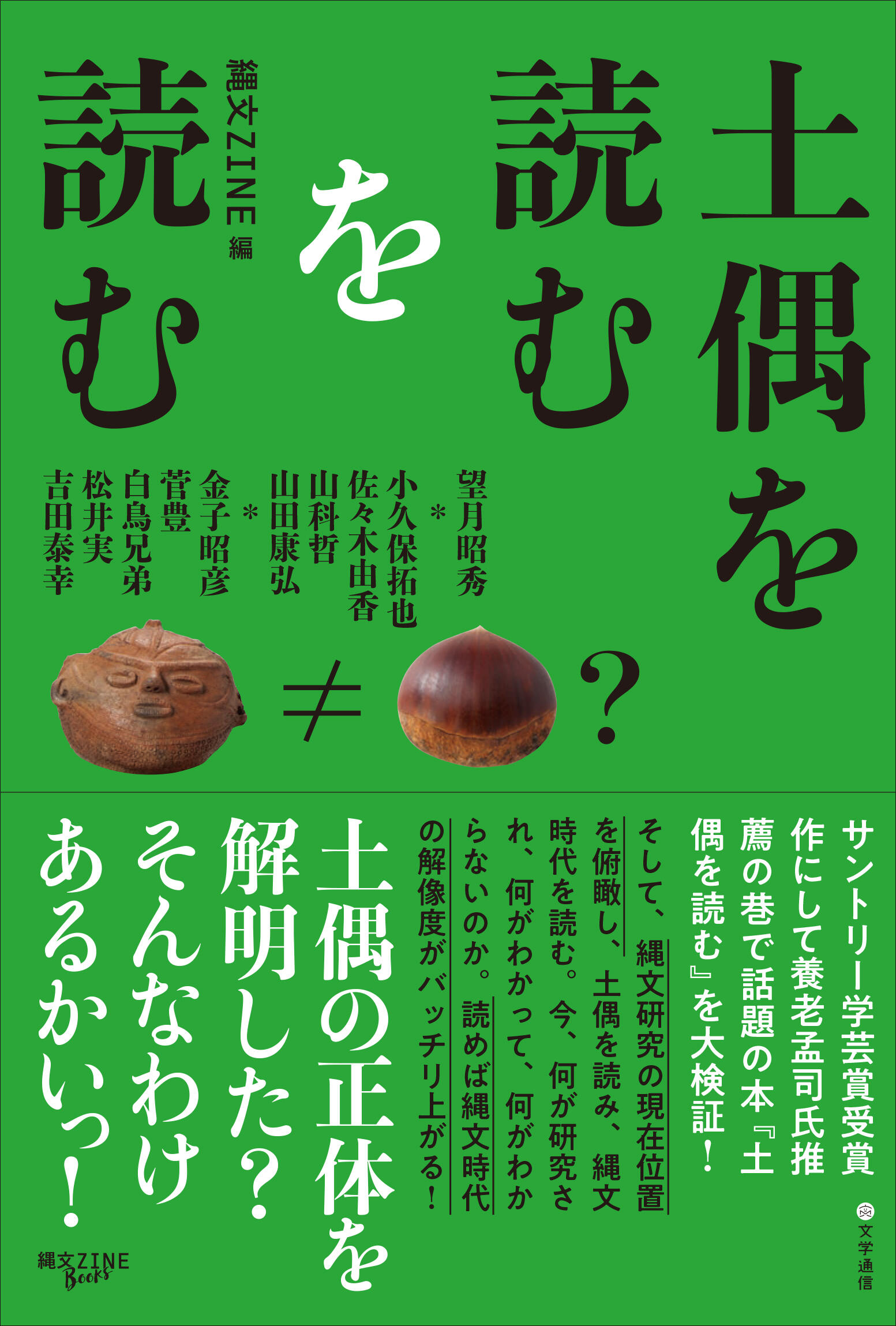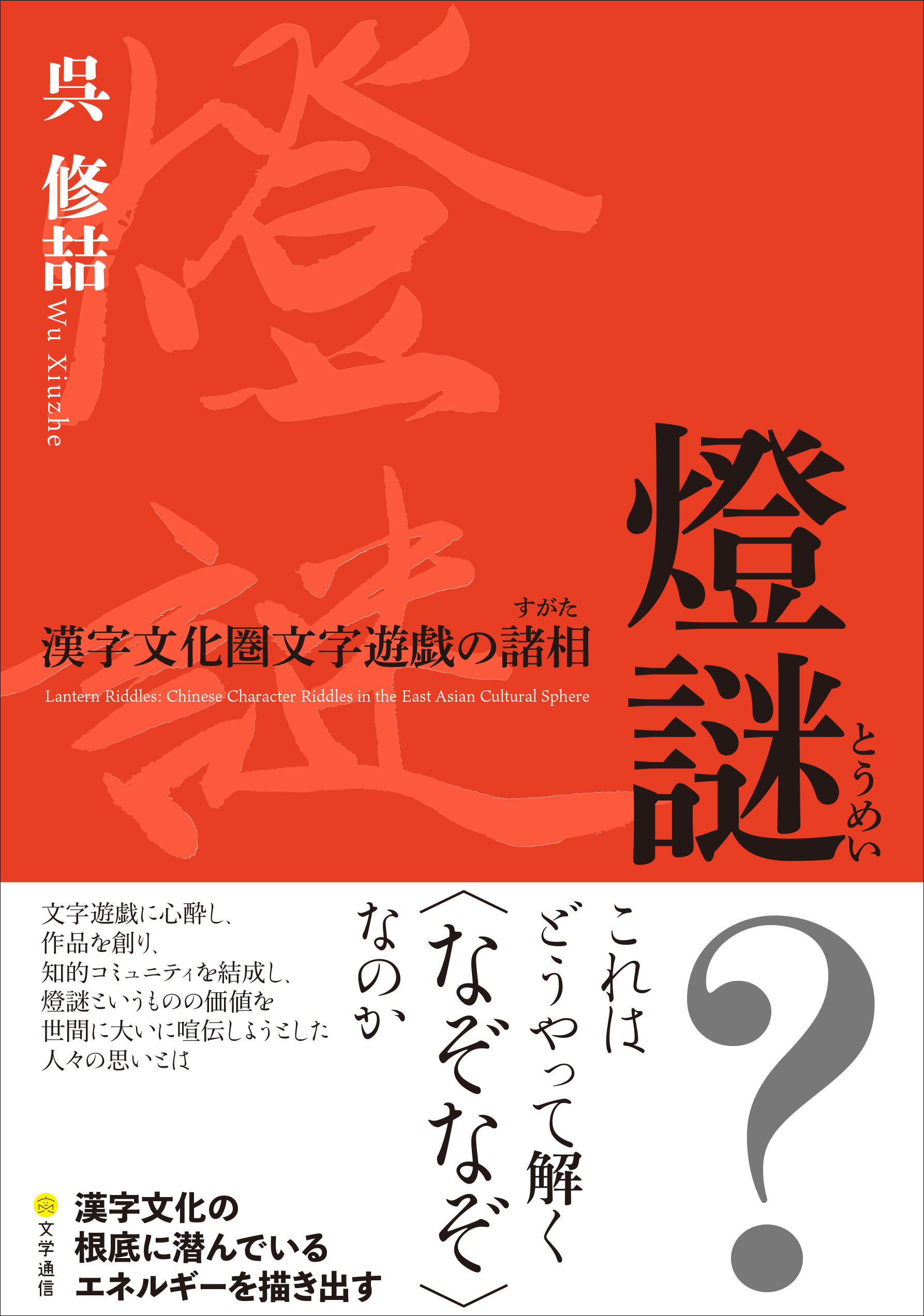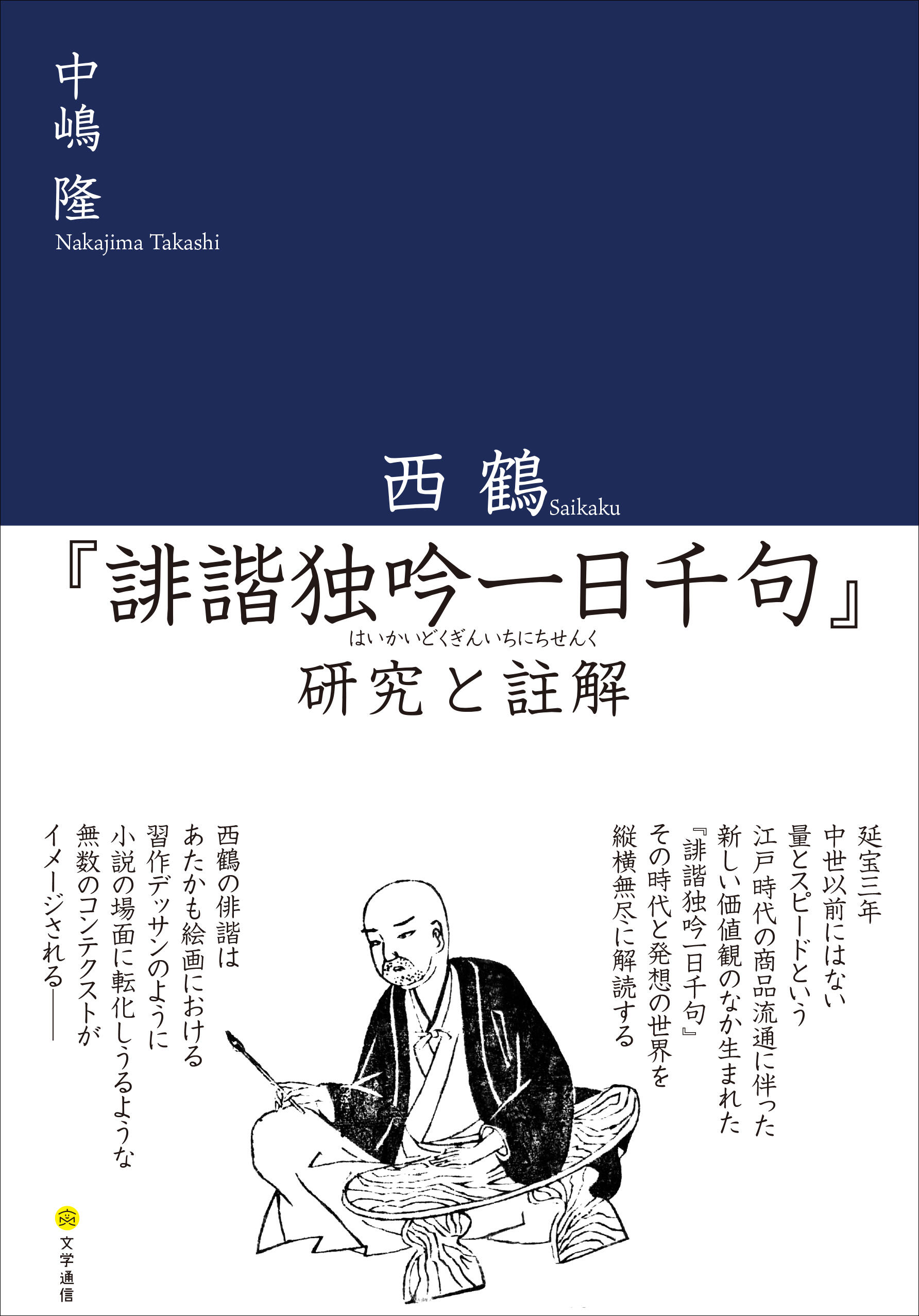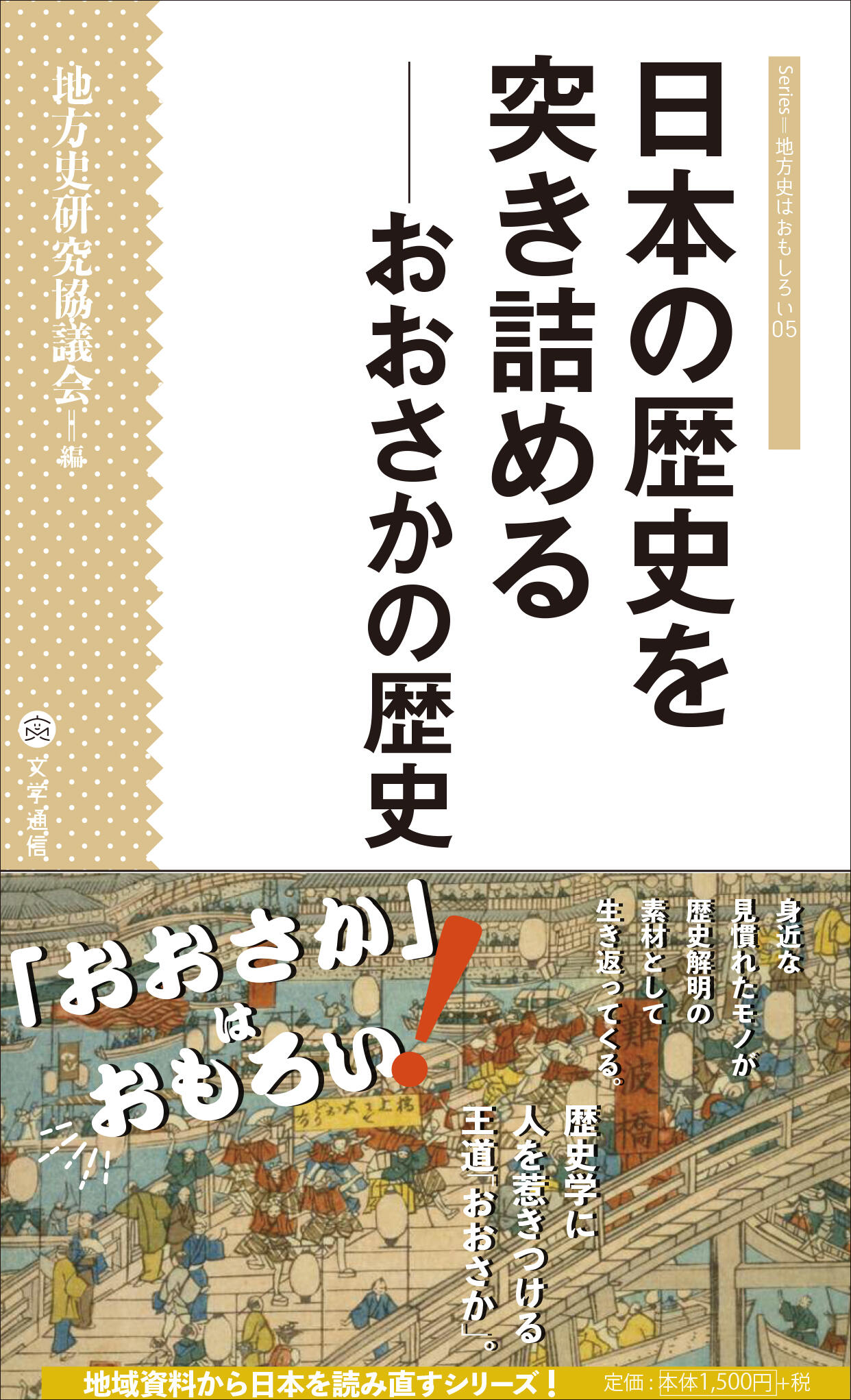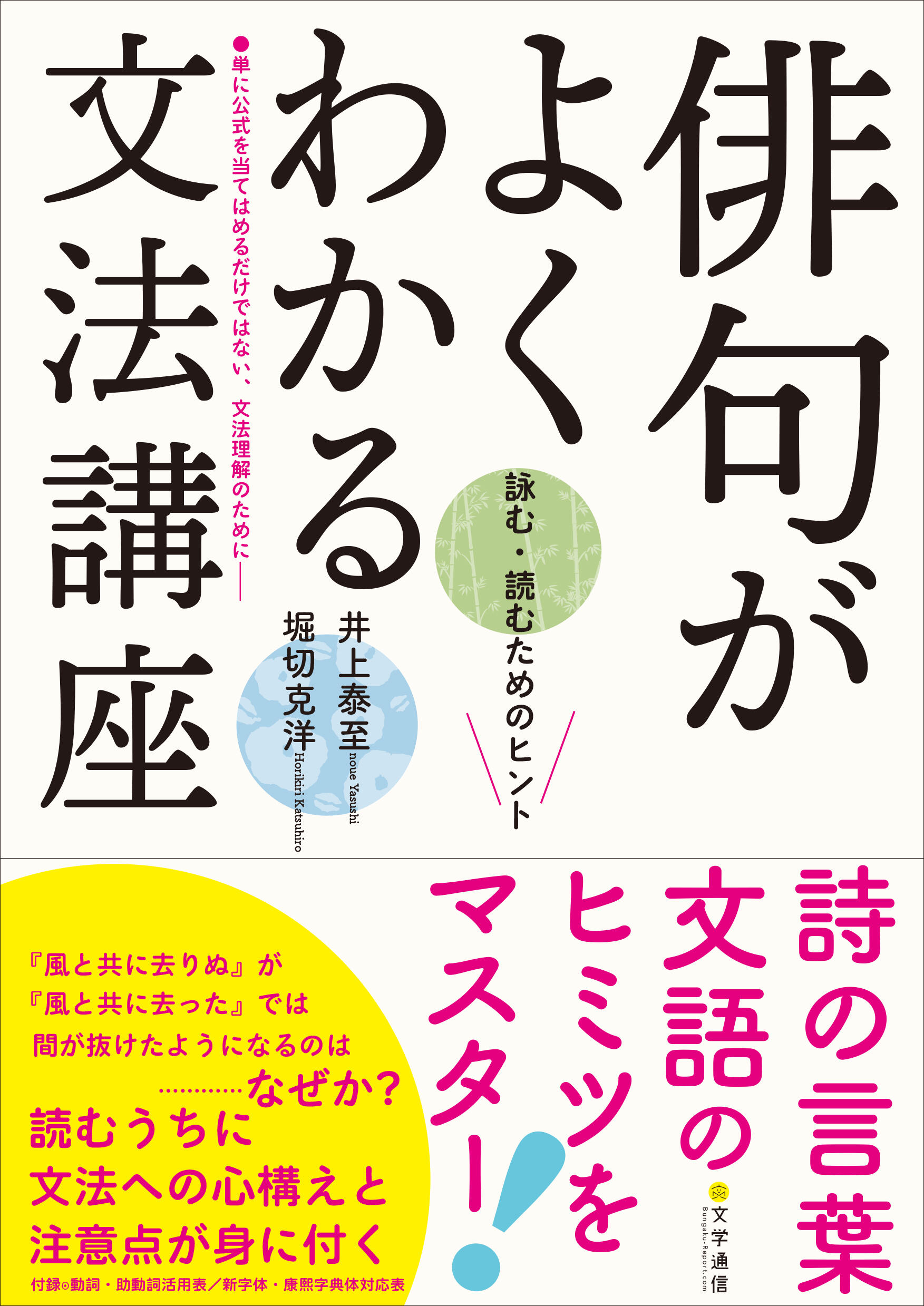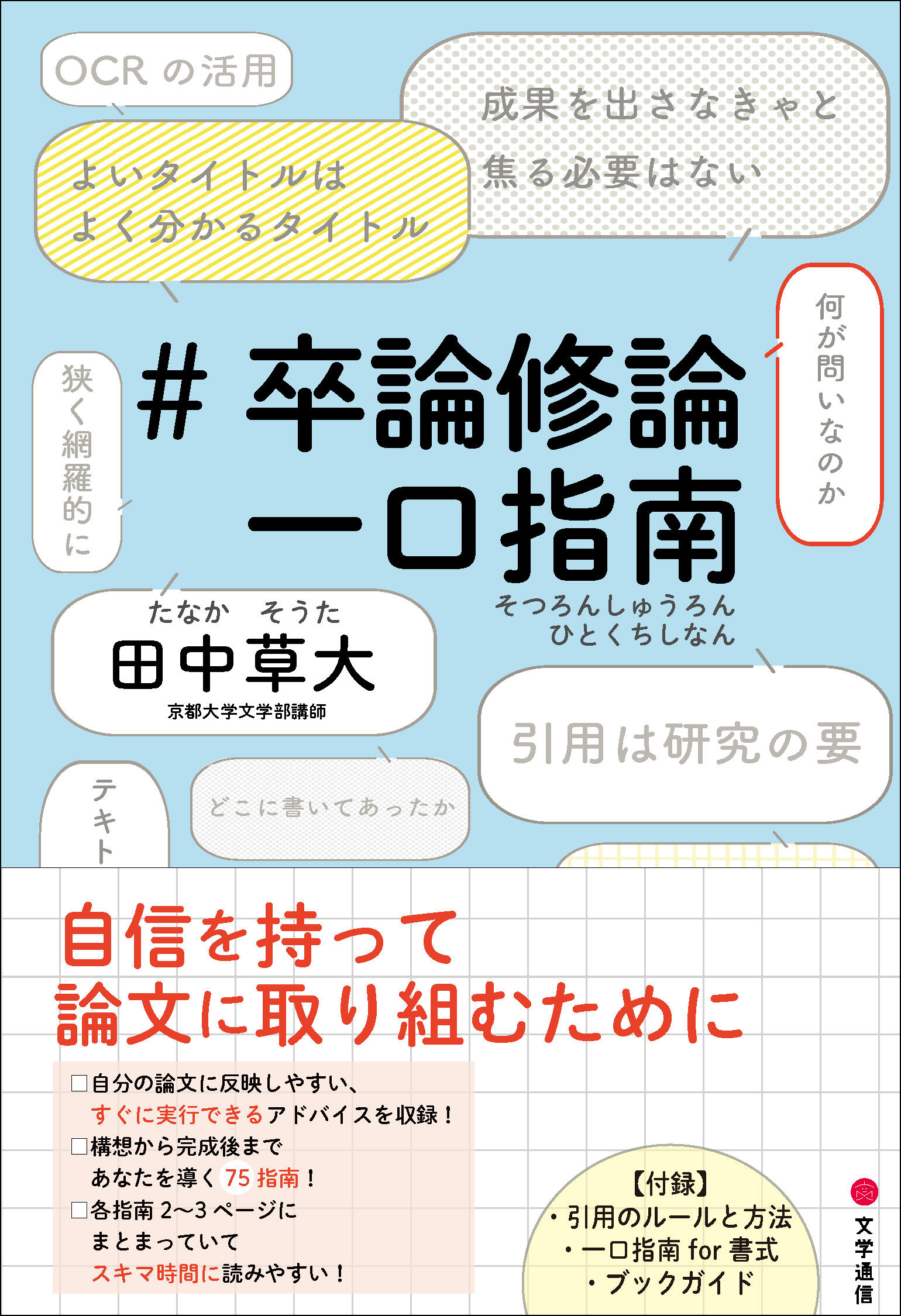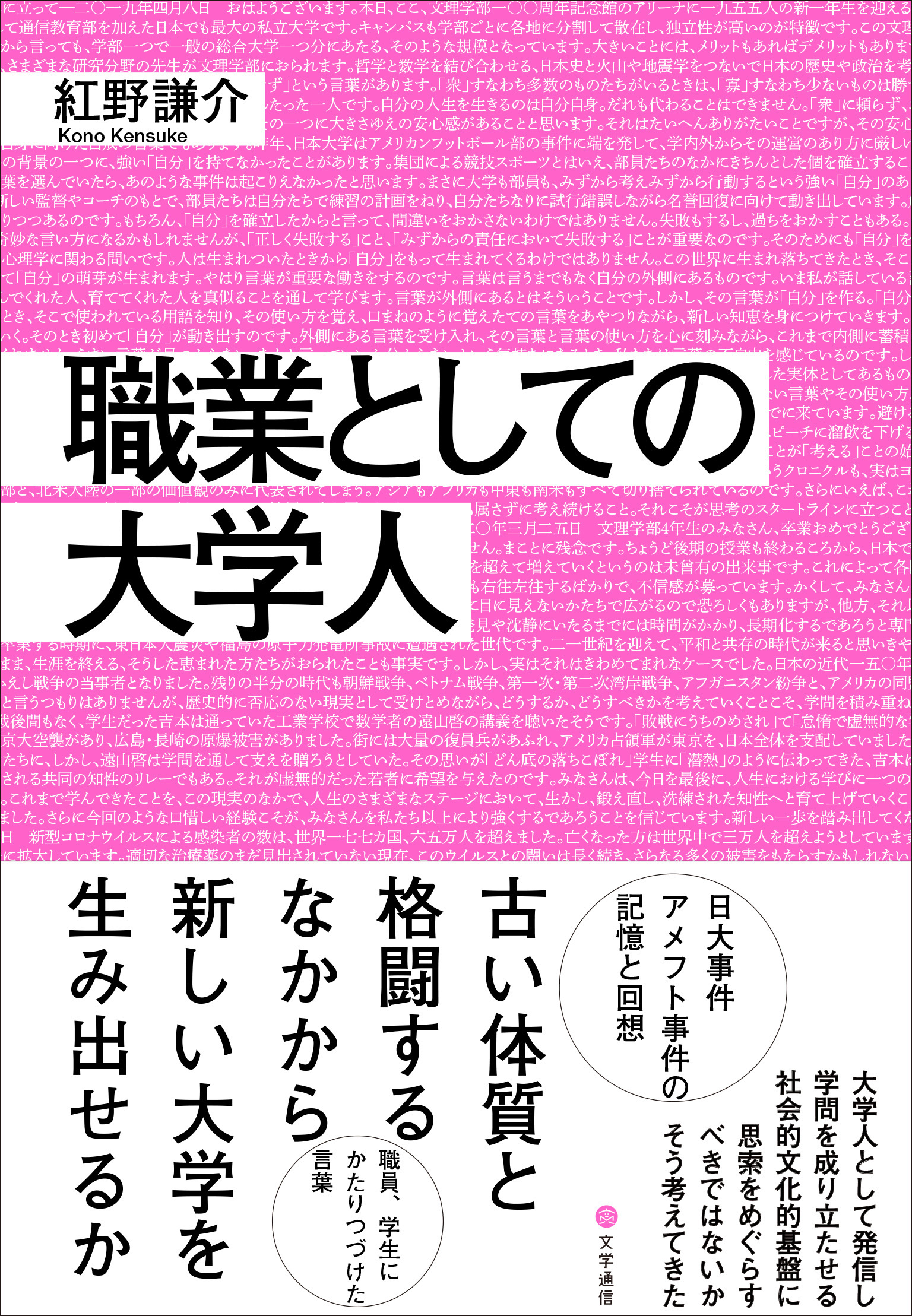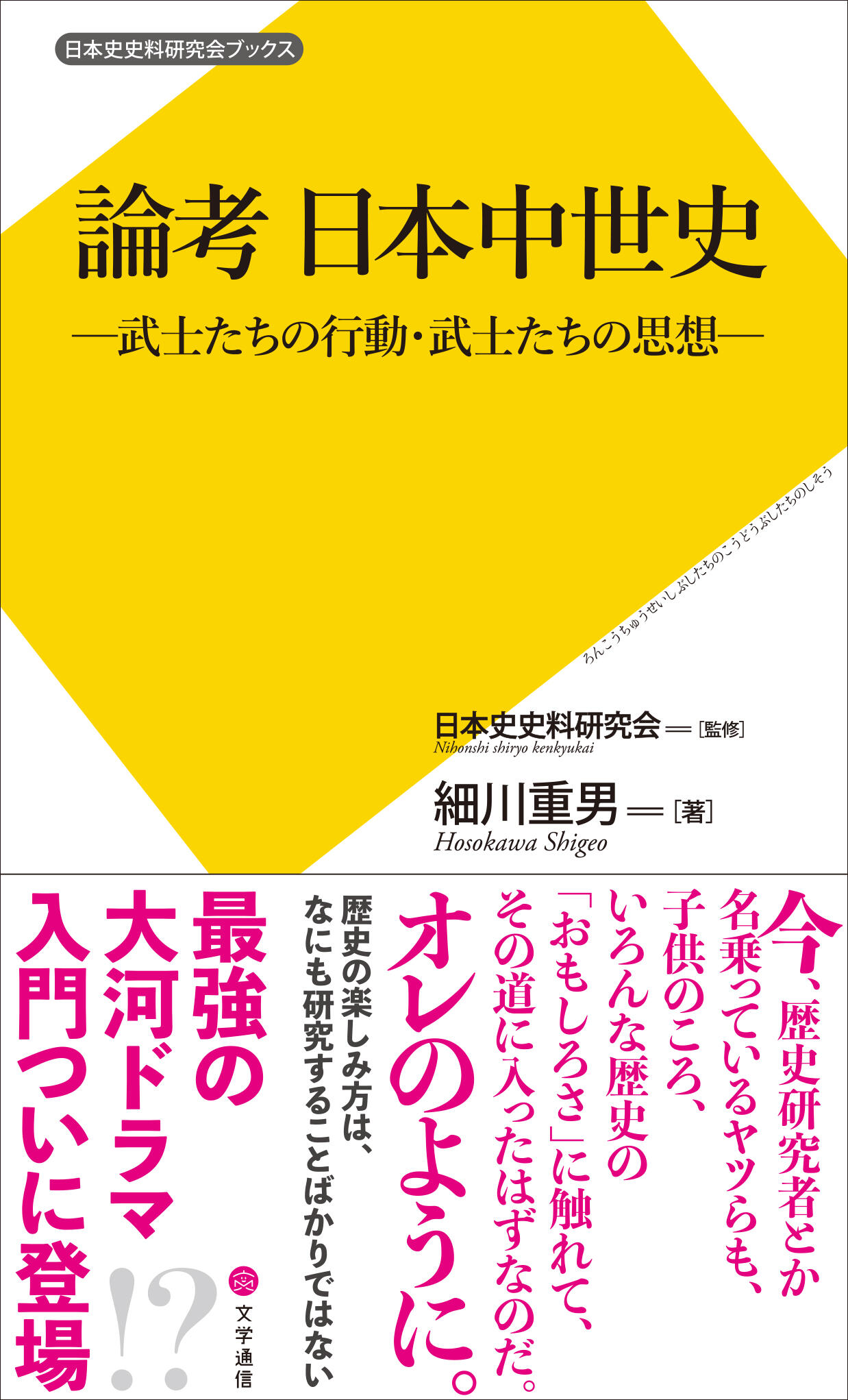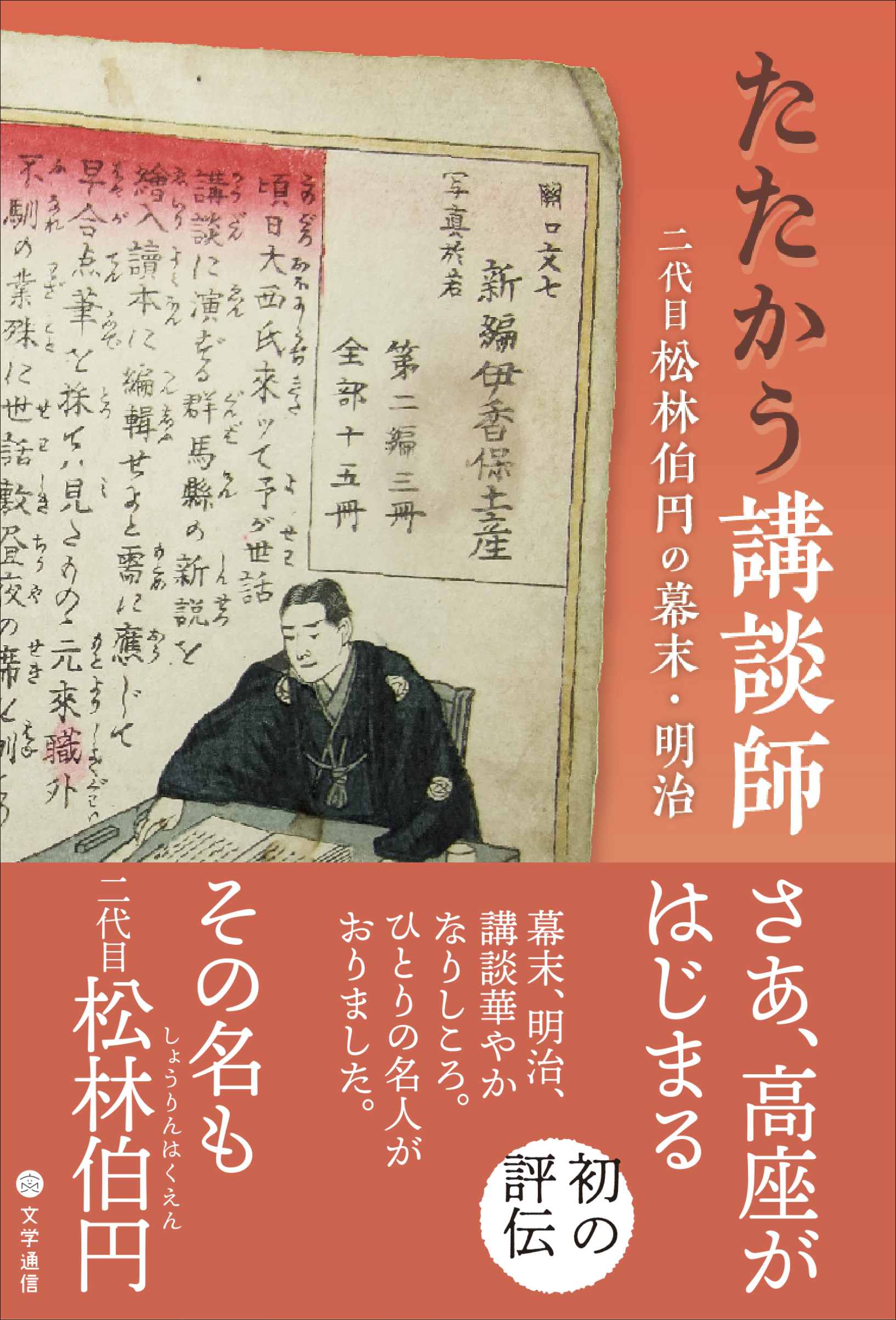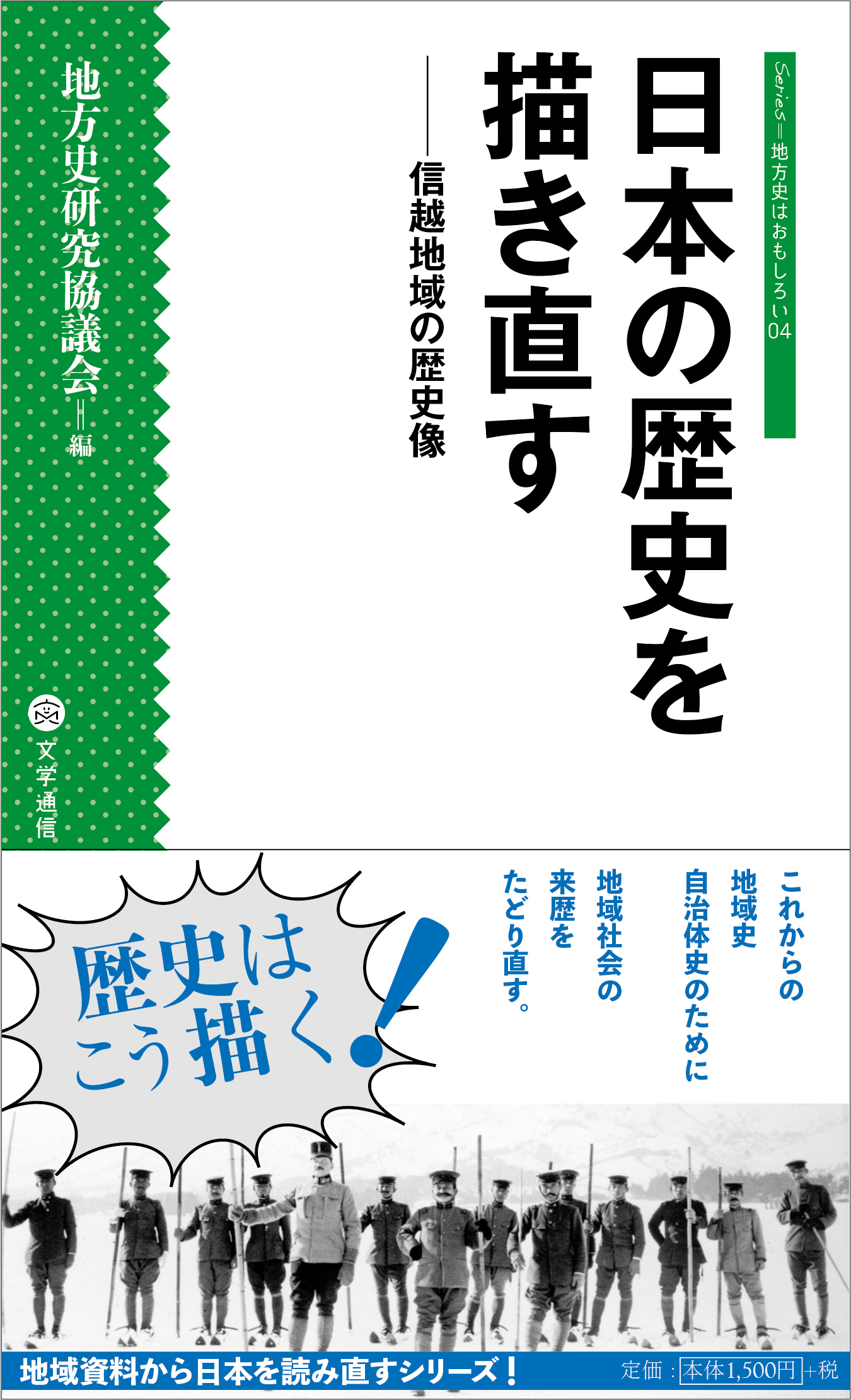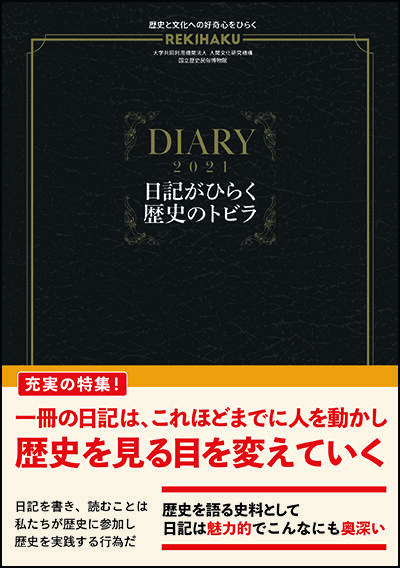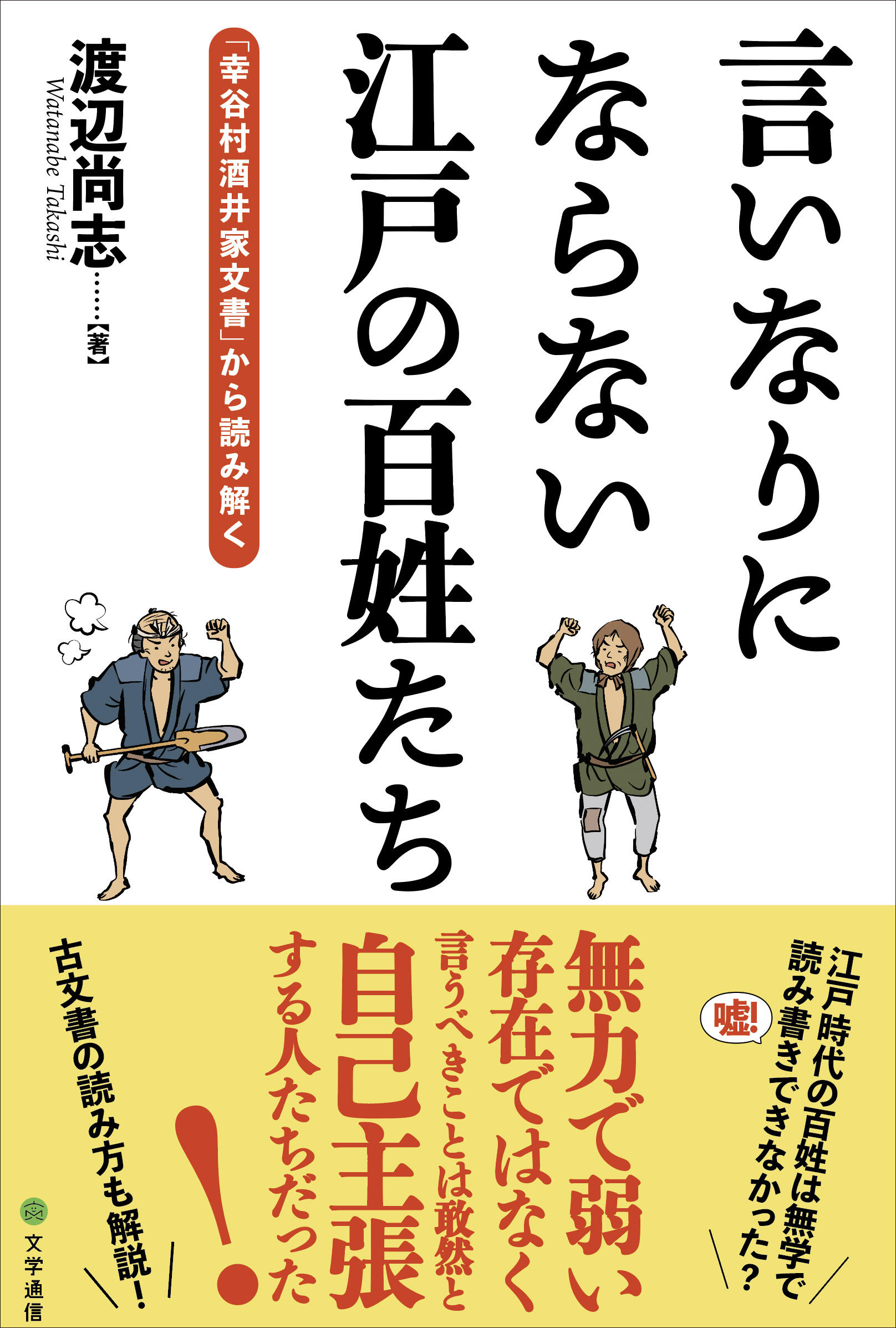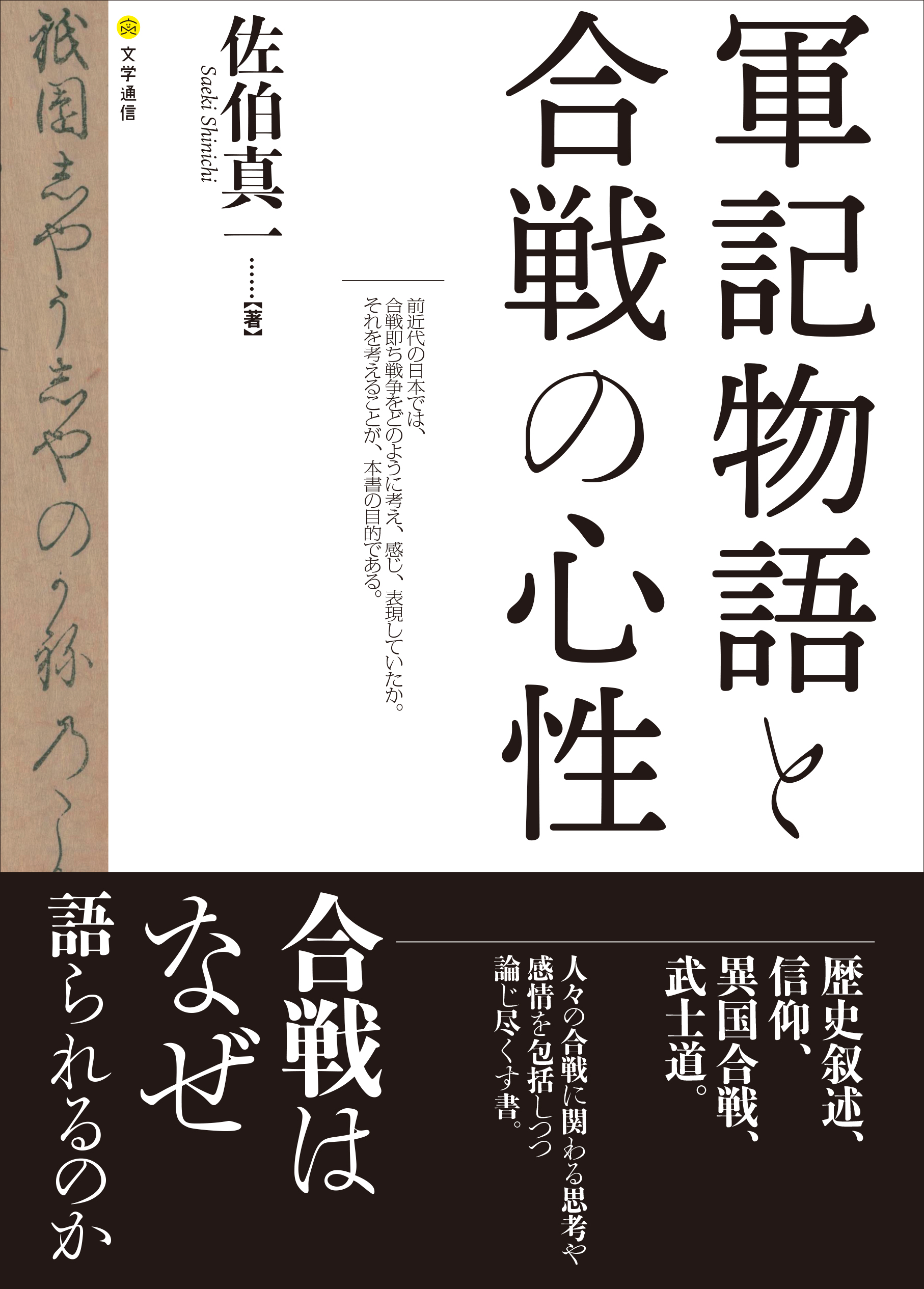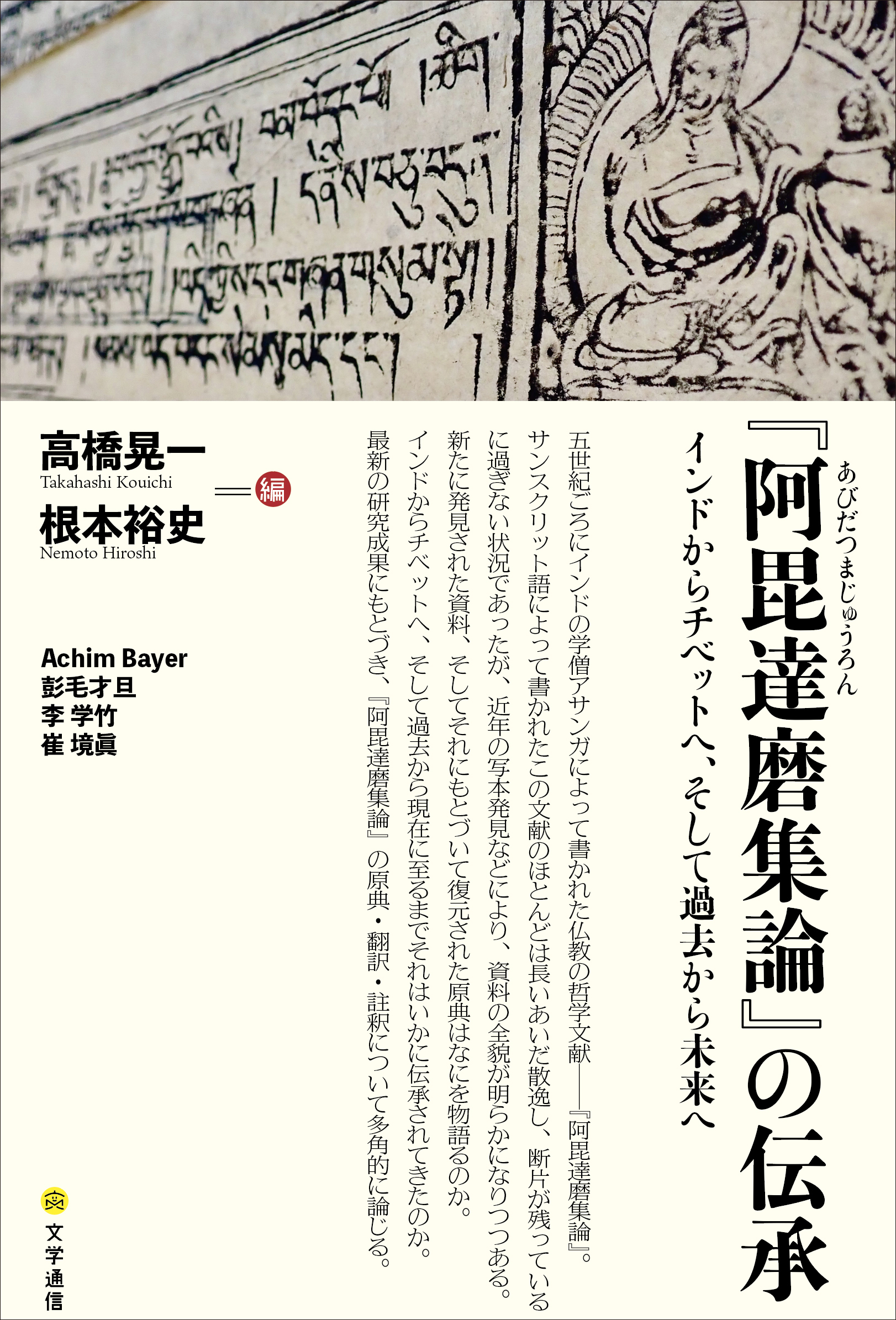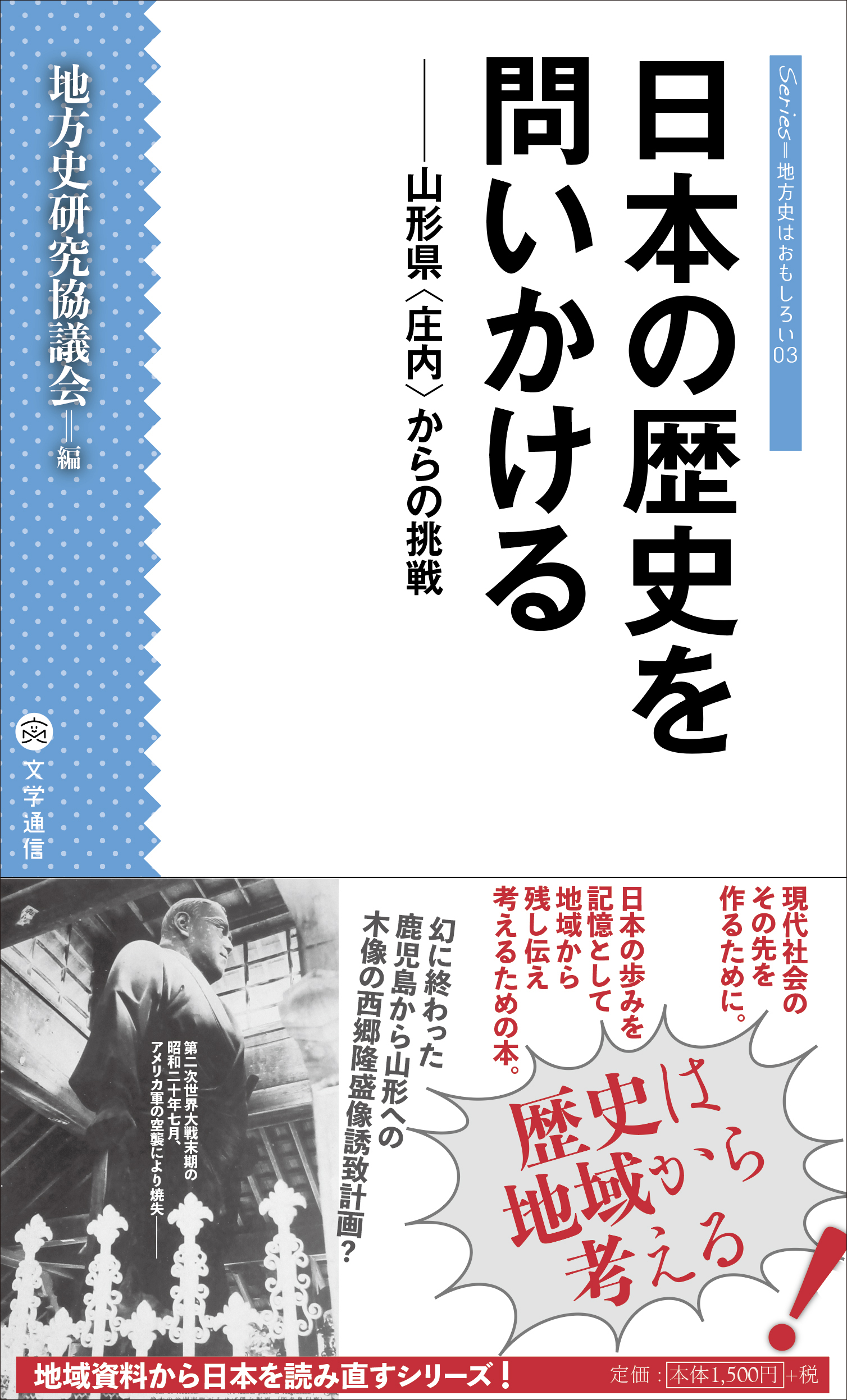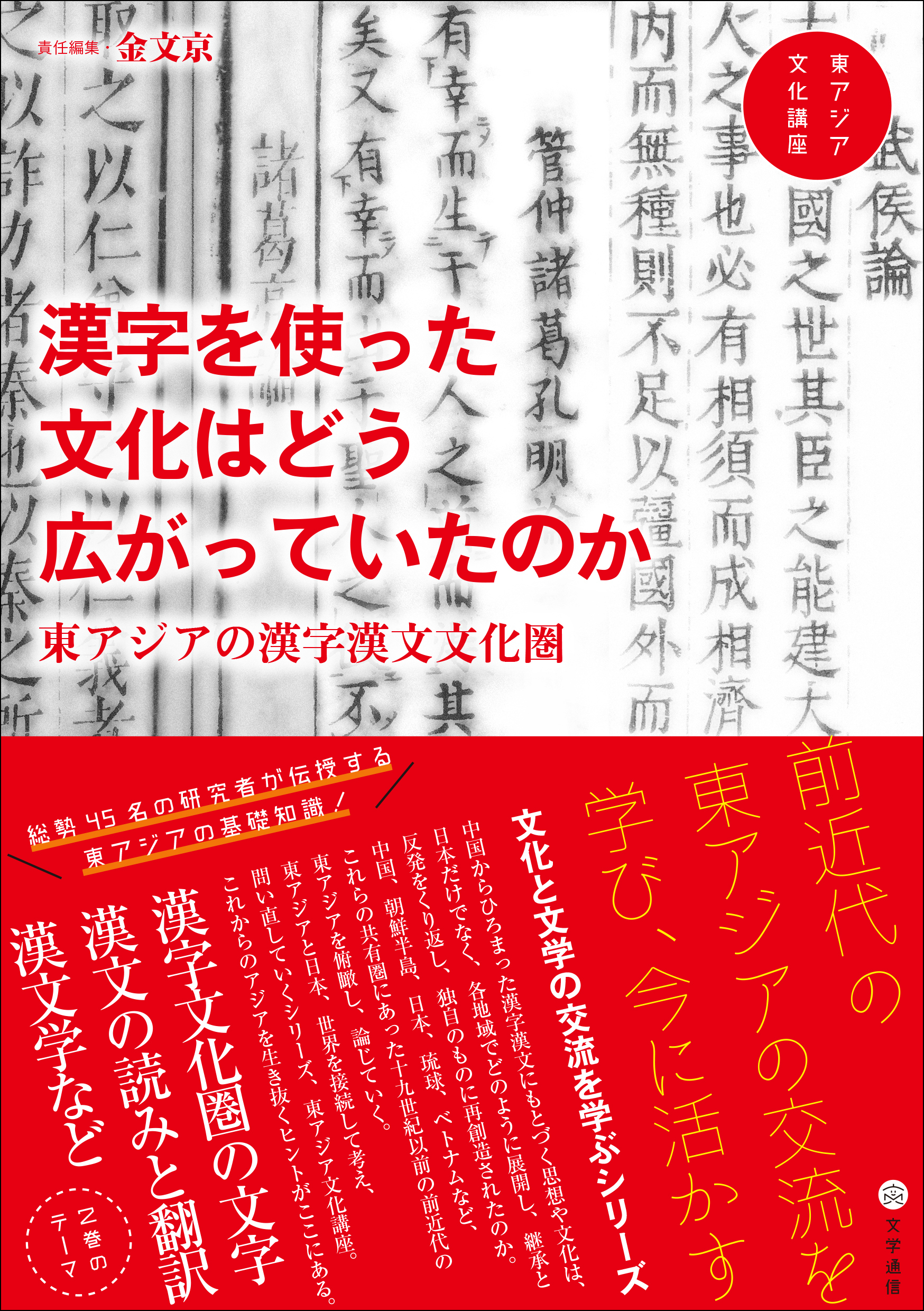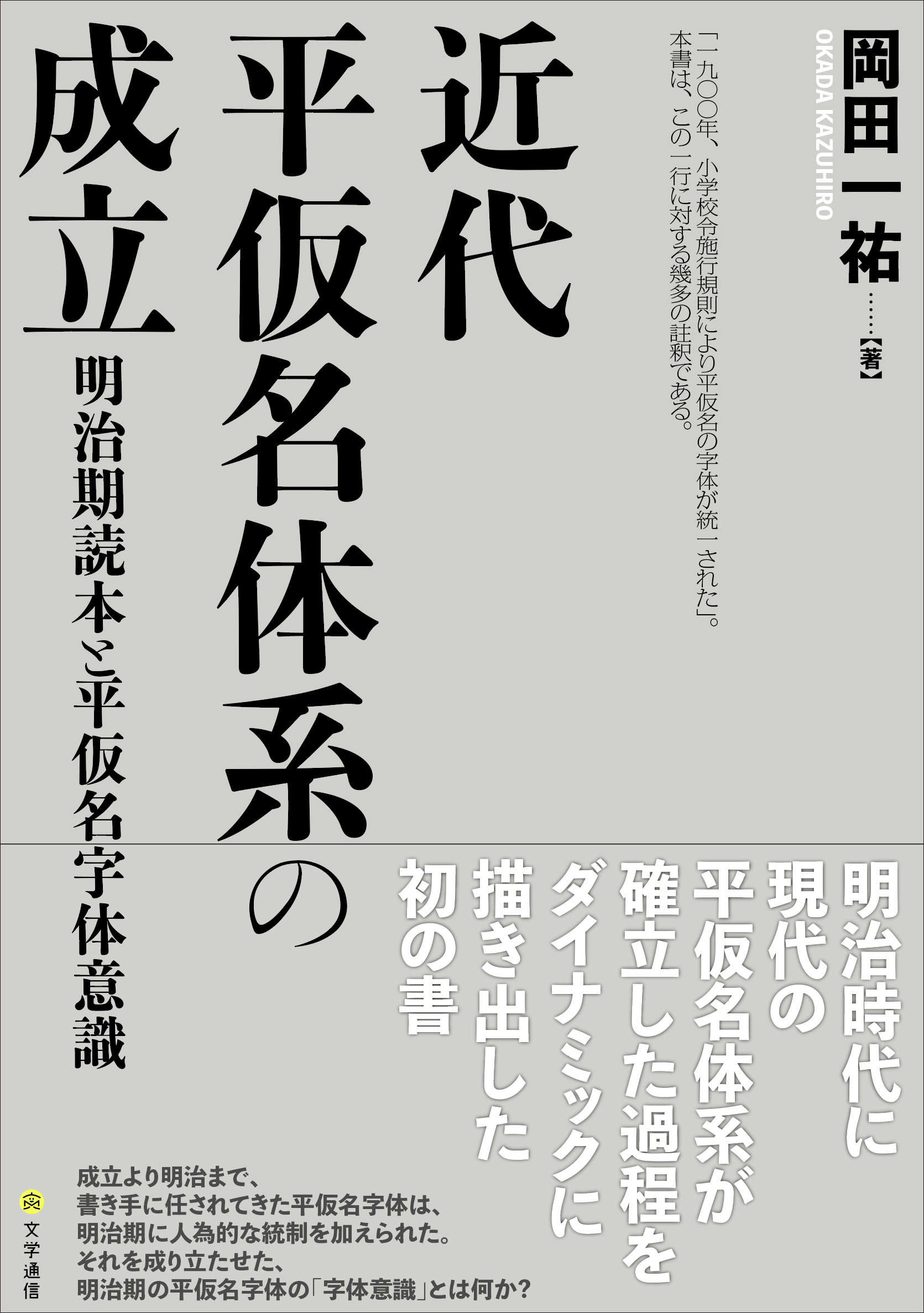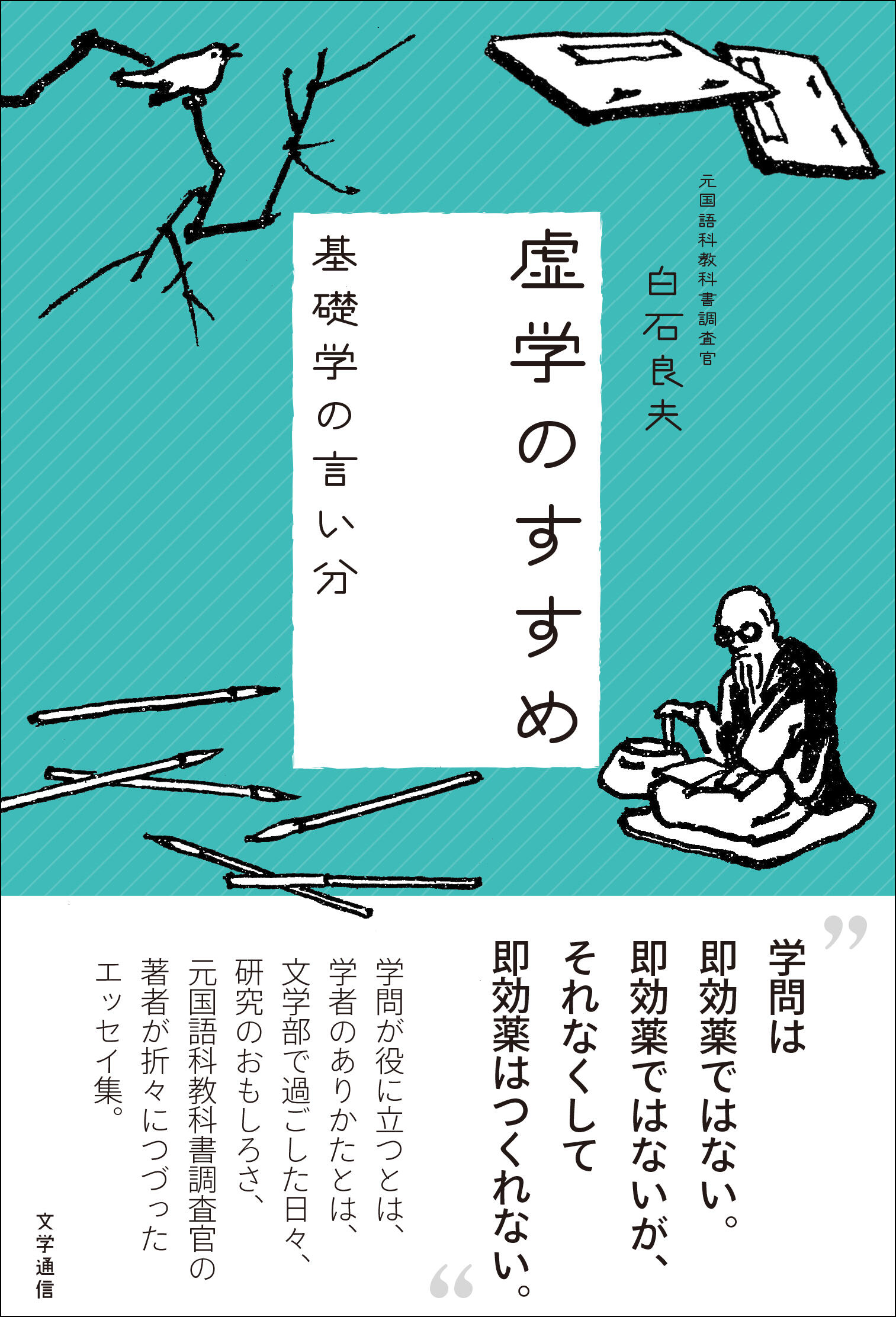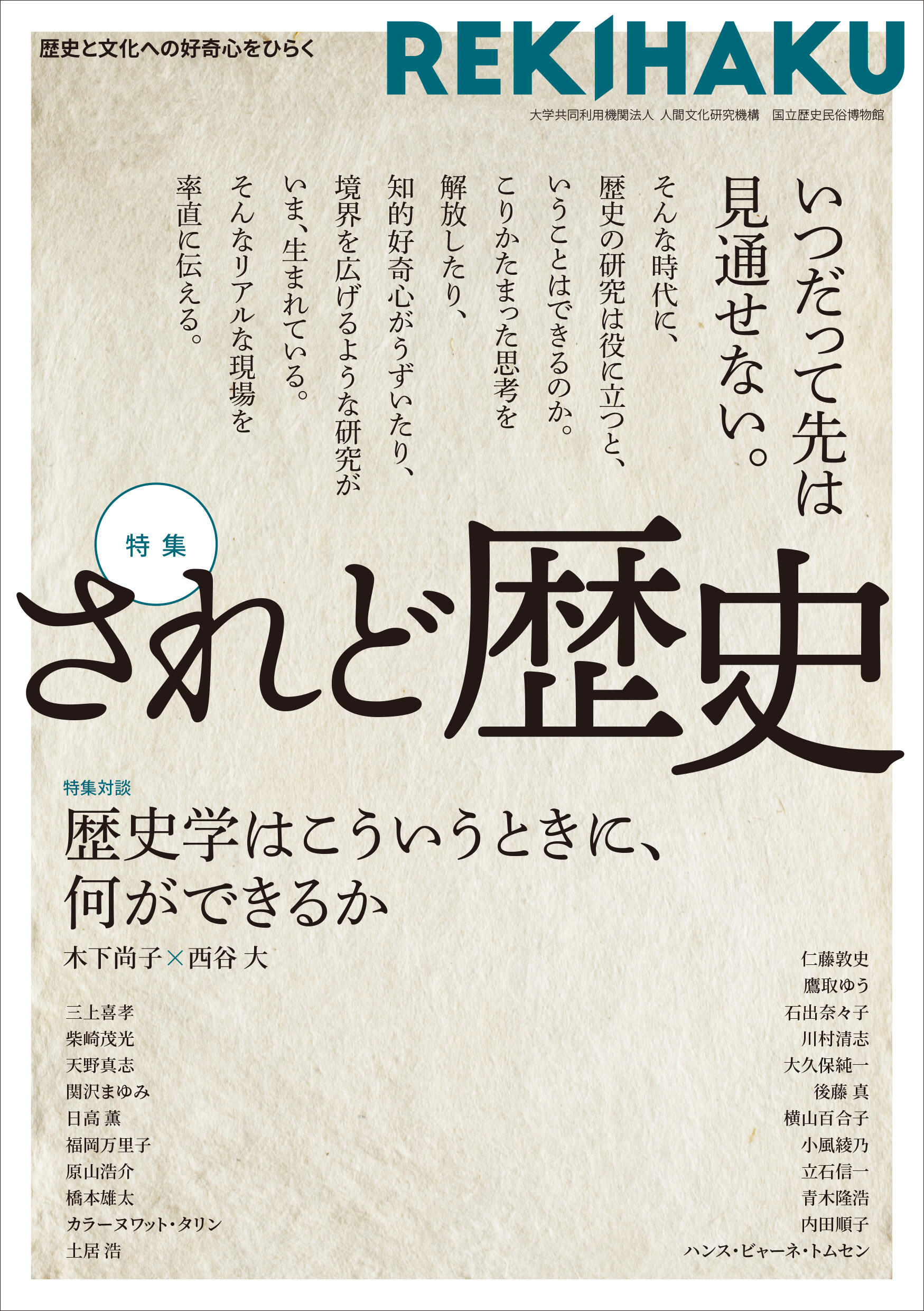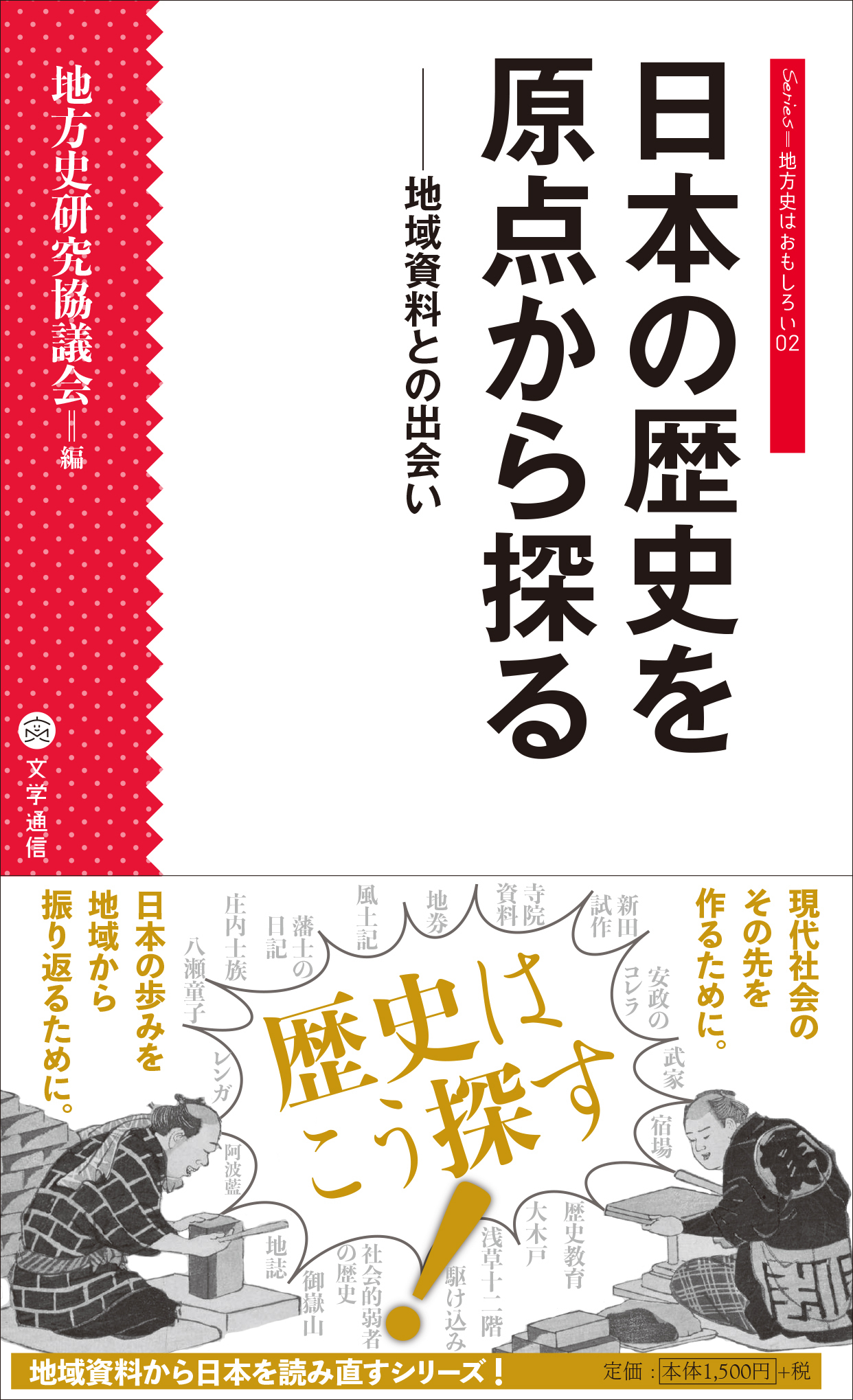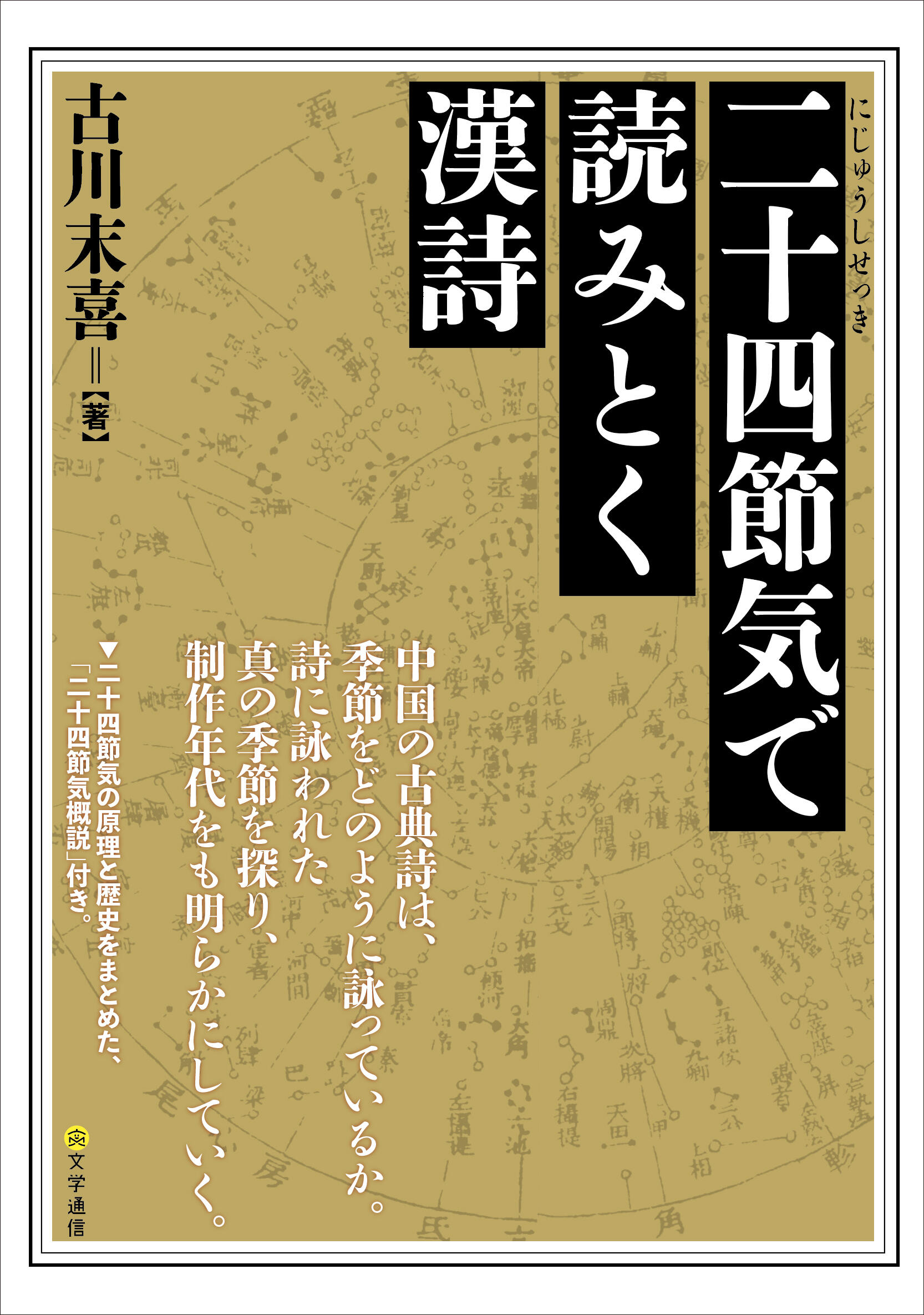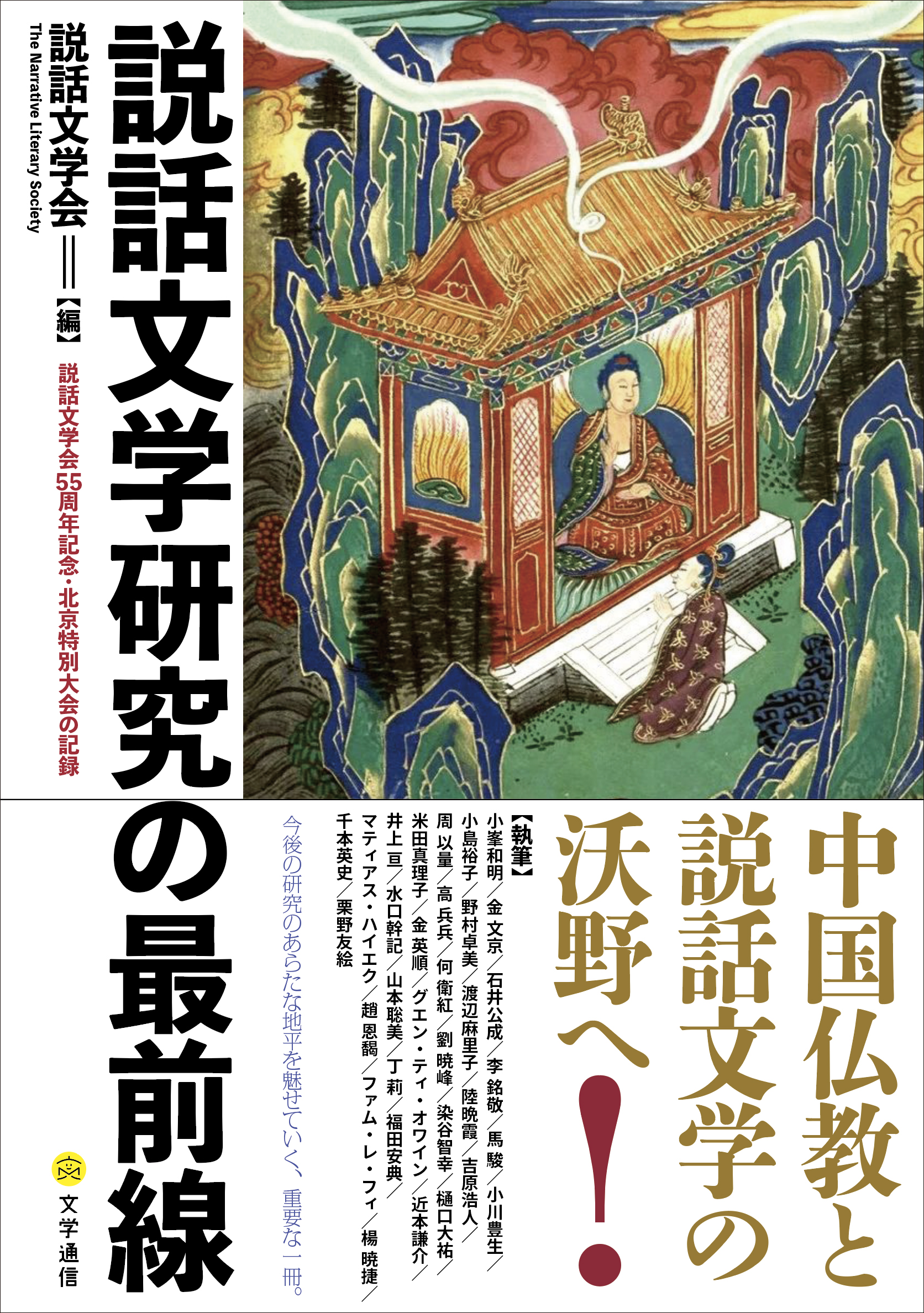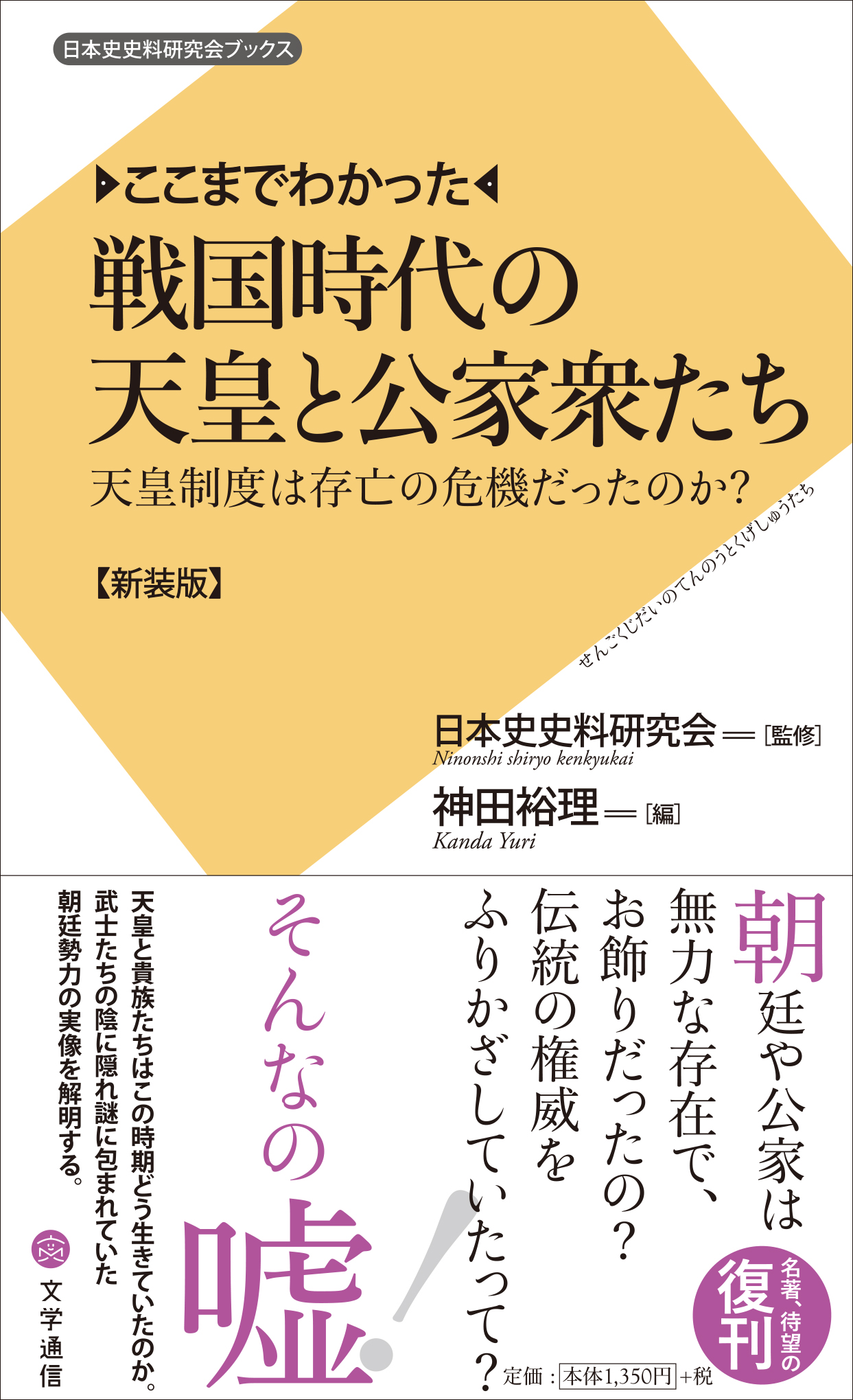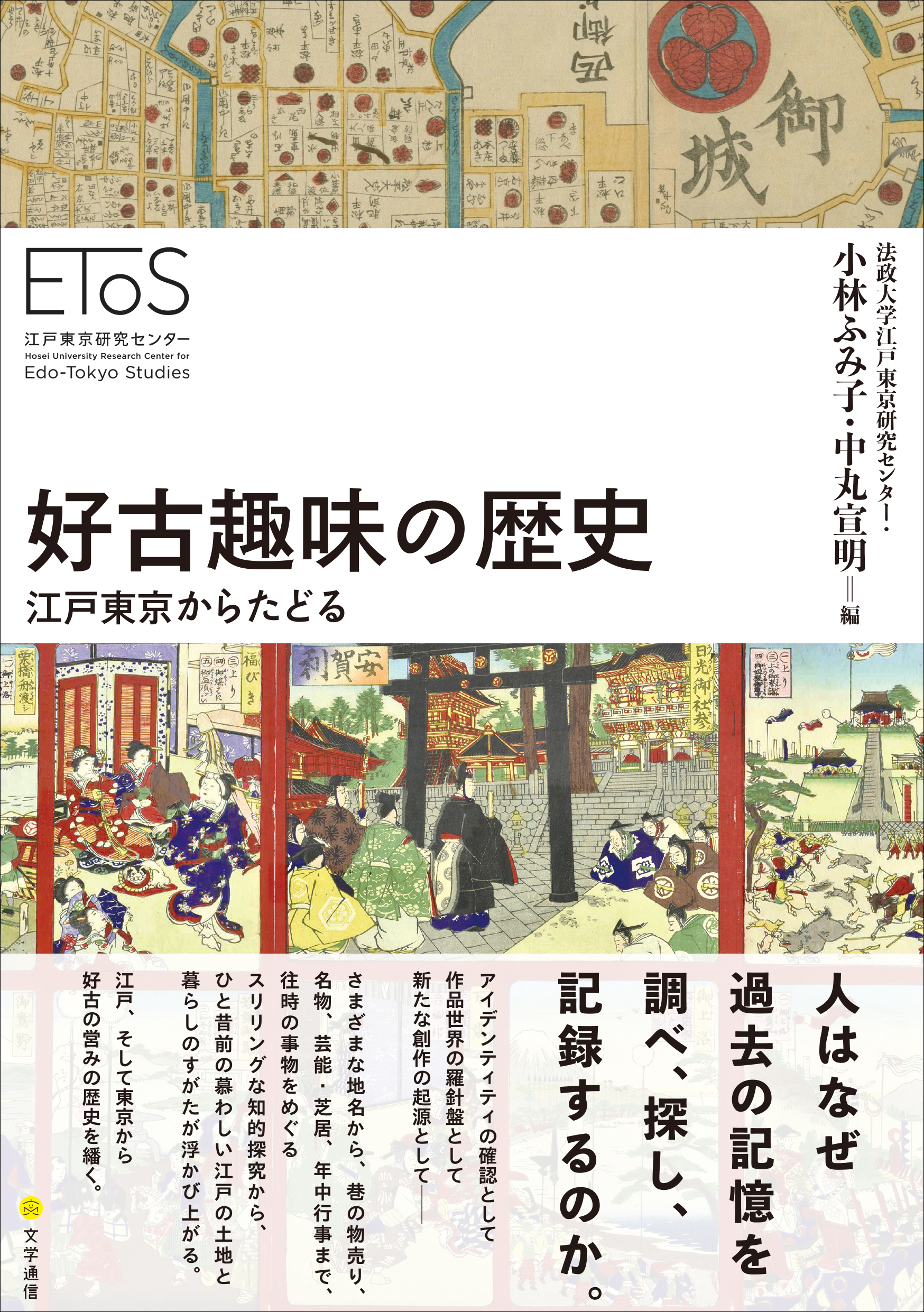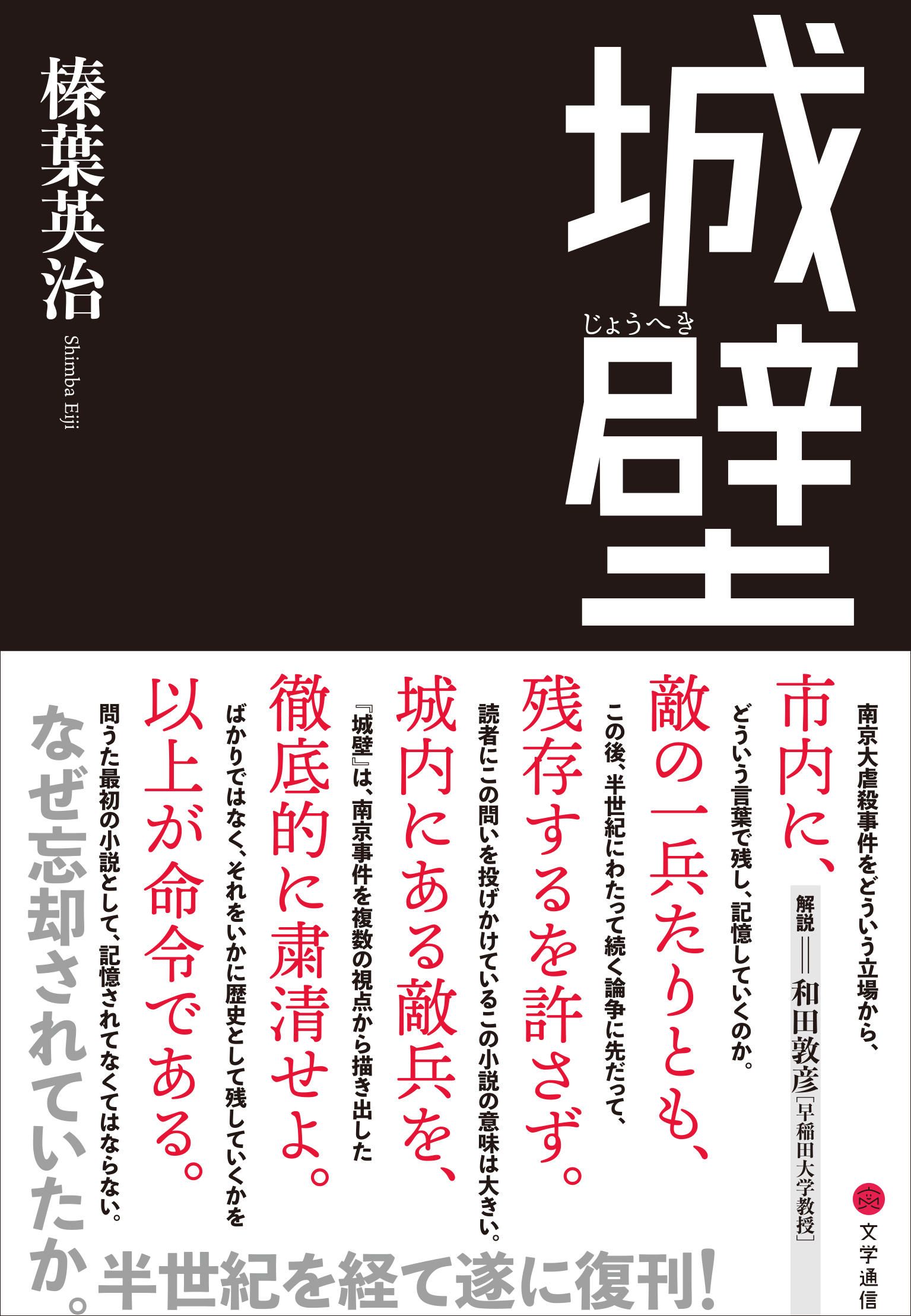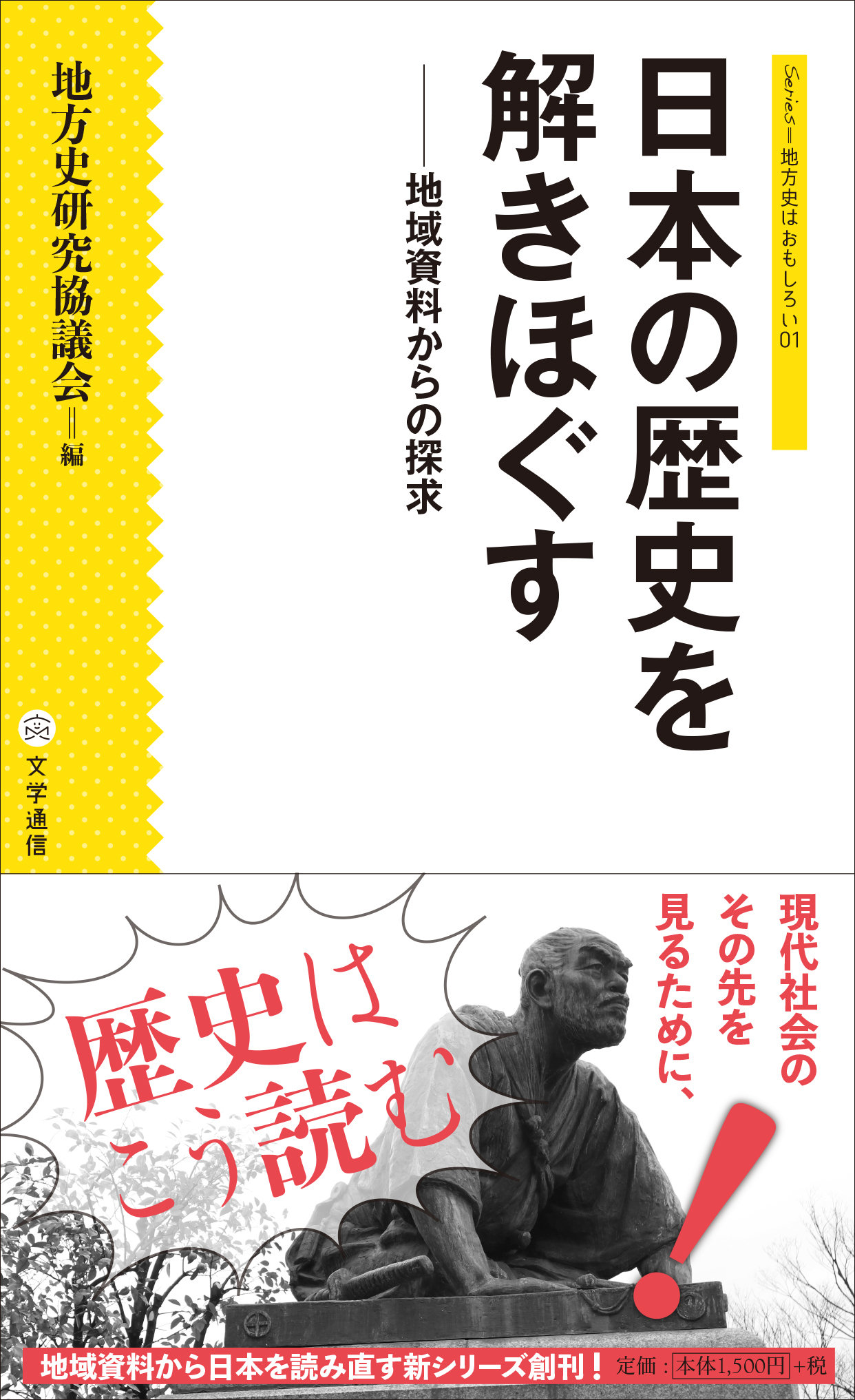2刷記念★「日本人論を終わらせるために――優越感なる劣情からの脱却」を期間限定全文公開○前田雅之『なぜ古典を勉強するのか 近代を古典で読み解くために』(文学通信)
前田雅之『なぜ古典を勉強するのか 近代を古典で読み解くために』(文学通信)から、原稿を一部紹介していきます。2刷(2018.8.10第1版第2刷)刊行記念です!
-------

前田雅之
『なぜ古典を勉強するのか 近代を古典で読み解くために』
ISBN978-4-909658-00-5
C0095
四六判・上製・336頁
定価:本体3,200円(税別)
●本書の詳細はこちらから。絶賛発売中です。
https://bungaku-report.com/blog/2018/05/post-167.html
-------
日本人論を終わらせるために――優越感なる劣情からの脱却
1―近代日本の「欧化」と「国粋」
アメリカの大規模書店に入って気づくのは、自伝とダイエット本の充実ぶりである。元大統領が自伝を記し、その多くがベストセラーになるのも成功者(アメリカン・ドリームの達成者)の自伝を好む国民性があるからだろう。ウォーターゲート事件で辞任に追い込まれたリチャード・ニクソン元大統領(一九一三〜九四)の頗る面白く役に立つ自伝(『ニクソン わが生涯の戦い』、文藝春秋)も例外ではない。
他方、日本人が好むのは、小説・エッセイ・人生論の類を除いて、さまざまなノウハウ本と並んで日本人論となるのではないだろうか。往年の大ベストセラー、中根千枝(一九二六〜)『タテ社会の人間関係』(講談社現代新書、一九六七年)、イザヤ・ベンダサンこと山本七平(一九二一〜九一)『ユダヤ人と日本人』(角川文庫、一九七〇年)をはじめとして、自己が所属する民族・国民とは何かを記した書物を好む人たちが他にいるのかどうかは分からないが、近代以降の日本人論を博捜し、観察・分析を加え、内容の豊富さでは未だにこれを超えるものがない南博(一九一四〜二〇〇一)『日本人論 明治から今日まで』(岩波書店、一九九四年)によれば、明治二十年代から今日まで蜿蜿と書かれ続けているのである。どうやら日本人とは自己が所属している日本人なるものが気になって仕方がない国民であるようだ。
当たり前の話だが、近代以前には日本人論などという類の書物は存在しない。元禄十四(一七〇一)年に『人国記』なる書物が刊行された。諸国の地誌・人情・風俗という情報を記したものであり、当時にしては画期的な出版であった。たとえば、「河内」とあるところを開くと、
当国の風俗は、上下男女ともに気柔にして、譬ばゆきのあしたに庭前の柳枝甚だたわむといへども、終に折るることなきが如し
とあり、河内人の気の柔らかさは、雪の重みでたわむけれども決して折れない柳の枝のようだと言っている。交渉するに際しては、敵はかなりの粘り腰を発揮するとでも言いたげな書きぶりである。江戸期に入り、視野や知識欲求が日本全国にまで行き届くようになったから、こうした地誌本が出されるようになったのだろう。中期以降盛んに出された『名所図会』や十九世紀初頭に出た十返舎一九(一七六五〜一八三一)『東海道中膝栗毛』(一八〇二〜二二)もその延長線にあると言ってよい。実際、お伊勢参りだけではなく、宿場町や街道が整備されさまざまな場所を訪ねる人も増えてきたのである。
だが、だからといって、『人国記』には日本人なる概念は言うまでもないがない。日本は暗黙の前提ないしは枠組・範囲にはなっているが、そこに住む日本人なる概念や共通イメージがまだ成立していないからである。日本人なる概念が国民的規模で承認され、日本人意識なるものが形成されたのは、一八九四~九五年の日清戦争以降となるのではないか。一八八九年に憲法が制定公布され(翌年施行)、近代国家として形を整えていたとはいえ、日本人だという国民的自覚・アイデンティティは、戊辰戦争・西南戦争のように国内(=内部)ではなく、海外(=外部)に敵をもつことによって国内が結束して一つとなり、さらに外敵に勝利することによって悦びと共に生まれ確立していくということである。日清戦争とその勝利が果たした国家的かつ国民的意義はこの点にある。原因はともかく国民国家日本の成立のためには必要不可欠な戦争ではなかったのではないか。
仮にこの戦争がなかったらと仮定したらどうだろう。戊辰・西南戦争や自由民権運動の余塵も収まるどころか、藩閥対反藩閥や政党の対立をさらに激しくする原因ともなり、下手をすると、国内分裂の危機に陥っていた可能性がある。開戦が決まると、あれだけ対立していた議会対政府も挙国一致でまとまった(終戦後、また対立するが)のだから、対外戦争と国民国家の成立は日本やプロシャ(ドイツ)のような国にとっては他に選択のないものであった(アメリカの場合は南北戦争がそれに相当するだろう)。ここに国民国家なるものの欺瞞性をかぎ取ることもむろん可能である。
加えて、帝国憲法発布の恩赦で、明治維新の最大の殊勲者にしてその後最大の反逆者となった西郷隆盛の名誉回復が行われたことも、国民統合を助けたことも疑いない。内村鑑三(一八六一〜一九三〇)は、英文著作『Japan and Japanese』(一八九四年、後に改訂されて一九〇八年の『Representative Men of Japan(代表的日本人)』となる。岩波文庫)で西郷を取りあげて絶賛しているが、本書が書かれたのはまさに名誉回復の五年後であった。以後、西郷は、国民的英雄およびアジア主義や右翼の元祖として文明開化の負け組たちの精神的拠り所となって、国民国家の統一性を実は裏で支えていったのである。
対して、日清戦争の十年後に勃発した日露戦争は、日清戦争に比べると、比較にならないほどの人的物的損失がありながらも、なんとか大国ロシアに辛勝した(大勝利ということにしたが、賠償金がなかったために日比谷暴動となったことは周知の通り)ことによって、夏目漱石(一八六七〜一九一六)『三四郎』の広田先生の台詞ではないが、日本は「一等国」になったという自信と日本人という誇りが広く国民に共有され定着することとなった。簡単に言えば、世界列強=帝国主義国家への仲間入りを果たしたのである。
だが、日露戦争開戦の一年前には、ずっと語り継がれることになった一高生藤村操(一八八六〜一九〇三)の自殺があり、徳富蘇峰が言うところの「煩悶青年」が登場し始めていた(三四郎や一高を中退し東大選科にしか進学できなかった岩波茂雄〈一八八一〜一九四六〉もその一人だろう)。国民的自覚・アイデンティティの定着とエリート青年たちの目標喪失あるいはモラトリアム的精神状態はほぼ同時期に生まれたことは注意しておいてよい。社会が固まってきて、少し余裕ができて落ち着いてくると、社会自体を窮屈に感じ、かつまた、自分とは何かと考え込む青年も当然のように出て来る。彼らは極めて恵まれた例外的な少数者だが、それなりに影響も与える。秦郁彦(一九三二~)編『日本官僚制総合事典』(東京大学出版会)によれば、明治三十(一八九七~)年代には官僚の落ちこぼれが登場しており、既に立身出世主義だけではいけなくなってもいた。ポストは上に行くほど限られているから、皆が漱石を満洲に招待した大学予備門の同級生で親友だった満鉄総裁中村是公(一八六七〜一九二七)にはなれないということである。これが「一等国」の現実でもあった。
それでは、日本人論はいつ頃から生まれたのか。おそらく一八九一(明治二四)年に刊行された三宅雪嶺(一八六〇〜一九四五)『真善美日本人』『偽悪醜日本人』を以て嚆矢とするだろう。雪嶺はその三年前に雑誌『日本人』を創刊し(その後『日本及び日本人』と改題)、日本第一主義と化する前のまだバランス感覚もあり、「文明開化」に対する「国粋」を重んずる立場から活発な評論活動を展開していった。早く没したものの卓越した文明史家であった生松敬三(一九二八〜八四)は、近代の日本人論をこのように総括してくれている。
それは、要約していえば多くは明治開国以来の欧化と国粋の反復的回帰の動向に対応しているのであって、戦後、とくに昭和三十年代以降今日にいたる日本人論・日本文化論の流行もまた基本的にはその大枠を出るものではないように思われる(生松編『三宅雪嶺 芳賀矢一 日本人論』冨山房百科全書)
なんのことはない、すべては「明治開国以来の欧化と国粋の反復的回帰の動向」への「対応」なのであった。前近代には現れないのも、この「欧化と国粋の反復的回帰」がないからである。逆に言えば、近代日本人は国民自覚があろうがなかろうが、「欧化」と「国粋」の枠組から逃れられないということになる。これでは煩悶青年も出て来るだろう。
こうした対応を丸山眞男(一九一四~九六)は「思い出」をキーワードとして以下のように述べている。
過去に「摂取」したものの中の何を「思い出」すかはその人間のパーソナリティー、教養目録、世代によって異なってくる。万葉、西行、神皇正統記、吉田松陰、岡倉天心、葉隠、道元、文天祥、パスカル等々々。これまでの思想的ストックは豊富だから素材に事欠くことはない。そうして舞台が一転すると、今度はトルストイ、啄木、資本論、魯迅等々があらためて「思い出」されることになる。(『日本の思想』、岩波新書)
パスカル・トルストイ・資本論が欧化なら、万葉・西行・神皇正統記・松陰はさしずめ国粋となるだろうか。丸山はこうした態度(概ねインテリの傾向だろうが)に日本の無思想性を捉え、批判を加えているものの(一言言っておくと、丸山が称讃気味に描く西欧社会にも似たような傾向はあるのではないか。ポストモダンはどこに行ったのだろう。最近ヘーゲルが復活したようだ。なぜ「思い出」されたのか)、書きぶりにはかなり諦めムードが漂っている。この論文が書かれたのは一九五七年。今も状況は変わっていないと感ずるのは私だけではないだろう。
但し、引用されているから言及するのではないが、近代日本には魯迅(一八八一~一九三六)のような純正ニヒリストは生まれなかった(せいぜい皮肉屋の斎藤緑雨〈一八六七〜一九〇四〉程度だろう)。上滑り文明化批判はあっても、漱石は、『こゝろ』にあるように、明治精神なるものを存外評価していた。また、あれほど英語ができていながら、漢詩・俳句は最後まで手放さなかった。欧化と国粋をなんとか調和させようともがいていたのだ(これは鷗外〈一八六二〜一九一三〉も同様である)。ましてや、魯迅のように「革命」の後は「反革命」、その後は「反反革命」だ、「水に落ちた犬は打て」などとは口が裂けても言わない。日本という「近代」社会に留学して、日本語及び日本の近代文学を学んで中国の小説を根源的に変えた、否、近代中国文学に作り上げた魯迅の根柢にある闇はどうやら欧化と国粋という二分類ではなんとも収拾がつかない、伝統中国がこれまで堆積し沈殿した大量の澱と深く絡んでいるのではないだろうか。逆に言えば、日本にはこれほどの澱がなかったということでもあるだろう。だから、脳天気に「反復」し「思い出」すことができるのである。
2―優劣感から脱却するために
古代国家も近代国家も、くり返し述べたように、カール・シュミット(『政治的なものの概念』)の指摘するように他者=敵をもつことによって生まれる。ここには時代差はない。日本の律令国家も大唐を敵=対等国とし、新羅を従属国(大唐に朝貢している新羅を対等国にすることは論理上できない)とすることで成立した。だから、当時の支配層は、日本人という自覚はなかったとしても日本という自覚は明確すぎるほどあったと言ってよい。そこから和漢世界という世界観が生まれた。九〇五年、和歌と漢詩の対等を主張した紀貫之作『古今集』「仮名序」(和文)・紀淑望作「真名序」(漢文)はこの図式によっている。
これに先立つ八一八年に天台宗を確立した最澄は、三国という世界観を呈示した。天竺(梵)・震旦(漢)・本朝(和)によって成り立つ三国世界観である。その後、三国観は様々に変奏していくが、三国の中から朝鮮半島を排除していることを含めて、世界を三つの国で代表させている端的な事実からも、安然型自国優越意識が出て来ることは、半ば必然であった。史実的に言えば、天竺であれ、震旦であれ、三国という世界観など存在せず、日本を知らない(自称はともかく厳密に言えば、日本に来た天竺人は婆羅門僧正のみ)天竺はさておいて、震旦にしてみても、日本など辺境の一島国くらいの存在だったと思われる。
だが、三国世界には、和漢世界にない素晴らしい意味合いが隠されていた。文明国の中国と後進国の日本では、どう頑張っても漢>和という構図から逃れられない。その反動として、空海や寂照(?〜一〇三四)の説話のように、中国に留学して、現地の中国僧よりも優秀だったといった類の屈折した優越感を語る説話や日本の神仏に祈って窮地を逃れたといった霊験説話が存在するが、いくら漢=和ないしは漢<和と強がってみても、所詮は、対中国劣等感は抜けない。そこで、日本人が現実に選んだのは和と漢の共存であった。これは途中重大な変更(後述)を蒙るものの、大正期まで維持された(明治期漢詩が隆盛を誇ったのだ)。
漢>和の構図が逃れる方法、これが三国観であった。仏教を基軸にしているから、仏を生んだ天竺が最高位にある。そこから、天竺>震旦=本朝という構図が出て来るだろう。つまり、天竺を第三項として震旦との対等関係が論理上導き出せるのである。さらに、鎌倉初期の高僧(歌人でもある)慈円が出した梵=和>漢という構図になると、天竺と本朝をイコール化して、震旦を下位に置いてしまうのである。慈円がこれを言い出したのは、和歌=仏法という構図の主張であった。むろん、優劣感は疑いなくあるが。
しかし、慈円の図式が別段、勢力を握ったのではない。鎌倉末期、渡来僧と入宋・入元僧が相次ぎ、禅宗が日本に根付いた。そこで生まれたのが、菅原道真(天神)(八四五〜九〇三)が三百年を経て径山の無準師範(一一七六〜一二四九)のところに教えを乞いに行くという説話である(渡唐天神説話、芳澤元『日本中世社会と禅林文芸』、吉川弘文館参照)。中国服を着て梅を持つ天神の絵も多く描かれ、室町期にはかなり影響力があった説話であった。この説話がこれまでとは異なるのは、日本の神(=天神)が中国の禅僧に教えを乞いに行くという明らかに漢>和の構図に立っていたことである。だが、そこになんら劣等感の気配がないのである。
禅宗がもたらした文化は、室町将軍や武将の庇護を得て、茶・能・和漢聯句(漢和聯句)・宋学・唐宋詩・水墨画と拡大して、江戸期以降の和漢(漢和)構図を作り出していくが、どうやら禅宗とは、三国世界を事実で以て破壊したポルトガル人の来航以前に、三国間になんらかの優劣感を生み出す三国世界観や漢>和を前提とする和漢世界観を無化して、漢=和という新たな漢和世界をもたらしたのではないか。
その後、十八世紀後半に本居宣長が出てくるまで、漢と和の間をどうのこうの言う人はいなかった。漢意・仏意を避け、古代の清らかな日本に戻れと宣長が説いたとき、またもや漢・和、梵・漢・和の優劣関係が持ち込まれた。いずれも古代と同様に、日本内部の議論ではある。だが、明治以降、漢・梵の代わりに欧米が入ってきたとき、またしても、同じことをまさしく「反復」しているのではないか。
やはり、鎌倉から江戸期を覆った漢和世界(唐物=舶来趣味も目につくものの)に一度戻ってみるべきではないか。優劣感なる劣情から脱却することが、日本人論の終焉に導く方法であると確信する。